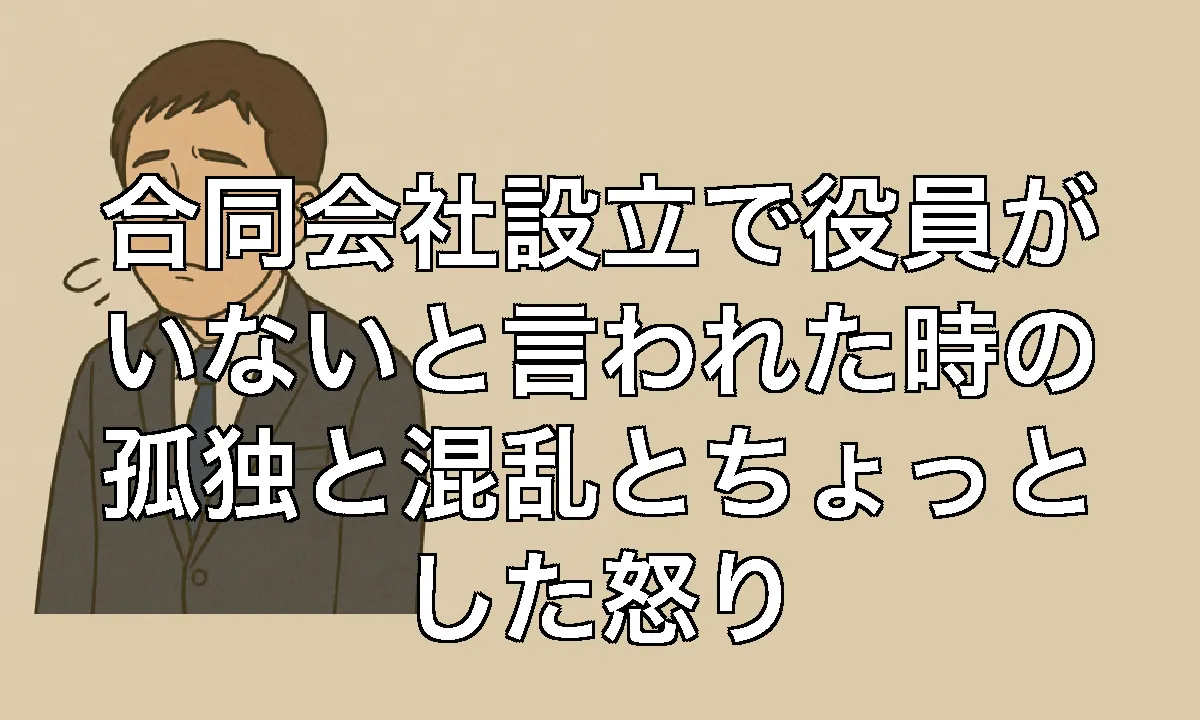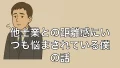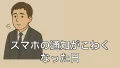合同会社設立の書類提出で出鼻をくじかれる
「え、役員がいないってどういうこと?」
そんな一言を、法務局の窓口で投げかけられた日を、僕は今でも忘れられません。合同会社の設立登記の相談で訪れたはずが、窓口の担当者に言われたのは「この書類、役員の記載がありませんけど?」という指摘。え?代表社員を書いてるのに?と一瞬、頭が真っ白になりました。司法書士であるはずの自分が、制度の細部に足を取られ、目の前の依頼人にも冷や汗をかく始末。まさに出鼻をくじかれるとはこのことでした。
法務局で言われたまさかの一言
「役員がいない会社なんておかしいでしょ」——その一言が、妙に脳に刺さりました。
自分としては、しっかりと代表社員を記載していたつもりだったし、合同会社はそもそも取締役とかいない形式じゃなかったっけ?と内心で焦る。けれど、目の前で「これは不備ですね」と言い切られてしまえば、それ以上反論もできず、ただただ曖昧な返事でごまかすしかなかったのです。情けない話ですが、こんな場面でも「先生頼りになりますね」と言われてしまうことが逆につらい。
「役員がいない会社なんておかしいでしょ」と言われて
世の中の大半の人にとって、「会社=社長がいて役員がいて」というイメージがあるのは当然です。けれど、合同会社では“役員”という制度的な存在がそもそもない。それを知っているつもりでも、こうして「常識」として言われると、自信がグラつきます。「常識」と「制度の正しさ」のズレ。これが現場で一番やっかいなんですよね。
代表社員って役員じゃないのか問題
合同会社における“代表社員”は、株式会社でいうところの“代表取締役”のような立ち位置。でも、「取締役」でもなければ「役員」とも明示されていない。その曖昧さが、司法書士である僕自身も混乱させる原因でした。依頼人は「社長」になった気分でいて、書類を提出したら「あなた役員じゃないですよ」と返される。そりゃあ、混乱するわけです。
そもそも合同会社の仕組みを分かっていなかった
実は、恥ずかしながら、僕自身も最初は株式会社の延長のような感覚で合同会社を捉えていた節がありました。形式が違うとはいえ、会社は会社だろうと。
しかし、合同会社は「社員=出資者であり経営者」であり、「役員」という考え方とは別世界の存在。そこを明確に理解していないと、こうして窓口で恥をかくことになる。知識として知っていても、肌で理解していなかったことが露呈しました。
株式会社との違いに振り回される
株式会社では「役員の選任」「就任承諾」「取締役会」など、お決まりの形式がありますが、合同会社はそれがない。自由度が高い反面、その“自由さ”が曲者。依頼人に説明しても「え?じゃあ誰が経営するの?」と返ってくるし、法務局ですら「役員がいないのは不自然」と感じる人も多い。結局、正しい制度でも“違和感”で疑われるんです。
実は「いない」は正しいけど分かりにくい
合同会社に「役員がいない」のは制度上当然なんですが、書類に書く時に“役職欄”がないとか、“役員の任期”が存在しないとか、いろんな部分で「これでいいのか?」という疑問が湧いてきます。司法書士ですらそうなるのだから、一般の依頼人にとっては、なおさら理解しづらいはず。制度が正しくても、分かりやすさがないと現場では混乱するばかりです。
自分の無知を思い知らされる瞬間
司法書士とはいえ、すべての制度を完璧に把握しているわけではありません。今回の合同会社の“役員がいない”問題も、自分の理解不足を突きつけられたようで、情けなさがこみ上げてきました。依頼人の前では平静を装いながらも、内心は「やっちまったな」と自己嫌悪でいっぱい。こんなとき、誰かに愚痴でも言えれば少しは楽になるんですけどね。
司法書士でも知らなきゃ詰む制度の落とし穴
仕事をしていく中で一番怖いのは、「知っているつもり」が一番危ないということ。
細かい制度の差異や用語の違いに敏感にならなければ、こうした“ちょっとしたミス”が信用問題にまで発展してしまうこともある。合同会社のような形式は増えていますが、制度を深くまで理解していないと足をすくわれる。それが、身に染みて分かりました。
恥ずかしいけど、知らなかった
正直に言えば、今回の件で初めて「あ、合同会社ってこういうものなのか」とちゃんと理解したところがあります。恥ずかしい話です。でも、それを経験として残せるか、単なる失敗で終わるかは、自分次第。とはいえ、やっぱり事務員さんの前でも少し恥ずかしかったですね。見て見ぬふりしてくれてたけど…。
誰も教えてくれない基本のキ
合同会社の登記に関して、専門書でもネットでも断片的には載ってるんですが、「誰かが一から教えてくれる」ような環境はほとんどありません。実務経験から学ぶしかない。それが司法書士という仕事のリアルです。新人さんならともかく、ベテランの僕が「今さら…」って聞ける場もなかなかない。だから余計に孤独を感じるのかもしれません。