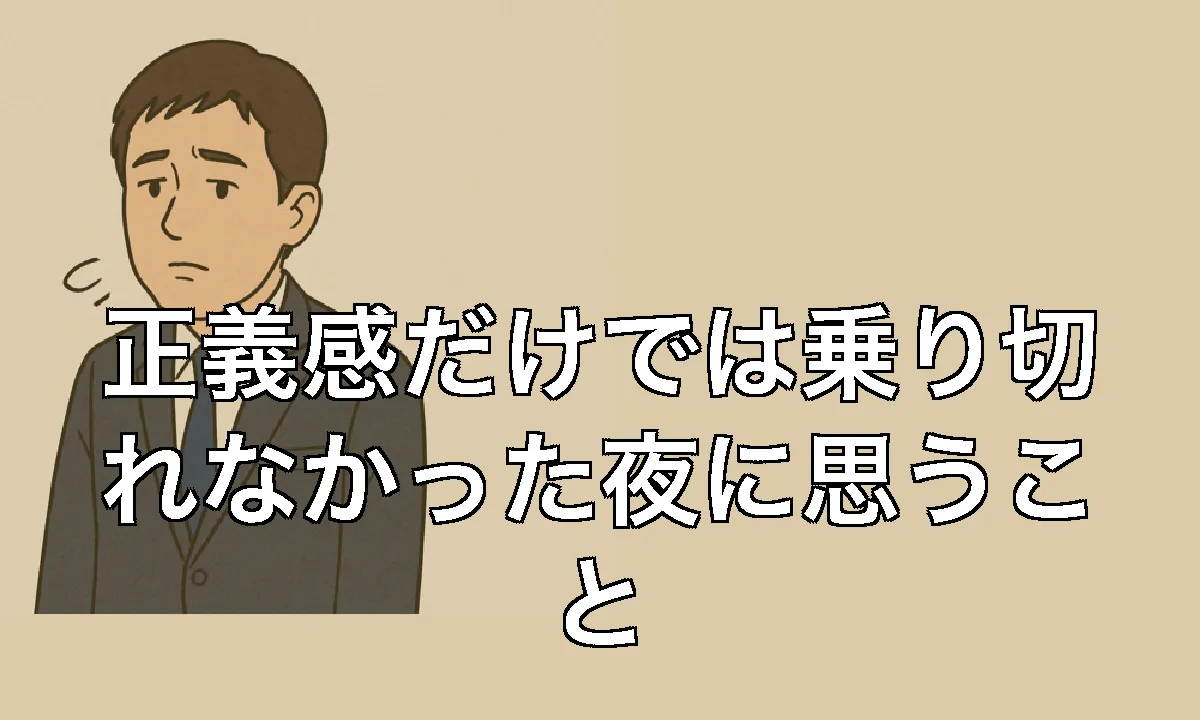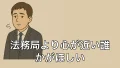まっすぐな気持ちが空回りしたあの夜
司法書士として独立して十数年、今でもはっきり覚えている夜がある。あの時は依頼者のために全力で動いたつもりだった。自分の中では正義感で突き動かされていたのに、結果はクレームと罵声。事務所に戻っても、事務員さんには気を遣って愚痴も言えず、ひとりコンビニの駐車場で缶コーヒーをすすっていた。あの時、「正義感だけじゃ通じない世界もある」と心底感じた。誰かを思って動いても、結果が伴わなければ無意味だと突きつけられることがある。
理想を掲げてスタートしたあの頃の自分へ
開業したばかりの頃、私は熱に浮かされていた。人の役に立つことが何よりだと思っていたし、「間違ったことを正すのが自分の仕事だ」と信じて疑わなかった。でも現実は、制度も社会も人間関係も、そんなにスムーズにはできていなかった。理屈じゃ動かない感情、正しさじゃ届かない距離があった。理想の旗を掲げていたけれど、気づけばその旗が風にあおられて、自分自身を傷つけていた。
「正しさ」が通じない現場に直面して
ある日、相続登記でトラブルになった案件があった。依頼者の主張は法律的に間違っていたけれど、感情的には正当性があった。私は手続きを説明し、法に則った対応を伝えた。けれど返ってきたのは「あなたは血も涙もないんですね」という言葉だった。あれは堪えた。正しさを貫くことが、時に人を遠ざけてしまう。どんなに説明しても、相手の心に届かない虚しさに、胸がしぼんだ。
登記ミスじゃないのに怒られる理不尽さ
登記が完了しているにもかかわらず、依頼者から「もっと早く終わらせられたはずだ」と責められたことがある。私の責任ではない遅延が原因だったが、そんな事情は通用しない。「専門家なら先を見越して動け」と言われ、言い返したい気持ちをぐっと堪えた。正論を振りかざすのは簡単だけれど、依頼者の心情に寄り添えないなら、それはただの独りよがりかもしれない。司法書士とは何なのか、根本を揺さぶられるような経験だった。
一人で責任を背負うという孤独
責任を取るのが自分しかいないという状況が続くと、時に呼吸が浅くなる。事務所の運営、事務員の生活、ミスの重さ——全部が自分にのしかかってくる。仲間がいないわけじゃないけれど、最終的な判断をするのは自分しかいない。夜中に電気もつけず、薄暗い部屋で報告書を読み直していたあのときの息苦しさは、今でも夢に出る。誰にも言えない不安を抱えたまま、朝を迎えることが何度あっただろう。
誰のための正義だったのか分からなくなる瞬間
ふと立ち止まったとき、自分が何のために戦っていたのか分からなくなることがある。依頼者のため、社会のため、法律のため? 本当にそうだったのか。もしかしたら、自分を認めてもらいたかっただけなんじゃないか。そんな自問自答が、夜になると顔を出す。正義感という言葉の裏に、承認欲求が潜んでいたかもしれないと思うと、なんとも言えない情けなさが込み上げてくる。
依頼者の感情と法律のズレ
「先生、なんとかならないんですか?」この一言が胸に刺さることがある。法律は万能じゃない。感情を救う力はないこともある。けれど依頼者は、感情ごと抱きしめてくれることを期待している。そこで「法律ではできません」と切り捨てるのは、冷たい人間に見える。だけど、私たちは魔法使いじゃない。できることと、できないことの線引きをするたび、心のどこかが削れていく。
「助けたい」気持ちが通じないとき
ある老婦人の相続案件で、私はできる限りの配慮をしたつもりだった。書類の説明も丁寧に、スケジュールも柔軟に対応した。けれど最後に「なんだか冷たい人ね」と言われたとき、涙が出そうになった。自分の気持ちが伝わらなかっただけでなく、むしろ裏目に出たことがつらかった。「やさしさ」の形は一つではないと分かっていても、すれ違うときの無力感は大きい。
法務局の一言で崩れる一日
完璧だと思って提出した書類に、法務局の担当者から「これじゃだめですね」と一蹴された日。小さなミスとは言えない程度の微妙な解釈の違い。こっちは何日も準備して、依頼者の信頼も背負っている。それでも、あのカウンター越しの冷たい一言で、一日の努力が瓦解する。ミスではないが納得もされない。そういう積み重ねに、心がすり減っていく。
事務所という小さな船を漕ぐ日々
たった二人の事務所だけれど、毎日が船出のような気分だ。波の穏やかな日もあれば、突風のようなトラブルに見舞われる日もある。そのたびに、私は舵を握って耐えなければならない。事務員さんには頼ることもできるけれど、最終的に責任を取るのは自分。正義感も理想も、時には荷物になることがある。それでも進まないと、船は沈む。
事務員さんに愚痴をこぼせないつらさ
どんなにしんどくても、事務員さんの前では気丈に振る舞ってしまう。彼女に心配をかけたくないし、私が弱ると事務所全体が沈んでしまいそうで。けれど、本当は聞いてほしい夜もある。家に帰っても誰もいない。話せる相手もいない。冷めたご飯を食べながら、ひとり反芻するだけ。愚痴すら吐き出せない日々が、心を静かに蝕んでいく。
元野球部の自分に「チーム戦」は遠かった
高校時代は野球部だった。チームプレーがすべてだったはずなのに、司法書士になってからは「個」で戦うことばかりになった。誰にも頼れず、相談もできず、ひとりで抱えることに慣れすぎた自分。今でも、グローブを握ったときの仲間の顔が浮かぶと、少し泣きそうになる。司法書士という仕事は、想像以上に孤独なものだった。
正義感よりも必要だったもの
ここまで来て思うのは、正義感だけでは足りなかったということ。むしろ、正義に縛られることで視野が狭くなっていたかもしれない。必要だったのは、受け流す力、肩の力を抜く勇気だった。完璧を目指すことよりも、うまく転がす柔軟さの方が、長く続けるには必要だったと気づいた。
割り切る強さと、流す余裕
全ての案件に全力でぶつかっていた頃は、燃え尽きるのも早かった。今は、「これは自分のせいじゃない」と割り切ることを覚えた。もちろん適当にはしない。でも、自分を守るためには、感情を切り離すことも必要だった。「今日はツイてなかった」と笑える日が増えると、心が少し軽くなる。
感情をぶつけず受け流す練習
感情的な依頼者に対して、つい熱くなりそうなときもある。でも、そこで同じ土俵に立つと、あとで後悔する。深呼吸して、相手の怒りを受け止めつつ、自分の言葉を選ぶ。これは完全に経験と失敗の積み重ねだ。若い頃の自分に「そんなに頑張らなくてもいい」と言ってやりたい。
モテなくても誰かの役に立てたらいい
正直、女性にモテたことはない。でも、「先生にお願いしてよかった」と言われた瞬間は、何にも代えがたい報酬だと思っている。外見でも、肩書でもなく、自分の行動で誰かの役に立てる。そう信じられると、少しだけこの人生に意味があるような気がしてくる。
それでもやめなかった理由
辛いことも多かった。それでも辞めずにここまで続けてこられたのは、どこかで誰かの力になれているという感覚があったからだと思う。小さな「ありがとう」に救われて、また明日も頑張ろうと思える。そういう積み重ねが、今の自分を作ってくれた。
夜のラジオから流れてきた救いの言葉
ある夜、仕事帰りの車中で聴いたラジオ番組。「誰かのために頑張っている人は、それだけで価値がある」——パーソナリティの何気ないその一言に、思わず涙が出た。私も、誰かのために頑張っているうちの一人だと思いたい。そう信じて、また朝を迎える。
愚痴を言える相手がひとりでもいれば
愚痴は悪いことじゃない。誰かに話すことで、自分を取り戻せることもある。もし、同じように苦しんでいる司法書士さんがいるなら、私はその人の愚痴を聞いてあげたい。誰かが私にしてくれたように。正義感だけじゃやっていけない夜を、少しでもあたたかくするために。