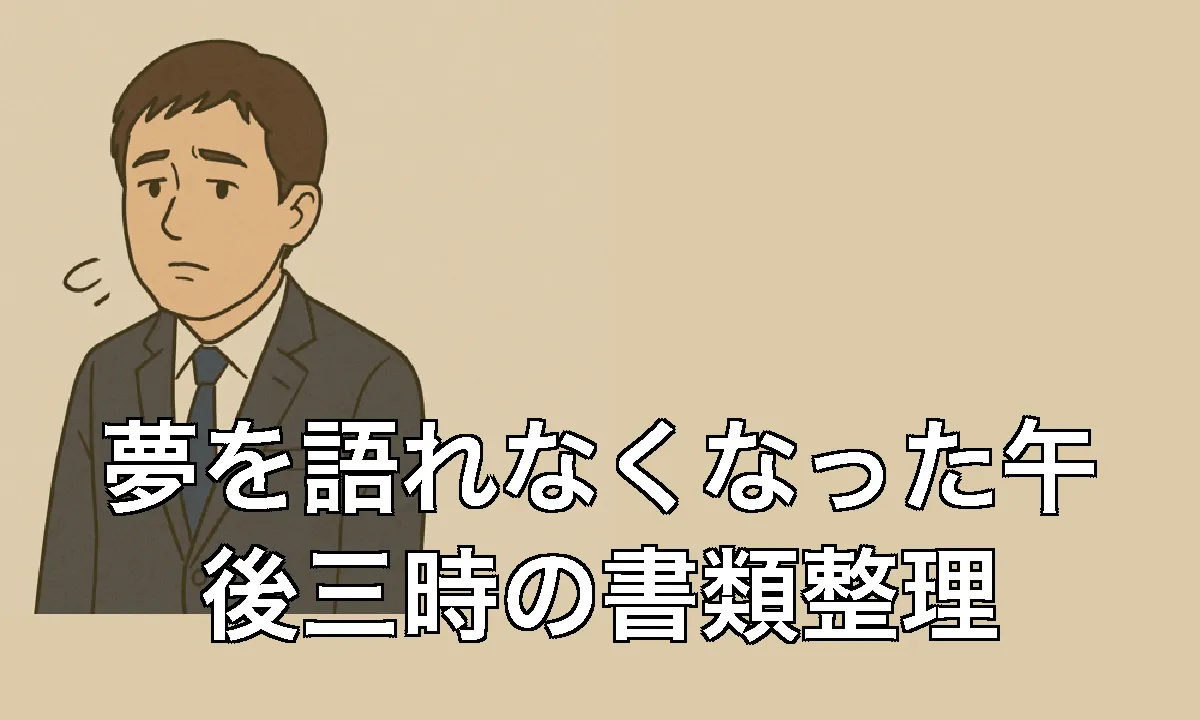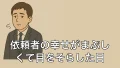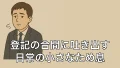夢を語ることに疲れた日常
夢を持って開業したのはもう十年以上前。あの頃は「登記の専門家として地域に貢献したい」とか「相談しやすい街の法律家になりたい」なんて言ってた気がする。でも今は、目の前の業務をこなすことで精一杯で、夢の“ゆ”の字も浮かばない。午後三時、事務所の静まり返った時間に、ふと手を止めて書類の山を見つめる。夢を語るなんて、今の自分には贅沢すぎる言葉に思えてくる。ただ生活のために働いている。そんな気がして仕方ないのだ。
書類の山に埋もれて思い出したこと
午前中から続く抵当権抹消の登記依頼、区役所への照会対応、顧客からの電話応対…。一段落ついた頃にデスクに広がるのは、まるで「片付けてくれ」と訴えるような未処理のファイルたち。ふと、開業当初に作ったパンフレットが一枚出てきた。そこには理想と情熱が詰まっていた。「地域の人々の信頼に応える司法書士を目指します」と書かれたコピーが、なんだか遠い昔の話のようで切なくなった。あの熱意、どこにいったんだろうか。
あの頃は開業したらこうしたいと言っていた
「事務所の相談室には観葉植物を置いて、優しい空気を作りたい」「困っている人がふらっと入れるような、敷居の低い場所にしたい」。そんなことを同期との飲みの席で熱く語っていた自分がいた。事務所の壁紙の色まで真剣に迷ったりして、希望に満ちた日々だった。でも、気づけば植物は枯れ、観葉植物どころか雑誌すら置いていない。訪れるのは予約のお客さんだけ。夢は、日々の忙しさの中で確実に薄れていった。
机の上のコーヒーと色あせた希望
コーヒーを淹れる暇もなくインスタントの粉をお湯で溶かしたマグカップが、いつも書類の端に追いやられている。立ち止まって飲む時間も惜しくて、気づけば冷めきっている。まるで今の自分の情熱のように。理想を抱いていた頃は、コーヒー片手にノートを開いて夢を広げていたはずなのに。今はマグカップに手を伸ばす余裕すらない。あの頃の自分が今の僕を見たら、きっと「なんでそんなに疲れてるの?」って聞いてくるだろう。
語る夢がなくなったのではなく語る余裕がないだけ
夢が消えたわけじゃない。語るための余裕がなくなっただけ。それが本音だと思う。やりたいこと、理想像はまだ心の奥底に眠っている。でも、それを言葉にするには時間と心のゆとりが必要で、それが今は圧倒的に足りない。毎日誰かの手続きのために奔走し、間違えられない責任の重さに押しつぶされそうになる。自分の夢なんて二の次、三の次。そのうち、夢を語ることすら思い出せなくなってしまう。
朝から晩まで電話と登記と締切
事務員ひとり、私ひとりの小さな事務所では、分業なんてものは存在しない。電話が鳴れば私が出る。郵便物が来たら私が開封する。登記情報の確認から書類作成、送付、報告…すべて自分でやる。さらに月末が近づけば登記の締切ラッシュ。顧客とのやりとりで神経を使い、法務局とのやりとりでは胃を痛める。そんな毎日の中で「夢を語ってる暇があるならこの登記早く出して」と自分に言い聞かせている気がして、悲しくなることがある。
夢は語るものじゃなく消耗するものになった
本来、夢って前向きで希望に満ちた言葉のはず。でも今の私にとっては、夢は語るものじゃなく、気力を消耗するものになってしまった。語れば語るほど、「じゃあなんでやってないの?」と自分に責められるような感覚になる。「ああしたい」「こうしたい」と語るたびに、現実との差に苦しくなる。そのギャップが痛くて、だから夢から目を背けてしまう。夢って、こんなにもしんどいものだったのかと思い知らされる日々だ。
また来週でいいですかが積もっていく
「これ、また来週でいいですか?」。つい口に出してしまうこの一言。たとえばパンフレットの刷新、ホームページの更新、昔の目標ノートの見直し。すべて「今じゃない」と棚上げにしてきた。夢も同じ。何度も「今じゃない」を繰り返すうちに、それはもう二度と手が届かない場所にある気がしてくる。でも本当は違う。「今じゃない」が「もう無理」にならないように、少しずつでも自分を取り戻したいと思っている。
夢を語れないことに気づいた瞬間
ある日、久々にあった高校時代の友人と昼飯を食べていると、「今、やりたいことってある?」と聞かれた。何も答えられなかった自分に驚いた。司法書士になりたての頃なら、語りたいことが山ほどあったのに。あの瞬間、自分が夢を語れない状態にあることを突きつけられたような気がして、少しだけ泣きそうになった。話すことがないというより、話す気力がない。夢という言葉の重みに負けていた。
ふとした会話の中で沈黙してしまった
「最近どう?」と聞かれて、「まぁ忙しいよ」としか返せない。何か一歩踏み込んだ話をする余裕がなくて、仕事の愚痴と疲労ばかりを口にしてしまう。本当は「こんなことにチャレンジしたい」とか「いつかこんな仕事もしてみたい」と言いたいのに、その前に沈黙が落ちる。夢を語るのは、元気がある人の特権のような気がして、黙り込んでしまう自分が少し情けなかった。あの沈黙が、今でも胸に引っかかっている。
夢を笑う人が増えたのではなく自分が笑えなくなった
若い頃は、誰かの夢を聞くのが好きだった。無茶でも、理想論でも、その人の顔がイキイキしているのを見ると元気をもらえた。でも、今は他人の夢を聞くのがつらいと感じることすらある。羨ましくて、恥ずかしくて、自分が情けなくて。夢を笑う人が増えたんじゃなくて、自分が素直に笑えなくなっただけだ。そんな自分を認めるのが怖くて、また仕事に逃げる。気づけば夢は、ただの遠い記憶になっていた。
夢を口にすると涙が出そうになるのはなぜか
夢の話をしようとすると、なぜか涙が出そうになる。それはたぶん、悔しさと疲れと、ちょっとの希望がまだ心のどこかに残っているからだと思う。夢をあきらめたわけじゃない。ただ、「夢を語れる自分じゃない」と思い込んでいた。でも本当は、もう一度語ってみたい。涙をこらえてでも、自分の気持ちを聞いてやりたい。そんな風に思えるようになったのは、この午後三時の書類整理のおかげかもしれない。
もう一度夢を思い出すという作業
夢を大きく語らなくていい。派手な目標じゃなくてもいい。ただ、自分が「少しでもワクワクすること」を思い出すことから始めてみたい。誰かに語らなくても、書き留めておくだけでも、心は少し軽くなる。夢は他人に見せるためのものじゃなく、自分を支えるためのものなのかもしれない。日々に埋もれかけた夢を、もう一度拾い上げる。そんな作業を、午後三時にひっそりと始めてみた。
人に話す前にまず自分で聞いてやる
誰かに話す前に、自分の夢を自分で受け止めてやることが大事だと気づいた。紙に書いてみる、声に出してみる、昔のメモ帳を読み返してみる。どれも最初は気恥ずかしかったけど、だんだん「やっぱり自分にはこういう願いがあったんだな」と思い出せてきた。夢を語ることに慣れていなかっただけ。自分に対しても素直に語る時間を持つこと、それだけで少しずつ、心の整理ができていくのを感じた。
大きなことじゃなくていいから目の前の一歩を
司法書士として大成功するとか、メディアに出るとか、そんな大きな夢じゃなくてもいい。目の前の机を片付けて、休憩時間に好きな音楽を聴く。それだって夢に近づくための小さな一歩。理想の働き方に近づけるように、少しずつ行動していけばいい。「夢」という言葉に押しつぶされるのではなく、自分なりのペースで向き合っていけばいい。そう思えた瞬間、少しだけ心が軽くなった。
夢を語る気力がないなら書いてみるという選択肢
話す気力がないなら、まずは書けばいい。誰に見せるわけでもない、自分だけの夢ノートを作ってもいい。手書きでも、パソコンのメモでも、スマホのアプリでも構わない。書くことで気づくことがある。「あ、まだこんなこと考えてたんだ」と、自分の中にある小さな火種を見つけられるかもしれない。夢は、声に出さなくてもいい。ただ、自分の中で温め直すだけで、もう一度歩き出せる気がした。