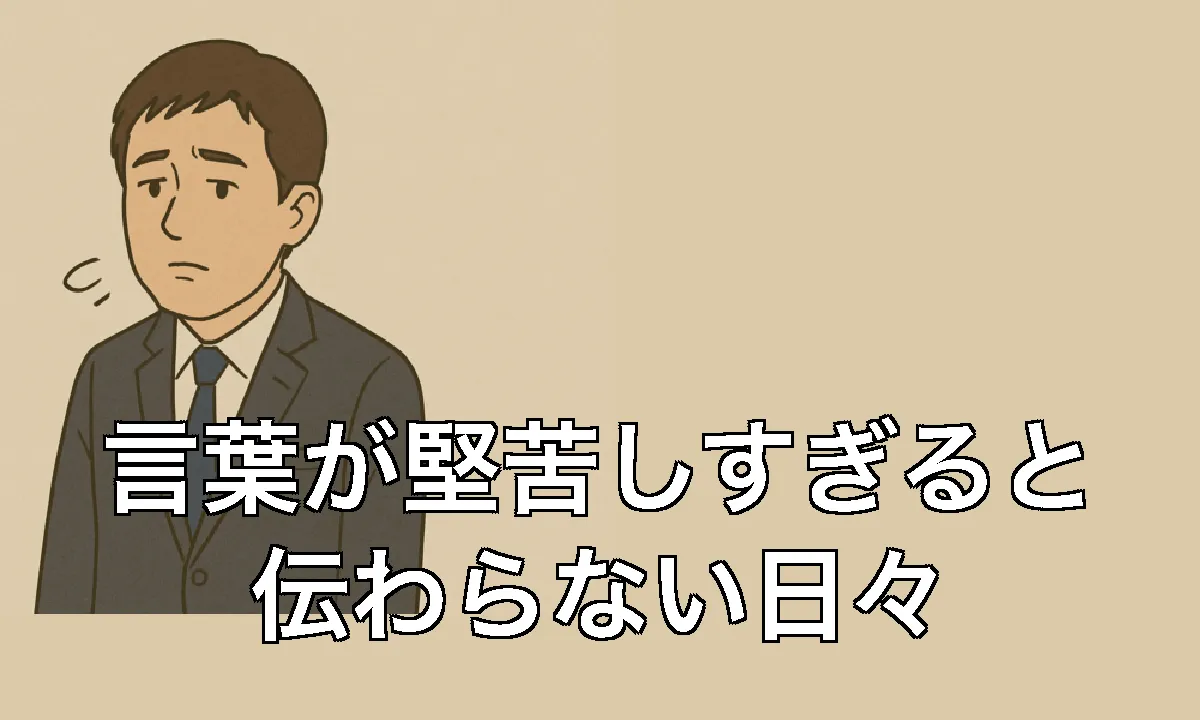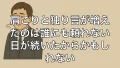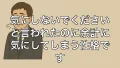固い言葉を使う癖が身についてしまった理由
気づけば、口を開けば専門用語ばかり。昔はもう少し砕けた話し方もできていたはずなのに、司法書士として働くようになってからというもの、「正確さ」を追い求めるあまり、どんどん言葉が硬くなっていった気がする。依頼者にとって大事なのは「わかりやすさ」だと頭ではわかっているけれど、いざ説明の場面になると、どうしても専門的な言い回しになってしまう。悪気はない。むしろ丁寧に伝えたい気持ちが強すぎるのかもしれない。
司法書士の世界に漂う「正確であること」の圧力
司法書士の仕事は、言葉ひとつで意味が変わってしまう。だからこそ、書類でも会話でも「間違えたくない」という思いが先行する。たとえば登記の説明ひとつ取っても、「不動産の権利移転に関する登記手続き」と言ってしまいがち。でもこれ、普通の人には伝わらないんだよね。自分でも「ちょっと堅すぎるな」と思いつつも、業界の中で鍛えられた言葉の癖が抜けない。まるで硬式野球のフォームのように、癖づいてしまったんだ。
専門用語を使うことで安心してしまう自分がいる
専門用語を使っていると「自分は間違っていない」という安心感がある。逆に言えば、噛み砕いた言葉で説明して「それ違うよ」と言われるのが怖いのかもしれない。依頼者に質問されて答えに詰まると、「あれ、俺ってちゃんとわかってるのかな」と不安になる。だから、難しい言葉で逃げてしまう。まるで自分を守る盾みたいに。でも、その結果として、相手との距離がどんどん広がっていってしまっている気がする。
それって本当に依頼者のためになっているのか?
あるとき、依頼者に言われた。「説明を聞いても、よくわからなかったです。なんか、大学の授業を思い出しました」。そのときハッとした。自分の安心のために言葉を選んで、相手の理解は置いてけぼり。それってプロとして失格じゃないか?と思った。それ以来、できる限り日常の言葉に置き換えるように心がけている。でも、それがまた難しい。言葉って、習慣で染みつくものなんだなと痛感した瞬間だった。
「丁寧」と「堅苦しさ」の違いがわからなくなる瞬間
「丁寧に説明してください」と言われて、「堅苦しく説明してしまう」ことがある。これは本当にややこしい。たとえば、「売買契約書の瑕疵担保責任に関して…」なんて言ったところで、大半の人はポカンとしてしまう。丁寧さとわかりやすさは両立できるはずなのに、司法書士業界の中にいると、それが逆になってしまう瞬間があるんだよね。気をつけているつもりでも、長年の習性はなかなか手ごわい。
マニュアル通りが正解ではないと気づいたきっかけ
ある日、事務員が一言、「先生の話、たまに理解できません」って笑いながら言ってきた。最初はショックだったけど、逆にありがたかった。いつの間にか、自分の説明が「マニュアル通り」に偏っていた。例えるなら、教科書に忠実な野球理論だけでプレーしていた感じ。臨機応変に、その場の状況に応じた対応が必要なのに、それを忘れてしまっていた。事務員のその言葉は、今でも脳裏に焼きついている。
元野球部だった頃はもっと単純明快だった
野球部の頃は、キャプテンが「そこ、もっと腰落とせ!」とか「声出せ!」とか、シンプルでわかりやすい言葉をかけてくれていた。複雑な理屈よりも、行動に直結する一言が力になる。それが人に伝えるということなんじゃないかと、今になって思う。司法書士になって、言葉に縛られてしまった。でも、本当に伝えたいことって、もっとシンプルで、もっと人間味のあるものだったんじゃないかと思うようになった。
言葉の壁がコミュニケーションの壁になっていた
あるときから、依頼者の反応が気になるようになった。「この人、本当にわかってくれてるかな?」って不安になる瞬間が増えてきた。形式上は説明しているけれど、相手の顔はどこか不安そう。そんなとき、自分の言葉が「伝わっていない」のではなく、「届いていない」のだと感じた。司法書士としてではなく、人として話さないと、心には響かないのかもしれない。
依頼者の表情が曇った瞬間に気づく違和感
昔、ある相続登記の説明をしていたとき、依頼者の奥さんが「…つまり、どういうことですか?」と申し訳なさそうに口を挟んだ。その瞬間、自分が一方的に「説明してやってる」ような態度になっていたことに気づいて、自己嫌悪に陥った。相手の立場に立っていなかった。その表情の曇りは、自分への違和感の表れだった。あの顔、今でも忘れられない。
「それって、結局どういうこと?」と聞かれて焦る
「えっと…つまりですね…」と口ごもると、焦る。焦ると余計に言葉が難しくなる。「法定相続分に基づく持分割合が…」とか言い出す自分が怖い。結局、相手が聞きたいのは「自分は何をすればいいのか」だけなんだよね。それがわかっていても、うまく言葉を選べない。もっとシンプルに、もっと自然に話したいだけなのに、その“自然”が難しい。何をそんなに気張っているんだろうか、自分。
専門家になりすぎて説明が下手になった
専門家として知識は増えた。でも、それに比例して説明は下手になった気がする。もしかして、初心者だった頃の方が、相手の気持ちを汲んで話せていたかもしれない。知識が増えると、つい全部を伝えたくなる。でも、それが逆効果だってことに、ようやく気づき始めた。知ってることと、伝えることは別。それが今の課題だ。
試行錯誤の末にたどり着いた言葉のほぐし方
じゃあ、どうすればいいのか?最近ようやくたどり着いたのが「日常会話に寄せる」ということだった。言葉を飾らず、身近なたとえで説明する。それだけで、相手の反応がまるで違う。以前は堅苦しくなりすぎていた自分も、少しずつやわらかくなってきた気がする。完璧には程遠いけれど、少なくとも、相手の「わかった」という顔を見る機会は増えてきた。
事務員との雑談がヒントになった
ふとした事務員との雑談で、「それ、うちの母にも伝わるように話してくれたら嬉しいんですけど」と言われた。ああ、そうか、家族に話すつもりでやればいいんだと気づいた瞬間だった。その日から、頭の中で「うちの姉ちゃんだったらどう説明するかな」と想像しながら話すようにしている。別に砕けすぎる必要はない。でも、相手の背景を想像するだけで、言葉の選び方は変わってくる。
難しい話を一度「家族に説明するつもりで」話す
この「家族に話す感覚」は、自分の中で革命だった。以前は「司法書士として正確に」ばかり考えていたけれど、それだと逆に伝わらない。でも、妹や親に話すようなトーンを意識するだけで、言葉が自然になる。たとえば「登記原因証明情報」なんていうワードも、「なぜこの土地がこの人の名義になるのかを説明する書類です」と変換できるようになった。すごくシンプルだけど、すごく効果的。
それでも直らない時は、もう一回深呼吸
どれだけ意識しても、やっぱり時々は元に戻ってしまう。そんなときは、自分に「まあ、そんなもんだ」と言い聞かせて深呼吸するようにしている。完璧を目指すと、また堅くなる。肩の力を抜いて、「伝えたいことがちゃんと伝わればいい」と思えば、少しだけ楽になる。愚痴も多いけれど、伝えたい気持ちは誰よりもあると思っているからこそ、これからも言葉と向き合っていくつもりだ。