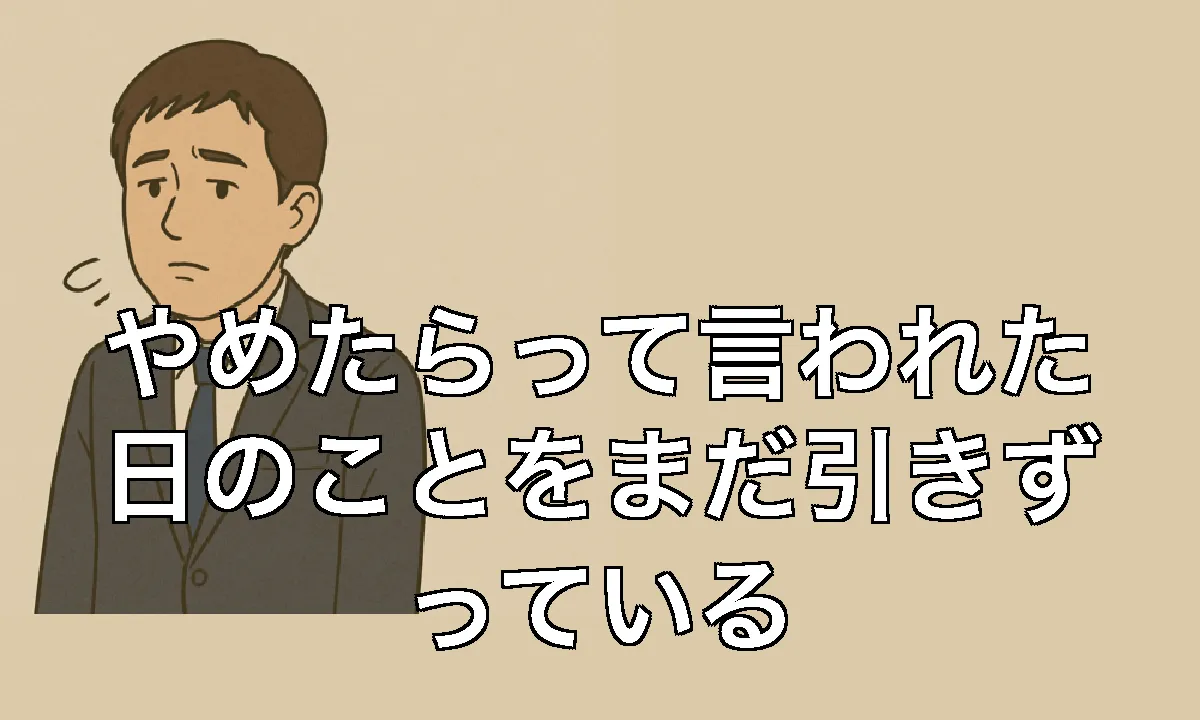ふとした一言に心がざわついた日の記憶
その日は何気ない雑談の延長だった。依頼人との電話を終え、ため息まじりに事務所でボヤいた。「もう、やってられんな……」。すると、パソコンを打っていた事務員がこちらを見ずに一言、「じゃあ、やめたら?」。声のトーンは淡々としていて、冗談なのか本気なのか、判断がつかない。でもその瞬間、心の奥にズシンと響いた。ずっと溜め込んできた疲労や孤独が一気に浮かび上がってきた。たった一言で、すべてのやる気が抜けていくような気がした。
言われたのはほんの冗談だったのかもしれない
今になって考えれば、事務員のその一言には悪意なんてなかったのかもしれない。彼女なりに、「それなら思いきって休めば」という軽いニュアンスだった可能性もある。でも、その時の自分には、そうは受け取れなかった。四六時中張り詰めて働いて、ミスすればすぐに責任を問われる日々。そんな中で、投げつけられたように感じた「やめたら?」は、まるで「もうあなたの限界でしょ」と言われているようだった。
笑って流せばよかったと後悔する夜
夜、自宅に帰ってもその言葉が頭を離れなかった。テレビをつけても、晩酌をしても、どうしても「やめたら?」のフレーズがぐるぐると回ってくる。あのとき、冗談として受け止めて、「ほんとそうだね〜」とでも言って笑い飛ばせていれば、もっと軽く終わっていたのかもしれない。でも、どうしても心がついてこなかった。冗談を受け止める器の小ささに、自分でも呆れた。
でも、その日は妙に胸に刺さった
思い返せば、自分でも限界に近いとどこかで感じていたのだろう。「やめたら?」という言葉は、まるで自分の心の声を他人の口を通して聞かされたような感覚だった。実際にやめるかどうかではなく、「やめたい」と思っている自分に気づいてしまったことが、何よりつらかった。司法書士として踏ん張ってきたプライドが、その一言で崩れそうになった。
仕事の愚痴が多いのは分かっている
最近、愚痴が多くなっているのは自分でもわかっていた。「もう疲れた」「何でこんなに報われないんだ」そんな言葉を、知らず知らずのうちに毎日口にしていた。聞いている方はうんざりしていたかもしれない。言ったところで状況が変わるわけでもないのに、ただ不満を垂れ流している自分が嫌になることもあった。
誰かに聞いてほしいだけの日もある
だけど、それでも誰かに聞いてほしかった。「大変ですね」と一言もらえるだけで、どれだけ救われたかわからない。事務員さんに期待しすぎていたのかもしれない。仕事上のパートナーでありながら、精神的な支えにもなってほしかった。そんな甘えが、自分の中にあったのだと痛感する。
優しさに甘えていた自覚もある
事務員さんは本当に真面目に仕事をしてくれている。自分の雑な指示にも文句一つ言わず、毎日きっちりこなしてくれている。そんな彼女に、つい甘えてしまっていたのだと思う。自分のイライラをぶつけて、それを受け止めてくれる存在だと勘違いしていた。今思えば、自分のほうがひどい。
やめることと向き合った数日間
その日を境に、「やめる」という選択肢が頭の中にしっかり居座りはじめた。朝起きるたび、「今日でやめてもいいのでは」と考えるようになった。あの言葉が、心の中のフタを開けてしまった。今まで無理やり押し込めていた不満や不安が、止めどなくあふれ出すようだった。
この仕事をやってきた意味を振り返った
高校時代の野球部で鍛えた根性が、いままで自分を支えてくれたと思っていた。でもそれは、ただ耐えていただけかもしれない。司法書士として何年もやってきたけれど、それが本当に地域や人のためになっているのか、迷いが生まれてしまった。「誰かの役に立てている」と実感できる瞬間が、最近はとても少ない。
司法書士という肩書きの重さ
司法書士という資格は、簡単には取れない。その分、責任も重い。ミスをすれば信用を失うし、クレームも避けられない。それでも続けてきたのは、誰かの人生の節目に関われるやりがいがあったからだ。だが、そのやりがいも、日常に埋もれて見えづらくなってきていた。
元野球部だった頃の粘り強さが顔を出した
そんなとき、ふと浮かんだのが野球部時代のことだった。試合でエラーしても、最後まで諦めなかったあの頃の自分。あの粘り強さは、今もどこかに残っているはずだ。あのときのように、まだやれるんじゃないか。そう思えた瞬間、少しだけ前を向けた。
もし辞めたら何が残るのか
辞めたあと、果たして何が残るのかと考えた。自由な時間?孤独?生活の不安?確かに疲れは取れるかもしれない。でも、仕事を通して得てきた経験や信頼は、もう二度と手に入らないかもしれない。それを失う覚悟があるかと問われれば、まだ答えは出なかった。
地域の人の役に立てた小さな実感
たまに「助かりました」と言ってくれる依頼人がいる。その一言の重さを、思い出した。華やかな言葉じゃなくても、確かに役に立てた瞬間があった。それが、司法書士としての自分をつなぎとめている。大それた成功じゃなくても、誠実に続けることの価値を、忘れてはいけないと思った。
独身の自分にとっての居場所とは
家に帰っても、誰かが待っているわけじゃない。休日に予定があるわけでもない。そんな自分にとって、この小さな事務所は、唯一の「自分の居場所」だった。誰かと支え合えるわけではないけれど、少なくとも社会とつながっている感覚がここにはある。
やめないという選択がもたらしたもの
結局、やめることはしなかった。しばらく迷って、でもまたいつもの朝が来て、事務所のドアを開けた。「おはようございます」と事務員が言った。それだけで、「やめないでよかった」と思った。何も変わっていないけれど、確かに自分の中に少し変化があった。
事務員さんの言葉が救いになった
後日、思いきって事務員さんに「この間の言葉、ちょっときつかった」と伝えた。すると彼女は「あ、冗談のつもりだったんです、ごめんなさい」と少し驚いた顔で言った。そして「先生がいないと私も困るし、これからもよろしくお願いしますね」と、ぽつり。なんだか涙が出そうになった。
誰かが見てくれているという事実
大したことじゃなくても、誰かが自分の仕事を見てくれている。それがあるだけで、人は前を向けるのだと思う。見られている、期待されている、頼りにされている——それが、人を支える力になる。それを感じられる仕事に、もう一度向き合ってみようと思った。
一人で抱え込まない勇気
司法書士という仕事は、基本的に孤独だ。でも、だからこそ「誰かに頼る」ことも大事だと思うようになった。相談することは甘えではなく、生き延びるための選択だ。弱さを認めて、声をあげる。そこからしか、回復は始まらない。
少しずつでも吐き出していい
愚痴でも弱音でも、全部抱えていたら潰れてしまう。少しずつでいいから吐き出していい。誰かに届かなくても、自分の言葉として外に出すだけで、気持ちが軽くなることもある。そうやって、自分を守る手段を増やしていきたい。
モテなくたって支えてくれる人はいる
結局、モテなくてもいいのかもしれない。恋人がいなくても、家庭がなくても、自分を気にかけてくれる人はいる。その人たちを大切にしながら、今日も小さな事務所で、粛々と仕事をしている。まだやめるわけにはいかない。そんな気持ちで、また一日が始まる。