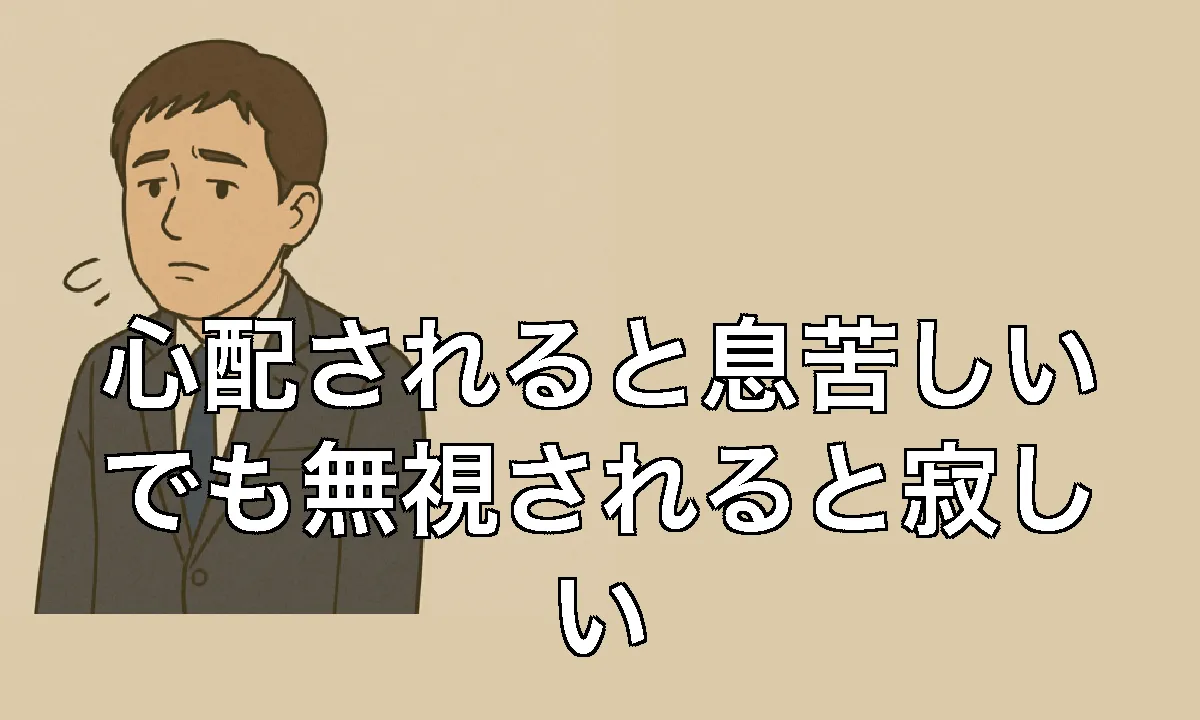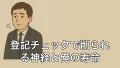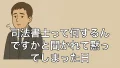心配されると息苦しいでも無視されると寂しい
誰かに気にされるとプレッシャーになる性格
気にかけてもらえるのはありがたい。頭ではそう思っている。でも、実際に心配されると、なぜか胸がざわつく。何かを期待されているようで、居心地が悪くなる。そんな感覚に心当たりがある人は、きっと少なくないはずだ。僕もそのひとり。独立して司法書士としてやってきたけれど、誰かから「大丈夫?」と聞かれると、「いや、別に…」と無愛想に返してしまう。優しさを受け取るのが苦手なのかもしれない。でも、そのくせして、放っておかれるとやっぱり寂しくなるのだ。
昔から「大丈夫」って言うのが癖になった
「大丈夫です」この言葉は、もう僕の口癖になっている。高校時代の野球部でも、ケガをしても、体調が悪くても、とにかく「大丈夫」と言ってしまっていた。「大丈夫って言ってんだから心配すんなよ」という態度をとりながら、内心では少しだけ「気にしてくれたんだな」と安心していた。その二重の感情は、大人になった今も変わらない。心配されると重たい。でも心配されないと、孤独感に包まれる。厄介な性格だなと思う。
野球部時代の「痛くないふり」が今も尾を引く
あの頃は、痛みよりも「迷惑をかけること」のほうが怖かった。練習中に足をひねっても「いけます!」と即答し、誰よりも早くグラウンドに戻った。その姿勢が評価される場面もあったけれど、今思えば、自分をすり減らしてただけだった気もする。そんな自己犠牲型のクセが、司法書士になった今も無意識に出てしまう。心配してくれる人がいるのに、それを素直に受け取れないのは、たぶんあの野球部で覚えた“我慢の美学”が原因だ。
心配=弱さだと思っていたあの頃
「心配される=自分は弱い存在」だと勝手に決めつけていた。それはたぶん、部活や家の中で「男なんだから」とか「気合で乗り越えろ」的な空気に慣れてしまったせいだと思う。司法書士という専門職に就いてからも、「頼られる存在でなければ」というプレッシャーのなかで、つい自分の弱音を隠してしまう。でも最近になってようやく、「弱さを見せること=信頼されなくなる」ではないんだと、少しずつ理解しはじめている。
だけど放っておかれるのも意外とつらい
誰にも気にされない日々は、思っている以上にこたえる。毎日淡々と仕事をこなして、誰にも話しかけられずに帰宅して、独りで食事をして、静かに寝る。自由といえば聞こえはいいけれど、ふとした瞬間に虚しさが顔を出す。何かが足りない。いや、誰かが足りない。心配されるのは苦手だけど、無関心でいられるのもそれはそれできついのだ。
ふとした瞬間に感じる孤独感
夜、コンビニの駐車場でカップラーメンを食べながらふと「こんなこと、誰も知らないんだな」と思った。どこかで事故にあっても、数日誰にも気づかれないんじゃないか。そんな妄想をしてしまう夜がある。誰かに依存したいわけじゃない。でも、完全な孤立はやっぱり怖い。心配されると反発したくなるのに、無関心には敏感に反応してしまう。この感情は、なかなか他人に説明できない。
誰にも頼れない日々が普通になった
仕事をこなす日々は、自分ひとりで完結してしまうことが多い。独立した時は「一人でも大丈夫」と思っていた。でも年々、「誰にも相談できない状況」が当たり前になってしまった自分に気づく。何かを共有できる人がいたら、今の苦しさは少しは和らいでいたかもしれない。でも、それを求めること自体が面倒だと思ってしまう自分もいる。この矛盾を抱えたまま、今日も事務所のドアを開ける。
事務所にひとりきりの時間がこたえる
平日の午後、依頼もなく電話も鳴らないときの事務所は、とても静かで、時に耐えがたいほどの孤独を感じる。雑用をこなしても、時計の針ばかりが進んでいく。事務員さんが不在の日は特に堪える。別に会話が多いわけでもないのに、いるかいないかで空気が変わるのだ。こういうときに思う。「誰かがそばにいるって、やっぱり大事なんだな」と。
事務員さんの何気ない一言が沁みる
うちの事務員さんは、干渉してこないタイプだ。でも、絶妙なタイミングで何か声をかけてくれる。その“さじ加減”が本当にありがたい。「先生、お昼食べました?」のひとことで、思わずホッとする。言葉にしないと伝わらないこともあるけど、言葉にしすぎると重たくなる。この絶妙な距離感が、今の僕には救いになっている。
「先生お昼まだですよ」それだけで救われる
ある日、朝からバタバタして昼飯を食べるのも忘れていたとき、事務員さんがポツリと声をかけてきた。「先生、お昼まだですよね?」その一言に、なんだか涙が出そうになった。大げさかもしれない。でも、誰かが自分のことをちゃんと見てくれてる、それが嬉しかった。心配を押し付けるでもなく、ただ気にしてくれる。そういう言葉が、いちばん沁みるのかもしれない。
干渉されない優しさに気づいた
世の中には、何でもズカズカ聞いてくる人もいれば、無関心を装う人もいる。その中で、うちの事務員さんのような「そっと気づく優しさ」は本当に貴重だと思う。心配はしてくれるけど、押し付けてこない。僕にとっては、このスタンスがすごく心地いい。きっと誰にでも合う“優しさの距離”ってあるんだろうな、と感じるようになった。
距離感が難しいでも人との関係は諦めたくない
人との距離感は、いつまで経っても正解が見つからない。でも、面倒だからといって完全にシャットアウトしてしまうと、人生が味気なくなる。だからこそ、関係を築く努力は、少しずつでも続けていきたいと思っている。心配されることも、されないことも、どちらも難しいけれど、そのあいだを探ることが、今の僕の課題だ。
心配より共感がほしい
何かに失敗したとき、慰められるよりも、「分かるよ」「俺もそうだったよ」と言ってくれる人のほうが、ずっと心強い。心配は時に「見下されてる」と感じてしまうけれど、共感は「同じ目線」でつながれる。司法書士という仕事も孤独な場面が多いからこそ、共感の言葉に救われる瞬間がある。だから、僕もなるべく共感を返せる人でありたいと思っている。
放っておいてくれるけど見捨てない人
ベタベタしないけど、ちゃんと見てくれている。そういう人が身近にいると、安心できる。うちの事務員さんもそうだし、たまに連絡をくれる昔の同期もそう。お互い干渉しすぎないけれど、いざというときはそっと支えてくれる。そういう人間関係を、これからも少しずつでも増やしていけたら、仕事の悩みも、人生の迷いも、もう少し楽に抱えられる気がしている。
この仕事を続けていく上でのちょうどいい距離
司法書士という仕事は、人と関わることが多い一方で、非常に孤独な職種でもある。そのギャップに苦しむこともあるけれど、自分なりの「ちょうどいい距離感」を見つけていくことが、長く続けるための鍵だと思っている。心配されすぎず、でも誰かに気にかけられる。そんな人間関係を築けたとき、この仕事も、人生も、もう少しやさしくなるはずだ。
お客さんとの関係にもそれは言える
お客さんとのやりとりでも、同じことを感じる。過剰な気遣いは相手に伝わってしまうし、逆に事務的すぎても冷たく感じられてしまう。だからこそ、“自然体”で向き合うことが大切なんだと、最近やっと分かってきた。こちらが無理をしても、相手には伝わる。だから僕も、お客さんに対して、無理なく誠実に接していきたいと思っている。
頼りにされるのも責められるのも紙一重
「先生、全部お願いします」と言われると、頼られてるんだなと嬉しくなる一方で、「もし何かあったら全部こっちの責任になるんだろうな」と思ってしまう。これは、司法書士という仕事の宿命かもしれない。信頼とプレッシャーは、常に表裏一体。でも、だからこそやりがいもある。これからも、その狭間でもがきながら、一歩ずつやっていこうと思っている。