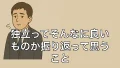職業柄弱音を吐けない日々の重さ
司法書士という肩書の裏側には、なかなか人には見せられない疲れや葛藤がある。誰かに「疲れた」と言いたくても、言った瞬間に「この人、大丈夫かな」と思われるんじゃないかという不安が先にくる。事務所を一人で運営している以上、倒れるわけにはいかないし、頼れる人も少ない。だから今日も「大丈夫です」とだけ言って、ぐっと堪える。それが続くうちに、自分の本音すらどこかに置き去りにしてしまう。
ひとり事務所という名の孤島
一人でやるという選択は、自由で気楽に見えるかもしれない。確かに、誰に気を遣うこともなく、仕事の進め方も自分次第。でも、その裏では、孤独という名の静かなプレッシャーがじわじわと迫ってくる。ちょっとしたことも自分で判断しなければならないし、誰にも相談できずに不安なまま進める案件も多い。そんな毎日が続くと、知らぬ間に「声を出す」ことを忘れてしまう。
助けが呼べない日常
例えば、登記でトラブルがあったとき。誰かに「ちょっとこれ見てくれる?」と言える環境ならどれだけ助かるだろうと思う。けれど、うちは事務員さんひとり。しかも専門知識が必要な内容だと、結局は自分で解決するしかない。助けを求める前に「これくらい自分でなんとかしないと」と反射的に思ってしまう自分がいる。それがどれほど精神的に負担になっているか、日常の中では見過ごしがちだ。
電話も応対も全て自分
依頼者からの電話、役所とのやり取り、急ぎの登記変更…。すべてが重なった日のことだ。一本の電話を取っている間に、別の着信が入り、FAXがガチャガチャと鳴り始める。タイミングが悪ければ来客もかぶる。もちろんそのすべてに対応するのは自分しかいない。電話を切ると同時にメモを取り、頭を切り替えながら次の案件に移る。そのスピードと集中力はもはや職人芸だが、内心では「誰か手伝ってくれ」と叫びたくなる。
元気なフリが仕事のうち
仕事柄、依頼者に不安を与えることはできない。だから、どれだけ眠れてなくても、頭が回ってなくても、笑顔で「お任せください」と言わなければならない。そのフリが上手くなればなるほど、自分の感情に蓋をするのも上手くなる。まるで舞台役者みたいに、事務所では役を演じている気分になる瞬間もある。
顔に出せない疲労の蓄積
特に相続案件などは、依頼者自身が精神的に不安定なことも多い。だからこそ、こちらは安定して見せる必要がある。ある日、前日に徹夜で準備した書類を抱えて、依頼者と面談した。体はフラフラなのに、必死で「安心してください」と微笑んだ。帰宅後、玄関で靴も脱がずにそのまま寝落ちした自分を見て、「ああ、今日も芝居をうまく終えたな」と思った。
「先生は頼れる」その言葉の重さ
「先生にお願いしてよかった」「やっぱり頼れるね」。そんな言葉をもらえると、正直うれしい。けれどその裏で「次も絶対にミスはできない」「完璧でいなきゃ」と自分にプレッシャーをかけてしまう。頼られるのは光栄だ。でも、いつからかその言葉に縛られるようになっていた。誰かに褒められるたびに、また一つ、弱音を吐く自由が遠のく気がする。
同業者に愚痴ることの難しさ
同じ司法書士同士でも、本音を言える関係は意外と少ない。みんな、表ではニコニコしているけれど、それぞれが孤独と戦っているのを感じる。だからこそ、逆に「大変だよね」と言い合える関係は貴重だ。でも、その貴重な相手を見つけるのが難しい。
本音が言えない関係性
飲み会の席で「最近ちょっと疲れててさ」と切り出したことがある。すると場が一瞬静まり返り、「俺もだよ!」と笑いながら返してくれる人はいなかった。むしろ「まあ、そういう時期もあるよ」と言われて、逆に気まずくなってしまった。それ以来、なんとなく弱音はしまっておこうと思うようになった。
打ち明けた瞬間に評価が変わる怖さ
士業の世界は、意外と人の評判が命取りになる。だからこそ、「あの人、最近疲れてるらしいよ」と噂になるのが怖い。そんな些細な一言で、紹介が減ったり、信頼が揺らぐこともある。結局、「頑張ってます」「順調です」と言い続けるしかない。そうやってどんどん本音が遠のいていく。
それでも、今日も机に向かう理由
毎日「今日はやめようかな」と思いながらも、やっぱり朝になると事務所の鍵を開けてしまう。仕事は確かにしんどいけれど、それでも誰かの人生に関わっているという実感は、何物にも代えがたい。ほんの少しでも人の役に立てたという感覚が、次の日の原動力になっている。
逃げたくても逃げられない現実
今さら別の仕事に就くこともできないし、田舎で一からやり直すのも現実的ではない。だからこそ、目の前の仕事を続けるしかない。それは「逃げられない」という重さでもあり、「逃げない」という自負でもある。どちらにしても、ここで踏ん張るしかない。
自分の価値を信じたくて働いている
この仕事をしていなかったら、果たして自分に何が残るのかと考えることがある。でも、少なくとも誰かの人生に役立っていると信じたい。それがある限り、自分の存在も捨てたもんじゃない。弱音を吐けない日々でも、どこかで「今日もよくやった」と言える自分でいたい。