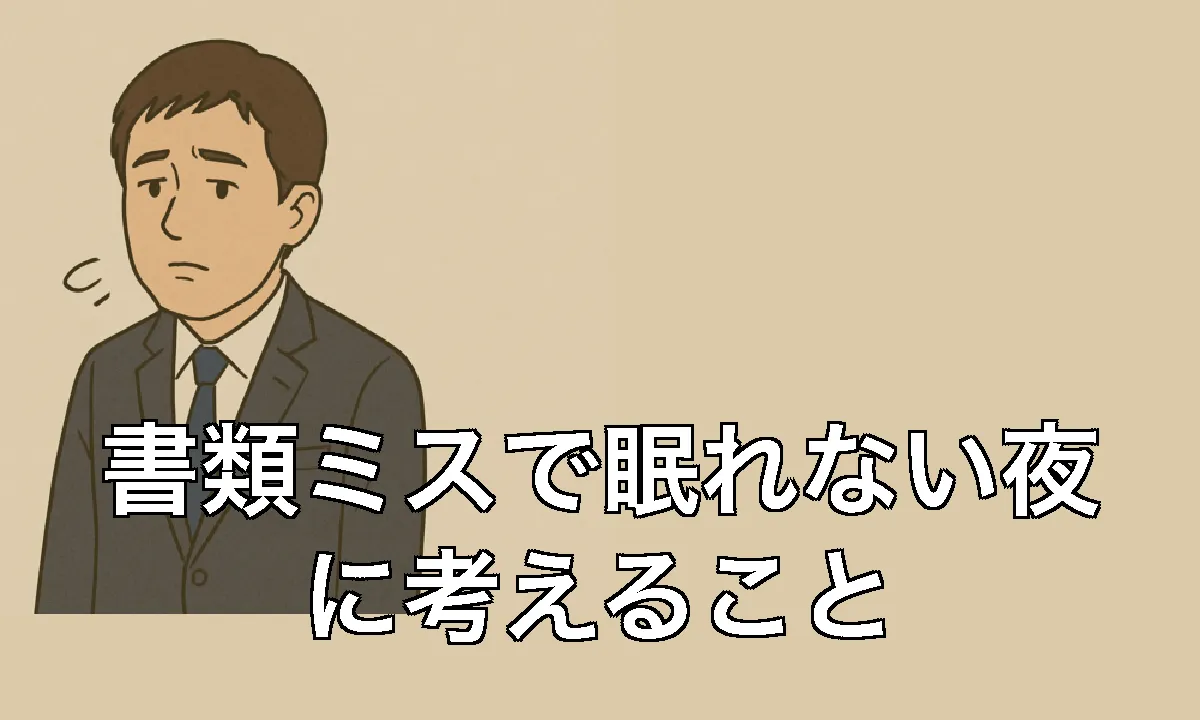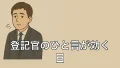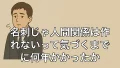書類の重みが眠りを奪う夜
たった一枚の申請書が、夜の静けさを乱すことがある。司法書士という職業柄、書類のミスは命取りになる。日中の業務に追われ、ギリギリで仕上げた登記申請。その中に一つでも間違いがあれば、依頼人の信頼を損なうばかりか、場合によっては損害賠償という言葉まで現実味を帯びてくる。そう思うと、布団に入っても目が冴えて眠れない。心臓の奥で不安がくすぶる夜は、司法書士としての責任の重さを改めて突きつけられる瞬間だ。
うっかりの一行がもたらす現実
よくあるのは、たった一文字の誤字。それだけで法務局からの補正通知が飛んでくる。先日は「乙山」を「王山」と打ってしまい、すぐに補正依頼が届いた。自分の目でも何度も見たつもりだったが、見落としていた。疲れていたのか、注意力が散漫だったのか。そんな理由では済まされないのがこの仕事。冷や汗をかきながら、依頼人に頭を下げ、再提出の段取りを取る。謝るのも慣れてはきたが、心のどこかで「またか」と自分を責め続けている。
些細に見えるが致命的な誤字
「様」と「殿」の違いも、案件によっては非常に重要になることがある。かつて、相続登記の際に「被相続人○○様」と表記してしまい、提出先の担当者から「亡くなった方に様付けは適切ではない」と注意された。自分としては丁寧なつもりだったが、形式に厳しい世界では礼儀が逆に失礼になることもある。その日、自分の常識が通用しない世界で生きていることを実感した。以来、表現には神経質すぎるほど敏感になった。
「様」と「殿」の取り違えすら怖い
昔、部活動の連絡網で「○○様」と書かれているのを見て、なんだか仰々しいなと笑っていた自分がいた。ところが司法書士としては、その一文字で立場や意味が変わってしまう現実を突きつけられる。ある依頼人が官公庁に提出するための書類で「○○殿」となっていたのを「○○様」に直したことがあった。丁寧に見えるかもしれないが、それでは通らない。些細なことが全体を揺るがす。昔の自分が今の自分を見たら、きっと驚くだろう。
登記の世界にミスの言い訳はない
「忙しかった」「前の日に寝てなくて」「確認したつもりだった」――そんな言い訳は、司法書士の現場では通用しない。相手は登記官であり、依頼人であり、そして法である。書類一枚に魂を込める。それがこの仕事の原点であり、逃げ場のない現実でもある。かつて、補正が続いた案件で「こんな仕事もう無理かもしれない」と思ったことがある。だが、そこで踏みとどまった。事務所に戻って深夜まで修正作業をし、翌日には何もなかったかのように提出する。そんな毎日の繰り返しだ。
訂正印と謝罪の電話のその後
ミスをしたときの第一声が、もうクセになっている。「、至急訂正いたします」。この言葉を何度言ったか数えきれない。あるとき、依頼人が苦笑いしながら「人間ですからね」と言ってくれた。それがどれほど救いになったことか。だがその一方で、安心した瞬間にまたミスが出るんじゃないかという不安がよぎる。訂正印を押す手が、時折震えるのは、仕事に慣れていないからではない。慣れてしまうことの怖さを知っているからだ。
眠れぬ夜に何度も読み返す申請書
申請書を出す前の夜、ふと気になって家に持ち帰ることがある。食事もそこそこに、書類を開いて読み返す。特に大きな案件や、急ぎの案件の前には必ずそうする。何度も確認したはずなのに、また目が止まる部分がある。そうやって、完璧を求めて睡眠を削っていく。翌朝、眠そうな顔で法務局に出すときの自分を鏡で見て、ふと「これは正しい努力なのか」と疑問を抱く。でも、それでも確認せずにはいられない。
自宅に持ち帰る癖がついた
事務所で集中できる時間は限られている。電話、来客、事務員への指示――気がつけば一日が終わっている。だからこそ、静かな自宅に持ち帰って確認するようになった。誰もいない部屋で一人、赤ペンを片手に申請書と向き合う。昔はテレビを観て笑っていたこの部屋も、今では緊張感のある小さな書類チェック場と化している。生活と仕事の境界がどんどんなくなっていく。それでもやらなければならない。それが「信頼」の維持だと信じている。
目を凝らしても消えない不安
何度も確認したはずの申請書を、目を凝らして見返す。それでも、どこかに「何か」があるような気がしてならない。錯覚かもしれないが、その感覚がとれない。夜中にふと起きて、もう一度ファイルを開いたこともある。確認し、何もなかったとわかっても、不安はゼロにはならない。不安はいつも心のどこかにこびりついていて、「大丈夫」とはなかなか言えないのが司法書士という仕事なのだと、最近ようやく理解しはじめた。
完璧主義という呪い
学生時代、野球部ではとにかく「ミスするな」と叩き込まれてきた。だからか、社会に出てからもミスを恐れる気持ちが人一倍強い。書類一つとっても、「100点じゃなければ提出できない」と思い込んでしまう。けれど、完璧を求めすぎると、それが自分を縛る鎖にもなる。「もっと気楽にやればいいのに」と言われても、頭では分かっていても、手が止まらない。完璧主義という呪いは、司法書士にとってある意味で必須のスキルであり、同時に自分を苦しめる毒でもある。
独り身の夜とひとつの印鑑
夜、事務所の照明を落とした後の帰路。街の灯りはやけにまぶしく感じる。家に帰っても誰かが待っているわけではない。独り身であることは気楽でもあるが、こういうときは少し心が寒い。机の上に置いた印鑑をぼんやりと見つめながら、「明日はちゃんと押せるかな」と不安になる。誰かに弱音を吐けたら楽だろうと思いながらも、結局口をつぐんでしまうのは、司法書士としての矜持なのか、単なる強がりなのか。
相談できる人がいない寂しさ
ミスをしたとき、ふと誰かに話したくなる。でも、業界内の人間には弱みを見せたくないし、かといって友人たちはこの世界のことを知らない。だから、自然と心に溜め込むようになった。電話越しの相手に謝って、事務員さんには「すみません、再出力お願いします」と伝えて、それで終わり。けれど、夜になっても心は終わらない。もう少し話せる相手がいれば、ときどき思う。でも、それを探す余裕すらないのが現実だ。
事務員さんに頼れない理由
うちの事務員さんは真面目で優秀だ。だが、自分の不安まで共有するわけにはいかない。「この書類、不安なんです」と言えば、彼女まで不安にさせてしまうだろう。だから、あえて平気なふりをして、黙って修正する。でも、内心では「一緒に背負ってくれたら楽だろうな」と思う瞬間もある。上司と部下の関係として、踏み込んではいけない一線がある。わかってはいるが、その一線が、夜の孤独をさらに深くしている。
責任を押しつけたくない気持ち
自分のミスを誰かにカバーさせたくない。特に、給料を払っている立場であればなおさらだ。どんなに信頼している事務員でも、自分のミスは自分で片付けたい。それは責任感というよりも、どこかで「頼ったら終わりだ」という思い込みに近い。そのせいで、誰にも弱音を吐けず、ただただ一人で責任をかぶってしまう。そして夜、眠れなくなる。そんなループに、もう何度も陥っている。でも、だからこそ、今日もまた自分で印鑑を握る。
自分を許せるようになるまで
書類ミスは許されない。でも、人間は完璧ではない。司法書士という職業の中で、その矛盾にどう折り合いをつけるか。たぶん、それがキャリアの中で一番難しい課題かもしれない。自分を追い詰めすぎず、でも気を抜かず。そのバランスをとる日々。完璧ではない自分を許すこと。それは、眠れない夜に少しだけ心を休める鍵になるのかもしれない。
ミスを経験して強くなれたか
正直、強くなったかどうかは分からない。ただ、耐性はできたと思う。ミスをしたときの対処法も、自分なりに身についてきた。でもそれが「慣れ」なのか「成長」なのかは、まだ判断がつかない。ただひとつ言えるのは、ミスをするたびに、自分の弱さと向き合う時間が増えたということ。そしてその弱さを、少しだけ受け入れられるようになったことだ。
怒られた日と優しくされた日
法務局の窓口で怒鳴られたこともある。逆に、「忙しいでしょうから、気をつけて」と優しく声をかけられた日もある。その一つひとつが、今の自分を形作っている。怒られた日は心が折れそうになるけれど、優しくされた日は涙が出るほど救われる。司法書士という仕事は、人と人の間に立つもの。書類の向こう側にいる人の気持ちを考えること。それが、結局一番大切なことなんだと思う。
寝不足でも朝は来る
眠れなかった夜の翌朝も、やることは変わらない。メールを開いて、電話を取って、今日も登記の処理をする。昨日の不安を引きずったままでも、時間は進む。だから、どこかで気持ちを切り替えなければならない。「大丈夫、今回は完璧にやった」と自分に言い聞かせて、また仕事に戻る。司法書士は、不安と戦う職業なのかもしれない。だけど、その戦い方は、自分で選んでいける。眠れない夜を経験するたびに、そう思えるようになってきた。