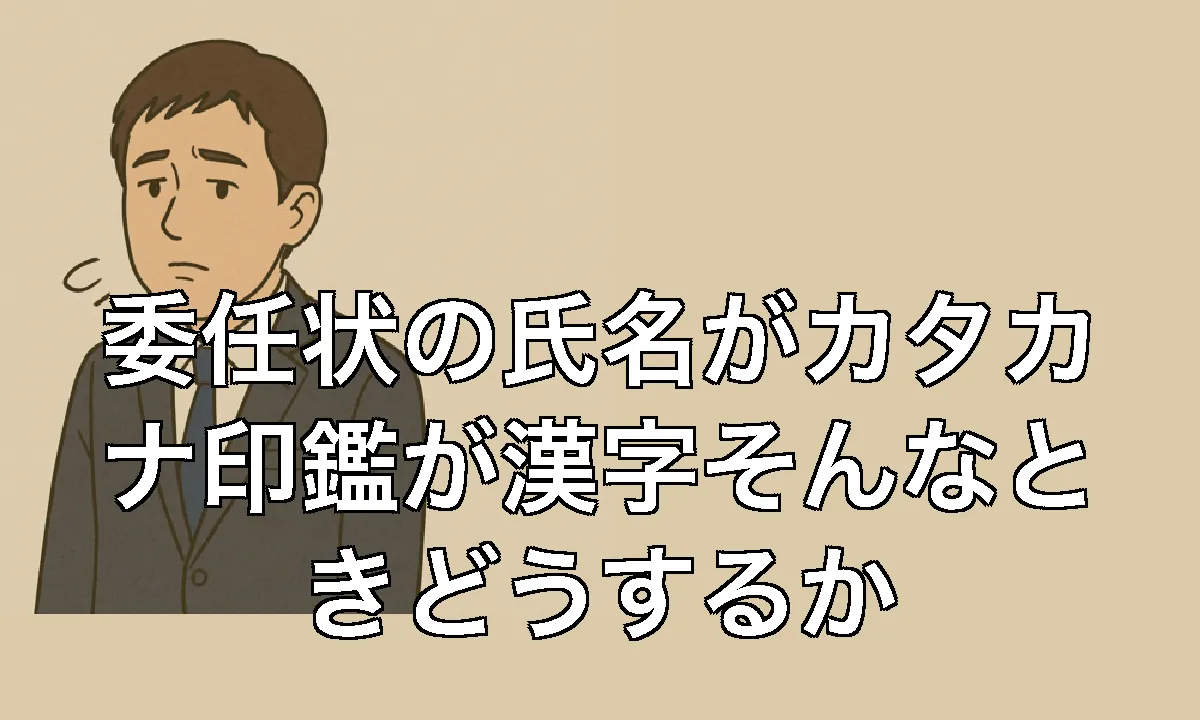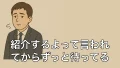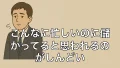委任状に違和感を覚えた瞬間
委任状を確認していると、ふと目にとまった「氏名:ヤマダタロウ」というカタカナ表記。それ自体はたまに見かけるのですが、そのすぐ下に押された印鑑は「山田太郎」としっかり漢字。あれ?と一瞬手が止まりました。おかしいとまでは言えない。でも、なんだか違和感。こういう細かいところ、誰も指摘しないけれど、登記の現場では後々モヤモヤの種になることがあるんです。書類に違和感があるときって、大体が後で「やっぱり…」となることが多いので、つい慎重になってしまいます。特に自分一人で判断するとなると、余計に悩みます。
カタカナ氏名と漢字印鑑の組み合わせ
漢字で書かれている印鑑の印影と、カタカナで書かれた委任者の氏名。この組み合わせ、実は珍しくはありません。特に高齢者の方や、海外在住で日本語に慣れていない依頼者だと「カタカナのほうが親切だと思って」と言われることもあります。親切心で書いているのはわかるんですが、司法書士からすれば、そこに整合性の欠如を感じてしまうんですよね。役所によってはスルーされることもあるし、逆に細かく突っ込まれることもある。だから結局、我々がどこまでOKと見るかが問われてしまうんです。
初見では見逃しがちな書類のズレ
この「カタカナと漢字の不一致」、初めて見たときは何も感じずに提出してしまったことがあります。そのときはたまたま補正にもならず、スルッと通ってしまいました。でも数年後、別の法務局で「氏名の表記と印鑑の一致がとれていないので補正を」と指摘されてからは、すっかり慎重になりました。見逃したって誰も怒りはしないけれど、後で依頼者から「何でそんなことに?」と責められると、自分の不注意を悔やむばかりです。小さな違和感、やっぱり見逃しちゃいけないなと思い知らされました。
なぜこんな表記になるのか依頼人事情
よくよく聞いてみると、「うちはずっとこうしてる」と言う方も多いです。たとえば商売をしていて名刺がカタカナだったり、子どものころから通称で書類を出していたり。中には「漢字だと間違えられるからあえてカタカナで」とか、「本人が書けないから家族が代筆した」といった事情もありました。事情はわかります。ただ、それをそのまま委任状に書かれると、我々としてはどこかで整合性を取る必要が出てくる。まるで書類のパズルを解いているような感覚になります。
司法書士としてどう対応するべきか
司法書士って、誰かに明確な答えをもらえる職業ではありません。結局のところ、自分で判断しなければいけない場面が多い。今回のような書類の違和感も、「補正するべきか」「そのまま出してみるか」で毎回悩みます。事務員に相談しても「先生の判断で」と言われ、法務局に問い合わせれば「そちらの判断で」と返される。何なんだこの無限ループは……と正直疲れます。でも、その判断が登記の成否を分ける。やっぱり責任重いですよね。
補正の判断はどこで線を引くか
一番悩むのが、「これはアウトかセーフか」という微妙なライン。明らかに違えば補正をかけるし、明らかに問題なければそのまま出せる。でも、今回のようなグレーゾーンは本当に判断に困ります。過去に補正になったことを思い出して「念のため直してもらおう」と言えば、依頼者に嫌な顔をされる。「前もこれで通ったんだけど」と言われると、もう何も言えなくなる。だから私は最近「リスクはありますがこのまま出してみましょうか」と、若干逃げ腰な提案をするようになってしまいました。
補正を求めるかそのまま通すかの葛藤
正直なところ、補正を求めるという行為自体がしんどいんです。手間もかかるし、依頼者に説明するのも面倒。それに「おたく厳しいね」と思われるのも嫌だし、事務員に二度手間を強いるのも心苦しい。だからといってそのまま出して補正になると、こっちの責任。だったら初めから補正しときゃよかったってなるんですが、そんなの結果論ですしね。いっそ「全部AIが判断してくれたらいいのに」と思ったこともありますが、それはそれで別のストレスがありそうです。
役所ごとのスタンスの違い
同じような書類でも、法務局によって判断が違うのが本当に厄介です。ある局ではスルーされたのに、別の局では「これは認められません」とばっさり。毎回どこで提出するかを意識しながら書類を整えるって、けっこう神経を使います。昔、隣県の法務局で出したとき「え、こんなの初めて見た」と言われた経験があって、それ以来、提出先ごとのクセをメモするようになりました。でもそんな情報、どこにも載ってないし教えてもくれない。ほんと、地味に疲れる仕事です。
事務員とのやりとりも地味に疲れる
一人でやってた頃は、「相談できる人がいればな」と思ってました。でもいざ事務員を雇ってみると、これはこれで別の疲れが出てきます。特に書類の細かいチェックに関して、「先生、これ変じゃないですか?」と言われると、「あーまたか」と思いつつ、内心ちょっとムッとしてしまう自分もいて。悪気がないのは分かってるんです。でも、全部俺が判断しなきゃいけないのかという気持ちがどこかにある。責任が分散しないって、地味にストレスですよね。
「これ変じゃないですか?」の一言に感じるプレッシャー
事務員からのその一言、たったそれだけの言葉なのに、妙にプレッシャーを感じることがあります。たぶん、自分がその違和感に気づいてなかったという恥ずかしさもあるし、そこで対応を誤ると全体の信用問題にも関わってくる。そう思うと、「うん、そうだね、ありがとう」と言いながらも、内心では「もう勘弁してくれ」と思ってしまうこともあるんです。でも、そういう感覚を持てるだけマシかもしれないとも思ってます。油断しないという意味では、事務員の存在に救われている部分も大きい。
誰が責任を負うのか曖昧な場面
書類の整合性でミスが起きたとき、「これは誰の責任なのか」という話になります。事務員がミスを見落としたとしても、結局は司法書士の責任になる。逆に、司法書士が気づかずに出した場合も同じ。だからこそ、最終確認は必ず自分でやるんですが、それが本当にしんどい。チェックすればするほど、「こんなところまで見なきゃいけないのか」と思ってしまう。でも、誰かに任せて失敗するより、自分で背負ったほうがまだマシ。そんな思いで毎日書類をにらんでいます。
結局こちらが謝る流れになる現実
何か問題が起きたとき、結局謝るのはこっちです。依頼者にしてみれば、「先生に任せてたのに」という思いでしょうし、事務員に責任を押しつけるわけにもいかない。そうするとやっぱり、自分が頭を下げるしかないわけです。たとえそれが相手の記載ミスだったとしても、「気づけなかったこちらにも落ち度がありました」となる。この繰り返しで、少しずつ心がすり減っていく感じがします。でも、それが仕事だと割り切るしかないのかもしれません。
依頼者にどう説明するか
「カタカナの名前と漢字の印鑑、整合性が取れません」とはなかなか言いづらい。依頼者によっては怒り出す人もいますし、「細かすぎる」と反論されることもあります。でも、こちらにも立場がある。だからこそ、言葉選びには気を遣います。やんわりと、でも確実に伝える。これが意外と難しい。正直、説得よりも自分のメンタルを保つほうが大変なんですよね。
違和感を伝える言葉選びの難しさ
依頼者に違和感を伝えるとき、「ここが変です」とは言えません。「念のためご確認を」や「場合によっては補正になることも」など、あいまいな表現で逃げることも多いです。でもそれが逆に「わかりにくい」と思われてしまうことも。過去に一度、「もっとはっきり言ってくれなきゃ困る」と怒られたことがあって、それ以来少しずつ伝え方を見直すようになりました。今でも正解はわからないままですが、とにかく場数を踏むしかないのかもしれません。
気を悪くさせない表現を探して
一番避けたいのは、依頼者を怒らせることです。特に年配の方やプライドの高い方だと、些細な指摘でもカチンとくることがあります。そういうときは、あえて「役所の方針が最近厳しくて…」と第三者を引き合いに出すようにしています。自分が悪者にならないようにするのも、ある意味では技術です。信頼関係があれば正直に話しても問題ありませんが、初対面だとやっぱり気を遣いますね。
過剰に説明して墓穴を掘ったことも
逆に、あまりに丁寧に説明しすぎて、「だったら先生が直せばいいじゃないですか」と返されたこともあります。それ以来、過剰に話しすぎないようにも気をつけるようになりました。説明は必要。でも説明しすぎてもダメ。そのバランス感覚を掴むのが本当に難しいんです。経験だけが頼り。だからこそ、こういう経験談を共有する意味があるんじゃないかなと思っています。
結局どう処理したのか
今回のカタカナと漢字の件、結局は「このまま出してみます」という形で提出しました。結果的には通りました。でも、心の中にはずっとモヤモヤが残ったまま。本当にこれでよかったのか。今でもたまに思い出してしまいます。たぶんこの仕事に「完璧な判断」なんて存在しないんですよね。ただ、少しでもリスクを減らして、納得できる判断を積み重ねるしかない。それが今の僕の答えです。
自分なりの判断基準を持つことの重要性
誰も答えを教えてくれない以上、自分の中で「これは大丈夫」「これは危ない」というラインを作っていくしかありません。たとえば今回のような表記のズレも、過去の経験と照らし合わせて判断する。失敗もあります。でも、その失敗が次の判断の基準になる。積み重ねていくしかない。だからこそ、この仕事には「ベテランの勘」みたいなものが必要なんだと思います。
ミスにしない工夫と覚悟
結局、どんな判断をしても「ミスにならないように」工夫することが一番大事。補足説明を加える、メモを残す、事務員と共有する、いろんな手を打つようになりました。そして、最後は「それでもダメだったら自分が謝るしかない」という覚悟も持つ。そこまでしてやっと、安心して提出ボタンが押せる。そんな世界で僕らは仕事をしています。たぶん普通の人には想像できないかもしれませんね。
一人事務所の孤独な最終判断
最終的に決断を下すのは自分。事務員は助けてくれるけど、責任は取ってくれない。相談できる同業者もいないわけじゃないけど、案件ごとに聞けるほど暇じゃない。結局、机の前で一人うーんと唸りながら、書類をにらむ日々。孤独です。正直、たまに全部投げ出したくなるときもあります。それでもなんとか続けてるのは、少しでも誰かの役に立ててる実感があるからかもしれません。