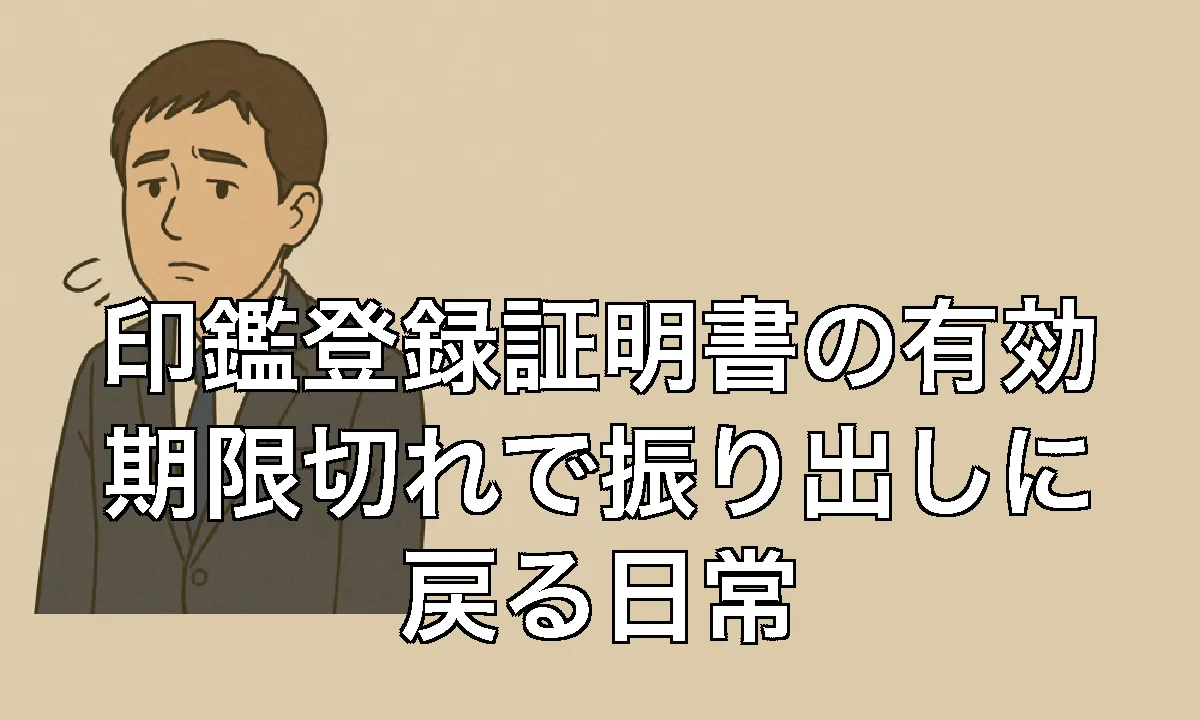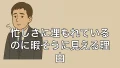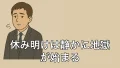忘れてた僕が悪いそれはわかってるけど
人は誰しもうっかりするものだ。けれど、司法書士という仕事はその「うっかり」が命取りになる。ある日、依頼者からの依頼で印鑑登録証明書を使う場面があった。用意していたつもりだった。机の引き出しから取り出した証明書を持って窓口に向かうと、職員の方が困った顔でこう言った。「こちら、有効期限が切れてますね」。耳を疑った。印鑑登録証明書にそんな期限があるなんて聞いたことがなかった。すべての予定が狂った瞬間だった。
期限があると知らなかった印鑑登録証明書
正直に言えば、印鑑登録証明書に有効期限があるなんて、45歳にして初めて知った。恥ずかしい話だが、これまで何度も使ってきた中で、期限切れに当たったことがなかったのだ。たまたま運が良かっただけなのだろう。今回は運が尽きた。期限が切れた証明書はただの紙切れで、役所では一切受け付けてもらえない。再登録をし、再度発行手続きを行わなければならない。依頼者には頭を下げて、日程を調整し直す。穴があったら入りたかった。
窓口で告げられた衝撃のひと言
「この証明書、もう期限切れてますね」——窓口でその一言を聞いた瞬間、体中の血の気が引いた。印鑑登録証明書って、無期限だと勝手に思い込んでいたんだ。そもそもそんなこと、誰にも教わってない。市町村によって扱いが違うとはいえ、そういう大事なこと、もっと強調して書いておいてくれればいいのに、と心の中で毒づいた。けれど、怒る相手なんていない。結局、自分の確認不足。ただただ恥ずかしい。
まさかの再登録からのスタートライン
印鑑登録証明書の再発行だけで済むと思ったのが甘かった。そもそも印鑑の登録自体が失効していた。つまり、再登録からやり直し。役所に印鑑を持って行って、身分証明書を提示して、新規登録。その後、証明書の発行申請。1件の手続きに、ここまで手間がかかるとは。依頼者には再び謝罪。たった1枚の紙がないだけで、スケジュールも信頼も崩れる現実。自分の無知と油断が、こんなにも大きなツケとなって返ってくるとは思わなかった。
印鑑登録証明書が必要なタイミングは急にやってくる
司法書士の業務では、「急に必要になるもの」が多い。その中でも、印鑑登録証明書はまさにその代表格だ。土地の売買契約、金融機関との取引、相続手続き…。依頼者から「今日中にお願いします」と言われることもざらだ。準備が間に合っていないと、致命的なミスにつながる。今回の件で、自分の「大丈夫だろう」という油断がどれほど危うかったかを痛感した。備えていても、備えすぎることはないのだ。
売買契約と決済日が迫るなかでのミス
今回の証明書のミスが発覚したのは、土地の売買契約の前日だった。依頼者も、不動産会社も、金融機関もスケジュールを固めていた。キャンセルできるような日程ではなかった。それなのに、こちらの手配ミスで証明書が使えない。再発行には最低1日かかる。つまり、スケジュールは崩壊。依頼者に連絡を入れた瞬間、電話口の空気が凍ったのがわかった。「ああ、信頼を失ったな」と、あきらめにも似た感情が胸に湧いた。
依頼者の信頼にヒビが入る音がした
人は一度のミスで信頼を失う。今回、それをまざまざと実感した。「次回もお願いしたい」と言われていた依頼者からの信頼。それが一枚の証明書で崩れていった。誠意をもって謝罪し、代替案も提案した。結果的に大きなトラブルにはならなかったが、「またお願いしたい」とは言われなかった。仕事って、こういう一つ一つの積み重ねなんだよなと、改めて痛感した。反省と後悔だけが残る1日だった。
書類は完璧でも証明書一枚で崩れる仕事
何十枚とある契約書類は完璧に仕上げていた。それでも、印鑑登録証明書一枚の不備で、すべてがやり直しになる。この仕事の厳しさ、繊細さを思い知るには十分だった。司法書士という職業は、見えない部分で地味に重要なものを扱っている。その中で、少しの油断が全体を崩す。努力が報われない、なんとも切ない仕事だ。それでも誰かがやらなければならない、と思ってはいるが、今日はちょっとやりきれない。
司法書士という職業の繊細すぎる現実
依頼者から見れば、司法書士は「書類のプロ」だと思われている。事実、そうでなければならない。でも実際は、書類の種類も期限も地域によって微妙に違うし、役所の対応もバラバラだ。そのすべてを把握しながら、失敗ゼロでこなすことが求められる。プレッシャーは常にある。でも、「これくらいは大丈夫だろう」と思った瞬間に落とし穴がある。今回の件で、自分はまだまだ未熟だと痛感した。
「これだけはお願いします」と言われた書類がこれ
依頼者からは、こう言われていた。「印鑑登録証明書だけは、間違いなくお願いします」と。その一言が、今でも頭の中でリピートされる。よりによって、それをミスした。自分を責める以外にできることはなかった。仕事としては一つのミス。でも、人としての信用としては、取り返しがつかないかもしれない。そう思うと、胃がキリキリ痛んだ。完璧を目指しても、ヒューマンエラーは避けられない。だが、言い訳にはならない。
事務員にも責任をかぶせられずひとり反省会
正直、事務員も一緒に確認していた。でも、責任を問うつもりはない。最終的にチェックして、持って行ったのは自分だ。彼女は一生懸命やってくれているし、これで責めたら職場の空気が悪くなるだけだ。だから一人で反省会。夜中にコンビニで買ったビールと、期限切れの証明書を見つめながら、「なんでこんなことになったんだろうな」と独り言をつぶやいた。誰にも聞かれない反省の時間が一番堪える。
「そんなの誰も教えてくれないよ」という本音
こういうミスって、誰かに教わるものでもなければ、教える側もなかなか気づかない。マニュアルにも書いてないし、先輩から引き継がれることもない。だからこそ、こうやって誰かが失敗して、それを共有することに意味があるのかもしれない。自分のミスが、他の誰かのミスを防ぐきっかけになれば…そんなふうに思えるようになったのは、だいぶ後の話だけれど。
マニュアルにも書いてない抜け落ちポイント
事務所にある業務マニュアルを改めて見直したけれど、印鑑登録証明書の有効期限についての記載は一切なかった。つまり、これは「知っているかどうか」で決まる知識。実務に入って初めて痛感する、そういう細かい落とし穴がたくさんある。完璧なマニュアルなんて作れないし、だからこそ現場の気づきを積み上げるしかない。うちのマニュアルにも、この件はしっかり追記しておいた。
気をつけてるつもりの人が一番やられる罠
実は、私は「細かいところに気がつくタイプ」だと思っていた。自分で言うのもなんだけど、書類のチェックには自信があった。でも、そんな自分がこうして見落とす。つまり、気をつけてる人こそ油断してやられる。プロ意識と過信は紙一重。その違いを見誤らないようにしなければならない。この出来事は、自分の中にある「自信」の部分を、一度リセットする良いきっかけになった。
失敗したからこそ覚えられたこと
今回の件は、正直なところ恥ずかしくて情けなくて、誰にも話したくなかった。でも、こうして言葉にしてみると、「これは大事な経験だったのかもしれない」と思えてきた。同じ失敗を繰り返さないために、記録として残す。そして、誰かがこの記事を読んで「自分も気をつけよう」と思ってくれたら、それでこの失敗にも意味があったと言える。いつか笑って話せるようになりたい。
次に同じミスをしないための備忘録
私は、すぐに「証明書管理リスト」を作成した。どの依頼で、どの証明書が必要か。誰が用意し、誰が確認し、いつ取得したか。そして、有効期限。Excelで作った簡単な表だが、これがあるだけで精神的にずいぶん楽になる。仕組みを作れば、人の記憶に頼らずに済む。忙しい日常の中では、こういう仕組みが何よりの保険になるのだと、今はしみじみ思う。
期限管理に必要なのは仕組みと余裕
「確認すればいいだけでしょ?」と言われるかもしれない。でも、日々の業務は予想以上に詰まっている。1件確認する時間さえ惜しい時もある。だからこそ、仕組みが要る。そして、時間的な余裕。ギリギリのスケジュールでは、どんな仕組みも機能しない。ミスを減らすには、時間のゆとりと心の余白が必要。それを確保するのが難しいのも、司法書士のリアルなのだけれど。
小さな失敗は共有して初めて意味がある
失敗は、ひとりで抱え込んでもただのストレスになる。でも、言葉にして誰かと共有すれば、それは「経験」と呼べるようになる。この記事を読んで、「あ、自分もやりそう」と思ってもらえたら、それだけで救われる気がする。同業の誰かが、同じようなことでつまずかずに済んだら、それが一番うれしい。ミスを語れる空気があること、それこそがチームや業界の強さなんじゃないかと思う。