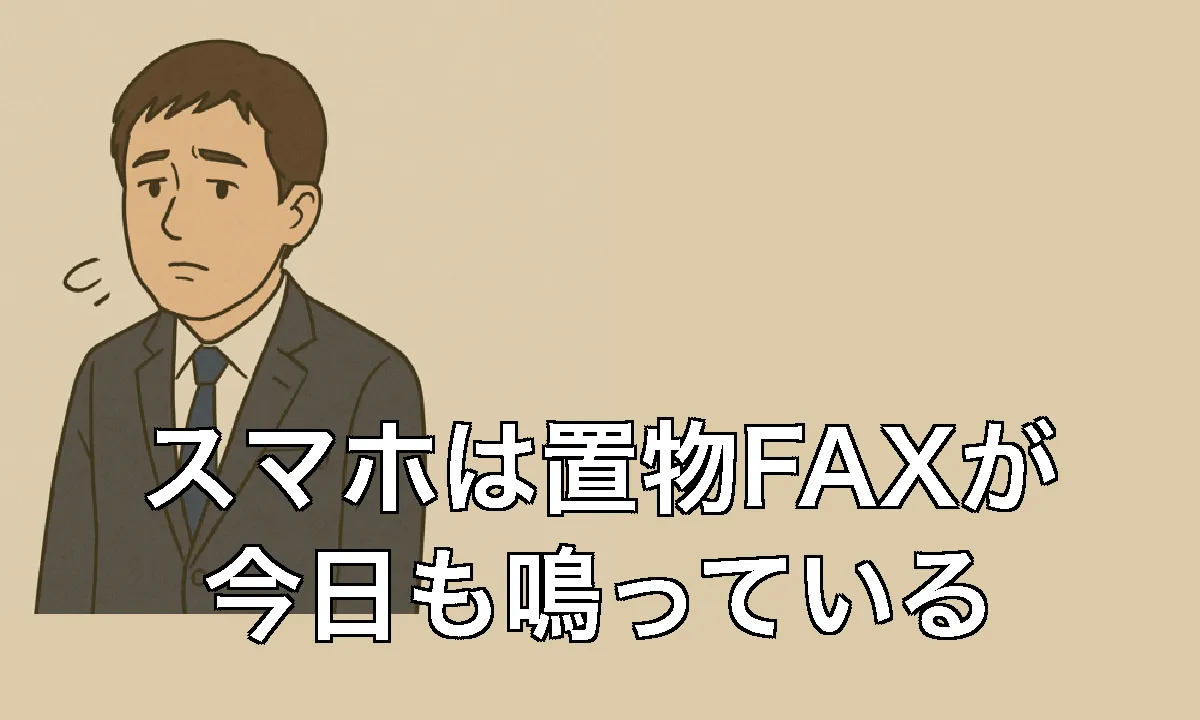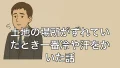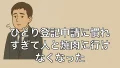スマホが役に立たない仕事の現場
朝、机の上に置かれたスマホを一瞥する。通知ゼロ。LINEもメールも何もない。なのに、横にあるFAXの受信ランプがピカピカと光る。まるで「こっちが本命だ」と言わんばかりに。司法書士の現場では、いまだにFAXが主力通信手段だ。これは田舎だけの話じゃないと思いたい。どうしてこんなにもデジタル化が進まないのか。理由はいくつかあるが、まず第一に、こちらの都合だけではどうにもならないのがこの業界だ。
なぜかFAXばかり届くという現実
例えば不動産屋さん、金融機関、行政書士さん。こちらがメールをお願いしても、戻ってくるのはFAX。添付ファイルをPDFで送るのは簡単なはずなのに、「プリントしてFAXで送っときました」とのこと。いや、ありがたいんですけどね。でもそれ、こっちが再度スキャンして保存するんですよ。業務の効率とか考えるとどうにも腑に落ちない。でも、業界の「慣習」という壁は厚くて高い。
顧客のITリテラシーは思った以上に低い
うちの事務所に来るお客様の中には、スマホを持っていても「メールはわからない」という方が少なくない。電話で住所を聞いて、こちらで書類を作って、印刷して、郵送。返信はFAXか直接持参。クラウドサイン?オンライン面談?都市伝説かなにかかと思っているんじゃないか。いや、わかります。高齢の方が多いこの地域では、それが現実なんです。
メールですら返信がないのにFAXは確実
実際、メールを送っても「届いてない」と言われることが多い。迷惑メールフォルダに入ってたり、開いてなかったり。でもFAXは違う。ピーヒョロロ…と音が鳴れば、紙がにゅっと出てくる。それを手に取って、「あ、来たんだな」と確認できる安心感。だから結局、こっちも「とりあえずFAX送っときますね」と言うようになってしまう。スマホは通知すら来ないのに、FAXは今日も仕事している。
通知が来ないスマホとにらめっこ
気づけばスマホをただの時計として使っている自分がいる。時間確認、たまに天気アプリ。電話は滅多に鳴らない。LINEの通知?ゼロですよ、ゼロ。これは業務用としても、個人用としても。結婚の予定もなければ、デートの約束もない。スマホが鳴らないのは、仕事のせいだけじゃないことには、もう気づいています。
鳴ることのないLINEの着信音
あの「ポーン」というLINEの着信音、最後に聞いたのはいつだろう。せいぜい、知り合いの司法書士が「あの案件どうなった?」と聞いてきたくらい。それだって半年ぶり。友達グループも無縁。世間では「スマホ依存」なんて言葉もあるけど、こっちは逆。スマホなんて、机の上で文鎮化している。昔の野球部時代、携帯を持つだけで浮かれていた自分が懐かしい。
人と繋がってないのはデバイスのせいじゃない
スマホが悪いわけじゃない。繋がりが少ないのは、こっちの問題だと自覚はしている。仕事漬けで人付き合いもろくにしてこなかった。同級生とも疎遠、婚活ももう面倒臭い。事務所と家を往復するだけの生活。だからこそ、FAXの「ピーヒョロロ」が鳴ると少しだけ安心する。ああ、自分はまだ社会と繋がってるんだなって。
紙の山と格闘する日々
FAXで届いた書類はプリントアウトされ、机の上に積み重なっていく。どんどん高くなる紙の山。デジタル保存しようと努力はしている。でも、「元の紙がないと不安」という気持ちが抜けきれない。結局、紙もPDFも両方保存。非効率極まりないのに、変えられない。これが現場の現実であり、地方司法書士の葛藤でもある。
結局、紙で処理するのが一番早い
クライアントから「この書類、手書きでお願いします」と言われるたびに、タイムスリップした気分になる。パソコンで打って、プリントして、手で書き足して、印鑑押して…そんなことをしているうちに一日が終わる。パソコンに入力する時間と、紙に書く時間、両方必要ってどういうことだろう。効率化を目指しているはずが、作業は増えていく一方。せめてどっちかに統一してくれ、と願う日々。
印鑑を押す快感と責任の重さ
ただ、印鑑を押す瞬間だけは少しだけ誇らしい。「これでこの人の人生が少し進むんだな」と思える。でもその分、間違いは許されないという重圧も大きい。押したあとに「間違ってた」と気づいた時のあの血の気の引く感覚。あれは何年やっても慣れない。だから余計に紙を何度も確認する癖がつく。スマホの画面だけで済ませるなんて、今の自分にはまだまだ無理だ。
時代に取り残された感覚との付き合い方
たまにネット記事で「司法書士業界もDX化が進んでいる」なんて見出しを見ると、別の国の話かなと思う。実感はまったくない。むしろ、こっちはFAXにしがみついて毎日を乗り切っている。「効率」より「安心感」、それがこの世界の空気だ。時代に逆行している自覚はある。でも、それを笑える余裕くらいは、残しておきたい。
デジタル化の波に乗れないまま45歳
若い頃は「40代にはスマートな仕事してるだろう」と思っていた。ところが現実は、紙に囲まれた地味で泥臭い毎日。スマホを活用するどころか、むしろ放置。せいぜい事務員さんが使い方を教えてくれる程度。ああ、昔は「ITが得意」と言ってた自分、どこ行ったんだろう。でも不思議と、そこに焦りはない。むしろ、FAXという「慣れ親しんだ道具」に安心してる自分がいる。
スマホを活かすよりFAXを信じる理由
FAXは、裏切らない。送信音が聞こえ、相手に届いたのを紙で確認できる。アナログだけど、確実だ。スマホやクラウドには不安が残る。「どこかでエラーが起きてるかも」「見落としてるかも」と思ってしまう。だからFAXのピーヒョロロは、今日も信頼できる音として耳に残る。新しい道具を使いこなせないのではなく、信じきれないだけなのかもしれない。
ひとり事務所の孤独と救い
この仕事、基本的に孤独だ。誰かと一緒に進めるというより、自分の責任で完結させる世界。事務員さんはいるけれど、基本的には別業務。雑談も少ない。そんな中、FAXの受信音や送信音は、妙に心の支えになる。誰かと繋がっている、仕事が動いている、そんな実感を与えてくれる。ただの機械なのに、ちょっとした相棒のように感じる日もある。
事務員さんとの会話が唯一の会話
一日中、事務員さん以外と口を利かない日もある。彼女がいなかったら、声の出し方すら忘れるかもしれない。昼に交わすちょっとした会話や、書類の確認を通して、「誰かと働いている」という感覚が保たれる。でも、その彼女に「スマホもっと使えばいいのに」と言われたときは、何も言い返せなかった。使わないんじゃない。使う相手がいないんだ。
人とのつながりをFAXがつないでいる
昔は「LINEグループ」とか「Slack」とか、羨ましいと思っていた。今ではもう、そこに入っていく気力もない。でも、FAXのやり取りには不思議な「文通感」がある。手書きのメモや、独特のフォーマットに、その人らしさがにじみ出る。どこかアナログな温かみがあるのだ。だからきっと、今日もFAXを待ってしまう。スマホの通知は来ないけど、FAXは今日も鳴ってくれる。