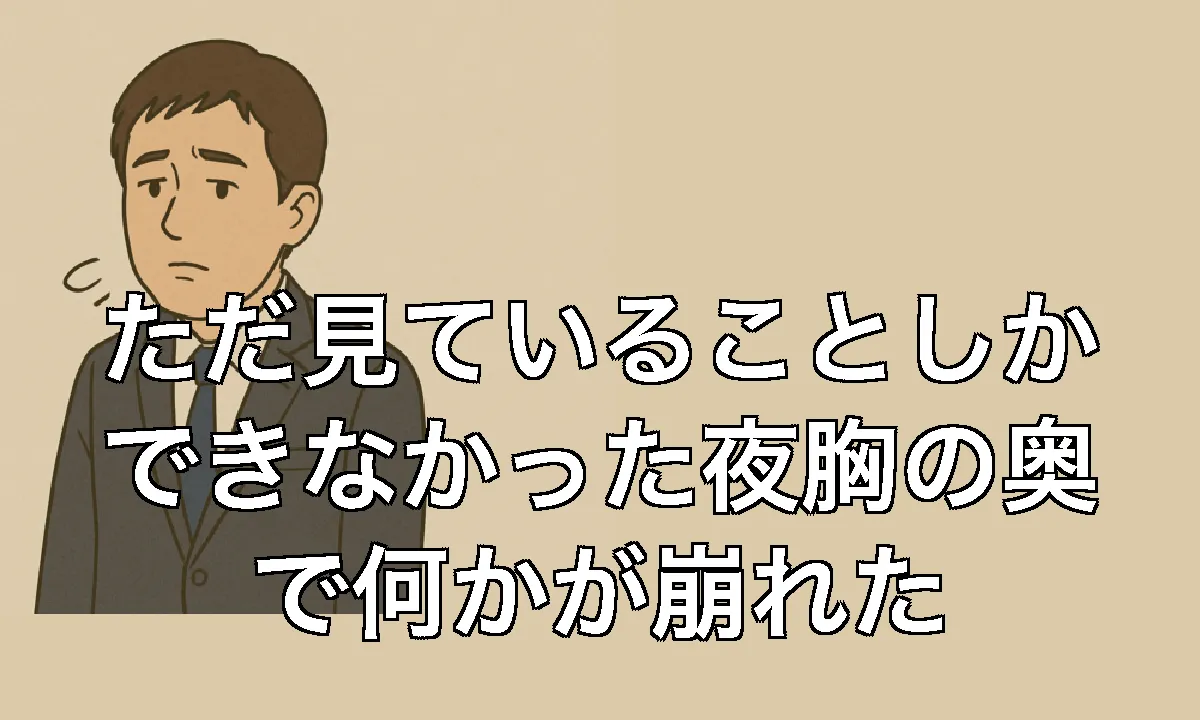相談を受ける立場としての限界を感じた日
司法書士として相談を受ける立場にいると、「何とかしてあげたい」という気持ちが常につきまとう。だけど、どうにもできないこともある。それが人間関係のもつれだったり、家族の問題だったり、法の範囲を超えたところに根っこがある話だったとき、僕はただ話を聞くことしかできない。ある夜、相談者の目に浮かぶ涙を前にして、心のどこかで「自分は無力だ」と強く思わされた。あの夜は、ただの悔しさではなく、胸の奥から何かが音を立てて崩れるような感覚があった。
頼られているのに何もできない現実
相談者は中年の女性だった。夫が遺言も残さず突然亡くなり、相続の件で親族間に激しい争いが起きているという。僕にできるのは登記の手続きだけ。それ以外は弁護士や調停の範囲になる。彼女の話を聞きながら、「どうにかしてこの人を助けたい」と思う自分と、「それは自分の役割ではない」という現実の板挟みに苦しんだ。
聞くことはできても解決できないもどかしさ
話を聞いて、共感して、うなずいて、それで何が変わるんだろう。そんな無力感に襲われたのは、あの夜が初めてではなかった。でも、その日はとくに重かった。事務所の灯りを落としても、胸の中に重石のような感情が残っていた。助けられなかったという罪悪感なのか、それとも無力な自分への怒りなのか、自分でもよくわからなかった。
元野球部の根性論が通用しない瞬間
学生時代、野球部では「気合いで乗り越えろ」が口癖だった。だけど、社会に出てからの困難には、気合いではどうにもならない場面が多すぎる。努力だけでは解決しない問題に直面すると、精神論が通用しないことを痛感する。あの夜もそうだった。「もっと強くなれよ」と自分に言い聞かせても、強くなったところで変えられない現実がそこにあった。
どうすればよかったのか自問自答の夜
家に帰っても頭の中がぐるぐるしていた。あの時、ああ言えばよかったのか。もっと違う提案ができたのか。だけど考えれば考えるほど、法の枠を越えることはできない自分に気づく。そして、そんな自分を責める癖がまた出てきて、気づけば深夜2時を回っていた。電気も消せずにベッドの上でただ天井を見つめていた。
自分を責める癖がまた始まる
昔からそうだった。何かうまくいかないと、自分のせいだと思い込む。努力不足だったのでは、知識が足りなかったのでは、人間性に問題があるのでは。そんな考えが延々と頭の中をループする。人を責めるよりも、自分を責める方が楽なんだろう。だけどそれは、結局何の解決にもならないということも知っている。
眠れぬ夜に仕事の意味を見失う
相談を受けることに、意味はあるのだろうか。そんな考えすら浮かんだ夜だった。相続や登記の手続きを通じて、依頼者の人生の一部に関わるこの仕事。でも、何もしてあげられなかったと感じる瞬間に、自分の存在意義が崩れそうになる。眠れぬ夜に布団の中で、何のためにこの仕事をしているのか、答えが見えなくなることもある。
事務員の前では強がったけれど
翌朝、いつも通り事務所に出ると、事務員の彼女が「先生、大丈夫ですか?」と声をかけてきた。何でもないようなふりをして「全然平気だよ」と笑って返したけど、本当はぜんぜん平気じゃなかった。事務員にまで心配されるようじゃ、頼れるボスとは言えない。そう思って、余計に強がってしまった。
大丈夫ですの裏側にある不安
「大丈夫です」って言葉、僕は何回使ってきただろう。けれどその多くは、本当は大丈夫じゃないときだった。人に弱みを見せるのが苦手だ。特に女性の前では、どうしても格好つけてしまう。情けない話だけど、それがモテない理由なのかもしれない。素直に「しんどい」と言えたら、もっと人間らしく見えるのかもしれないのに。
孤独な経営者の仮面
経営者って、どこか「強くあらねば」みたいな仮面をかぶってしまう。特に一人事務所でやっていると、誰かに頼ることがどんどん難しくなる。弱さを見せると、信頼まで失いそうな気がする。でも、そうやって抱え込むから、心の負担がどんどん積もっていくんだろう。時々、その仮面を脱ぎたくなる瞬間がある。
気づかれたくない疲れと焦り
仕事が重なると、焦りが出る。焦りが出ると、疲れがたまる。そしてその疲れを誰にも見せたくない。だけど、人間そんなに器用じゃない。目の下のクマも、口数の少なさも、事務員はきっと気づいているんだろう。けれどそれを指摘するでもなく、黙ってお茶を出してくれる彼女の気遣いに、心がジワっと温かくなる。
誰にも相談できない職業の苦しさ
司法書士って、何でも知っていて、何でもこなせると思われがちだ。でも、現実はそんな万能な存在じゃない。僕たちも悩むし、迷うし、泣きたくなる日もある。でも、相談できる相手がいない。仲間がいないわけじゃないけれど、変なプライドが邪魔をしてしまう。誰かに「実はしんどくてさ」と言えたら、どれだけ救われるだろう。
専門職だからこその孤立
専門職の宿命だろうか、どこか「一人で完結する」ことを求められる空気がある。だからこそ、同じ業界の人と本音で話す機会って本当に少ない。失敗談も、弱音も、なかなか口に出せない。でも、それが余計に孤独を深めてしまう。肩の荷を少しでも下ろせる場があったら、もっと楽になれるのにと思うことがある。
モテない自分がモテない理由
そりゃあモテないわけだ、とふと思う。こんなに弱音を抱えていて、それを一人で抱え込んでいるようじゃ、人として魅力的に見えるはずがない。元野球部のノリで、なんとなく明るく振る舞っているけれど、それも見透かされているんだろうな。だからこそ、誰かに本音を見せられるような人間になりたいと思う。
崩れかけた心を支えたのは意外な一言
その週の終わり、ふとしたタイミングで事務員が言った。「先生、いつも本当に頑張ってますよね」。その言葉に、不意に涙が出そうになった。別に泣くような話じゃないのに。けれど、誰かがちゃんと見ていてくれていたことが、何よりも救いだった。崩れそうだった心の支えになったのは、何気ないその一言だった。
事務員の何気ない言葉に救われた
僕は感謝の言葉をうまく伝えられない。けれど、この時ばかりは「ありがとう」と素直に言えた。それだけで、少しだけ自分を許せた気がした。人間って、たった一言で持ち直すこともあるんだなと実感した瞬間だった。やっぱり、誰かがそばにいてくれることって、大きい。
気づけば涙がこぼれていた
その夜、また遅くまで残業していた帰り道、なぜか涙が止まらなかった。嬉しいのか、情けないのか、自分でもわからなかったけれど、とにかく泣いた。そして泣いたことで、少しだけ前を向けた気がした。やっぱり、自分はまだこの仕事を続けていける。そう思えたのは、誰かが見ていてくれるからだった。
過去の自分が背中を押してくれた
帰宅後、ふと昔の写真を見た。野球部のユニフォーム姿の自分。あの頃は「絶対に諦めない」と目をギラつかせていた。今の僕はどうだろうか。あの目をしたままでいられているだろうか。悔しさを噛みしめる夜もあるけど、諦めずに立ち上がる自分でありたい。そう思わせてくれたのは、過去の自分だった。
あの日のグラウンドの景色を思い出す
汗と土にまみれて白球を追いかけていた日々。声が枯れるまで叫び、泥だらけになりながらも、勝利を信じて走り続けた。あの頃の僕が、今の僕にこう言う。「お前なら、まだやれる」。そう信じて、また明日も依頼者と向き合う。例え何もできない夜があっても、それでも僕は司法書士として生きていく。