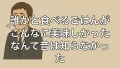職印を押すたびに感じる心の重さ
登記簿に印を押す瞬間、カチリという音が事務所に響く。その音が、時に心の深くに沈み込む。書類上は完璧に整っていても、なぜか自分の中にぽっかりと穴が空いているような感覚。判を押せば仕事が一区切りするはずなのに、そのたびに心の重さが増していく。事務所の静けさが、それをさらに強調する。
ハンコの重さより心が沈む日々
実際の職印はせいぜい100グラムにも満たないはずだが、夕方になるとその小さな印鑑がやたらと重たく感じる日がある。理由は単純だ。話し相手もおらず、昼休憩も1人。朝から晩まで誰かの手続きばかりを処理していると、自分の存在が事務作業の一部になってしまった気がしてくる。無機質な仕事に、心がついていかない。
書類は片付くのに心はどんどん散らかっていく
登記申請書や戸籍謄本は整理整頓できても、気持ちは整理がつかない。時間が経つにつれて、「このままでいいのか?」という思いがモヤのように積もっていく。ひとつひとつ片づけているのに、なぜか自分の中にはずっと散らかったままの何かがある。その感覚が、判を押す手をほんの少し鈍らせる。
判を押す音が空しく響く理由
誰にも気づかれないが、押印の音がやけに大きく感じることがある。朝から誰とも会話を交わしていない日に限って、音が耳に刺さるように響く。まるで「ここに私はいる」と自分自身に知らせているような錯覚。その音の先には誰もいない。ただ机の上に積まれた書類と、いつもと変わらない壁だけだ。
忙しさにまぎれて誤魔化す孤独
「忙しいのはいいことだよ」とはよく言われるけれど、それが本当に心を救ってくれるかというと、そうでもない。作業に没頭している間は、確かに孤独を忘れていられる。でも、ふとした瞬間に手が止まったとき、一気にそれが襲ってくる。忙しさで誤魔化しているだけで、本質は何も変わっていない。
毎日のルーティンが心を鈍くする
朝出勤してパソコンを立ち上げ、書類を確認し、郵便物を開封して判子を押す。それが毎日のルーティン。効率よく処理することはできても、心は鈍くなっていく。感情の起伏が少なくなり、嬉しいことも悲しいことも、淡々と通り過ぎていく。ただの「作業員」になってしまった気がしてくる。
会話はあるけど、気持ちは伝わらない
事務員さんとは日常の業務連絡程度の会話はある。でも、それ以上の話はしないし、できない。自分が抱えている感情や迷いを言葉にする勇気もなければ、聞いてもらえる雰囲気もない。会話があっても、それは心の距離を縮めるものではなく、むしろ「一線を引いている」ことを実感させられる瞬間になる。
事務員さんに弱音すら吐けない空気
相手に気を遣ってしまう自分がいる。「忙しいところに愚痴なんて聞かせたくない」と思ってしまい、結果的に何も言えずに終わる。こちらが社長である以上、強がっていなきゃいけない気がして、自分の弱さを見せる場所がどこにもない。そんな気持ちが、孤独にさらに拍車をかけていく。
司法書士という職業の孤独な宿命
専門職として誇りを持って働いている。でも同時に、「専門性」が孤独を生み出しているとも感じる。依頼人は感謝してくれるけれど、仕事の内容を誰かと共有することは少ない。話せば話すほど、「すごいね」で終わってしまう。深く理解してもらうには、あまりにも特殊な仕事すぎる。
専門家ゆえの相談できなさ
相談を受ける立場であるがゆえに、自分のことを相談できる相手がいない。ちょっとした悩みや不安を誰かに話したくても、「プロなんだから大丈夫でしょ」と片づけられてしまう。そう言われると、ますます口を閉ざしてしまう。人には話せない、だけど抱え続ける。それが専門職の孤独だ。
クライアントの悩みばかりを受け取る日々
相続、借金、離婚、登記。人の悩みは複雑で重たい。それを毎日受け取って、淡々と処理していく。こちらが感情を出す余地はない。だからこそ終わったあとにどっと疲れが来る。誰かの人生の断面を見続けながら、自分自身の感情はどこかに置き去りにしている。受け止めきれないものが心に残る。
同業者との距離感がつくる壁
同業の仲間はいる。でも、どこか張り合ってしまうような関係で、本音を言い合える間柄ではない。「忙しいアピール」「案件の多さ自慢」。気づけばそんな空気に飲まれてしまって、本当に苦しいときに「助けて」と言える相手がいない。士業の世界には、妙な孤独が横たわっている。
元野球部だった自分と今の自分
高校時代、毎日泥だらけになって白球を追っていた。あの頃は、つらくても誰かと一緒だった。声を掛け合い、励まし合い、勝っても負けても一緒に泣いて笑った。今は違う。どんな場面でも、基本的には一人。あのチームプレーの温かさが、心の奥で恋しくなるときがある。
仲間と戦ったあの頃の熱量はどこへ
今でもふと、あの土埃の匂いやグラウンドの感触を思い出す。あの時の自分は、試合に出られなくても必死で頑張っていた。誰かが応援してくれたし、自分も誰かを応援していた。今はそんな瞬間がほとんどない。熱量があるのはパソコンのファンくらいで、自分の中はいつもクールダウンしている。
声を掛け合うチームプレーが恋しい
「ナイスカバー!」「次、頼むぞ!」そういう声のやり取りが、どれだけ心を前向きにしていたか。今の仕事にそういう掛け声はない。電話を切っても「よくやったな」と言ってくれる人はいない。そんな小さな声のやりとりが、日々の孤独を打ち消してくれていたことに、今になって気づく。
一人で勝つことに意味があるのか
案件が無事に終わっても、誰かと喜び合うことはない。黙って封筒に書類を詰めて、次の仕事に移るだけ。一人で勝って、一人で終わる。それを積み重ねて何になるんだろう。そんな疑問が、夕方の事務所にぽつんと座る自分の背中に降りてくる。
孤独を少しだけ和らげてくれたもの
そんな中でも、ほんの少しだけ心が軽くなる瞬間がある。それは、誰かのひとことだったり、想定外の優しさだったり、同じように悩んでいる誰かの存在だったり。完全に孤独から解放されるわけじゃないけど、「自分だけじゃない」と思えることが、救いになる。
同じように頑張っている誰かの言葉
ネットで偶然見かけた、同じ士業の方のブログに共感したことがある。「やっぱりみんな、同じようにしんどいんだ」と思えて、少しだけ楽になった。その日から、意識して自分も発信してみようと思うようになった。誰かに届くかはわからないけれど、自分が感じた孤独を、誰かと共有できたらそれでいい。
小さなありがとうに救われる瞬間
「先生、ありがとうございます。本当に助かりました」——そのひとことが、どれほど救いになるか。書類のミスがなかったとか、手続きが早かったとか、そういうことじゃない。自分の存在が誰かの役に立ったことが、心にしみる。「ああ、まだ続けてていいんだな」と思える一瞬。
書類の山の向こうに見える小さな希望
今日も机の上には、山積みの書類。たぶん明日も、明後日もそう。でもその中に、誰かの人生の転機が隠れている。それを支えることが、自分の仕事。孤独だけど、無意味じゃない。そんな小さな希望を見つけながら、また明日も判を押す。