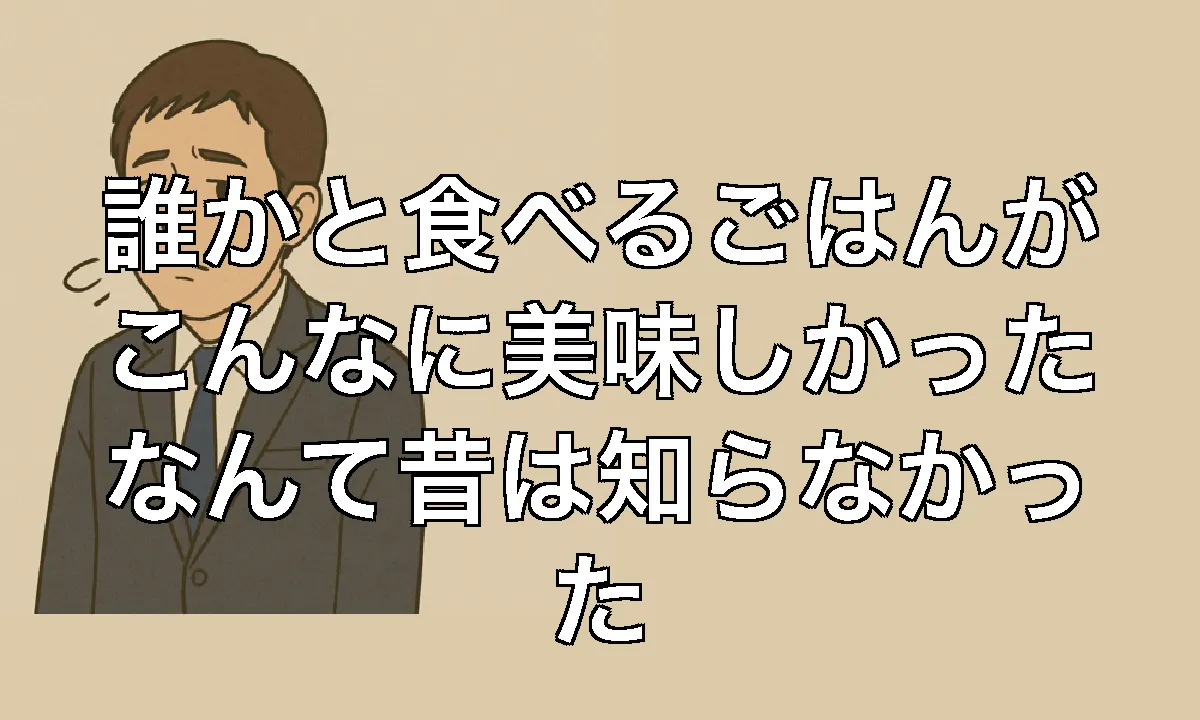あの頃の食卓には温かさがあった
子どもの頃、夕飯時になると家の中に漂ってくる味噌汁の香りが、どこか心を落ち着かせてくれていた。仕事帰りの父が不機嫌そうにテレビをつけ、母はそれを気にする様子もなく「ごはんできたよ」と明るく声をかける。私は宿題を投げ出して、テーブルについた。正直、母の料理はそんなに凝っていなかった。でも、なんていうか、みんなで食べる時間が確かに「ごちそう」だったように思う。
味噌汁の湯気越しに見えた家族の顔
あの湯気は、ただの水蒸気じゃなかった。湯気越しに見える父の顔や、妹が味噌汁の熱さに文句を言ってる様子。そのすべてが、今思えば宝物だったのかもしれない。味の記憶って不思議で、再現しようとしてもできないのに、ふとした拍子に思い出す。今はコンビニで買った味噌汁が多いけど、あの頃の味噌汁とは、まるで別物に感じてしまう。
父の文句と母の笑い声
父はいつも疲れていて、文句が多かった。「今日の味噌汁、ちょっとしょっぱいな」なんて言っては、母が「じゃあ自分で作ってみたら?」と笑い飛ばしていた。そんなやりとりも含めて、あの食卓には人間の温かさがあった。今なら、母の笑いには余裕じゃなくて、きっと我慢や気遣いが詰まっていたんだろうなと気づく。
黙っても許された安心感
黙って食べても、何も言われなかった。会話がない時間も、気まずさはなかった。むしろ、そこに安心感があった。今、誰かと食べるときに黙ると「疲れてる?」とか気を遣わせてしまう。でもあの頃は、黙っていても心がつながっている感覚があった。食卓とは、そういうものだったんだと思う。
コンビニ弁当の味がしない理由
最近は、昼ごはんも夜ごはんもコンビニ。忙しさにかまけて、温めてすぐに食べられるものばかりだ。でも、不思議と味を感じない。「味が薄い」とかじゃなくて、記憶に残らない味。それって、たぶん一緒に食べる相手がいないからなんじゃないかと思う。誰かと会話しながら食べたら、もっと味わえるんだろうな。
手軽さの代わりに失ったもの
レンジでチンして、スマホを見ながら食べて、あっという間に終わる食事。こんなに簡単になったのに、なぜか心は満たされない。手軽さと引き換えに、何か大事なものを失ってしまった気がする。それは、たぶん「時間」じゃなくて「誰かの存在」だったんじゃないかと、ふと思う。
電子レンジのチンでは心は温まらない
物理的には温かい。でも、心は冷えたまま。電子レンジで温めるごはんは、確かに便利だけど、そこに誰かの手や気持ちは込められていない。一緒に「いただきます」を言うだけで、心がほぐれて、食事の時間が特別なものになる。そういう経験が少なくなって、食べることが作業になっていくのが怖い。
誰かと食べるだけで味が変わる不思議
高校時代、野球部の仲間と食べた牛丼の味は今でもはっきり覚えている。牛丼自体はチェーン店の安いやつだったけど、部活終わりに汗を流して食べるそれは、どんな高級料理より美味しかった。誰かと一緒に食べると、同じごはんでもなぜか味が変わる。あれは、本当に不思議な感覚だ。
高校時代の部活終わりの牛丼
試合で勝った日も負けた日も、帰り道に立ち寄った牛丼屋。みんなでわいわい言いながら、どんぶりをかき込む。練習の疲れもあって、味の細かいことなんてわからなかった。でも「うまいな!」と誰かが言うだけで、自分の口の中にもその「うまさ」が伝染する。味って、共有されるものなんだと初めて知った。
うまいかどうかじゃなくて腹を満たせたことが喜びだった
財布の中身はスカスカで、トッピングなんてできなかった。でも、大盛りを頼んで満腹になれたときの満足感は、今の高級ランチよりも勝っていたかもしれない。そこには、仲間と過ごす時間と、戦ったあとの達成感があった。味は、空腹だけじゃなくて心の充足でも変わる。
仲間の存在が調味料だったあの日々
塩も醤油も大事だけど、あの日は「仲間の存在」が一番の調味料だった気がする。黙っていても、笑っていても、そこに誰かがいてくれることが安心だった。今は、一人で食べることが当たり前になってしまって、それが当たり前と思い込もうとしている。でも、本当は今でも誰かと食べたいのかもしれない。
仕事終わりに一人で食べるラーメンの味気なさ
登記の締切に追われ、帰りが夜遅くなることも多い。そんなとき、開いているラーメン屋にふらっと入って一人で食べる。味は美味しいはずなのに、どこか味気ない。目の前のラーメンより、空いた隣の席が気になってしまう。誰かと「うまいな」と笑い合えるだけで、このラーメンの味は変わる気がする。
誰かと分け合うってこんなに大事だったのか
子どもの頃は、兄弟と唐揚げを奪い合っていた。「なんで自分のが少ないんだよ!」って怒ってたけど、今思えば、それって豊かな時間だった。誰かと食べ物を分け合う。そこには、競争もあったけど、同時に信頼もあった。今の私は、それを分け合う相手がいないことを、ようやく寂しいと感じている。
司法書士という職業がもたらす孤食の現実
この仕事は、集中力と忍耐が求められる。それに、間違いが許されないプレッシャーもある。気を張って仕事を終えたあと、食事の時間は数少ないリラックスタイムのはずなのに、現実は一人。スマホ片手に、淡々とごはんを流し込む自分がいる。誰かと食べる時間が、これほど貴重になるとは思わなかった。
忙しさに追われる昼休み
書類提出の合間、法務局の近くでパンをかじる。時間に追われて、味わう余裕なんてない。むしろ「栄養さえ取れればいい」とさえ思っている自分に、ふと虚しさを感じる。事務員も一緒に食べようと誘っても、業務に追われてそれどころじゃない。孤独な昼ごはんが当たり前になっていく。
気がつけばデスクでパンひとつ
最初の頃は外でランチを取る努力をしていた。でも、段々と「その時間がもったいない」と思うようになってしまった。今では、コンビニのパンと缶コーヒーが定番。デスクでメールを見ながら食べるそれは、もはや食事というより作業の一部になってしまっている。
事務員と交わす今日も忙しいですねのひと言
せめてもの救いは、事務員との何気ない会話。昼前に「今日もバタバタですね」って顔を見合わせるだけで、ちょっと気が緩む。ほんの数秒でも、人と感情を交わせることで、午後のモチベーションが変わる。孤独な仕事でも、人とごはんを共にする時間があれば、心の持ちようは全然違う。
食事が義務になる日々
本来、食事は楽しみであるべきなのに、気がつけば「とらなきゃいけない義務」になっている。栄養補給、エネルギー補充、それだけ。そうしているうちに、味覚だけでなく、感情まで鈍くなっていくような気がする。食事って、ただの行為じゃなく、感情を回復する時間でもあるのに。
美味しいより早いが優先される
今日のごはん、何を食べたか思い出せない。そんな日が増えた。美味しかったかどうかより、「早く済ませられたかどうか」が基準になってしまっている。そうなると、食事は無機質な行為になり、心がすり減っていくのを感じる。これでいいのかと、自問する夜もある。
それでも一緒に食べる時間があれば救われる
たまに、友人と外で食べる機会がある。居酒屋で他愛ない話をしながらの食事は、それだけで特別な時間に感じる。料理の味というより、会話や空気が、ごはんを美味しくしてくれる。誰かと一緒に食べることの力を、歳を重ねてから痛感している。できることなら、また誰かと唐揚げを奪い合いたい。