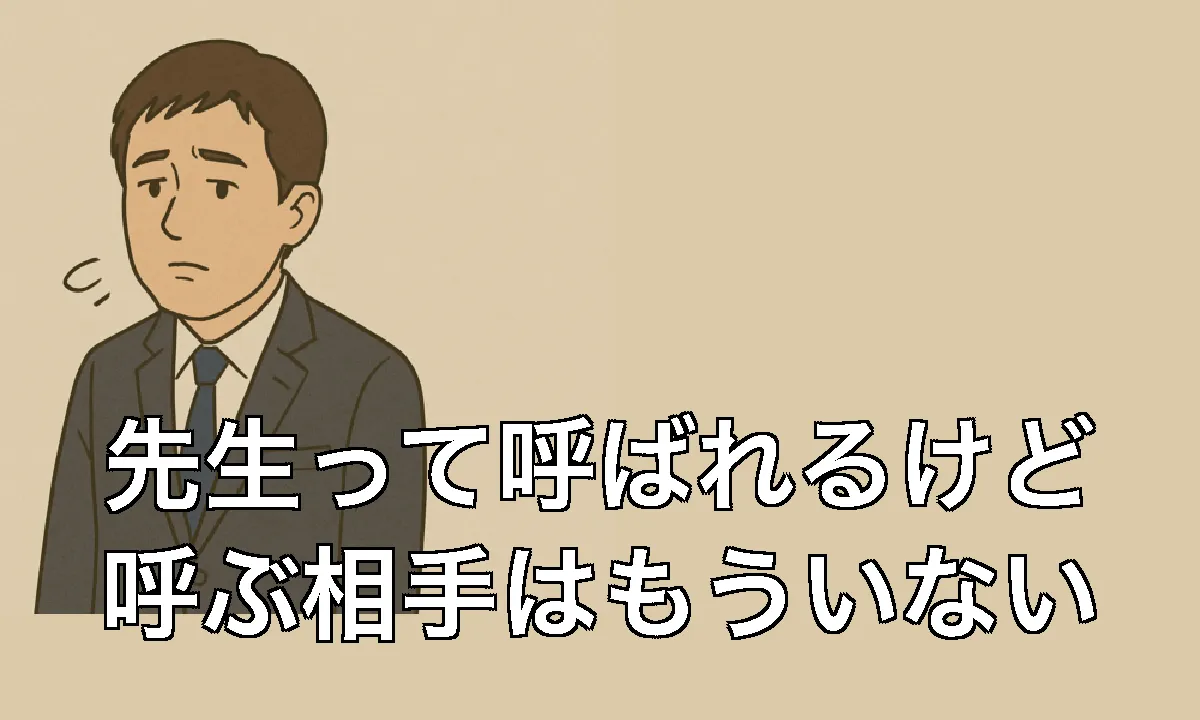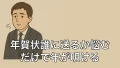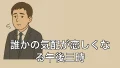先生と呼ばれることに慣れてしまった日常
司法書士として働いていると、「先生」という呼び名を当たり前のように耳にする。開業してから十数年、慣れとは恐ろしいもので、最初こそくすぐったかった呼称も、今では感情が動くこともない。ただ、最近ふと思う。呼ばれることには慣れたが、自分から誰かを「先生」と呼ぶ機会は、いつからなくなってしまったのだろうと。誰かに頼ることをやめてしまったのか、それとも頼れる人がいなくなったのか。気づけば「先生」という響きに、自分の孤独が照らされるような感覚さえある。
電話越しの先生が他人事のように聞こえる瞬間
「もしもし、〇〇先生いらっしゃいますか?」。事務員が受けた電話の向こうから聞こえるその声に、どこか距離を感じることがある。もちろん自分のことを指しているのはわかっているのに、まるで他人のことを呼んでいるかのように響くのだ。昔は、その一言に少し誇らしさを感じた。でも今では、その言葉の裏にある期待や責任の重みの方が勝っている。呼ばれるたびに「ちゃんと応えないと」と、また一つ肩に力が入ってしまう。
先生と言われてもうれしくない時がある
あるとき、若い依頼者から「先生って、やっぱり頼りになりますね」と言われた。笑顔で返しながらも、心の中はなんだかざわついた。自分が「先生」として完璧であることを求められているようで、逆にどんどん話しにくくなっていく。「先生」って便利な言葉だけれど、その呼び名の裏で、本当の自分を見てもらえていないような、そんな疎外感を覚えることがあるのだ。
初めてその呼び名をもらったあの日のこと
開業して初めて「先生」と呼ばれた日、実は少し泣きそうになった。努力が報われた気がして、親にすぐ電話したのを覚えている。今思えば、あのときは「誰かに認められたい」という気持ちが強かったのだろう。けれど時が経つにつれて、「認められること」と「寄りかかること」はまったく別だと痛感するようになった。あの頃のように、誰かに素直に相談できたら、どれだけ楽だったろうか。
呼びたい人がもういないという事実
今、自分が本当に心を許して「先生」と呼びたい人がいるかと問われれば、しばし沈黙してしまう。先輩たちは引退し、学生時代の恩師とも疎遠になった。気軽に相談できるような同業者も少なく、独立したことで、余計に壁ができたように感じる。誰かを頼るということが、だんだん難しくなってきてしまった。
相談したいことは山ほどあるのに
仕事をしていれば、「これ、どうしたらいいんだろう」と悩む瞬間は山ほどある。法改正の読み違い、トラブル案件の対応、そして何より、人との距離感。そんなとき、昔なら先輩に一言聞けた。今は自分で調べて、自分で判断して、自分で責任を取る。間違えたら「先生なのに」と言われるのは、自分自身だ。だから余計に、人に弱みを見せられない。
先輩も親もいない静かな夜
事務所の灯りを落とした夜、ふと机に肘をついて、天井を見上げる。親にも相談できなくなったし、恩師とももう十年以上会っていない。昔なら、誰かにLINEしてたような内容も、今じゃスマホを手に取るだけで終わってしまう。年齢を重ねるって、こういうことかと実感する瞬間だ。
「誰かに聞きたい」が口に出せない
何気ない疑問すら、人に聞くことをためらってしまう。聞いた瞬間、「あれ、この人わかってないの?」と思われる気がして、つい飲み込む。だからこそ、一人で悶々と考える時間が増える。答えが出ないこともあるけど、それもまた「先生」としての自分を保つための、仕方ない作業なのかもしれない。
一人で抱えるという選択肢しかない
独立してからというもの、「最後は全部自分で決めるしかない」というスタンスが染みついてしまった。人に任せることも、人に甘えることも、どこか苦手だ。事務員さんには本当に助けられているが、やはり「責任は全部自分」という思いが強く、心の奥底にある本音はなかなか出せない。
事務員にすら見せられない本音
事務員の前では、つい「大丈夫そうなフリ」をしてしまう。本当はパンク寸前でも、笑顔で「じゃあこの書類お願い」と声をかける。愚痴ひとつこぼせば空気が悪くなるし、弱さを見せると不安にさせてしまいそうで言えない。結局、自分の心の中で処理するしかないという結論に至る。
頼られるほど自分がすり減っていく
「先生、ありがとうございます」「本当に助かりました」と言われるたび、うれしい反面、どこかで疲弊している自分がいる。人の期待に応え続けるには、それなりの精神力が必要だ。でも、期待に応えられなかったときの自分が怖い。だから、完璧であろうとして、どんどん消耗していく。
人に話すより片付けた方が早いという諦め
誰かに相談するくらいなら、自分で抱えて片付けた方が早い――そんな思考に慣れてしまった。昔は「誰かに話してすっきりしたい」と思っていたのに、今では「話すエネルギーがもったいない」と思ってしまう。これは成長なのか、それとも心が固まってしまっただけなのか、自分でもわからない。
それでも先生であり続ける理由
「先生」と呼ばれる日々に、疲れや孤独を感じることはある。それでも辞めようと思わないのは、この肩書きに守られている部分があるからかもしれない。誰かの役に立っているという実感が、かろうじて自分を支えている。そして何より、昔の自分のように「先生」と呼ぶ側の気持ちを、今でも忘れていないつもりだ。
背中を見せる人がいないからこそ
見本となるような「先輩」がいない今、自分が誰かにとっての「背中」にならなければならないという自覚がある。新人の司法書士や、これからを考えている若い人たちにとって、「この人も一人で頑張ってるんだな」と思ってもらえる存在でありたい。それが、先生としての役割の一つなのかもしれない。
崩れそうでも踏ん張る一人芝居
正直、毎日がギリギリな時もある。それでも、「先生」としての顔を保ち続ける。まるで一人芝居だ。でも、誰かが見ていてくれるかもしれないと思うと、その舞台を下りるわけにはいかない。見えない観客のために、今日も淡々と仕事をこなす。
それでも誰かに届くかもしれないと思うから
こうして文章を書くのも、誰か一人でも「わかるよ」と思ってくれたら、それで報われる気がするからだ。先生と呼ばれる者として、時にはこうして自分の弱さもさらけ出すことが、次の誰かを励ますことになるのかもしれない。だから、もう少しだけこの道を歩いてみようと思う。