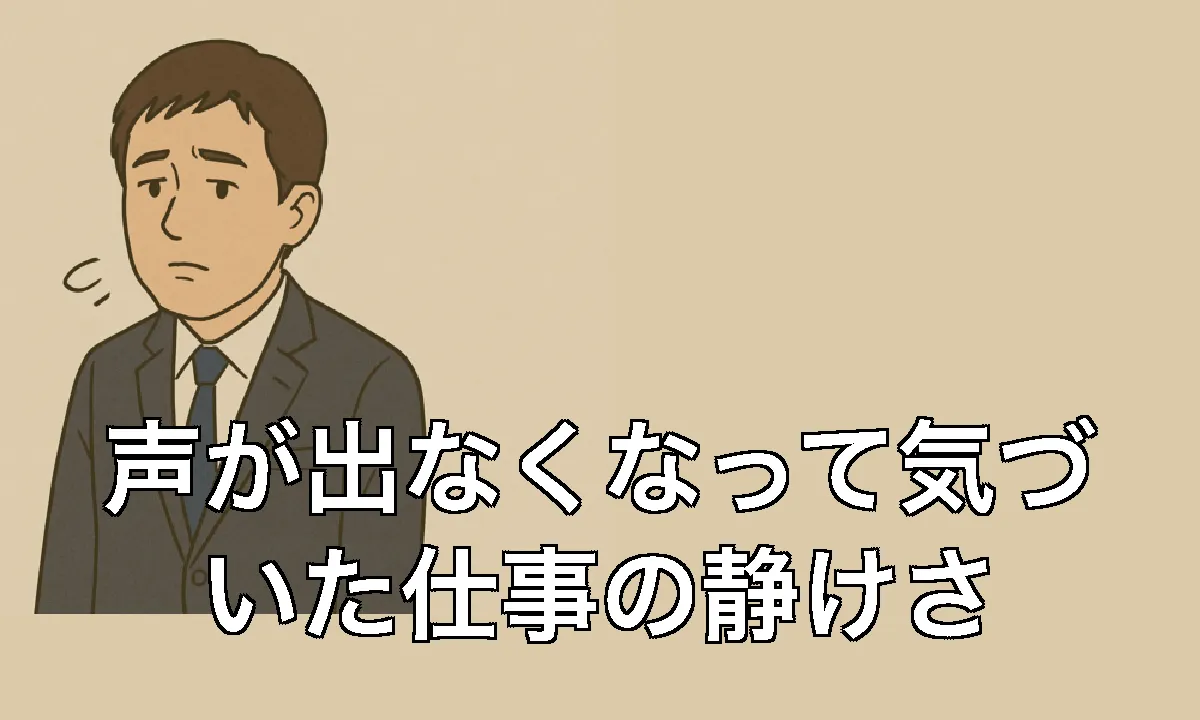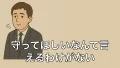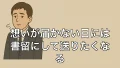声が出なくなった朝に訪れた違和感
その朝、何気なく「おはよう」と声を出そうとした瞬間、喉の奥に違和感を覚えた。声が出ない。かすれた音すらしなかった。風邪でもひいたのかと思ったが、体は至って元気。ただ声だけが、まるで長く使われていなかった古い楽器のように、音を出すことを忘れていた。前日の夜、誰とも話していなかったことを思い出す。その前も、前の前もそうだったかもしれない。気づけば、声を出すという行為が日常から消えていたのだった。
朝の「おはよう」が言えなかった
出勤して事務所に入り、事務員に向かって「おはようございます」と言おうとしたが、喉が詰まって声にならなかった。軽く咳払いをしても、かすれた音しか出ない。事務員が不思議そうにこちらを見る。私は慌てて「声が出ないみたい」とジェスチャーで伝えた。相手も驚いていたが、内心、自分自身が一番驚いていた。「おはよう」すら出ないとは思っていなかったからだ。たかが挨拶、されど挨拶。その一言すら口にしない生活が、どれだけ長く続いていたのだろう。
独り言すら出ていなかった現実
普段から業務に没頭していると、話しかけられることも少ないし、自分から声を出す必要もない。Wordに向かい、登記の申請書を黙々と作る。電話がなければ本当に一言も話さない日もある。昔は独り言でも言っていたような気がするが、それすらなくなった。業務効率化やペーパーレスの波で、どんどん静かになっていく事務所。ふとした瞬間に、こんなにも自分の声を使っていないという現実に気づいたとき、空恐ろしい気持ちになった。
人と話さない日々がもたらすもの
人と話さない日が続くと、声だけでなく心も閉じていくような気がする。業務は滞りなくこなしているし、誰にも迷惑はかけていない。ただ、何かが静かに失われている。自分の感情を口にする機会がないまま時間だけが過ぎる。寂しいとか辛いとか、そういった感情もいつの間にか鈍くなる。声が出なくなるというのは、ただの身体的な現象ではなく、精神的な沈黙の表れだったのかもしれない。
無言でこなす業務のルーティン
登記申請、不動産売買、相続手続き…。どれも集中してやるには静けさが必要だ。しかしその静けさが、知らぬ間に孤独と化していることに気づきにくい。事務員とも、必要最低限の業務連絡だけ。昼食も別々に食べ、午後もそれぞれの机に向かう。まるで機械のように、淡々と処理されていく書類たち。そしてその処理の過程で、自分の声も感情もどこかへと消えていくような気がするのだ。
便利さが招いた人間関係の希薄さ
昔はFAXを送りながら確認の電話を入れることが多かった。今はメール一本で済む。郵送で書類を送る際も、事前に電話していたのが、今では追跡番号だけで済む。効率化の裏で、確実に「会話」は減っている。もちろん時代の流れだし、悪いことばかりではない。でもその分、人との繋がりが薄れているのは否めない。孤立とはこうして静かに進行するものなのかもしれない。
昔は電話が鳴るのが当たり前だった
開業当初は電話対応に追われる日々だった。自分で営業もしていたし、知らない人とのやりとりも多かった。けれど今は顧客も安定し、問い合わせも減った。電話が少ないというのはある意味ありがたい。でも静まり返った事務所で、誰の声も聞こえない状態が当たり前になってしまった今、あの慌ただしい日々が懐かしく感じる。あの頃は、少なくとも自分の声を日常的に使っていたのだ。
事務員との会話だけが唯一の声
今、私が日常で声を出すのは、事務員とのやりとりだけかもしれない。それも、今日の予定確認や、申請書類の確認といった業務上のことばかり。雑談すらほとんどない。話しかけるのも気を遣うし、相手のリズムもある。でも、その「唯一の声の相手」がいることが、まだ救いだ。もし一人事務所だったら、完全な無音の中で声を失っていたかもしれない。
昼休みがなければ本当に一言も話さない
昼食の時間、たまに一緒に弁当を広げるときだけが、少しだけ和らいだ時間になる。雑談とまではいかないが、「この書類どうでしたか」とか、「今日は暑いですね」とか、そんな他愛ない一言が、ありがたく感じるようになった。話すという行為が、こんなにも大事だったのかと実感する。誰かと声を交わすことは、業務とは別の次元で自分を支えてくれていたのだ。
感謝していてもそれすら口にしていない
事務員には本当に助けられている。でも「ありがとう」や「助かるよ」といった感謝の言葉すら、最近は言えていないことに気づいた。言葉に出さなければ伝わらないのに、どこか照れくささや面倒くささで、黙ったままになっていた。感謝の気持ちも、声にしなければ存在しないのと同じ。思っているだけでは届かない。声が出なくなって初めて、それを痛感した。
司法書士という仕事の静かな孤独
この仕事は、一人でも成立する。むしろ、一人で黙々と進める力が求められる。誰かに頼るより、自分の責任で完結させることが信頼に繋がる。でもその一人で完結する力が、時として自分を閉じ込めてしまう。声を出すこと、人と関わること、自分の外側に何かを向けることを忘れてしまう。司法書士としての誇りと裏腹に、孤独との共存もまた、職業病のように思えてくる。
静かに集中できるは本当に良いことか
静かな環境で集中して仕事ができる。それは確かに理想的だ。でも、静かすぎると心の中に淀みが溜まっていくような感覚がある。考え事がぐるぐると頭の中で巡り、誰にも話せないまま膨らんでいく。声を出さないことで、思考すら内側に溜まりすぎてしまうのだ。集中とは紙一重で、孤独と表裏一体。司法書士という仕事は、そのギリギリのところで毎日をやりくりしている。
黙ってできるから向いていると思っていた
元々、人付き合いが得意な方ではなかったし、集団で何かをするより一人で黙々と進める作業が好きだった。だからこの仕事は自分に向いていると思っていたし、実際に合っていた。けれど、年齢を重ね、日々の孤独が濃くなっていく中で、「向いている」と「支障がない」は違うと感じるようになった。向いていると思っていたこの仕事に、少しずつ自分が侵食されていたのかもしれない。
でも声を使わない日々は心に効いてくる
喉だけでなく、心にもカサカサと乾いたような感覚が広がっていた。それは、声を使わない日々の積み重ねによるものだと思う。声には感情が宿る。感情を出さなければ、心も閉じてしまう。声が出ない日が続くと、だんだん気持ちまで出なくなる。そんな悪循環に気づいた今、私は少しずつでも言葉を取り戻していこうと思っている。たとえそれが、小さな独り言からでも。
自分の声で自分を保つということ
誰かと話すこと、感情を声に出すこと、それは自分を保つための大切な行為だった。司法書士という職業は、社会の中で静かに支える立場かもしれない。でも、自分自身が壊れてしまっては元も子もない。声が出ないことで気づいたのは、心の声も失いかけていたということだった。だからこれからは、少しずつでも声を出す時間を作っていきたいと思う。誰かと、そして自分と話すために。