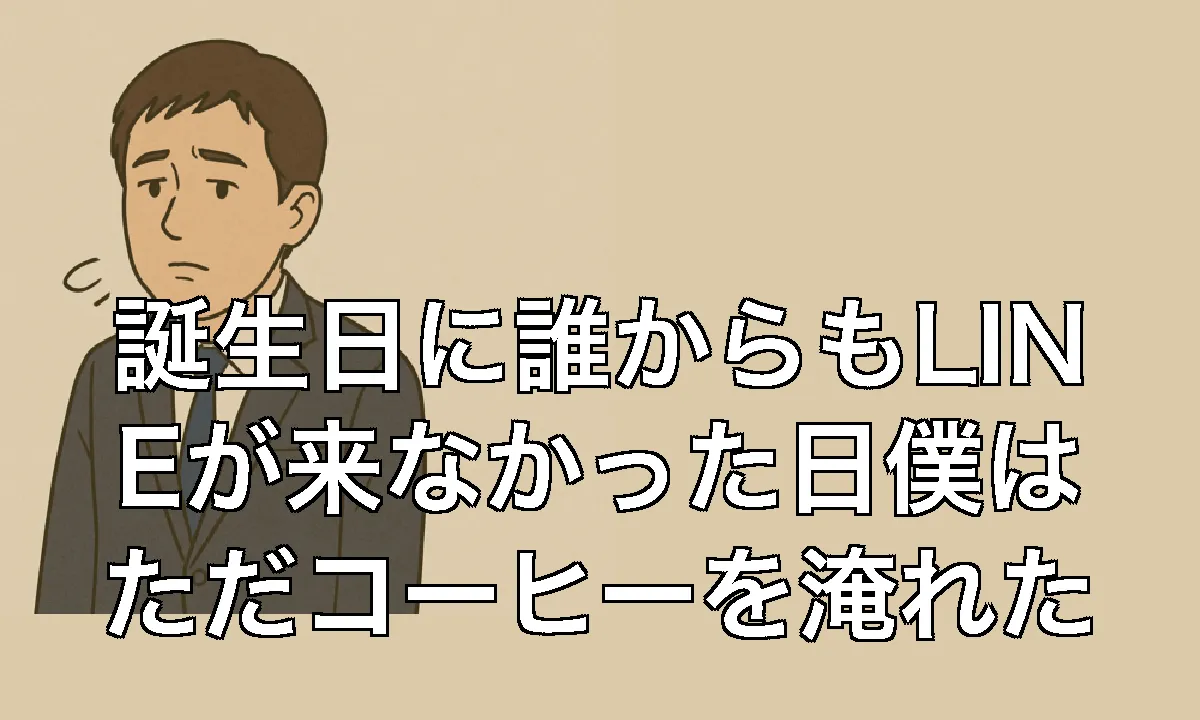誕生日の朝通知ゼロから始まる一日
スマホを開いた瞬間、画面は静まり返っていた。カレンダーには自分の誕生日が確かに表示されているのに、LINEもメールも通知は一切なし。これまでにないほどの“無”に近い感覚だった。毎年そこまで期待していたわけでもない。けれど、ゼロという数字が突き刺さる朝は、やはり堪えた。仕事で忙しくしていれば紛れるだろうと、自分を無理に納得させながら、いつものようにスーツに着替えた。
無音のスマホに向かってため息をついた
通知のないスマホはまるで石のようだった。誰からも何も届かない。着信履歴も空白。普段は煩わしいとさえ思っていた着信音が、今日は恋しかった。通知音が鳴らないことが、こんなにも心をざわつかせるなんて。思わずスマホをひっくり返して画面を下に向けたが、それで心が軽くなるわけでもなかった。
「まあそうだよな」と思えるようになっていた自分
実は、こうなることは予感していた部分もあった。ここ数年、仕事に追われて人間関係はどんどん疎遠になっていた。こちらから連絡することも減ったし、誰かの誕生日を覚えて祝う余裕もなかった。「お互い様」と思えば傷も浅いかもしれない。そんな風に割り切る自分が、少しだけ冷たい気もした。
人間関係の棚卸しをしてみたら見えてきたこと
司法書士という仕事は、日々書類と向き合い、クライアントとだけやり取りをする孤独な仕事だ。気がつけば、学生時代の友人とも疎遠になり、LINEの履歴も仕事関係のものばかりになっていた。人間関係の「棚卸し」をしたら、もはや仕事以外の繋がりは棚そのものがなかった。
気がつけば仕事以外の連絡は激減していた
誕生日のLINEが来なかったのは、単なる偶然ではなかったと思う。仕事にかまけて、友人からの連絡を後回しにしてきたツケかもしれない。既読スルー、返信忘れ、返信遅延…思い当たる節はいくつもある。友人たちも「この人は忙しそうだから」とそっと離れていったのだろう。
付き合いを断ち続けてきた結果だったかもしれない
元野球部の仲間たちとは、以前は年に1回集まっていた。でも、その誘いも2回断ってから音沙汰がなくなった。断る理由は「仕事が立て込んでて」で済ませてきたが、本当は疲れて人に会う気力もなかった。その積み重ねが、LINE通知ゼロの誕生日を導いたのかもしれない。
仲の良かった人の誕生日も祝ってこなかった
思い返せば、自分も人の誕生日をちゃんと祝っていなかった。SNSで気づいてもスルーしてきたし、忙しさを言い訳にして関係を維持する努力を怠っていた。誕生日というのは、人間関係の“通知簿”のようなものだと感じた。
事務所の中も相変わらず静かだった
朝から仕事は山積み。書類のチェック、電話対応、依頼の打ち合わせ。誕生日であることを自分から言うほどの年齢でもない。事務員さんもいつも通りで、「お疲れさまです」とだけ言ってくれる。気を遣わせたくないという気持ちと、気づいてほしいという矛盾が交錯していた。
事務員さんの「お疲れさまです」だけが今日の言葉
たった一言が、やけに胸に響いた。普段なら聞き流していたはずの「お疲れさまです」が、今日は少しだけ温かく感じられた。誕生日を知らなくても、変わらず声をかけてくれることがありがたかった。こういう日こそ、誰かの存在が救いになる。
気を遣わせたくないという建前で黙っていたけれど
「今日は誕生日なんです」と言えなかったのは、恥ずかしさと、言ってしまえば期待してしまう自分が嫌だったからだ。仮に伝えたとしても、気を遣わせるだけだと思っていた。でも、本当は一言「おめでとう」と言われたかっただけだった。
本当はちょっと気づいてほしかった気もする
何も言わず、何も期待しないふりをして、でもどこかで誰かが気づいてくれるんじゃないかと期待していた。勝手な願望だとわかっていても、それが叶わなかった時の空しさは想像以上だった。
司法書士の仕事は誰にも見えない祝福の積み重ね
誰かの相続が無事に終わったとき、不動産登記が完了したとき、「ありがとうございました」と言われることはある。でも、その人がこちらの誕生日を知っていることは、まずない。祝福する立場ではあっても、祝われる立場ではない。そんな日常の一端を、改めて実感した。
登記完了の連絡をするたび少しだけ誰かの役に立ってる
今日も変わらず、登記完了の連絡を数件済ませた。きっとその向こうでは、新しい生活が始まっている人もいる。そんな“見えない祝福”を届けている自分の仕事に、少しだけ誇りを感じた。それでも、祝ってくれる人がいないのは寂しいものだ。
でもその“誰か”は僕の誕生日は知らない
僕が誰かの人生の節目を手伝っても、その誰かが僕の節目を祝うことはない。それが司法書士の宿命かもしれない。だけど、それを不幸だとは思いたくなかった。誰かの大切な日を陰で支えている自分に、もう少しだけ自信を持ちたいと思った。
感謝されても忘れられる存在である現実
「ありがとうございました」と言われたその数日後には、僕の顔も名前も忘れられている。それが当たり前の職業。それでも、誰かの“安心”に繋がっていると思えば、それだけで十分だと信じたい。
次の誰かの誕生日にはLINEを送ってみようと思った
静かな夜、インスタントコーヒーを丁寧に淹れながら、ふと考えた。「誰も祝ってくれない」と嘆くより、自分から誰かを祝ってみようかと。自分のためではなく、誰かの“ゼロ通知”をひとつでも埋めるために。そう思えたとき、少しだけ心が軽くなった。
自分から始めるしかないという結論
孤独を嘆くより、孤独を減らす行動をとる方が性に合っている気がした。気づいてもらうのを待つのではなく、自分から手を伸ばす方が心地よい。司法書士という立場でも、ひとりの人間としても、できることはあるはずだ。
その人も誰からも祝われていないかもしれない
あのときの僕と同じように、誰からもLINEが来ずに過ごす誕生日の人が、きっとどこかにいる。その人にとっての「ひとつめの通知」になれるなら、今度は僕から送ろうと思う。
小さな言葉が救う瞬間を作れる司法書士でいたい
「おめでとう」の一言がどれほど救いになるかを、身をもって知った。だからこそ、同じように誰かを励ます存在でありたい。書類を処理するだけでなく、心に寄り添える司法書士であるために。