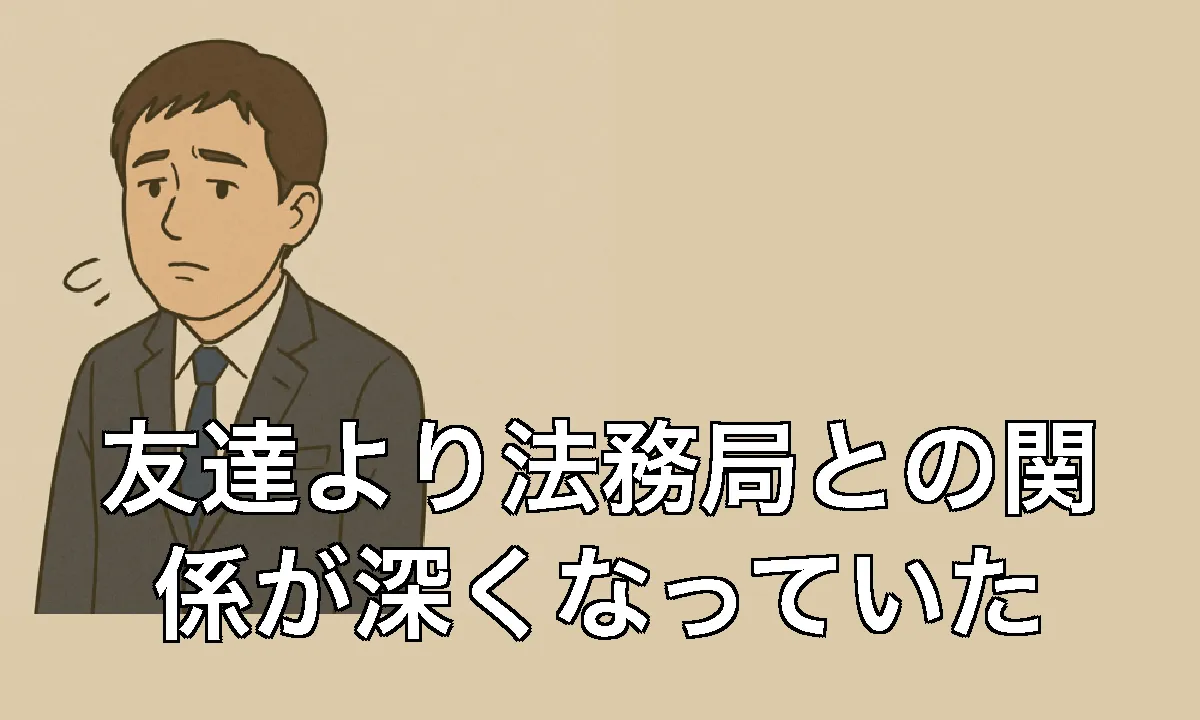気づけば法務局とばかり話している
気づいたら、ここ数ヶ月で一番多く会話を交わしているのが法務局の担当者だった。仕事柄、登記の申請や確認で頻繁に足を運ぶのは当然だが、さすがにこれだけ通っていると、顔も覚えられている気がする。雑談などはないが、窓口で交わす形式的な言葉のやりとりにすら、どこか安心を感じてしまう自分がいるのが少し怖い。昔は週末に友人と飲みに出かけたり、他愛もない話に笑ったりしていたが、今では誰かと話すのが業務連絡ばかりになってしまった。気を抜くと、ひとりごとすら事務的な言葉になっている。
昔はもう少し人と会っていたはず
司法書士になる前、あるいは開業したての頃は、まだ人と会う時間があった気がする。週末は地元の草野球に顔を出したり、元同僚と近況報告を兼ねた食事を楽しんだり。でも、案件が少しずつ増えるにつれ、時間の余裕はなくなり、連絡を取るのも億劫になっていった。気がつけば、連絡帳の名前を見ても、話題を見つける自信がない。今連絡しても、「どうしたの?」と警戒されるだけかもしれない。会っても話が続かない。自分の生活は、もう人付き合いから少し外れたところにある。
法務局の担当者の声の方が親しみ深い
日々の仕事で一番耳にする声が、法務局の担当者というのはなかなかシュールだ。電話口で聞こえてくる「こちら登記部門です」という声に、妙な安心感があるのはおかしいだろうか。相手はこちらを業者の一人としてしか見ていない。でも、自分にとってはその機械的な応答ですら、一定のリズムをくれる貴重な人との接点になっている。まるで、テレビの天気予報を毎日聞いているうちにキャスターに親近感が湧くのと似ているのかもしれない。
それでも名前を覚えられない寂しさ
頻繁に通っていれば、名前くらい覚えてもらえてもいいのに、と思うことがある。だが、法務局側は業務の中で数え切れない申請者と接しているのだから、当然といえば当然。あちらはこちらを「書類を持ってくる人」として処理しているだけなのだ。逆に、自分は同じ担当者の対応に「今日はあの人か」と反応している。この一方通行の関係性に、なんとも言えない寂しさを感じてしまう。まるで、片思いのような虚しさだ。
友達より登記との付き合いが長くなった
法務局だけではない。そもそも、友達との会話よりも登記申請の書式と過ごしている時間の方が長い。登記事項証明書を見て、「ああ、この物件また出たな」などと思うことはあっても、人の顔が浮かぶことは少ない。友人関係が希薄になったとはいえ、まさか登記との付き合いの方が密になるとは、学生時代には想像もしていなかった。
久々に友達に連絡しても話題が見つからない
たまに勇気を出して、昔の友人にLINEを送ってみる。でも、返ってくるのは「元気?」という短い一言か、既読スルー。それは別に冷たいわけじゃなくて、こっちが会話を広げる術を忘れてしまっているのが原因だ。昔はくだらない話を延々とできたのに、今ではどこか壁がある。自分が悪いのか、相手が変わったのか。たぶん、どちらでもなく「時間」がそうさせたのだろう。
自分の話が全部登記と相続の話になる
いざ会話になっても、自分が話せる話題がもう「登記」と「相続」しかない。友達が子どもの運動会や家族旅行の話をしてくれても、こっちは「いや、この前の相続登記がさ……」と話してしまう。そして、自分で気づく。こんな話、誰が聞きたいのかと。人と話していても、結局業務の延長みたいな話しかできなくなっている自分がいる。
人間関係よりも法的関係の方がスムーズにいく皮肉
登記の世界では、必要書類を揃えればだいたいのことは進む。スケジュールも組めるし、予測も立つ。人間関係はそうはいかない。タイミングや気分、言葉選びひとつで簡単に崩れてしまう。だからこそ、法的な枠組みの中で生きている方が安心だと感じてしまう時もある。でも、その安心感の裏にあるのは、柔らかい関係性への諦めかもしれない。
法務局とのやり取りに感情を持ち始めた頃
ある日、申請書類に軽いミスがあって補正通知が来た。普通なら「やれやれ」と思うだけなのだが、その文章を見た瞬間、どこか安心している自分がいた。「ああ、ちゃんと見てくれてるな」と。完全に仕事に取り憑かれている証拠かもしれない。気づけば、法務局とのやりとりに一喜一憂している。人間関係の代替物のように。
手続き完了の受話音にちょっと安心する日々
「登記完了通知が届きました」――その一報があると、胸をなでおろす。特に大きな案件や、時間のかかる案件だと、まるで子どもの卒業式を迎えたような気持ちになる。自分の仕事が一段落したという達成感と、また次の案件が来るという終わりのないループの予感。けれど、その一報を待つ間のドキドキや、届いた瞬間の安堵感が、どこかで生活の支えになっている。
担当者の言葉遣い一つで一日が左右される
窓口での一言、「今回は丁寧に出してくださってありがとうございます」。それだけで一日が少し明るくなる。逆に、ちょっと不機嫌そうな対応をされると、その日ずっと気にしてしまう。相手は単なる業務上の反応でも、こちらは妙に気にしてしまう。これはもう、法務局が職場というより、人生の一部になってしまっているのかもしれない。
なぜこうなったのかを考える夜
仕事が一段落してふと時計を見ると、もう21時。コンビニで買った冷めたご飯を食べながら、「なんでこうなったんだろう」とぼんやり考える。司法書士になったのは、自分なりに人の役に立ちたかったからだ。でも、いつの間にか書類とスケジュールと数字に追われ、感情を置いてきてしまった気がする。人を助ける仕事のはずなのに、自分が置き去りだ。
土曜日の夜に登記申請の準備をしている
世の中の人が飲みに行ったり映画を観たりしている時間、こちらは事務所でひとり登記申請の準備。間違いがあれば月曜日に指摘が来るから、念には念を入れる。効率的とは言えないが、それでもやらないと気が済まない。休日なのに、いや、休日だからこそ落ち着いて仕事ができる。それが何よりの皮肉だ。
昔の自分が聞いたら笑うだろうな
高校時代の自分が今の生活を聞いたら、おそらく大笑いすると思う。女の子にモテたい、将来はかっこいい仕事がしたいと言っていたあの頃。今や、女性にはモテないどころか、法務局の窓口にしか顔を出していない。そんな生活を、当時の自分が想像できただろうか。でも、どこかで「まあ、お前らしいよな」と苦笑してくれる気もしている。
それでもこの仕事を続けている理由
文句ばかり言いながらも、この仕事を辞めようとは思わない。書類の向こうには必ず誰かの人生がある。会うことも話すこともないけれど、その人の人生の節目に関わっているという実感がある。友達とは疎遠になったけれど、どこかで誰かを支えている。そんな風に考えることで、今日もまた、法務局へ足を運ぶのだ。