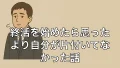恋人と聞かれて答えに詰まったあの日
あの夜、いつものように仕事終わりに飲みに行った居酒屋で、たまたま隣にいた常連のおじさんに聞かれた。「その人、恋人さん?」——何でもないひと言だった。けれど、返事が出てこなかった。隣にいたのは、確かに女性だった。でも「恋人です」とは言えなかった。いや、正確には“そうじゃない”から言えなかったんだけど、それでも「取引先の方です」って答えた瞬間、どっと疲れが押し寄せた。恋愛から遠ざかって、もう何年になるんだろう。人と向き合うのが仕事のはずなのに、自分の本音と向き合うのがこんなに難しいとは思わなかった。
あの場の沈黙が教えてくれたこと
あの沈黙の時間、5秒もなかったと思う。でも僕にとってはずっと永遠みたいだった。口が動かない。言葉が選べない。心の中では「あの人に失礼にならないように」なんて建前が渦巻いていたけれど、結局のところ、自分がどう思われるかを気にしていた。恋人ではない。でも「ただの仕事相手」とも言い切れない微妙な距離感。あの瞬間、僕の人生は“グレー”に染まっているんだって、妙に実感してしまった。
まるで嘘みたいな本当の関係性
実際のところ、その女性とは何度か仕事で顔を合わせただけで、プライベートな関係なんて何もなかった。でも、彼女はいつも丁寧で優しくて、つい「また会いたいな」と思ってしまう相手だった。そんな想いがあるくせに、「取引先」と答えてしまうのは、自分でも情けない。まるで本音を隠すために嘘をついたみたいな罪悪感だけが残った。きっと彼女には、あの場での僕の答えなんてどうでもよかったんだろう。でも僕にとっては、自分の小ささを突きつけられた出来事だった。
相手は何も悪くないからこそ苦しい
彼女はそのあとも変わらず笑顔だった。きっと僕の返答なんて気にもしていなかったんだろう。でも、それが余計にこたえた。責められたわけでもないのに、勝手に落ち込んで、勝手に後悔している。相手が優しいほど、自分の不甲斐なさが浮き彫りになる。恋人と聞かれて、そうだと答えられない現実。司法書士としては信頼されていても、一人の人間としては誰の心にも寄り添えていないんじゃないか——そんな気がしてならなかった。
取引先ですと言った瞬間に広がる虚無
あの一言、「取引先です」が喉を通った瞬間、自分で自分を切り捨てたような感覚があった。誠実な答えだったかもしれない。でも、何かを諦めたような、どこか取り返しのつかない一歩を踏み出したような、そんな気がして仕方なかった。誰かと関係を深めることに、もう自分は慣れていないのかもしれない。仕事の顔と、それ以外の顔。気づけば、仕事の顔しか残っていなかった。
仕事の肩書きが人間関係を覆ってしまう
司法書士という肩書きは、信頼されるし便利だ。でもそれが、僕自身を覆い隠しているようにも思う。どこへ行っても「先生」と呼ばれることで、知らず知らずのうちに人との距離ができている。誰かとフラットに話すことすら、難しくなっている気がする。肩書きが立派になるほどに、本音で話せる相手がいなくなる。そうやって、「仕事上の関係」で説明がつく人間関係ばかりが増えていく。
恋愛も友情も説明ができない立場
この年齢になると、恋愛の話をするのも照れくさい。ましてや独身で、特定の相手もいない。そういう人間が「彼女です」と言うのは、なんだか滑稽に思えてしまう。でも、だからといって「取引先です」と言えば、それもまた味気ない。説明がつかない関係、名前のない関係にこそ、本当のぬくもりがあったりするのに、それを伝える語彙もタイミングも、いつの間にか失っていた。
司法書士ってそういうもんだよねで片付けられたくない
たまに言われる。「司法書士さんって忙しいもんね」「独身多いよね」とか。確かにそうかもしれない。でも、だからといってそれで片付けられてしまうと、何だか救いがない気がする。本当はもっと人間らしくいたいし、誰かと笑っていたい。でも、そんな自分を出せる場所も相手も、気づけばどこにもいない。職業に人格が飲まれてしまう感覚——それが、今の僕の現実だ。
気がつけば名刺入れの厚みだけが増えていた
財布は薄くなっていくのに、名刺入れだけがパンパンになっていく。人脈という名の紙の束。でもそこに、プライベートの連絡先を交換した人は、ほとんどいない。気がつけば、休日に届くLINEはゼロ。既読もつかないメッセージを見つめながら、「ああ、仕事だけが人生になってしまったな」と苦笑いする。
休日に連絡してくるのは得意先だけ
最近は、日曜の午前中に仕事の相談がLINEで届くようになった。「お休みの日にすみません」と前置きがあるだけマシだけど、正直言えば、そこにすら返信をする気力が湧かない。昔は友達とドライブに行ったり、誰かと映画を見たりしていた日曜が、今では“仕事の予備日”になっている。疲れは取れず、心も休まらない。自分が作ったはずの仕事のペースに、気づけば支配されている。
人間関係がスケジュール帳の中に収まっていく
予定帳を開けば、びっしりと書き込まれたアポイントや締切。そこに「友人との飲み」なんて書かれている日は、数ヶ月に一度あるかないか。全部「業務」だ。「調査」「面談」「書類作成」——誰とも心を通わせず、ただこなすだけの予定。そこに本当の“誰か”の存在がないことに、気づいてしまった。
結局誰かにとっての恋人でいられる資格とは
誰かにとっての「恋人」になることは、思っている以上に難しい。優しいだけでも、誠実なだけでも、足りない。生活の余白に誰かを迎え入れるには、まず自分が自分を整えていないといけない。でも、日々の仕事に追われて、心の中は荒れ放題。そんな状態では、誰かを思いやる余裕なんてあるはずもない。だからこそ、「恋人です」と胸を張って言える人が、いないままなのだ。
優しさだけでは足りないのかもしれない
僕は優しいってよく言われる。でも、優しさだけでは人はついてこない。決断力も、情熱も、タイミングも必要だ。優しいだけの人間は、誰かの「いい人」で終わる。選ばれることもなければ、踏み込まれることもない。気づけば、距離をとられる側になっていた。恋愛も友情も、やっぱり“踏み込む覚悟”がなければ成り立たない。
司法書士としての信頼と男としての存在感のギャップ
司法書士としては、信頼されていると思う。依頼は絶えないし、感謝されることもある。でも、それと“男として”の自分はまったく別物だ。人として魅力があるかどうか、自分ではわからない。ただ、誰にも必要とされていない夜は、虚しい。仕事の信頼と、人生の温もりは、まったく別のスキルセットが求められている。たまにはそっちの自分も、育ててやらないとなと思う。