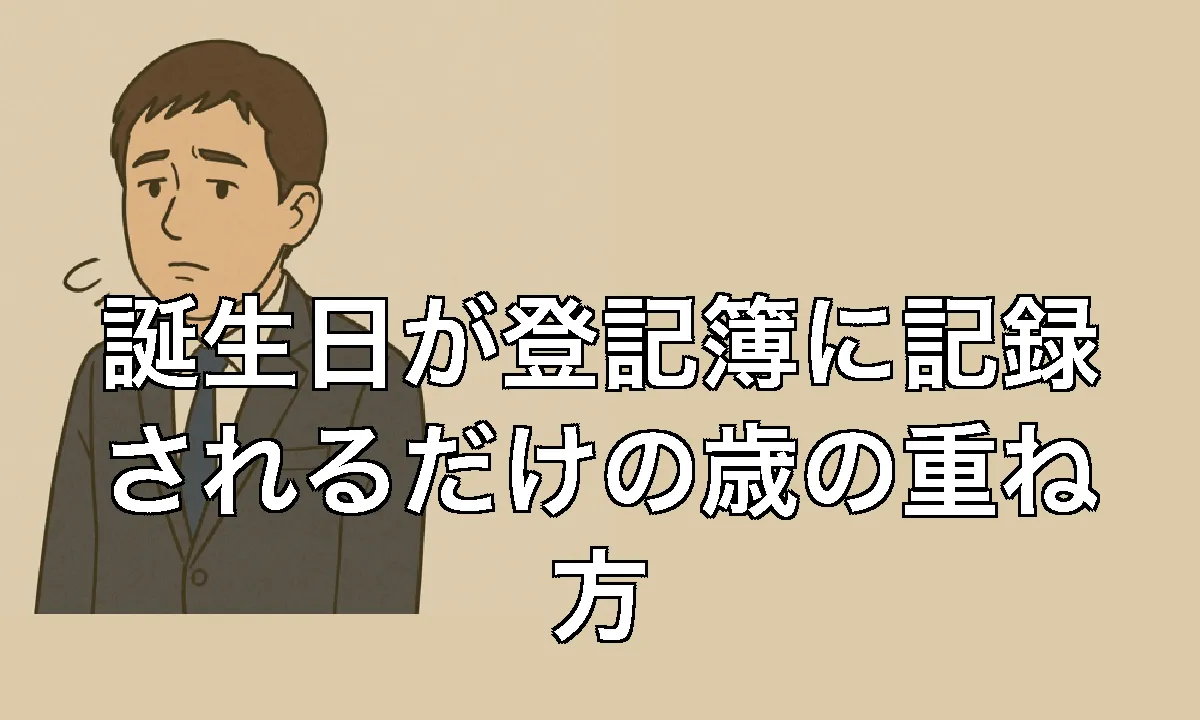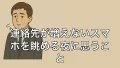登記簿に載るだけの誕生日に思うこと
毎年、誕生日が来るたびに思うのは、「また一つ歳を取った」という事実だけだ。何かが劇的に変わるわけでもなく、誰かから祝福されるわけでもない。ただ登記簿に記録される年齢がひとつ増える。そうやって静かに年を重ねていく自分を、どこか遠くから眺めているような感覚になる。誰に頼まれたわけでもないが、ここまで続けてきた司法書士の仕事に、なんのご褒美もないというのが現実だ。
誰にも気づかれず過ぎていく日
朝から普通に事務所に出て、予定されていた相続登記の打ち合わせをこなし、合間に書類を確認し、午後には法務局への提出と郵便物の確認。そういえば今日が誕生日だったと気づいたのは、夕方のコンビニでレジのモニターに「お誕生日おめでとうございます」と表示された瞬間だった。機械に言われるまで気づかない自分にも驚いたし、それを誰も覚えていない現実に、ほんの少しだけ寂しさを覚えた。
ケーキもプレゼントもなく
子どもの頃は、誕生日といえばケーキやプレゼント、家族の笑顔が当たり前だった。友人からのお祝いの電話や、教室でのちょっとしたサプライズ。大人になると、それが徐々に薄れていき、ついには完全に「ただの平日」になる。この歳になってケーキを買うのも気恥ずかしいし、プレゼントなんて自分で買うのも虚しい。せめてケーキくらい買おうかと思ったが、仕事帰りの疲労感が勝って、結局何もせず家に戻った。
今年も郵便局員の不在通知が一番のイベント
自宅のポストに入っていたのは、司法書士会からの郵便物と不在通知票。「ご不在のため持ち帰りました」——その一枚が、今年の誕生日に届いた唯一の“メッセージ”だった。こんなものでも、誰かが自分の存在を認識していたという証として、少しだけホッとしてしまう。情けないと思いながらも、それが今の自分の現実なのだ。
自分の存在証明は登記簿だけかもしれない
依頼者の名前の横に、自分の名前が記載されている登記簿。それがこの世の中で自分が生きていたという証なのかもしれない。誕生日という節目すら、もはや自分の中では記念日ではなく、単なる事務的な更新日になりつつある。誰かに祝われなくても、法務局の記録の中では確実に一歳年を取っていく。そうやって記録にだけ生きていく自分に、ふと空しさがこみ上げる瞬間がある。
誰の記憶にも残らない司法書士という仕事
司法書士という仕事は、縁の下の力持ちだ。名前が表に出ることもなければ、テレビで紹介されることもない。依頼者の中には、「行政書士さん」や「弁護士さん」と間違える人も多いし、登記が終わればすぐに忘れられることもある。誕生日も、自分がこの仕事に人生を捧げてきた証も、きっと誰の心にも残らない。登記が済めばそれで終わり。まるで人生そのものが、登記の一行のように完結してしまう。
それでも記録にだけは残っていくという皮肉
どれだけ孤独でも、登記簿は嘘をつかない。確かにこの人がここにいて、この不動産に関わったという記録だけは、しっかり残される。感情はなくても、手続きの証として、自分の仕事はそこに残る。それが誇らしいのか、それとも虚しいのか、自分でもよくわからない。ただ、少なくとも誰かの人生の一部に、自分が関与したという事実が残る。それだけが、今の自分の“存在証明”なのかもしれない。
忙しさのなかで自分を祝う余裕はない
仕事が山積みで、休む暇もない日々。そんな中で「誕生日くらい自分を祝おう」と思っても、現実はそう甘くない。登記の締切、急ぎの相談、急な依頼対応……結局、目の前の業務をこなすことが優先で、自分の気持ちに向き合う時間なんて取れない。忙しさにかまけて、自分の存在すらスルーしてしまう。それがこの仕事の、そしてこの歳の取り方の現実だ。
登記の締切と依頼者の要望で一日が終わる
誕生日当日も、午前中から相続関連の登記準備で書類を見直し、午後は法務局への提出。合間に別の依頼者から「明日までに契約書の内容を確認してほしい」と電話が入り、バタバタと対応に追われた。気づけば夜の7時を回っており、夕飯はコンビニの冷たい弁当。誕生日だからといって特別扱いされるわけもなく、むしろ“いつも通り”が余計に身にしみる。
昼食はコンビニのパンをかじりながら申請チェック
昼食の時間も惜しく、コンビニで買ったツナパンを片手に、パソコンで申請書類のチェック。画面の文字が滲んできたのは、疲れのせいか、それとも心のせいか。昔はもう少し、誕生日を特別に扱っていた気がする。だが今は、申請の一文字のミスが致命傷になるこの仕事で、感情に時間を割いていられない。パンの味も覚えていない。それが誕生日の昼食だった。
誕生日すら忘れていたのは自分自身だった
夕方、スマホのカレンダーを見て「今日は○○さんの命日か」と思った瞬間、「あ、自分の誕生日でもあるな」と気づいた。誰かに祝ってほしいとか、何か欲しいとかではない。ただ、自分ですらその日を忘れていたことに、少しだけショックを受けた。年齢を重ねるということは、日々に埋もれて自分を見失っていくことなのかもしれない。誕生日が記念日から“更新日”に変わっていく、それが今の自分の現実だった。
事務員との会話が唯一の癒し
唯一、日常にホッとできる瞬間といえば、事務員とのちょっとした会話だ。コーヒーを入れてくれたときの何気ない一言、帰り際の「お疲れさまでした」。それだけでも、気持ちが少し軽くなる。誕生日の話題が出るわけではない。でも、無理に気を遣われるより、こうして変わらぬ日常が続くことのほうが、もしかすると救いなのかもしれない。
それでも誕生日の話題は出なかった
「最近、暑くなってきましたね」という天気の話は出ても、「今日は先生の誕生日ですね」という言葉は出なかった。別に責めるつもりもないし、事務員に覚えていてほしいという期待もない。ただ、どこかで「もしかして覚えてくれてたら」という気持ちがあった自分が少しだけ情けない。でも、そんな期待をしないのがこの歳だ。誰かに祝ってもらう歳ではないし、仕事上の関係性に余計な気遣いは不要だ。
そもそも覚えてもらう努力をしていない
そういえば、誕生日が近いなんて一言も話していなかった。事務員の誕生日はカレンダーにメモしてあるが、自分のは書いていない。祝ってもらいたいなら、それなりの準備が必要なのに、それをしていない自分に気づく。やっぱりどこかで「どうせ誰も気にしていない」と思っていたのだ。期待しないことで傷つかないようにしている。そのくせ、どこかで祝われたいと願っている自分がいるのが面倒くさい。
司法書士として生きていく覚悟と孤独
この仕事をしていると、誰かに必要とされている実感と同時に、深い孤独にも向き合うことになる。依頼者の人生の節目には関わるが、自分自身の節目には誰も立ち会ってくれない。誕生日という些細な出来事すら、誰の記憶にも残らない。けれど、それでも登記簿には名前が残る。誰かの記録の中に、自分の手が関わったことがあるという事実がある限り、前を向いて仕事を続けるしかない。
誕生日が苦しく感じるのは期待があるから
「誰にも期待しない」と言いながらも、どこかで「誰かに覚えていてほしい」と願ってしまう。だからこそ、誕生日が余計に苦しく感じるのだろう。誕生日に傷つくというのは、他人への期待と、自分への失望が重なった瞬間なのかもしれない。そう思うと、自分の心の弱さを突きつけられるようで、苦しくなる。でも、それでもいい。そういう気持ちを持てるだけ、まだ人間らしさは残っている。
でもこの年齢で祝われたら逆に戸惑う
とはいえ、実際に誰かがサプライズでケーキを用意してくれたら、たぶんものすごく戸惑うと思う。「いやいや、そんなのいいから」と照れ隠しをしつつ、内心では嬉しいのかもしれないが、素直に喜べる自信がない。変に気を遣わせたくないという気持ちもあるし、そういう“演出”を受け止める器が自分にあるのかも怪しい。だからやっぱり、「登記簿に記録されるだけ」で十分なんだろう。
数字が増えるだけの現実を笑うしかない
今年もまた、登記簿に年齢が一つ増えた。それだけのことだ。でも、それが日々積み重ねてきた結果であり、誰かの役に立ってきた証でもある。祝ってくれる人はいないし、プレゼントもない。でも、そんな日常のなかで、今日も黙って仕事を続けられた自分を、少しだけ褒めてやろう。結局はそれしかない。笑うしかないのだ、この数字が増えるだけの誕生日を。