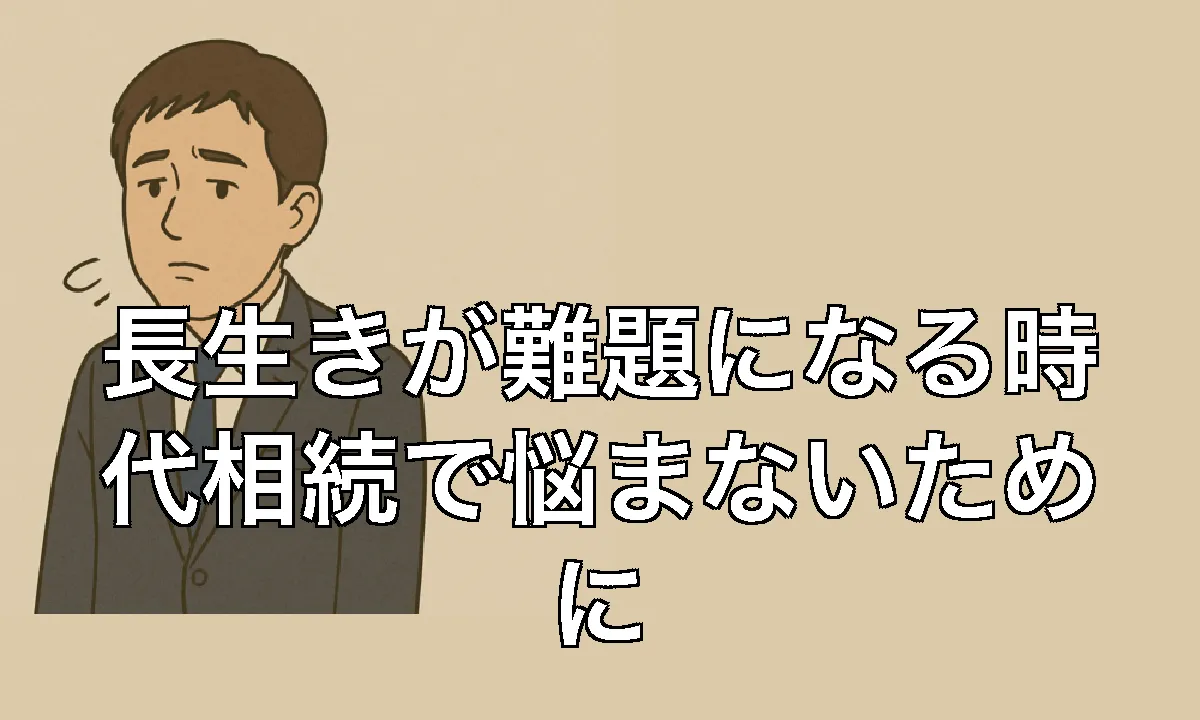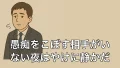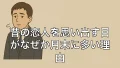長生きが難題になる時代相続で悩まないために
親が元気なうちにはじまる相続の難しさ
「うちの親はまだ元気だから相続の話なんて早いよ」——そう思っている方、実は多いのではないでしょうか。司法書士として十数年やってきましたが、相続の相談に来るタイミングって、だいたい“何かが起きた後”なんです。病気や認知症の発覚、あるいは亡くなった後。そこから慌てて書類を集めたり、兄弟で話し合いをしたり…。でも、そんな時に冷静な判断なんてできませんよね。だからこそ、元気なうちの話し合いが一番大事なんです。とはいえ、それが難しい。実の親に「遺言書書いてよ」なんて言いづらいのは、僕だってわかります。
相談はまだ早いと言われるもどかしさ
「そんな縁起でもない話するな」と言われたこと、僕もあります。実家に帰省した際、母に「相続のこと、そろそろ考えといたほうがいいよ」と軽く口にしたら、「あんたは私が死ぬのを待ってるのかい」と怒られたんです。冗談のつもりでしたが、真顔で言われると、こっちも黙るしかない。でも、心のどこかでは“そろそろ準備しなきゃ”という思いがあるんですよね。こういう“話したいけど話せない”時間が、どんどん事態をこじらせていくんです。
「元気なうちは大丈夫」という安心の罠
親が元気で明るく過ごしていると、「まだ先の話」と思ってしまいがちです。でも、元気な人ほど急な病気や事故で状況が一変することもあります。実際、僕の依頼者にも「昨日まで畑仕事してた父が、今日倒れて意識が戻らない」と泣きながら来られた方がいました。元気だったことが逆に油断につながってしまうケースもあります。だからこそ、“今が一番話しやすいタイミング”だと考えてほしいんです。
準備しない家族ほどトラブルに直面する
「うちは仲がいいから大丈夫」と言っていた家族ほど、揉めるときはとことん揉めます。例えば、父が急逝し、遺言書もなかったため、長男と次男で財産分けをめぐって対立したケースがありました。長男は「親の介護は俺がやったんだから多めに」と主張し、次男は「それは勝手にやったことだ」と言い返す。結果、家族の絆はバラバラに。準備をしなかった代償は、金銭的な損失以上に、関係性の崩壊として表れることがあるのです。
長寿が当たり前になったからこその相続リスク
今や人生100年時代。長生きすることは喜ばしいことですが、その分、老後の生活費や医療・介護費も膨らみます。「まだ相続税のことは考えなくていい」と思っていたら、逆に親の貯金が底をついて、いざ相続の段階で“遺産がない”なんてことも珍しくありません。特に地方では、自宅の土地建物しか財産がないケースも多く、流動性のない資産が争いを生む原因になってしまいます。
遺産が減る心配より介護費用が先にくる
数年前、僕の友人の家でも似たようなことが起きました。親が要介護状態になり、施設に入ることに。月額20万円以上かかる介護費用は、親の年金だけでは足りず、兄弟が分担して支払うことに。しかし、その後「こんなにお金出したんだから、その分相続は多くもらって当然」と言い出す兄がいて、結果、兄弟関係が壊れてしまったそうです。相続の前に、介護という現実的な“出費”が先にやってくる。これは、長生き社会ならではの落とし穴だと思います。
「親の預金が尽きた」から始まる争い
あるご家族では、父親の入院費が重なり、貯金をすべて使い切ってしまいました。「財産は家しか残っていない。どう分けるか」と相続人たちが集まったとき、それまで穏やかだった兄弟の雰囲気が一変。「俺が介護した分を評価してくれ」「固定資産税は誰が払うんだ」などの不満が噴出しました。資産が多くても争いになりますが、むしろ資産が少ないと“わずかなものをどう取るか”で争いになる。皮肉なものです。
長生きする親と相続を待つ子の心の距離
僕の知り合いの司法書士が言っていました。「長生きは幸せだけど、相続を待つ立場の子にとっては複雑だよな」と。言葉には出さなくても、「まだ生きてるのか」「いつまで施設費払い続けるんだ」と思ってしまう子もいるのが現実です。こんな感情、誰にも言えない。でも、相続という仕組みの中で、どうしても“親の死”が前提になってしまうから、そんな心の距離が生まれてしまう。こうしたモヤモヤをどう解消していくかも、僕ら専門職に求められているのだと思います。
兄弟間の温度差はなぜ生まれるのか
相続に関わる相談で、特に多いのが「兄弟仲が悪くなった」というケースです。これ、本当に多いです。僕が扱った案件でも、相続をきっかけに数十年会っていない兄弟が再び顔を合わせたものの、話し合いはすぐに決裂。あとは弁護士を通すしかない…そんな状況も少なくありません。その原因の一つが“温度差”です。
面倒を見てる子ほど報われない感情
親の介護や通院の付き添いをしていた子ほど、「自分ばかり苦労してるのに」と感じやすい。なのに、いざ相続となれば、法律は“公平”を前提とする。「平等じゃない、納得いかない」という感情が募るのも無理はありません。ある依頼人は、「兄は一度も親に会いに来なかった。なのに遺産は半分?ふざけてる」と吐き捨てていました。気持ちは痛いほど分かる。でも、それを法の下でどう整理するかは、本当に難しい問題です。
話し合いができない家族のリアル
多くの家族が「話し合えば済む」と思っています。でも実際には、何十年も会っていない兄弟がいきなり冷静な話し合いなんてできるはずがない。ましてや、感情がこじれている相手なら、なおさらです。「弁護士を呼ぶのは最後の手段」とよく言いますが、感情が暴走する前に、第三者の専門家を交えた方がいいと僕は思っています。冷静な視点が入るだけで、対立が和らぐこともあるからです。
「うちは揉めない」がいちばん危ない
「うちは兄弟仲がいいから大丈夫」——この言葉を、僕は何度裏切られてきたかわかりません。普段仲が良くても、お金が絡むと人は変わります。特に“実家の処分”や“仏壇の管理”といった感情面が絡む問題は、争いの火種になりやすい。油断せず、元気なうちにきちんと話し合っておく。これが一番の予防策だと思います。
専門家が見てきた失敗とその対処法
僕たち司法書士は、争いの現場にも立ち会いますが、できればその一歩手前で関わりたいといつも思っています。問題が起きる前に、「予防する」という視点で動くことで、家族を守れる可能性が高まるんです。経験上、失敗するパターンには共通点があります。
遺言書があっても解決しないパターン
「遺言書を書いておけば大丈夫」——これも、誤解の一つです。たしかに遺言書は有効な手段ですが、それだけでは不十分な場合があります。例えば、遺言の内容が曖昧だったり、相続人の間で感情的なわだかまりがあったりすると、結局は調停や訴訟になるケースも。だからこそ、遺言書は“書くだけ”ではなく、“どう伝えるか”が大事なんです。
形式よりも本音の共有がカギになる
法的な書類は整っていても、家族の間で気持ちの整理ができていなければ、トラブルの火種は残ります。形式だけに頼らず、本音で話せる場をつくること。それができるのは、当事者だけでなく、時には僕たち外部の人間かもしれません。だからこそ、書類作成だけでなく、家族の“橋渡し”も僕の仕事だと感じています。
司法書士としての現場から見えること
田舎の小さな事務所ですが、日々いろんな人生と向き合っています。長生きは素晴らしい。でも、その先にある現実も知っておくべきです。僕たちの役目は、単に登記を済ませることじゃない。家族が、未来を穏やかに迎えるための“整備係”なのかもしれません。
書類の準備はできても気持ちは整理できない
相続手続きは期限もありますし、やるべきことは山ほどあります。でも、一番の課題は、手続きじゃなくて「気持ちの整理」なんです。書類を前にして涙をこらえる依頼人を見るたび、僕も心が揺れます。だからこそ、形式だけでなく、気持ちに寄り添うサポートが必要なんだと痛感しています。
長生き社会に求められる法務の役割
100歳まで生きる人が増えていく中で、法務の役割も変わってきています。相続は「死後の手続き」ではなく、「生きているうちの準備」です。そんな時代だからこそ、司法書士は“予防法務”の担い手として、家族に寄り添いながら、冷静なアドバイスをしていく必要があると思います。愚痴も多いけど、これからも誰かの役に立てたら、と思いながら仕事しています。