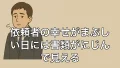家より事務所が落ち着くと言い切った日
気づけば家に帰る理由がなくなっていた
仕事が終わっても、なかなか家に帰る気にならない日が増えた。家に帰れば誰かが待っているわけでもなく、テレビをつけたところで虚しさが広がるばかり。冷蔵庫を開けても、空気しか入っていないような感覚。事務所には紙の匂いとパソコンの低い音、微かに漂うインスタントコーヒーの香り。それがなぜか安心する。自宅よりも事務所の方が、自分にとって「今ここにいていい」と思える空間になっていた。
夕方のチャイムよりも安心できる書類の山
小学生の頃、夕方のチャイムが鳴るとなんとなくホッとしたものだ。「そろそろ家に帰らなきゃ」と思わせる、あの音。でも今は、書類の山に囲まれているほうがずっと安心する。山積みの書類は、誰かの人生の一部であり、それを自分が預かっているという実感がある。あの「面倒くさい案件たち」が、逆に自分の存在を肯定してくれているように思えるのだ。サインのインクが染みる音が、今日も自分を支えている。
気づけば事務所が「居場所」になっていた
いつの間にか「帰る場所=家」ではなく、「帰る場所=事務所」になっていた。パソコンを閉じて、電気を落とすその瞬間に、自分が1日を終えたことを実感できる。自宅では、どこか終わらない時間がだらだらと続くだけで、けじめがつかない。結局、事務所で時間を過ごすほうが、自分の輪郭を保てる気がする。友人には「病気かよ」と笑われたが、それでも事務所のほうが居心地がいいのだから仕方がない。
電気ポットの音が一番ホッとする時間
事務所にある電気ポットが、ふつふつと湯を沸かす音を聞くと、自然と気持ちが落ち着く。誰もいない静かな部屋に響くその音は、もうひとりの同居人みたいなものだ。ポットに「ただいま」と言いたくなる夜もある。家のキッチンではこんな感情は湧かない。お湯を注いでインスタントコーヒーを飲む時間が、今の自分には一番落ち着くひとときかもしれない。寂しいと感じることすら、もう感覚が麻痺しているのかも。
家にいても誰も待ってない
かつては帰る家があった。もっと言えば、誰かが待っていてくれる家だった。でも今は違う。玄関を開けても、真っ暗な部屋と無言の空気が迎えてくれるだけ。おかえりの声がない生活に慣れてしまったら、逆に誰かが待っている空間が落ち着かなくなる。家が「ただの空間」になってしまった今、感情のよりどころを求めて事務所に居座るようになってしまったのかもしれない。
テレビの音よりFAXの受信音が心地いい
家に帰ってテレビをつけても、何も頭に入ってこない。ニュースキャスターの声も、バラエティ番組の笑い声も、どこか遠くで響いているような感じがする。それよりも、事務所で突然「ピーヒョロロロ…」と鳴るFAXの受信音のほうがよっぽど安心できる。誰かとつながっている音。仕事という役割を自分に与えてくれる証拠。事務所の機械音が、自分を現実につなぎとめてくれている。
独り身には静かすぎる自宅の夜
独身生活が長くなると、静かな部屋に耐性がなくなる。いや、逆に耐性がありすぎてしまうのか。音のない部屋、話し相手のいない時間。それが延々と続くと、たまに帰ってきたはずの家がまるで他人のもののように思えてしまう。照明のスイッチを押す手も、どこか無機質になる。だったら、24時間体制で動いている事務所の方が、まだ生きている実感がある。
布団に入っても眠れない理由
家の布団に入ると、なぜか眠れない。身体は横たわっているのに、頭の中はぐるぐると考え事が止まらない。むしろ、事務所の仮眠ソファのほうが寝つきがいいなんて、普通の人からしたら意味不明だろう。でもそれが現実だ。眠れない原因は、もしかすると「何も起きない安心感」による不安なのかもしれない。事務所の緊張感の中の安堵の方が、今の自分には合っている。
事務所の方が人とつながっていられる
意外かもしれないが、事務所には人との接点がある。電話、来客、事務員さんとのやり取り。家にいれば一言も発さないで終わる日だってあるけれど、事務所にいれば、どんな形であれコミュニケーションが発生する。その些細なやり取りが、自分を人間らしく保ってくれているのかもしれない。だから、ついつい仕事が終わってもダラダラと事務所に残ってしまう。
事務員さんとの雑談に救われることもある
うちの事務員さんは、たまに愚痴を聞いてくれる。こっちが忙しくてイライラしている時でも、コーヒーを出しながら「今日は雨ですね」とか「なんか静かですね」なんて言ってくれるだけで、心が少し軽くなる。家では誰とも言葉を交わさない自分にとって、そうした一言がどれだけありがたいか。仕事の話じゃなくてもいい。ただ人間らしい会話が交わせる場所、それが今の事務所だ。
お客さんとの会話が一日のハイライト
相続や登記の相談に来るお客さんと、時には関係ない世間話で盛り上がることもある。世間話が長引いて「で、今日は何のご相談でしたっけ?」なんて笑い合う瞬間が、何よりの救いになる。司法書士って、淡々と書類を処理する仕事と思われがちだけど、案外人間味のある時間もある。そういう時間に触れているとき、「ああ、自分まだ捨てたもんじゃないな」と感じる。
電話が鳴らないと不安になる矛盾
本来なら「電話が鳴らない=平和」なはずなのに、最近は電話が鳴らないと逆に不安になる。誰からも必要とされていない気がして、ソワソワしてしまう。逆に電話が鳴ると、多少面倒な内容でも嬉しい気持ちが混じる。これって職業病なのか、ある種の依存なのか。いずれにせよ、事務所の「音」が今の自分には必要な支えになっているのは間違いない。
居心地の良さは諦めた先にあった
事務所が居心地よくなったのは、ある意味「諦めた」結果かもしれない。家を快適にする努力も、プライベートを充実させる気力も、どこかで手放してしまった。そんな自分が行き着いたのが、無機質だけど妙に落ち着く事務所という空間だった。理想の居場所じゃないけど、今の自分にはちょうどいい。そんな折り合いのつけ方も、人生にはあるのだと思う。
自宅を快適にする努力はいつしか途絶えた
最初は観葉植物を置いたり、アロマを炊いたり、自宅を快適にしようとした時期もあった。でも、仕事が忙しくなるにつれ、それらのメンテナンスが億劫になり、気づけば植物は枯れ、アロマは埃をかぶったまま。結局、自宅が快適にならない理由は「継続できない自分」だった。それならば、整える努力をしなくても落ち着く場所を選ぶしかなかった。
背中を預けるのはソファではなく事務椅子
リクライニングソファなんて、夢のまた夢。結局、自分が毎日背中を預けているのは、事務所の少しギシギシいう椅子だった。でも、その椅子の背もたれに体を預ける瞬間が、なぜか一番安心する。背筋を伸ばして座るその姿勢が、自分に「まだやることがある」と言い聞かせてくれる。ラクな姿勢よりも、踏ん張れる姿勢を選んできた人生。その結果がこれなのかもしれない。
落ち着ける場所が仕事場という不思議
仕事場で落ち着くって、普通は変だと思う。でも今の自分にはそれが自然になってしまっている。誰もいない事務所の夜、パソコンの光だけが灯る空間に、自分の存在を感じる。静寂の中にある使命感、孤独の中にある安心。仕事に逃げているのかもしれない。でもそれでも、落ち着ける場所があるというだけで、少し救われている気がする。