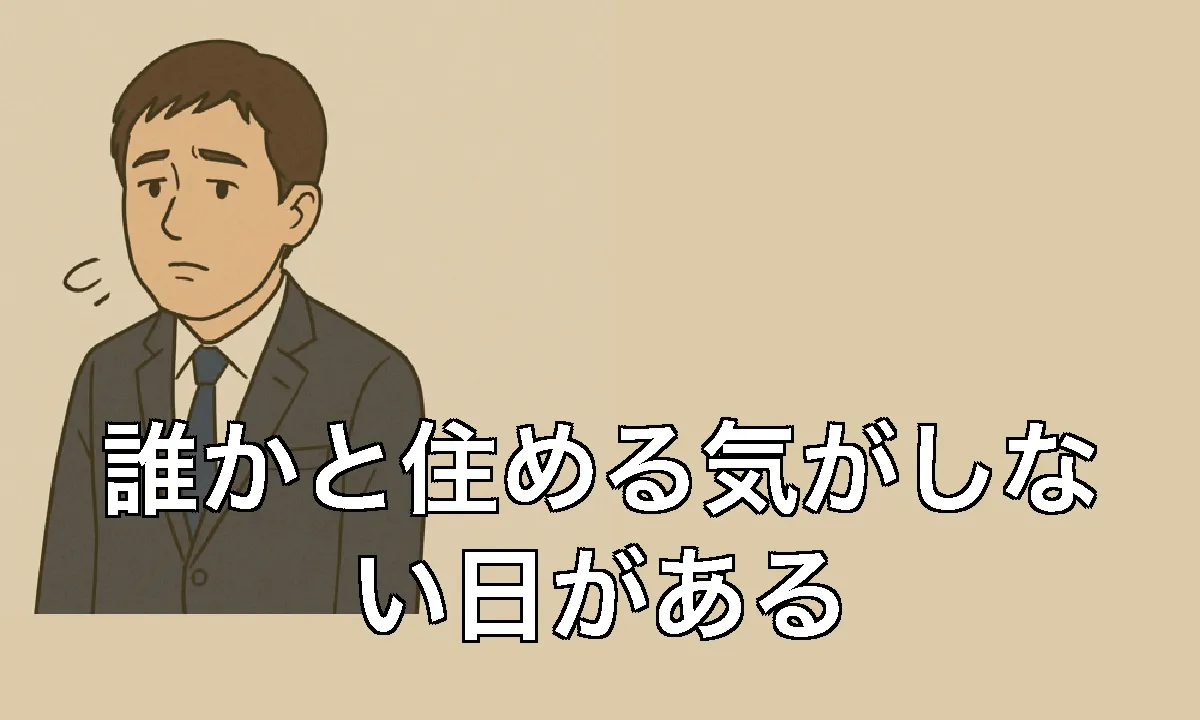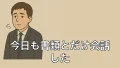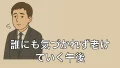ひとり暮らしが当たり前になった日常
司法書士という仕事柄、毎日多くの人と関わっているように見えて、実は意外と孤独です。登記の申請も、打ち合わせも、事務員との最低限のやり取りで済んでしまう。そんな生活が続くうちに、自宅では誰かと一緒にいることが煩わしく思えるようになってきました。自炊も洗濯も掃除も、すべて自分のペースでできる。昔は「寂しいな」と思っていたひとり暮らしが、今では快適すぎて、もう誰かと一緒に住む生活なんて考えられなくなってしまいました。
人と暮らすのが想像できないという感覚
大学時代、下宿の隣人と風呂やトイレの取り合いになったことがあります。そんな日々を思い出すと、今の静かな生活は天国のようです。誰にも気を遣わずにテレビを消して眠れる夜。冷蔵庫に入れたプリンが翌日も無事に残っている幸せ。こうした些細な「自由」が積み重なると、誰かと空間を共有すること自体がストレスのように感じてしまいます。まるで自分専用の世界が完成してしまったかのようです。
無言の時間にストレスを感じなくなった
家に帰ってきてから一言も声を発しないまま寝る、そんな日があっても何も感じなくなりました。以前は「誰かと話したいな」と思ったこともありましたが、今ではむしろその無音こそが心地よい。誰にも話しかけられず、誰にも邪魔されない時間が、自分にとっての癒しの時間になっているのです。それはまるで、ひとりきりの図書館に閉じこもっているような安心感があります。
話し相手がいない日でも平気になった理由
最初は「誰とも会話してないな、まずいかな」と不安になることもありました。でも、話し相手がいないことに慣れてしまうと、その不安も消えていきます。最近では、週末に誰とも連絡を取らなくても何の問題も感じなくなりました。仕事では人と接するし、それで充分だと感じてしまう自分がいます。むしろ、誰かと予定を合わせる方が面倒に感じるようになったのです。人間関係に疲れたというより、「ひとりが快適すぎる」ことが原因かもしれません。
孤独と快適のあいだで揺れる気持ち
とはいえ、完全に孤独を楽しんでいるかというと、そうでもない時もあります。夜中にふと、テレビもスマホも見ずに静かな部屋でぼーっとしていると、「この生活いつまで続けるんだろう」と怖くなることがあります。誰にも必要とされていないような気がしてしまうのです。快適だけど、どこか虚しさもある。そんな複雑な感情が、ふとした瞬間に押し寄せてくるのです。
帰宅してから一言も発さない夜
仕事が終わって、事務所を閉めて、コンビニで晩酌用の缶ビールと冷凍チャーハンを買って帰る。そのまま何も喋らず、テレビを見ながら食事を終え、風呂に入って寝る。そんな生活が続くと、ふと「今日、誰とも会話してない」と気づく瞬間があります。でも、そのことに対して特に寂しさを感じない自分がいて、逆に怖くなるのです。孤独というより、「慣れ」が感情を麻痺させているような感じです。
インターホンが鳴るだけで動揺する
ひとり暮らしが長くなると、突然の訪問にものすごく敏感になります。宅配便ならまだしも、玄関チャイムが鳴ると「誰だ?」と一瞬身構える自分がいます。たとえそれが知人だったとしても、突然の来訪に心の準備ができない。人と接することへの耐性が、どんどん下がっている気がします。この感覚、昔はなかったはずなんですけどね。
気配に敏感になりすぎた副作用
一人暮らしだと、家の中の物音や外から聞こえる足音にも敏感になります。たとえば深夜、どこからともなく聞こえるドアの開閉音や足音に、不安になることがあります。「誰か入ってきたんじゃないか」と身構えるのですが、たいてい何も起こりません。普段は誰もいない空間だからこそ、ちょっとした音がやけに気になるのです。ひとり暮らしの快適さには、そんな“神経質”という副作用もあるように感じます。
結婚とか共同生活とかの現実味がなくなる
たまに親戚や友人から「結婚しないの?」と聞かれることがありますが、正直、結婚して誰かと暮らすという未来がまったく想像できません。もともと恋愛が得意なほうでもないし、仕事も忙しいし、「ひとりでいること」に完全に慣れてしまった今となっては、他人と生活を共有するのが怖いのです。ひとり暮らしが長くなると、心のハードルがどんどん上がっていくのかもしれません。
共有スペースのストレスが想像できてしまう
他人と風呂やトイレを共有するのは、今やちょっとした恐怖です。自分のペースで過ごせない、使いたいときに使えない、掃除の基準が違う…そう考えると、どうしても共同生活に対して抵抗感が出てきてしまいます。たとえ恋人や家族でも、自分の空間に他人が入ってくるということ自体に、強い違和感を覚えてしまうのです。これも、ひとり暮らしに「慣れすぎた」証拠なのかもしれません。
他人に合わせる感覚を忘れつつある
昔は「相手に合わせるのが大人の対応だ」と思っていたのですが、今はその感覚すらも薄れてしまいました。自分のリズム、自分の判断、自分のタイミングが一番心地いい。それが続くと、他人に気を遣うことがどんどん面倒に感じてしまいます。そうなると、人と一緒に住むという選択肢はどんどん遠のいていくのです。
誰かと暮らす未来が怖く感じる瞬間
将来もし、体調を崩して誰かに世話になるような時が来たら、そのとき自分はうまく受け入れられるのか、と考えることがあります。誰かと一緒に住むということは、甘えたり頼ったりすることでもある。でも、長年「誰にも頼らず生きる」が当たり前になると、急にそれができるか不安になります。結婚に限らず、介護や同居の話も、今の自分には重く感じてしまいます。
ひとりの生活に潜む落とし穴
自由で快適なひとり暮らし。でも、その裏側には、見えにくい落とし穴がいくつもあるように思います。人との距離が開きすぎることで、いざというときに助けを求めにくくなる。感情の共有を避け続けて、共感の仕方を忘れてしまう。そんな小さな「ひずみ」が、じわじわと心を蝕んでいるような気がしてならないのです。
突然の体調不良に気づく人がいない
ある日、風邪で寝込んだとき、誰にも連絡せずにひとりで寝ていました。ポカリを買いに行くのも面倒で、水だけ飲んで1日中ベッドにいたことがあります。そのときふと、「もし自分が倒れてたら、誰が気づくんだろう」と思って怖くなりました。普段の生活では気にならないけれど、いざというときの孤独は想像以上に重いものです。
休日に声を出さないまま一日が終わる
日曜日、どこにも出かけず、誰にも会わず、テレビも見ず、スマホすらほとんど触らない。そんな日が何度もあります。気づけば夜になり、声帯を一度も使っていないことにハッとする。この無音の空間が、最初は贅沢だと感じていたけれど、今では少しだけ怖くなることもあります。人として、何かを失っている気がするのです。
気を張らなくていい生活が心を緩ませすぎる
誰にも見られていない生活は、どこまでもだらしなくなれます。服装も、食事も、生活リズムも、全部が「自分基準」。それはとても自由だけど、同時に「気を張る」場面が極端に減る。緊張感のない生活に慣れすぎると、社会との接点がどんどん希薄になっていくようで、たまに不安になります。このまま歳を重ねたら、自分はどうなってしまうのか…。そんな不安がふとよぎるのです。