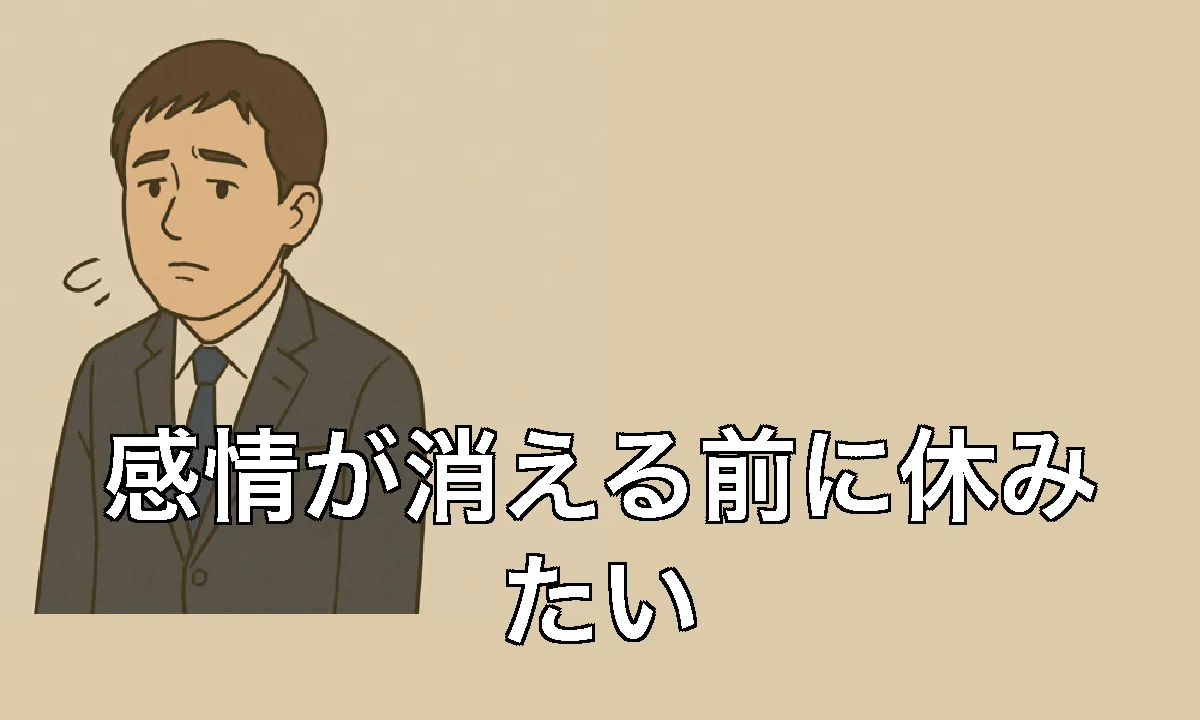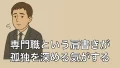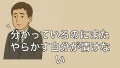感情が消える前に休みたい
一見やりがいがあるようで削られていく感覚
司法書士という仕事は、一見すると「人の役に立つ」やりがいのある仕事だと思われがちだ。でも、実際はどうだろう。依頼がひっきりなしに届き、感謝の言葉すら心に響かなくなる日がある。人の感情に寄り添いながら、いつのまにか自分の感情がすり減っていることに気づかなくなるのだ。自分でも怖いのは、「ありがたい」と思う気持ちが薄れていくこと。誰かの人生に関わる責任の重さと、感情を削る日々。その狭間で、心のブレーキが効かなくなっていく。
相談されることが喜びだったはずなのに
独立して事務所を構えたばかりの頃は、相談されることがうれしかった。自分の知識が誰かの役に立つ。それが誇りでもあった。でも、ある日ふと気づいた。相談の数が増えれば増えるほど、心の余白がなくなっていく。事務員は一人だけ。電話は鳴りっぱなし、締切は迫る。そんな中で「ちょっといいですか?」と軽く声をかけられるたび、かつての自分なら笑って応じていたはずなのに、今では心の中で舌打ちしている。
依頼が続くと、声すら聞きたくなくなる
疲れがたまってくると、電話の着信音ですらストレスになる。人の声が、要望や文句にしか聞こえなくなってくるのだ。まるで、耳元でずっとドリルが鳴っているような感覚。たとえそれが「助けてほしい」という純粋な相談であっても、こちらの心の余裕がなければただの「負担」になる。電話に出る前に、深呼吸してから応対する自分を見て、「あぁ、自分はもう限界に近いのかもしれない」と思った。
「ありがとう」が重荷に感じる日もある
「ありがとう」って、本来うれしい言葉のはず。でも、疲れ切っているときに言われる「ありがとう」は、自分の中で「もっと頑張って」というプレッシャーに聞こえてしまう。優しい依頼者ほど、申し訳なさそうに感謝を伝えてくれる。その姿を見るたび、「こちらこそすみません、休ませてくれ」と心の中でつぶやいている自分がいた。これは本当に、感情が枯れかけているサインだったと思う。
「休みたい」と言えない空気
休むべきだと頭では分かっている。でも、現場の現実はそんなに甘くない。特に地方の小さな事務所で、スタッフは自分を含めてたった二人。誰かが抜けたら、即、業務が回らない。だから「休みたい」と思っても、口にはできない。いや、言ったところで代わりがいない。「今日だけでも寝かせてくれ」なんて、弱音すら贅沢なような気がしてしまう。
事務員ひとりの現場で倒れたら終わり
以前、軽いめまいで倒れかけたことがある。ちょうどその日は登記の締切直前で、書類の山に埋もれながら作業をしていた。ふと立ち上がった瞬間、目の前が真っ白になった。すぐに椅子に戻ったが、「このまま倒れたら、あの登記どうなるんだ?」という思考が真っ先によぎった。自分の体よりも、業務の心配。これはもはや、職業病なんだと思う。
自分が抜けた後のことばかり心配してしまう
休むことを考えるとき、まず浮かぶのが「誰が代わりをやるのか」という問題。事務員に任せられる部分もあるけれど、司法書士としての責任ある部分は自分にしかできない。仮に一日休んだとしても、その分のしわ寄せは確実に後日にくる。だから結局、休んだことで余計に疲れるだけ。そんな悪循環が続くうちに、「休む意味あるのか?」と思い始めてしまう。
休むことが「逃げ」だと思っていた
昔から「休む=サボり」という刷り込みがある。野球部時代も、風邪を引いてでも練習には顔を出していた。「根性」と「我慢」が美徳とされてきた。だからこそ今でも、どこかで「休むと負けだ」と感じてしまう。でも本当は、休むことこそが自分を守る手段なんだ。頭では理解していても、身体がそれを許してくれない。そんな矛盾に、何度も自分で自分を苦しめてきた。
野球部時代の根性が足を引っ張る
高校時代、炎天下で倒れかけながら走ったグラウンド。あのときの「もう一歩前へ」の精神が、いまだに抜けない。司法書士として働くようになってからも、その根性論はずっと自分の中に残っていた。だけど今、思う。「もう一歩前へ」じゃなくて、「一歩引いてもいいんだよ」と誰かに言ってほしかった、と。
「踏ん張れ」が染みついた身体
朝、目覚ましの音を聞いて、「もう少しだけ寝たい」と思う日が増えた。でも、すぐに「いや、今日も踏ん張らないと」と立ち上がる。無意識のうちに、身体が「我慢モード」に切り替わっている。学生時代の部活の習慣が、いまだに自分の行動原理に残っていて、それが逆に今では足かせになっていることに気づいた。
休む勇気より我慢の癖が先に出る
本当は、今日はもう何もせず寝ていたい。気力がまったく湧かない日だってある。でもそんなときに限って、「○○さんから至急連絡」とか「登記申請が通らない」とか、何かしらのトラブルが起きる。そして「じゃあ、やるか…」とパソコンに向かう。こういう小さな我慢の積み重ねが、結局、自分の心を削っていく。
壊れてからじゃ遅いと知ってはいるけれど
壊れてからでは遅い──そんな言葉、何度も聞いてきた。でも実際に、自分が壊れる一歩手前になってみて、やっとその意味が分かった。疲れ切って布団の中で涙が出たとき、「もうダメかもしれない」と思った。そのとき初めて、心がSOSを出していたんだと気づいた。でも、できればその前に、誰かに「休んでいい」と言ってほしかった。
誰も責めていないのに責めているのは自分
一番厳しいのは、自分自身だったのかもしれない。他人は何も言わない。「そんなに働かなくてもいいよ」「もっと休んで」と言ってくれていたかもしれない。それでも自分で「いや、まだやれる」「やらなきゃダメだ」と無理をする。責めているのは、自分だった。
「あの先生はもっと働いてる」と比較してしまう
業界内には、タフで仕事もバリバリこなす司法書士がたくさんいる。SNSを見れば、「今日も登記完了10件!」なんて投稿が並んでいる。それを見るたび、自分はまだまだだと落ち込む。他人と比べても意味がないと分かっていても、気になってしまう。そして「自分は甘いのかも」と思って、また休めなくなる。
独立したのに自由を感じない理由
独立したのは、自分のペースで仕事をしたかったから。でも、現実は違った。自由なはずなのに、自由がない。休みを決めるのも自分、働きすぎるのも自分。全部自分次第だからこそ、逆に「もっと頑張らなきゃ」となってしまう。自由と孤独は、表裏一体なのかもしれない。
本当の「責任感」とは何かを考え直す
最近、責任感って何だろうと考える。無理して続けることが責任? それとも、自分を守ることもまた責任? 感情が消える前に、ちゃんと休む。それは「逃げ」ではなく、長くこの仕事を続けるための選択なのかもしれない。次の世代にバトンを渡すまで、ちゃんと生きていくために──。