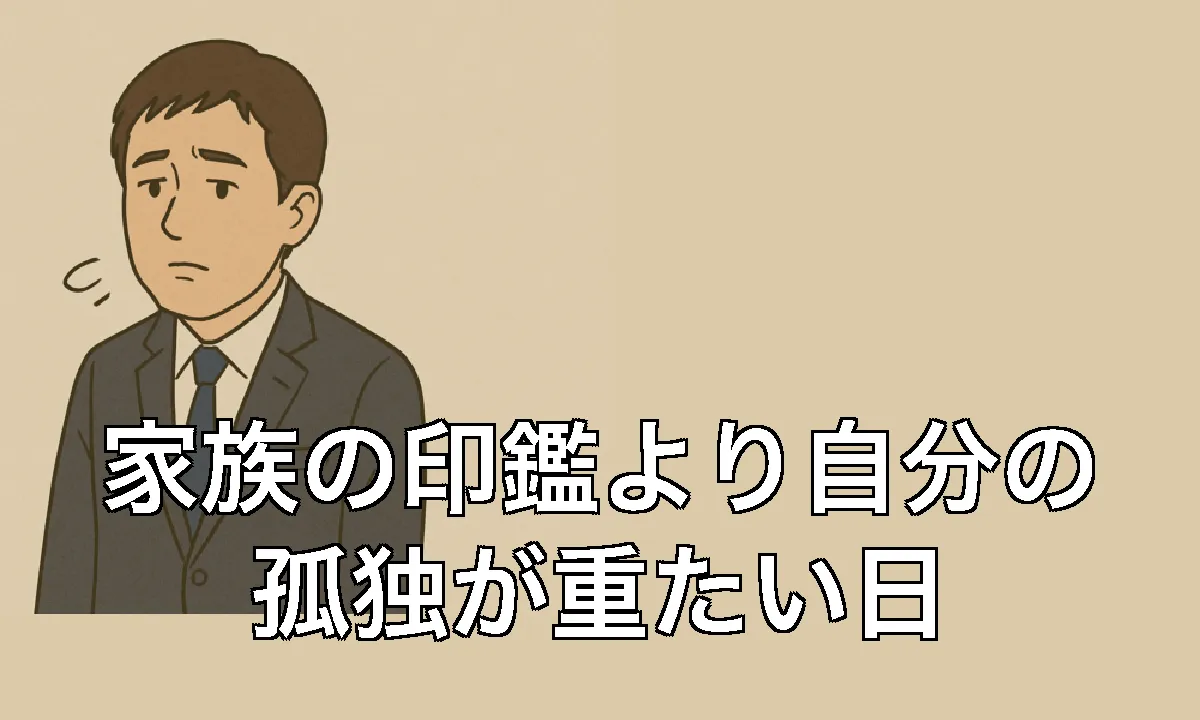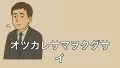家族の印鑑より自分の孤独が重たい日
家族の印鑑を預かるという仕事
「お世話になります。父の遺産分割協議書、こちらでお願いしたくて……」
控えめに差し出された封筒の中には、兄弟姉妹全員の実印と印鑑証明が揃っていた。仕事としては滞りなく進む案件。けれど、僕の胸の奥には別の重さが沈んでいた。
役所の書類が語る無言のドラマ
依頼人の兄妹は不仲かと思いきや、全員が同じ日に印鑑を用意していたらしい。その連携の良さに少し驚いた。「フネさん家の大家族かよ」と、ふと心の中で呟いた。みんなで波平の印鑑を押す日が来たら、こんなふうになるのだろうか。
形式的な手続きの裏にある人間模様
印鑑はあくまで形式。でも、そのひとつひとつが血縁をつなぎ、あるいは断ち切る証でもある。役所で交わされる数秒のやり取りの裏には、何十年の記憶と感情が詰まっている。
他人事のようでいて胸がざわつく瞬間
「家族って、いいですね」と笑う依頼人の顔が、妙にまぶしく見えた。僕は無言でうなずきながら、内心ではこう思っていた――自分には、もう実家の住所さえ思い出せない。
朱肉のにじみより濃い心の孤独
書類に押された印鑑は鮮やかな朱だった。でも、それを受け取る僕の心には、色も形もない何かがどす黒く滞っていた。
孤独は音もなく押し寄せる
仕事を終え、椅子に深く腰を沈めたとき、不意に訪れる静寂。昼間の喧騒がまるで嘘のように消え、自分の存在がぼんやりと浮かび上がる。
依頼人の家庭の絆を見せつけられるたび
「兄が全部手配してくれたんですよ」「姉が昔から仕切り屋でして」そんな些細な会話に、僕は嫉妬すら覚えていた。兄も姉も、僕にはいない。
自分だけが透明になっていく感覚
「書類はこれで完璧ですね」笑顔で答える僕は、透明なレインコートを着ているようだった。誰からも見えるけれど、誰の心にも触れられない存在。
シンドウの密かな気づき
「サトウさん、今日はもう帰っていいよ」「えっ、先生は?」「僕は少し残るよ。印鑑の確認があるから」サトウさんは小さくうなずいて、気遣うようにドアを閉めた。その静けさが、今夜も僕の孤独を確かなものにする。
忙しさでは埋まらない空白
机の書類を眺めても、心は一向に満たされない。作業量で誤魔化してきたはずの寂しさが、今夜は騒がしく暴れている。どこかで見た、探偵漫画の主人公みたいに――「推理より、孤独が一番難事件」なんて、皮肉なセリフが脳裏をよぎった。
事務員サトウさんの気遣いに救われる
昼間、サトウさんがさりげなく差し出してくれた缶コーヒー。「甘いやつの方が、今日はいいかと思って」その一言だけで、僕の心は少し救われていた。
でもそれは一時の灯りにすぎない
一口飲んだ缶コーヒーは、すぐにぬるくなってしまった。優しさの温度は、保温ボトルに入れておきたいほどに貴重なのに。
この仕事が好きかと問われたら
「好きだよ」と即答できるほど、僕は正直じゃない。「向いてるとは思う」と濁すのが精一杯だった。
使命感と孤独は共存できるのか
誰かの大切な手続きを担うこの仕事は、確かに誇りがある。でも、それと僕自身の人生とは別問題だ。名探偵コナンはいつだって「真実はひとつ」と言うが、真実が救いになるとは限らない。
独身でいるという選択の裏側
「時間が自由でいいですね」と言われるたび、「いや、余白が多すぎて怖いんだ」と心の中で反論している。けれど、それを口に出す相手もいない。
やれやれ、、、また今日も一人だ
帰り道、電気を点けた瞬間の無音が、今日の終わりを告げる。「やれやれ、、、」テレビもつけず、カバンも投げ出し、今日もまた、家族の印鑑よりも重たい自分の孤独と向き合う時間が始まる。