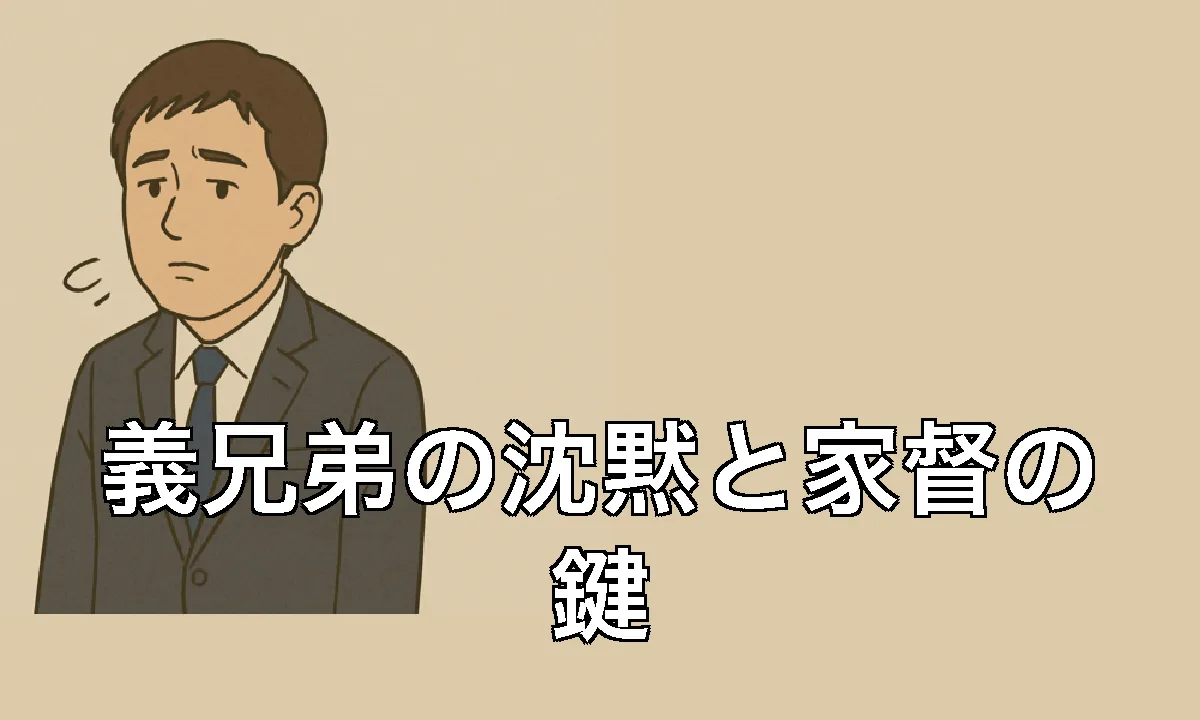相続の相談は唐突に
静かな午前の訪問者
その日も、事務所にはいつものように古びた壁掛け時計のカチカチ音が響いていた。コーヒーの香りとともに始まる、どこにでもある地方司法書士の朝。だが、扉を開けて入ってきたのは、黒い喪服姿の中年男性だった。
「兄が亡くなりまして……」と男は口を開いた。「家督相続のことでご相談がありまして」——それは、まるで昭和の時代から抜け出してきたかのような台詞だった。
私は一瞬眉をひそめた。いまどき「家督」という言葉を口にする依頼人は珍しい。しかし、珍しいほどに面倒なことが多いのもまた事実だ。
義兄弟という名の壁
名義と家の継承者
相談の内容はこうだ。亡くなった兄には実子がいない。そのため、義理の弟である彼が後を継ぐべきだと親族内で話が進んでいるらしい。だが、兄が遺言を残していなかったため、法的な根拠に乏しい。
「兄は私を『実の弟以上の存在』と言ってくれてました」と彼は語る。だがそれを証明する手段は、口約束しかなかった。
さらにややこしいのは、兄の家屋敷の登記がまだ昭和時代のままだったことだ。相続人調査からやり直し、未登記の古文書が出てくる可能性もある。面倒な匂いしかしない。
鍵が語る沈黙
屋敷に残された封印
「鍵は、兄しか知らなかったんです」——彼が差し出したのは、年季の入った木箱と一本の古鍵だった。中を開けると、見慣れたはずの権利証のようなものが……だが、それは正式な登記済証ではなく、明らかに何かが改ざんされていた。
「これ、フォントがおかしいですね」と横からサトウさんが冷静に指摘する。まるで印鑑証明をルパン三世の変装道具で偽造したような雑さだ。
「やれやれ、、、」と思わず口から漏れる。なんだってこう、昭和の亡霊みたいな事案が舞い込んでくるのか。
亡き兄が遺したもの
サザエさん家系図の罠
調べを進めるうちに、思いもよらない事実が浮かび上がる。戸籍上、兄は一度養子に出されていたことがある。そのため家督相続の「本家」と「実家」の線引きが二重構造になっていたのだ。
「つまり、波平さんがフネさんの家に婿養子に入ったと思ったら、実は逆だった……みたいな話ですね」とサトウさんがたとえる。
依頼人の顔が一瞬引きつる。「それって、私が本当の家族じゃなかったってことですか?」——否定も肯定もできない。法的な立場と心の距離は、時にこれほどまでに乖離する。
登記の終わりと沈黙の始まり
相続人欄の空白
最終的に、家屋敷の名義は相続人代表として彼に移された。ただし、それはあくまで形式的なもの。亡き兄が遺した心の遺産までは、書類に記すことはできなかった。
「兄はいつも黙って笑ってたんです」——依頼人は静かに言った。「何も言わなくても、伝わることってあるんですね」
だが、法の世界は言葉と証拠でできている。沈黙は、時に一番の敵なのだ。
そしてまた、日常へ
次のコーヒーを沸かすころ
事件でもなければ、感動の美談でもない。ただ、誰かの人生の節目を見届けるのが、司法書士という生き方だ。
「サトウさん、次のお客さんは?」と声をかけると、「『名義変更と猫の引き取り』って書いてあります」と素っ気ない返事。
やれやれ、、、。コーヒーをもう一杯淹れながら、私は今日もまた黙って書類に向き合う。