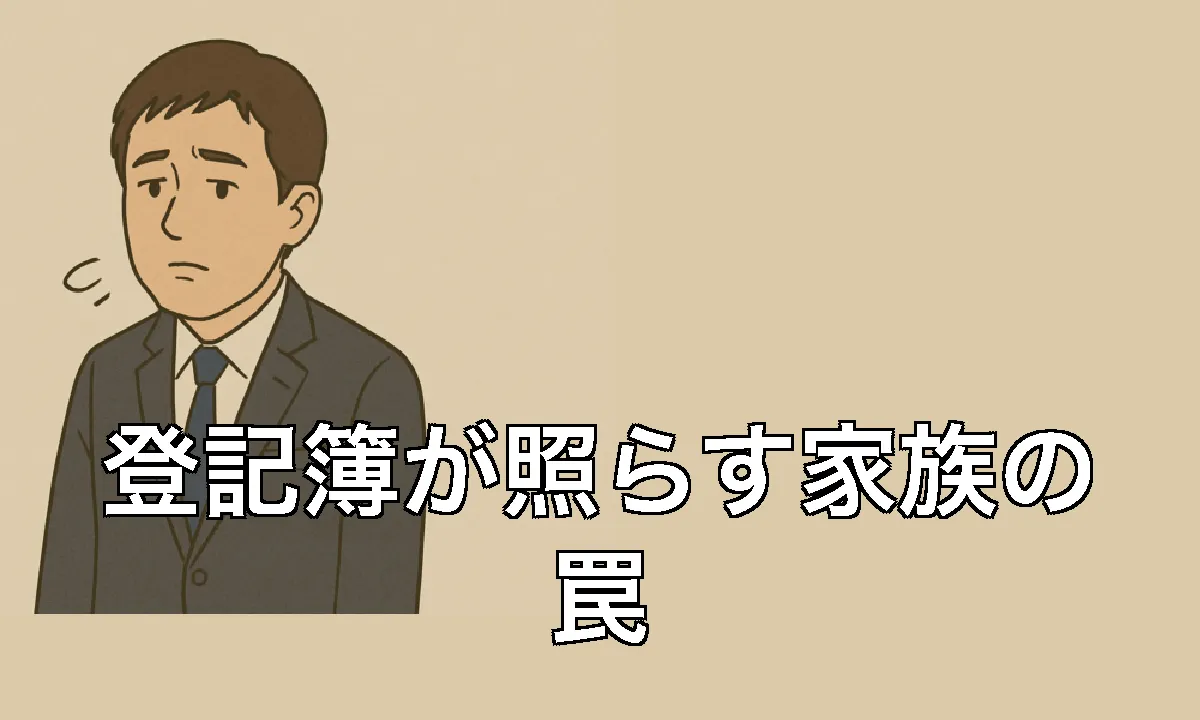古びた家屋と謎の依頼
雨の中の訪問者
午後三時、事務所のドアが重たく開き、ずぶ濡れの女が一人、無言で立っていた。肩にかけたバッグから濡れた書類の束を取り出し、無造作にデスクへ置く。「登記簿が、おかしいんです」それだけ言って、ソファに腰を下ろした。始まったな、と思った。
遺言書の真偽と登記簿の矛盾
出された遺言書は形式的には整っていた。しかし、その記載と照らし合わせた登記簿の内容に、どうにも合点がいかない。被相続人の名義が生前に変更されていたはずなのに、記録では亡くなる直前まで本人名義のままだった。「こういう時、だいたい裏に誰かいるんですよね」とサトウさんがつぶやいた。
サトウさんの冷静な観察
台所の違和感
現地調査に赴いた古びた家屋は、外観こそ荒れていたが、台所だけが異様に整頓されていた。「誰かが使ってるわね、ここだけ異常に新しい」サトウさんが壁の電気メーターを指差した。「数日前にも誰かが電気を使ってる形跡がある」不在のはずの誰かが、まだこの家を使っているらしい。
記録と記憶のズレ
隣人に話を聞くと、「あの家、まだ息子さんが時々来てるみたいよ」と証言が取れた。しかし登記簿では、息子は既に数年前に遠方へ転居したことになっていた。「実は転居届だけ出して、居住実態はこっちってパターンかもな」曖昧な空間が、どこかサザエさんの町内のようで現実味を欠いていた。
登記簿が語る時系列
数年前の相続登記
一番不可解だったのは、相続登記の日付だ。亡くなった父の名義が、死亡から一年以上経ってから変更されていた。「そんなに遅れるものか?」と自問しながら、登記識別情報の通知書を確認すると、封筒の消印がその日付より三ヶ月も前になっていた。つまり、何者かが手続きの前倒しを仕掛けた形跡がある。
「空白の一年」の謎
この「空白の一年」に何があったのか。家は使われていた、名義はそのまま、でも誰もいないことになっている。仮面ライダーじゃあるまいし、変身して別人になった訳でもあるまい。だが、現実はもっとややこしい変身をしていた。登記簿が示していたのは、「存在しない相続人」だった。
隣人の証言と消えた名義人
庭先の会話が鍵を握る
「こないだも夜中に灯りが点いてたよ」そう証言したのは隣の老人。妙に記憶が鮮明で、具体的な日時まで挙げてきた。そこにピンときた。登記簿と防犯カメラの時間軸を突き合わせたところ、一致したのは息子ではなく、依頼人本人の動きだった。つまり、彼女がずっと家にいたのだ。
遺族が隠したもう一つの顔
依頼人は「兄が遺産を独り占めした」と言っていた。だが実際には、兄の名義変更すらされていなかった。それどころか、兄はすでに亡くなっており、彼女自身が遺言書を偽造していた。理由は簡単、「遺産を守りたかった」。守るために嘘をつく――それが、今回の罠の正体だった。
真相に迫る仮説と証拠
名義変更に隠された細工
偽造された遺言書には、筆跡のブレがあった。専門家の分析により、異なる時期に書かれた部分があることが判明。「こりゃ、複数の遺言書を切り貼りして作ったな」と苦笑する。昔読んだ名探偵コナンで、切手を張り替えて偽装した話を思い出した。
小さな登記の注記が示す真実
見逃しそうな小さな一文、「原因 平成二十七年六月三日 遺贈」。それが全ての鍵だった。遺言書の日付と食い違っており、しかもその日は父が入院していて意識もなかったはずの日だ。「やれやれ、、、また面倒なパズルだな」と呟きつつ、手元の資料を閉じた。
決定的証拠と告白
古い納屋から見つかったもの
調査の最後、古い納屋からボロボロの手帳が見つかった。中には、父親が自筆で書き残した「遺言書もどき」のメモがあった。それは法的には無効だが、感情的には真実を語っていた。そこに記されていた相続人の名前は、「兄と妹、平等に」とだけあった。
やれやれ事件は人の欲で動く
結局、登記は法の手順に従って修正されることになったが、感情のしこりまでは消えない。事務所に戻ると、サトウさんが一言「遺産って、人の化けの皮を剥がしますね」。やれやれ、、、全くその通りだと、深く息を吐いた。
事件の結末と司法書士の役割
正しく登記を戻すということ
最終的に、公正証書遺言の検証と相続登記のやり直しが行われた。僕の役割は、単なる登記の代行者ではない。嘘を排除し、事実を記録として残すこと。それが司法書士の本分だと、改めて感じた。
サトウさんの一言と苦い珈琲
「今回の依頼料、追加ありますよね?」とサトウさんが無表情で言った。「いや、まあ、そこは気持ちで…」「気持ちじゃ電気代は払えませんから」苦い珈琲を飲みながら、今日もまた僕の財布は寒くなる一方だった。