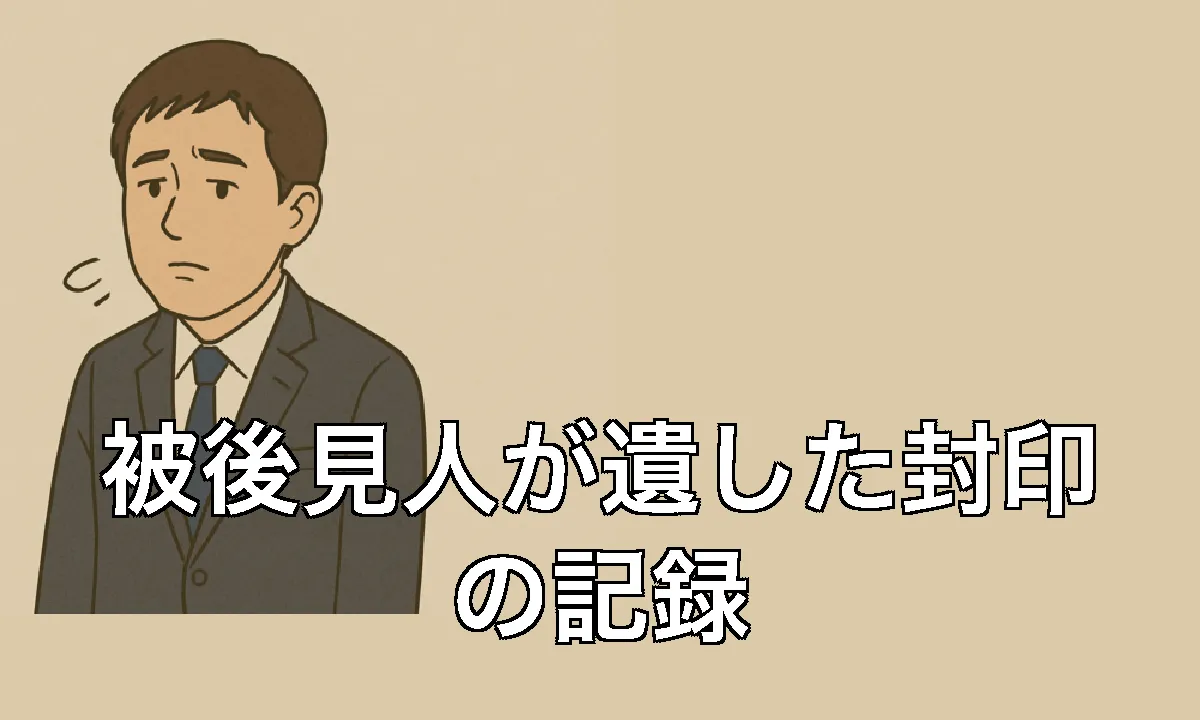朝の事務所に届いた一通の封書
朝9時、事務所のポストに無造作に差し込まれていた茶封筒を、サトウさんが無言で机の上に置いた。「差出人不明です」とだけ言って自席へ戻る。中には薄くて古びた紙が一枚だけ入っていた。
便箋には「この記録が真実です」とだけ書かれていた。署名はない。しかし、文面の端に見慣れた地名がある。被後見人として、去年亡くなったある女性の名前も小さく記されていた。
やれやれ、、、今日もまた、謎のスタートか。思わず心の中で呟いた。
依頼人の娘が語る後見の経緯
数日後、その女性の娘が事務所を訪ねてきた。小柄で控えめな彼女は、母の死後、なぜか預貯金が消えていたことに気づいたという。家庭裁判所から送られてきた報告書にも、財産の記載が曖昧だった。
「母は、後見人の方にすべて任せていたようです。でも何かがおかしいんです」と、震える声で言った。
報告書を読み返しながら、胸の奥に嫌な予感が湧き上がる。数字と登記が噛み合っていない。
後見開始から死亡までの空白期間
問題はその空白期間にあった。後見開始から、わずか半年後に被後見人は亡くなっていた。にもかかわらず、なぜかそれ以前に不動産の名義が変更されていたのだ。
本来なら、本人の判断能力が低下して以降は、名義変更は厳格な手続きを経なければできない。
だがその変更は、まるで「本人の意思」であるかのように処理されていた。ここに何かある。
謎の財産目録と消えた不動産
目録には、存在しないはずの土地が記されていた。すでに売却された物件が、まだ本人名義のまま残っている。
登記簿と照らし合わせてみると、1年前のある日に突然、所有者が変わっていた。しかもその相手は、どこかで見たような名前だった。
「この売買契約書、本人の筆跡じゃないですよね」サトウさんが無表情で言う。鋭い。まるでルパンの銭形警部みたいだ。
登記簿に記された奇妙な所有権移転
登記簿の記載は正しい。しかし、その裏付けとなる書類に矛盾がある。売買契約の日付と、後見開始の審判確定日が一致していない。
つまり、名義変更が行われたとされる日には、すでに本人には判断能力がなかったはずなのだ。
これは、ただの手続きミスではない。意図的な操作の可能性が出てきた。
不一致を示す後見人の報告書
後見人が家庭裁判所に提出した報告書には、「不動産の売却はしていない」と記載されていた。しかし実際には登記が動いている。
それは、彼が売却の事実を隠したということか。だとすれば、報告義務違反どころではない。刑事事件に発展する恐れすらある。
この報告書が、本当に彼の手によるものなのかも疑わしくなってきた。
法定後見のはずが任意契約の影
さらに調査を進めるうちに、過去に作成された任意後見契約書が見つかった。だが、そこに記された代理権目録の内容が奇妙だった。
「不動産の売却に関しては、後見人の判断に一任する」と書かれている。しかしその文言には、強引に付け加えられた形跡がある。
訂正印もなし。これは本当に公証人の目を通ったものなのか。
公証人役場で見つけた意外な名前
旧知の公証人に事情を話し、記録簿を調べてもらった。すると、契約書作成時に立ち会ったという「紹介者」の名に見覚えがあった。
それは、被後見人の近所に住んでいた男性。しかも、今回名義変更を受けた人物の親戚だった。
偶然とは思えない。つながってきた。バラバラだったピースが、ようやく形になってきた。
任意後見契約書に残された矛盾
契約書には、本人の署名がある。しかし、あまりに筆跡が粗く、震えていた。これは、認知症が進んだ後のものではないか。
つまりこの契約自体が、既に本人の判断能力が失われた後に作られた可能性が高い。
任意後見制度の悪用。その実態が、ここに露わになりつつあった。
被後見人が最後に面会した人物
福祉施設の記録によれば、亡くなる1週間前に一人だけ面会していた人物がいた。その名前は、やはりあの親戚だった。
面会時に持ち込んだ封筒の中身は不明。しかし、その直後から被後見人の体調が急激に悪化していた。
職員の証言では「少し怖がっていたようだった」とのことだった。
元介護士の証言に潜む嘘
さらに施設の元職員から連絡があった。「実は、書類にサインをさせていた現場を見た」と証言した。
それは介護記録には残っていない話だ。だがその日、施設のコピー機が数枚の文書を出力していた履歴が残っていた。
現場を直接見ていたかはともかく、サインを強要された可能性は濃厚だ。
福祉施設内の監視カメラに映った影
監視カメラ映像を確認すると、封筒を手に施設を訪れる姿が映っていた。時間は、面会終了の10分前。
そしてその直後、職員用トイレから出てくる姿も。何かを隠した可能性が高い。
「やれやれ、、、これはまた面倒な仕事だ」呟いて、サトウさんを見ると、彼女は既に施設へ連絡を始めていた。
調査の果てに浮かび上がる不在者
最後の鍵を握っていたのは、長男の存在だった。10年前に家を出てから音信不通。だが、彼名義の口座に不審な送金があった。
そこには後見人の個人名義からの振込履歴が。しかも、それが不動産の売却直後だった。
長男は何も知らなかった。ただ金だけが彼に届いていたのだ。
消えた長男と遺産の行方
長男を探し当て、話を聞いた。彼は母親が後見されていたことすら知らなかったという。そして、遺言があったことも初耳だった。
「そんなことより、母さんが最後どう過ごしていたのか、それが知りたい」と彼は涙ぐんだ。
この一件の結末を、彼にきちんと届けねばならないと、強く思った。
結末としての後見制度の盲点
事件としては、後見人の背任と文書偽造、そして任意後見制度の形骸化による不正。だがそれ以上に、この制度の「信頼」が問われる出来事だった。
制度を利用する人が、最も守られなければならないのに、それが一番無防備だったのだ。
そう思いながら、登記簿に最後の記載を確認したとき、小さなため息が出た。
善意と制度の隙間に潜む罠
善意で始まった制度が、時に人を傷つける。それは、法律の世界でも例外ではない。今回の件は、それを証明していた。
正しさとは、制度の中だけで測れるものではない。実際に現場に関わる者として、改めてその重みを感じた。
サトウさんがぼそりと呟いた。「これ、サザエさんだったら最終回レベルの展開ですね」。皮肉だが、言い得て妙だった。