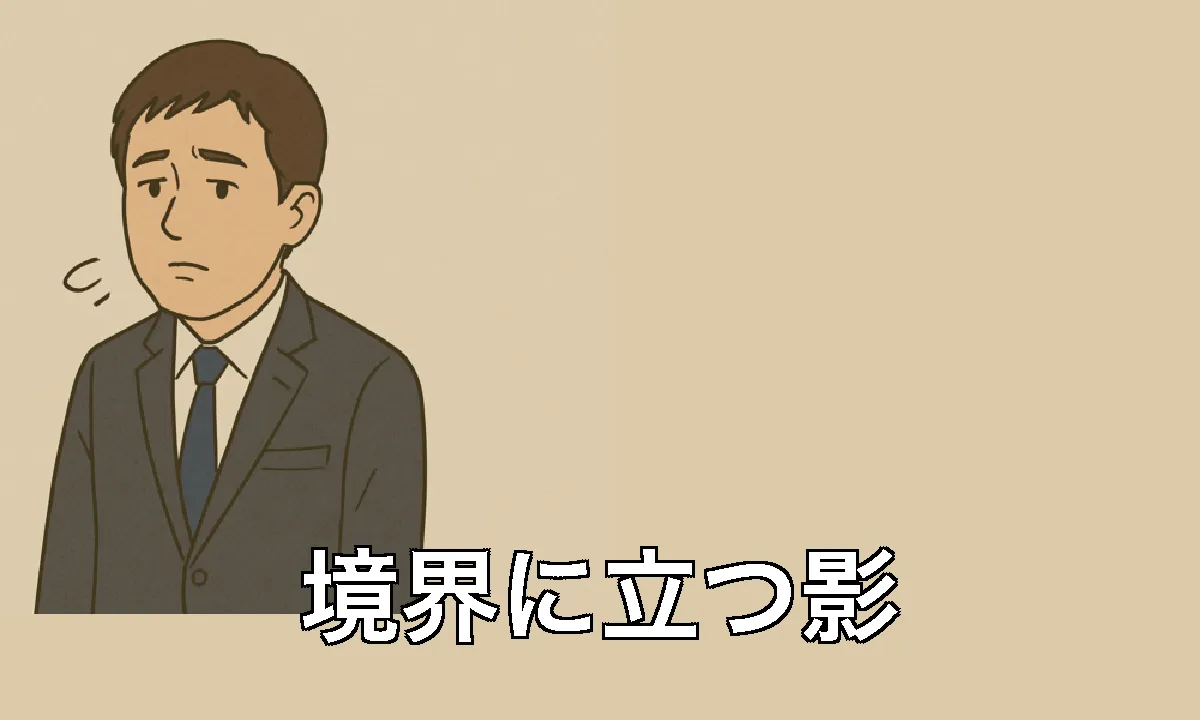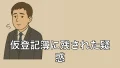境界に立つ影
梅雨の合間の晴れ間。青空の下、私は車の窓を開けて深呼吸をしたが、気分が晴れることはなかった。司法書士という仕事は、いつも何かしらの「線」と向き合っている。それが人の心に引かれた線であっても、地面に打ち込まれた杭であってもだ。
そして今日は、その境界線が人を殺したのかもしれないという話だ。やれやれ、、、また厄介な一日が始まる。
静かな里山の騒動
事務所に届いたのは、山間の集落にある土地の境界トラブルだった。小さな擁壁をめぐって、隣人同士が口論になり、ついには警察沙汰になったという。だが、今日の騒動はそれどころではなかった。
古びた境界杭と新築の擁壁
現地に着いた私は、地面に埋もれかけた古い杭と、最近建てられたピカピカの擁壁を見比べた。目測で見る限り、確かに少しズレている。だが、それが命を奪うほどの問題になるとは思いもよらなかった。
シンドウの憂鬱な朝
私はコーヒーをすすりながら、現地調査の準備をしていた。隣でサトウさんが無言で資料をめくっている。彼女の無表情は、天気よりも読みにくい。ふと、机の上に置かれた依頼書の角が妙に鋭く光っているように見えた。
依頼人は無口な老人
依頼人の田所氏は80歳を超える無口な男性だった。彼は境界線の主張を頑なに繰り返すばかりで、こちらの質問にもほとんど答えなかった。まるで、自分の正しさに確信を持ちすぎているように思えた。
境界確認の調査依頼
「とにかく、測ってくれればわかる」とだけ言い残し、彼はさっさと庭の奥に引っ込んでしまった。困ったことに、相手方の家主は既に東京に住んでおり、現地には代理人しかいなかった。
サトウさんの冷静な初動対応
サトウさんは黙々と過去の測量図を広げ、法務局から取り寄せた筆界確認資料と照合していく。その冷静な目は、まるで名探偵コナンが現場を見渡すようだ。私はただ、その横で頷くだけだった。
奇妙な二重の筆界線
測量を進めるうちに、地積測量図に二重線のような奇妙な記載を見つけた。1本は現在の登記簿に記載された境界線、もう1本は過去の旧台帳にあった線だった。何かが重なっている。
古地図に残された線
古い公図には、かつての畦道が描かれていた。戦前にあった農道が、昭和の区画整理で消されたという。つまり、現在の登記と実際の利用状況には乖離がある可能性が高い。
過去の売買記録との食い違い
旧地主が書き残した売買契約書には「隣地から三尺空けて構造物を建てること」と記されていたが、現状の擁壁はそれを無視している。つまり、どこかで故意の線引きがあった可能性が出てきた。
第一発見者の嘘
その日、擁壁の裏で男性の遺体が見つかった。第一発見者は工事業者の若者だったが、彼の証言はどこか曖昧だった。「気づいたら倒れてた」と言うが、足跡が一組しかない。
崩れた擁壁と足跡
擁壁の下部には崩落の跡があり、地面には靴の跡が一対。つまり、被害者と加害者のものではなく、一人分だけだった。それが嘘をついている証拠だった。
遺体が示す不自然な姿勢
遺体はまるで誰かに持ち上げられて落とされたような体勢だった。これは事故ではない。サトウさんは静かに言った。「これ、計算された落下ですね」。彼女の言葉に背筋が冷えた。
やれやれ、、、またか
私は頭をかきながらため息をついた。「境界で争って、ついには死人とはな、、、」。やれやれ、、、まるで昔見た『ルパン三世』のように、境界を越えた瞬間にすべてが崩れるような、そんな感覚だった。
かつての境界トラブルの記録
昭和の終わりに、同じ場所で境界トラブルがあり、隣人同士が訴訟を起こしていた記録が見つかった。あの時は死人は出なかったが、今回も同じ登場人物が関わっていた。
元地主と現所有者の確執
田所氏は、そのときの原告だった。勝訴したものの、境界杭は動かされぬまま、時間だけが過ぎた。今回、その杭が「誤っていた」と証明されることを恐れていたのだ。
影の持ち主は誰か
疑惑の中心にいるのは、あの若い業者ではなかった。影のように動いていたのは、田所氏の孫で、土地の相続予定者だった。彼の証言と行動に不自然さが多すぎた。
土地の影に潜む動機
もし境界が修正されれば、価値が大きく下がるのは田所家側の土地。そこで「擁壁を壊したのは隣人で、そこに落ちた」と偽装すれば、正当防衛に見せかけることができる。
サザエさん的ご近所トラブルの闇
ご近所付き合いとは、まるでサザエさんの世界のように平和に見えて、裏では複雑だ。表面上は笑顔でも、ひとたび境界をめぐって揉めれば、言葉のナイフが飛び交う。
逆転の登記ロジック
私は、過去の地積測量図と公図、そして地元役場の古い測量資料を照合し、登記上の境界線に明確な誤りがあることを突き止めた。これにより、擁壁の位置が不正であることが裏付けられた。
失われた測量結果の行方
昭和の記録の一部は、当時の測量会社がすでに廃業していたが、その社員が自宅で資料を保管していたという話を聞き、私はその家を訪ねた。そこには、手描きの貴重な図面が残されていた。
事務所に舞い込んだ一本の電話
その図面が決定的証拠となり、警察の捜査も一気に進んだ。数日後、私の事務所に警察から連絡があった。「あの孫さん、供述を変えましたよ」と。やはり、影の正体は彼だった。
サトウさんの推理
「全部、最初から見えてたんですよね」とサトウさんは淡々と言った。彼女は最初に杭を見たときから、違和感に気づいていたという。まるでキャッツアイの瞳のように、鋭く静かだった。
冷静な視点と意外な証拠
彼女が指摘したのは、靴底の土の種類だった。現場の土と靴の裏についた土が一致しなかったのだ。それは、遺体が別の場所で倒れたことを意味していた。
真相に至る地積測量図の罠
そしてもう一つ、地積測量図の「面積」が現地と合わなかった。彼女は「人の記憶より、面積の方が正直ですね」と笑った。私はただ、唸るしかなかった。
判明する犯人と動機
最終的に、犯人は田所氏の孫と断定された。遺産相続を有利に進めるために、意図的に隣地とのトラブルを偽装し、事故に見せかけた殺人だった。
すり替えられた境界票
境界票は、数ヶ月前に夜中にすり替えられていた。古い杭の位置を記録していた地元の測量士の証言が決め手になった。すべてが、地道な記録に支えられていた。
見えない杭が指し示す真実
見えなくなっていた杭が、むしろ最も多くを語っていたのかもしれない。線を引くとは、誰かの意思を残すこと。そして、意思は時に刃にもなる。
終わらぬ境界と人間関係
事件は解決したが、境界の争いが消えるわけではない。田所家と隣人の関係も、これで完全に壊れてしまった。土地とは、人の思いが宿るものだと痛感した。
司法書士という職業の限界
私は地面を見つめながら思う。法で線を引いても、人の心にある境界までは書き換えられないのだと。やれやれ、、、司法書士という仕事は、今日も心が削れる。
それでも現場に戻る理由
帰り道、助手席のサトウさんがボソッと呟いた。「結局、やるしかないんですよね、こういうの」。私は苦笑いしながら答えた。「まあ、俺たちがやらなきゃ誰がやるって話だ」。