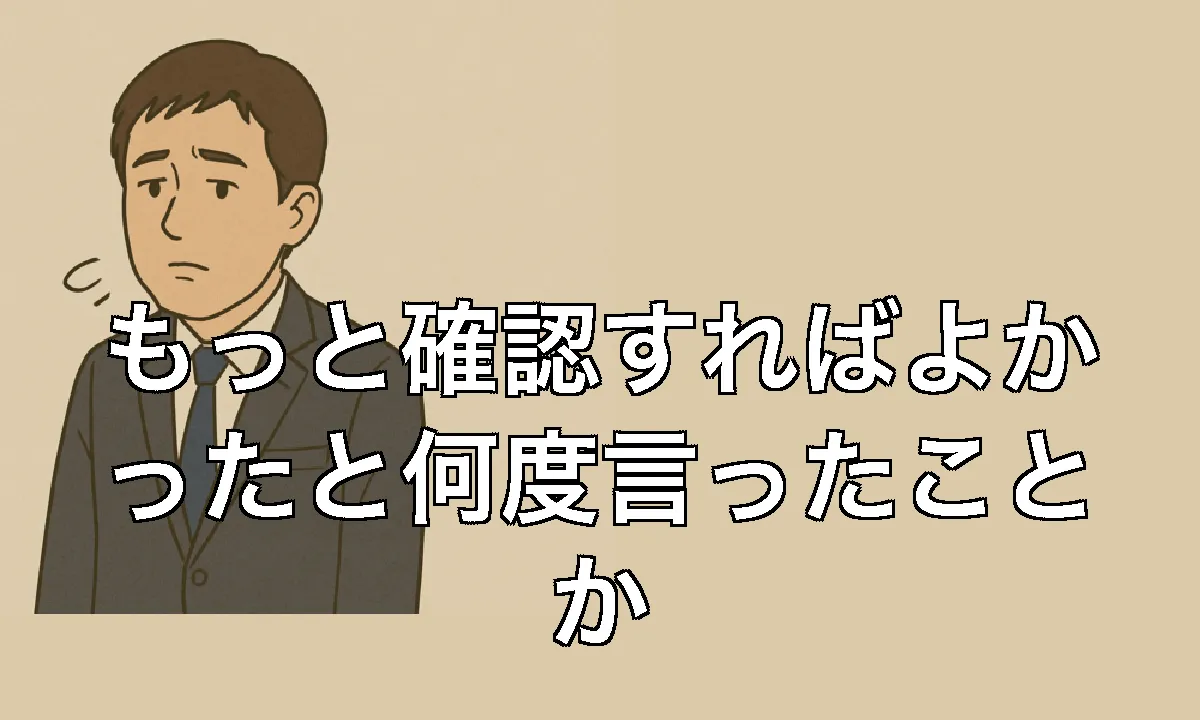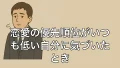見落とした書類が招いた小さな地獄
司法書士の仕事は、確認の連続です。にもかかわらず、ある日、その確認を怠ったばかりに、まるで落とし穴に落ちたような感覚を味わいました。土地の相続登記の依頼だったのですが、依頼人から預かった資料に一通だけ不鮮明なFAXが紛れていて、それを「まぁ大丈夫だろう」と放置してしまったんです。結果として登記申請に不備が生じ、依頼人に謝罪の電話を入れる羽目に。夜中に一人で缶ビール片手に、なんであのときちゃんと確認しなかったのかと自問していました。
あの一通のFAXがすべての始まりだった
思い返せば、そのFAXは確かに読み取りにくかった。でも、時間がなかったのと、「だいたい分かるし、まぁ大丈夫だろう」という慢心があったんです。元野球部のクセで、勢いだけで乗り切ろうとする癖がまだ抜けてないのかもしれません。書類の中身をちゃんと見ずに進めてしまった自分の甘さに、後から自分でも呆れました。あれ一通の確認をしていれば、その後の数時間の謝罪と修正の作業はなかったと思うと、ただただ情けないです。
確認のつもりが「見たつもり」だった
「見たよ」と言いながら、実際は「見た気がする」だけってこと、ありませんか? そのときの私がまさにそれでした。目は通していても、内容を理解していない、つまり確認したとは言えない状態。それを「確認済み」と思い込んでいるから、あとから発覚したときのショックも倍増します。まるでキャッチャーがサインを確認せずに球を投げて、バッターに打たれるようなもの。確認という基本をおろそかにしていた自分への戒めとして、今でもその書類をデスクに置いています。
事務員に頼んだつもりが伝わってなかった
「これ、お願い」と言ったつもりでも、相手には伝わってないことがあります。そのときも私は、事務員に「この書類、チェックしておいてね」と言ったつもりで、完全に任せた気になっていました。でも、実際には彼女は別の業務で手一杯で、確認まで手が回っていなかった。そりゃそうですよね、忙しさの波が押し寄せる中、口頭で曖昧に依頼されたことなんて、優先度が低くなるに決まってる。お互いが「やってると思ってた」で進むと、こういう落とし穴にハマります。
お客様からの一本の電話で青ざめる
数日後、依頼人からの電話で事態が明るみに出ました。「進捗どうなってますか?」という何気ない質問に、私は心臓が止まりそうになりました。そのとき初めて、「やばい、あの書類…」と気づいたんです。慌てて書類を引っ張り出し、登記情報を見直すと、案の定、不備がありました。その場で冷や汗をかきながら、「申し訳ございません」と何度も頭を下げる羽目になったのは言うまでもありません。
「まだですか」の一言が胸に刺さる
「まだですか?」という言葉、こんなに怖いんだと思いました。たった一言なのに、全身が硬直するようなあの感覚。依頼人に悪気はなかったと思います。ただ、こちらのミスが原因で不安にさせてしまったことは事実。信頼を損ねるというのは、ほんの些細なミスからでも一気に起こる。信用で成り立っているこの仕事において、「確認ミス」は命取りです。改めて、丁寧な仕事の大切さを痛感しました。
冷や汗と後悔で何も手につかない午後
あの電話の後、午後はもう何も手につきませんでした。ミスを認めて頭を下げるのは、慣れているようでやっぱりしんどい。電話口では冷静を装っていたものの、受話器を置いた瞬間、心の中では「終わった…」とつぶやいていました。事務員にも事情を説明したけど、空気がどんより重くなってしまって、その日の事務所はまるでお通夜。確認一つ怠るだけで、こんなにも空気が変わるのかと痛感した日でした。
確認を習慣にするための小さな工夫
失敗を経験しても、それを活かせなければ意味がありません。確認ミスを繰り返さないためには、意識だけでなく「仕組み」が必要です。私は元野球部の習性を活かして、ルーティン化することにしました。朝一番に確認タイムを設け、案件ごとにルール化したチェックを通すようにしています。完璧ではありませんが、ミスは確実に減ってきました。
元野球部流ルーティンの導入
野球の練習では、同じ動きを何百回と繰り返しますよね。確認作業にもあのリズムを取り入れて、日々の業務に組み込むようにしています。朝来たら必ず申請中の案件をチェック、昼前には事務員と進捗確認のミーティング、夕方には明日の予定を再確認。身体が自然に動くようになれば、確認ミスも格段に減る。習慣は最大の防御策です。
朝イチの「確認タイム」は効果アリ
朝の一番はまだ頭が冴えていて、余計な電話も来ない時間。そこで全案件の進捗と書類の確認をする時間を強制的に設けました。最初は面倒だったけど、毎日続けると「朝の確認をしてないと落ち着かない」くらいになります。朝食後の歯磨きのようなものですね。やってないと気持ち悪い。確認もそれくらい生活に溶け込ませるべきだと気づきました。
ボールを握る代わりにペンを握る覚悟
昔はボールを握って仲間にサインを送っていましたが、今はペンを持って細かくメモを残しています。確認とは「未来の自分へのサイン」だと思うようになりました。「このときこうだったよ」と記録を残すことで、後からの不安が減る。野球で培った「記録と再確認」の感覚が、今の仕事にも生きているのはちょっと面白い発見でした。
事務員との意思疎通を見直す
確認を一人で完結させようとすると限界があります。だから、事務員との連携も見直しました。「なんとなく伝わっただろう」は、たいてい伝わっていません。きちんと口に出して、文字にして共有すること。面倒でもそれが結局、後の混乱を防ぐ最善策だとわかりました。
口頭伝達ではなく「書く」文化へ
口頭でのやり取りは便利ですが、曖昧になりがちです。だから、業務の指示や確認は、すべて紙かチャットで残すようにしました。簡単なメモでもいい。伝えたつもりが伝わっていない、という悲劇をなくすには、記録が一番確実です。お互いのストレスも減るし、何より「言った・言わない」でモヤモヤしないのがありがたい。
お互いの「勘違いリスト」が役に立つ
最近始めた取り組みのひとつが「勘違いリスト」。お互いがやらかしたミスや勘違いを簡単にメモして貼り出しておくんです。「このパターン、またやったね」って笑える雰囲気にもなりますし、気をつけるポイントが可視化される。恥ずかしいこともあるけど、笑いに変えられるなら悪くないなと思っています。