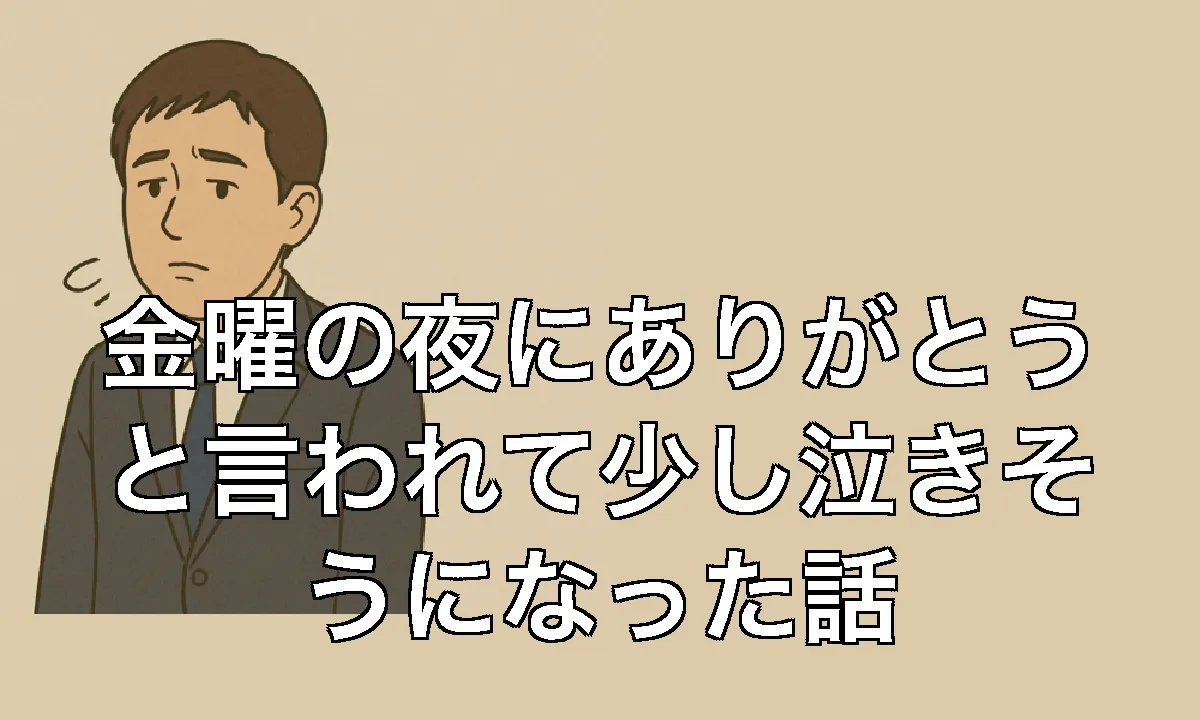一週間の終わりは決まってヘトヘトだ
金曜日の夜になると、毎週のように「もう限界だな」と感じてしまう。登記の準備や書類の山、相談者とのやり取り、そして事務所を一人で支えてくれている事務員への気遣い。誰かに助けを求めたいけど、頼れる人がいない。そんな日常がずっと続いている。40代を超えてもなお、働き詰めで、家庭もなく、誰かと喜びを分かち合うこともない。それが司法書士という仕事の現実だった。
金曜の夜は疲労のピークで誰とも話したくない
週末が近づくにつれて疲労は積み重なり、金曜の夜はもはや人と関わるのも億劫になる。案件の山を片付けながら、気力だけで動いているような状態だ。夜になっても電気が消えない事務所の明かりを見て、ふと「こんな働き方、いつまで続けられるんだろう」と自問する。昔、野球部でヘトヘトになるまで走った練習後には、仲間と笑い合う時間があったけど、今はその余裕すらない。
疲れているのにやり残しは容赦なく残る
今日こそは早く帰ろう、そう思っても書類の不備に気づいたり、クライアントからの電話が鳴ったりして、思い通りにはいかない。残ったタスクを翌週に回せばよいという気軽さもない。「あの案件、来週トラブルにならなきゃいいけど」そんな不安があるからこそ、金曜の夜も気を抜けない。それが司法書士の日常だ。
事務所の空気も重くて誰も笑わない
忙しさのあまり、事務所の雰囲気はどんよりしている。笑い声が聞こえるわけでもなく、パソコンのキーボード音だけが響く空間で、事務員も黙々と作業している。誰かが冗談を言えば少しは緩むのだろうが、そんな余裕が誰にもない。空気が重くなるほどに、心も沈んでいく。
自分の感情を誰にも吐き出せないもどかしさ
一人で事務所をやっていると、弱音を吐く場所が本当にない。事務員に愚痴を言うのも気が引けるし、友達付き合いも減ってしまった今、飲みに誘える相手もいない。SNSで同業の愚痴を見かけても、結局「みんな頑張ってるんだな」と思うだけで、自分の気持ちは吐き出せずに蓄積されるばかりだ。
愚痴をこぼす相手がいない独身の悲哀
家に帰っても話し相手はいない。テレビをつけても心が癒されるわけでもなく、寝る前のスマホが唯一の娯楽。家族がいれば、多少の愚痴をこぼして「大変だったね」と返してくれるかもしれないけど、独身の身ではそれもない。黙って飲む缶ビールが唯一の慰めだ。
元野球部でも今はチームメイトもいない
高校時代は野球部で、どれだけキツい練習も仲間がいたから乗り越えられた。試合で負けて泣いた時も、みんなで悔しさを共有できた。でも、司法書士という仕事は孤独の連続。励まし合う仲間もおらず、自分の責任で自分の判断を下すしかない。孤軍奮闘とはまさにこのことだ。
その「ありがとう」は不意打ちだった
週末の作業を終え、ようやくパソコンの電源を落とそうとしたとき、事務員がぽつりと一言「今週もありがとうございました」と言った。何気ない言葉だったけれど、その瞬間、体の力がふっと抜けた気がした。まさか「ありがとう」という言葉がこんなにも心に響くとは思わなかった。
一言だけで心が緩むことがある
「ありがとう」の五文字が、重く沈んでいた気持ちを一瞬で和らげてくれた。いつもは気丈に振る舞っているつもりでも、本当は限界寸前だったのかもしれない。感情が不意に溢れそうになって、思わず目をそらしてしまったほどだ。
事務員の小さな気遣いに救われた
彼女は特に感情を表に出すタイプではないけれど、ちゃんとこちらを見てくれていたんだなと感じた。普段は「業務」として接している間柄でも、人と人との関係には温度がある。あの一言で、今週の苦労が少しだけ報われたように思えた。
誰かに認められた気がして涙腺が緩む
司法書士の仕事は「ありがとう」と言われることが少ない。だからこそ、あの一言は想像以上に効いた。「今週も頑張ったんだな」と、自分で自分を認めることができた気がして、じんわりと涙腺が熱くなった。人間って、やっぱり言葉で生きてるんだなと思う。
言葉に出してくれる人のありがたさ
心の中で思っていても、言葉にしなければ伝わらない。そのことを改めて実感した。小さな「ありがとう」でも、口に出してくれる人がいるだけで、救われることがある。逆に、何も言わずに黙っていると、どんなに良い関係でもすれ違ってしまうのだろう。
「当たり前」に感謝する文化の大切さ
仕事をきっちりこなすのは当然のこと。でも、だからこそ「当然」を感謝してもらえると、その価値が何倍にも感じられる。日本では「やって当たり前」文化が強く、司法書士もその例外ではない。でも、たまには「ありがとう」と言い合える空気があってもいいと思う。
疲れ果てた時こそ心に刺さる一言
体も心も限界だったときにかけられた言葉は、まるで乾いた土に染み込む雨のようだった。普段なら聞き流してしまうような一言が、疲労困憊のタイミングだと、特別な意味を持つ。言葉の重みは、相手の状況によって何倍にも変わるのだと知った。
司法書士という職業は感謝と無縁だと思っていた
書類の正確さが命のこの仕事では、誰かに感謝されることは少ない。むしろ、ミスがあれば怒られ、問題がなければ何も言われない。そんな日々が当たり前になっていて、「ありがとう」なんて期待しないほうが楽だった。それが今回、価値観を少し揺るがせた。
「やって当然」な風潮に押し潰されそうになる
司法書士の仕事は、外から見ると「専門家」「しっかり者」といったイメージかもしれないが、実態は地味な裏方だ。目立たず、文句を言われずにこなすことが求められる。「やって当然」だからこそ、誰にも褒められず、静かにプレッシャーだけが積み重なっていく。
手続きはスムーズでも感謝されることは稀
どれだけスムーズに登記を終えても、クライアントからは「早かったね」の一言で終わることが多い。ありがとうもないし、感謝もされない。でも、逆に少しでも遅れればクレーム。そんな一方通行のやりとりに、気持ちが疲れてしまう。
責任ばかりが積み重なっていく日々
何か起きれば責任はすべてこちらにくる。どんなに慎重にやっていても、ゼロリスクにはならないのがこの仕事だ。事務所を支える重圧と、ひとり事務所長としての孤独。無意識に肩に力が入ったまま、毎日が過ぎていく。
でもたった一人の「ありがとう」が報われた気にさせる
評価もない、拍手もない、でも、あの金曜の夜に言われた「ありがとう」は、今でも心に残っている。人の言葉は、報酬にもなる。頑張る意味を与えてくれることがある。司法書士という職業に誇りを持ちたい、そう思えたのは、ほんの一瞬のやり取りがきっかけだった。
他人の評価より自分の感情が大事になる瞬間
「ありがとう」と言われたことで、自分の仕事に対する姿勢や思いが再確認できた。誰かに評価されることよりも、自分自身が納得して働けることが一番大事だと思えた。社会的な立場や報酬ではなく、自分の心がどう反応するかが、原動力になる。
誰のために働いているのかを考え直す
依頼者のため、社会のため、そう思って働いてきたが、実は一番大切なのは「目の前の誰か」なのかもしれない。事務員の一言がそう教えてくれた。小さな職場でも、感謝が循環する関係性があれば、仕事は続けられる。その原点を、忘れないでいたい。