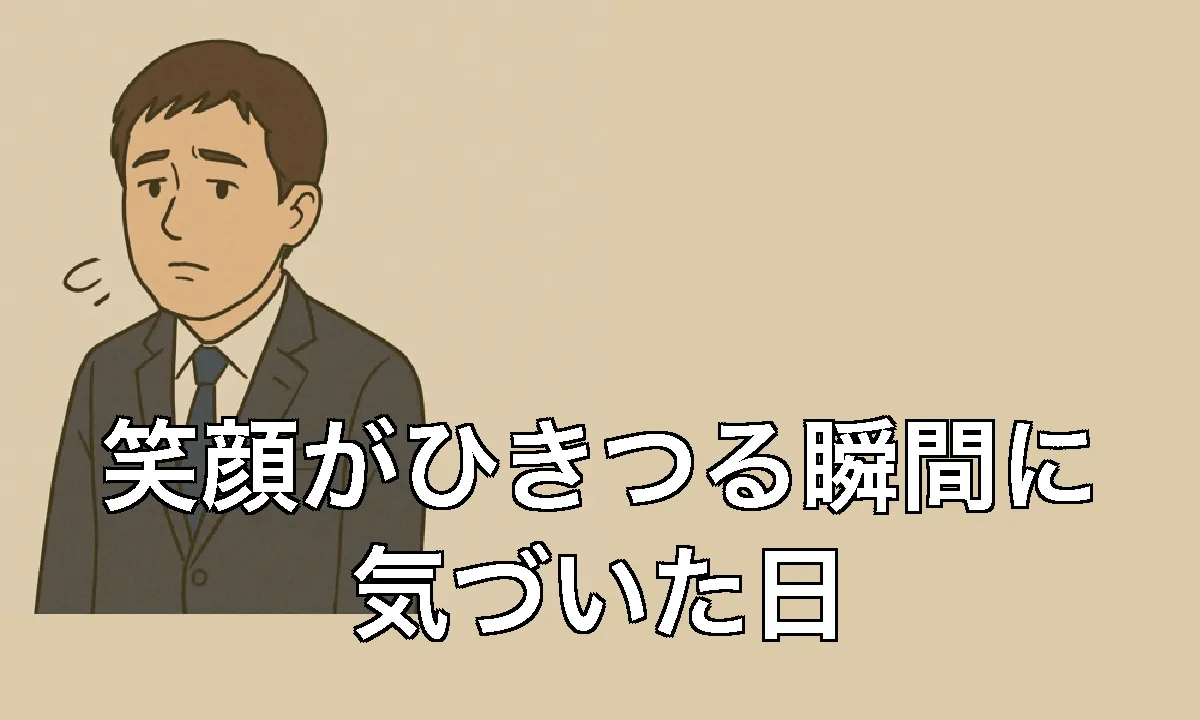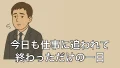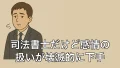誰のための笑顔かを考えた日
ある日ふと鏡を見た瞬間、自分の顔が妙にこわばっていることに気づいた。笑顔を浮かべているつもりだったが、どこかぎこちない。それはまるで、顔だけが他人のもののように感じられた。司法書士として「笑顔で接すること」は当たり前だと信じていた。でもその“笑顔”は、本当に心から出ているものだったのだろうか。誰かのために作ったはずの表情が、気づけば自分自身を傷つけていたような気がした。
気づいたのは鏡の中の自分だった
朝の身支度中、鏡に映る自分を見てハッとした。目の奥が死んでいた。口角は上がっているのに、まるで心が伴っていない。思い返せば、最近は仕事中に無理に笑顔を作ることが習慣になっていた。相談者が不安げな顔で訪れるたび、「大丈夫ですよ」と言いながら口元を緩める。でもそれは“安定した専門職の顔”を演じていただけで、本心は疲労と焦りの塊だった。
口元は笑っていたけれど目が笑っていなかった
相談が立て込むと、感情が追いつかなくなることがある。特に遺産分割や相続放棄など、感情の揺れる案件が続いた週は、笑顔を維持するのが苦痛だった。それでも「笑っていれば何とかなる」と思い込み、いつもどおりの表情を作っていた。だが、それを続けた結果、知らず知らずのうちに“顔が疲れる”という感覚が残り、ある朝ふと「あ、これひきつってる」と自覚した。
「笑顔で対応してくれる先生ですね」と言われた違和感
ある相談者に「いつも笑顔で安心します」と言われたとき、内心ザワッとした。嬉しいはずの言葉なのに、「本当に安心されているのか?」「笑っていれば信用されるのか?」と疑心暗鬼になってしまったのだ。それはきっと、自分でもその笑顔が“本物ではない”ことをどこかで知っていたからだろう。安心させるための笑顔が、自分を不安にしている皮肉な現実がそこにあった。
無理して作っていた優しさの正体
人に優しくしたい。そう思って笑顔を保ってきた。でもそれは、「怒って見られたくない」とか「冷たいと思われたくない」といった自己防衛でもあった。本当は余裕がなくて、心の中では「早く終わらせたい」と思っているときですら、表情だけは穏やかに装っていた。優しさの仮面が、いつのまにか本音を押し殺す鎧になっていたように思う。
本音ではイライラしていたのに微笑んでいた
たとえば、電話対応中に横から「急ぎの確認です」と資料を差し出される瞬間。心の中では「ちょっと待ってよ!」と思っていても、顔は笑って「はい、わかりました」と答えていた。その積み重ねが、いつのまにか怒りを内に溜め込む癖につながり、気づけば疲れ果てていた。感情を外に出すことが苦手な性格が、笑顔に逃げていたのかもしれない。
感情のすり減りが限界を越えた瞬間
疲れがピークを迎えたある日の夕方、帰宅後に鏡を見た自分の顔に愕然とした。ほうれい線が深くなり、目の下にはクマ、頬はこけていた。それでも無意識に口角だけが上がっていて、どこか気味が悪かった。身体は限界なのに、「笑っていないと崩れてしまう」という変な思い込みが残っていた。あれはまさに、自分で自分を追い詰めた結果だった。
なぜ笑顔を保とうとしていたのか
「笑顔は武器」と言われてきた。確かに第一印象は大事だし、安心感を与える要素として有効なのもわかっている。でも、自分がすり減ってしまっては意味がない。誰のための笑顔かを見失ったとき、ふと立ち止まる勇気が必要だと痛感した。これまでの価値観が間違っていたとは思わない。ただ、限界を超えてまで笑顔を保つ必要はなかったのだ。
元野球部だった自分に染みついた精神論
「辛くても顔に出すな」「気合で乗り切れ」――中学・高校時代の野球部で叩き込まれた精神論は、司法書士になってからも無意識に影響していたように思う。雨の日も泥だらけでも歯を食いしばって練習を乗り越えるのが当たり前だった。その延長で、「しんどくても笑顔」という思考が根付き、結果として自分を追い込むことになっていた。
「苦しくても顔に出すな」と言われ続けた日々
あの頃の監督の口癖は「顔に出すな、相手に気づかれるな」だった。エースピッチャーが打たれても、ベンチに戻ってくるときには笑顔を見せろと教えられてきた。だから今でも、つらい場面でこそ笑顔を出す癖が抜けない。だが司法書士は野球とは違う。勝ち負けではなく、信頼と向き合う仕事。だからこそ、自分の心の声にもう少し耳を傾けるべきだったのかもしれない。
無言のプレッシャーに耐える癖
忙しそうな事務員の前で「疲れた」と口にすることすらはばかられた。お客様の前ではいつも明るく、職員の前では頼りがいのある姿を貫こうとする。そうして“言えない自分”が笑顔を固めていく。気づけば、自然な表情を忘れてしまっていた。無言の圧力は誰でもない、自分自身が作っていたのだ。
司法書士としての立場が生む見えない鎧
「司法書士なんだからしっかりしていて当然」という世間の目。どこかでそれを背負いすぎていたように思う。弱音を吐くと「頼りない」と思われるんじゃないか。愚痴をこぼすと「プロじゃない」と言われるんじゃないか。そんなプレッシャーに飲まれて、本来の自分を見失いそうになっていた。そしてその結果として、笑顔すら“役割”になっていた。
「プロなんだから当然」な目線の重圧
登記ミスが許されない職業。説明のミスも命取り。そんな日々の中で、「ミスのない自分」を演じ続けるのは思った以上にしんどい。そして、そのしんどさを隠すために使っていたのが“笑顔”だった。まるで、演技者として舞台に立っているような感覚すらあった。観客の前では笑顔、でも舞台裏ではぐったり。そんな日常が続けば、いつか壊れるのは当然だ。
頼られたい気持ちが裏目に出る
本音では「頼られる存在でいたい」と思っていた。でもその気持ちが、無理を重ねる原因になっていたのかもしれない。「先生にお願いしてよかった」と言われると、嬉しい反面、「次も頑張らなきゃ」と自分にさらに負荷をかけてしまう。その循環のなかで、笑顔が“盾”になり、やがてその盾が自分を締め付ける鎖になっていたのだと、今ならわかる。