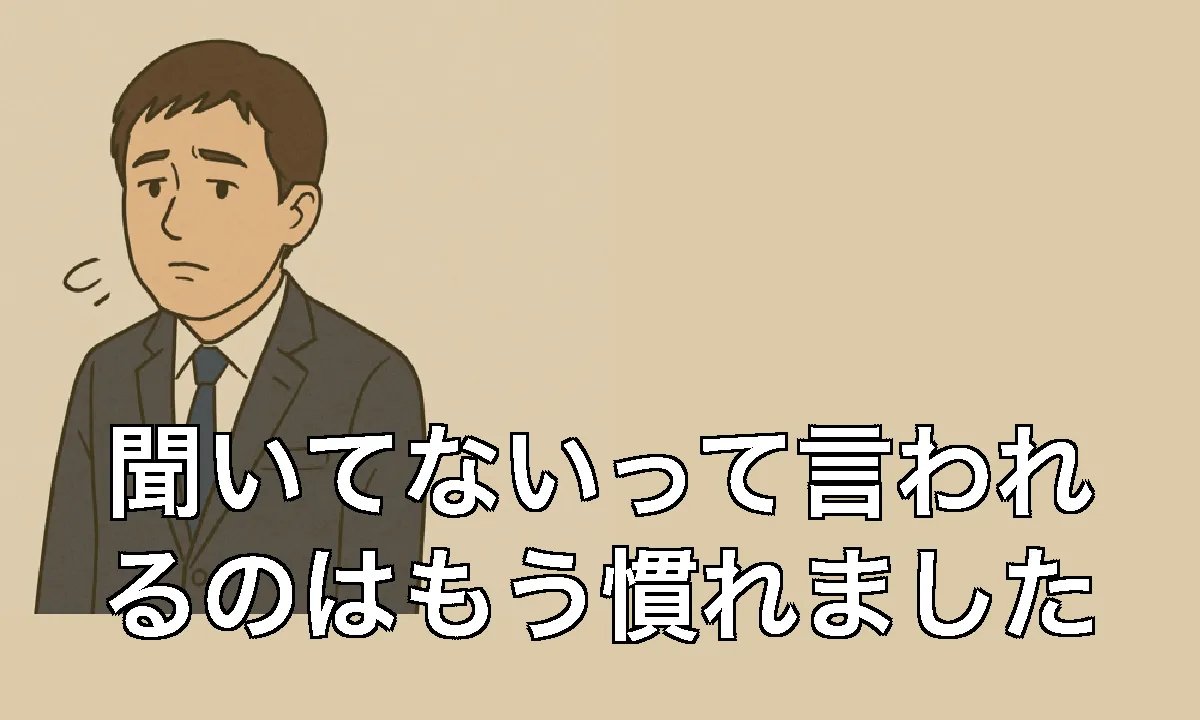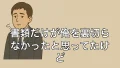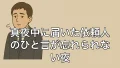僕がまた言われました聞いてないって
このフレーズ、もう何度目か分かりません。「聞いてないんですけど」。事務所でこの一言を投げられると、胃のあたりがぎゅっと縮む感じになります。事務員に言われるときもあれば、お客さんに言われることも。どっちにしても、「いや、それ言いましたよね…」と喉まで出かかる言葉をぐっと飲み込みます。伝えたつもりで伝わってない。それが原因で関係がギクシャクして、何とも言えない空気になる。独りでやってた頃にはなかった、コミュニケーションの壁。聞いてないって言われるたびに、自分が信用されてないような気分になります。
電話口でピシャリと放たれるその一言
電話で「その話、聞いてませんけど」と言われた日。よくあることとはいえ、やっぱりズキンと来ます。こちらはきちんと説明したつもりなんですよ。契約内容の変更についても、期日も、料金の件も。でも相手は「初耳だ」と言い切る。録音してるわけでもないし、メールの文面に残してるわけでもないと反論の余地がなくなる。冷静を装いながら、「そうでしたか、すみません」と口では言っても、心の中は敗北感でいっぱいになります。まるで野球でエラーした後の守備交代みたいな心境です。
本当に言ってなかったのか毎回疑心暗鬼
「言ったはずなんだけどな……」と頭の中で何度も巻き戻し再生するんです。あの時の面談、どんな流れだったっけ? 自分の記憶に自信が持てなくなる。忙しさにかまけて口頭だけで済ませたんじゃなかったか、メモに残し忘れたんじゃないか。そうやって自分を責めるようになってくると、どんどんしんどくなってくるんですよ。結局、言ったかどうかの話よりも、「きちんと伝えようとしたかどうか」に疑問を持ち始めて、答えのない反省会が始まります。
メモも記録もあるのに消される自信
何ならメモもあるんですよ。カレンダーにも予定入れてるし、顧客ごとに記録も残してる。それでも「聞いてない」と言われると、もう自信がなくなる。記録は残ってても、証拠にはならないし、確認不足だと思われるのが関の山。ああ、もう全部紙に書いてハンコでももらうしかないのかと思う瞬間もあります。そうなると仕事のスピードも落ちるし、結局また別の「遅い」とか「連絡がない」とかいうクレームにつながる。負のループです。
伝えたつもりの罠と司法書士の孤独な戦い
僕らの仕事って、ほんと「伝えたつもり」が命取りになる。書類の手続き、登記の進行状況、費用の目安——細かく伝えたつもりでも、相手には伝わっていない。司法書士って、説明が命なのに、伝える相手は一般の方が多いから、専門用語も避けなきゃいけないし、言い回し一つで誤解される。何よりつらいのは、結局全部こちらの責任になること。誰も「伝わってなかったのは自分の聞き方が悪かったかも」とは言ってくれないから、孤独です。
忙しさに紛れて確認が漏れる現実
毎日バタバタしてると、「伝える」ってこと自体が雑になってくるんです。つい、口頭で済ませてしまう。「あ、ついでにこの件もお願いね」みたいに。それが後で「あの件はどうなってますか?」になって、「え、頼んでなかったっけ?」となる。頭の中ではきちんと伝えた気でいるから余計にズレる。で、気づけばお互いにストレスが溜まってる。これはもう、業務過多という名の伝達障害なんですよね。
お客さんと事務員の板挟みあるある
一番つらいのは、お客さんからのクレームを事務員が受けて、その事務員がこっちに「聞いてません」と怒ってくるとき。もう、どこからどうフォローすればいいのかわからなくなる。お客さんには「確認不足でした」と謝り、事務員には「ごめん、伝え方悪かった」と謝り、自分には「何でこうなったんだ」と問いかける。全方向土下座です。それでも信頼回復には時間がかかるし、自分の評価はジワジワ下がる。地味に効きます。
どうしても発生する伝達ミスの根っこ
どんなに気をつけていても、「聞いてない」はゼロにはできません。問題は、その原因がひとつじゃないってこと。人と人の間には、どうしても“ズレ”がある。こちらが10伝えたつもりでも、相手は5しか受け取れてない。しかもその5がズレてる。気を抜くと、それがトラブルの火種になります。話した内容をどう記録するか、どう確認し合うか。意識してても、抜けるときは抜ける。それが現場の現実です。
人に頼んだ瞬間に発生する責任の曖昧さ
司法書士って、「自分でやった方が早い」が通用しない職種です。事務作業を誰かに任せないと、そもそも回らない。でも、人に任せた瞬間に「誰の責任か」が曖昧になる。お願いしたつもり、引き受けたつもり、やったつもり、伝えたつもり——全部“つもり”が積み重なって、気づけば「聞いてないんですけど?」の完成です。誰が悪いとかじゃなくて、仕組みがこうなるようにできてる気がします。
僕がやるべきか事務員がやるべきか毎度迷う
細かい確認や補足説明って、本来僕がやるべきなんだろうけど、事務員が対応してくれてることも多い。だからこそ、「この件、どっちが対応したんだっけ?」と迷うことがある。うちは人手も少ないし、マニュアルがあるわけでもない。現場対応でなんとか回してるから、こういう“役割のグレーゾーン”が日常茶飯事です。結果、伝えるべきことが誰にも伝わってなかった、なんてことも。
曖昧な分担がトラブルの種になる
たとえば、「次回の来所日時をお伝えしておいてくださいね」と僕が言ったとします。事務員も「はい」と答えてくれた。でもその「はい」が、「私がやります」なのか「先生が言ってくれるだろう」なのか、そこがズレるんです。言葉にしただけでは不十分。役割を明確にする、それをお互い確認するって工程が抜けると、そこでミスが生まれます。でも、毎回そこまで丁寧にやる時間も正直ありません。
どう向き合えばいいのか僕なりの答え
「聞いてない」と言われるたびに落ち込んでたけど、最近はちょっとだけ考え方を変えるようになってきました。全部の伝達を完璧にしようとするより、「ミスが起きたときのリカバリー」をいかに早くできるかを考えるようにしてます。もう、完全に防ぐのは無理。だったら、その後の対応で信頼を取り戻せるように動く。そう思えるようになったのは、何度も失敗してきたからです。
書く伝える残すを徹底してみたけど
最近はとにかく、「書く」「伝える」「残す」を意識しています。口頭で伝えた内容も、できるだけLINEやメールで補足するようにしたり、手帳にメモを残したり。正直、それでも「聞いてない」は発生します。でも、少なくともこちらとしては「ここまでやった」という自信が持てるだけで、少しは気持ちが楽になります。証拠を残すというより、自分の中で納得できる手段を確保する感じですね。
メモは取ってるのに読まれてない現象
書いてはいるんですよ、ちゃんと。でも読まれてないんですよ、これが。事務員に伝える内容をメモにして渡しても、机に置かれたままだったり。お客さんにメールを送っても、「届いてなかったです」と言われたり。情報って、「伝えた」だけじゃなくて、「届いて読まれた」までがセットなんですよね。だから、確認の確認をしないと安心できない。これがまた面倒なんだけど、やらないとまた言われる。
説明文にイラストまで描いたら伝わった
これ、冗談じゃなくて本当にやったんです。ある高齢のお客さんに登記の流れを説明するとき、手書きで図解を描いて渡したら、「これならわかりやすい」と感動してもらえたんです。しかもその後の連絡でも「ちゃんと書いてあったね」と感謝された。伝え方って、文字だけじゃないんだなって思いました。伝わればいい。形にこだわらず、相手に届く手段を選ぶことが大事なんだと痛感しました。
もういっそ諦めるくらいがちょうどいい
全部伝えきるなんて無理なんですよ。相手のコンディションもあるし、こちらの疲れ具合もある。だからもう最近は、多少の伝達ミスは「まぁ、そういうもんだ」と思うようにしています。怒られても、責められても、「はいはい、またか」と流せるようになってきた。それくらいの力の抜き方が、今の僕にはちょうどいい。完璧主義をやめるって、意外と気楽になれるんですよね。
完璧主義は孤独を深めるだけだった
昔は、自分の伝達ミスでミスが起きたら「自分がダメなんだ」と責めていました。でもそれって、どんどん自分を追い詰めるだけだった。周りと距離ができるし、孤独になる。完璧を求めるほど、自分の不完全さが目について苦しくなる。今は、「どっかでミス出るよね、それも仕事の一部だよね」って思えるようになってから、だいぶ楽になりました。少なくとも、笑えるようになった。
最後はまぁそんなもんかとつぶやく自分
今日も誰かに言われたんです、「それ、聞いてないです」。その瞬間、ちょっと心が沈みました。でも帰り道、自転車を漕ぎながら思ったんです。「まぁ、そんなもんか」って。司法書士って、そんなもんです。聞いてもらえなくても、伝え続けるしかない。届かなくても、また明日話せばいい。そうやって積み重ねていくしかないんだなと、最近は思ってます。独り身は気楽だけど、こういう瞬間は少し寂しいですけどね。