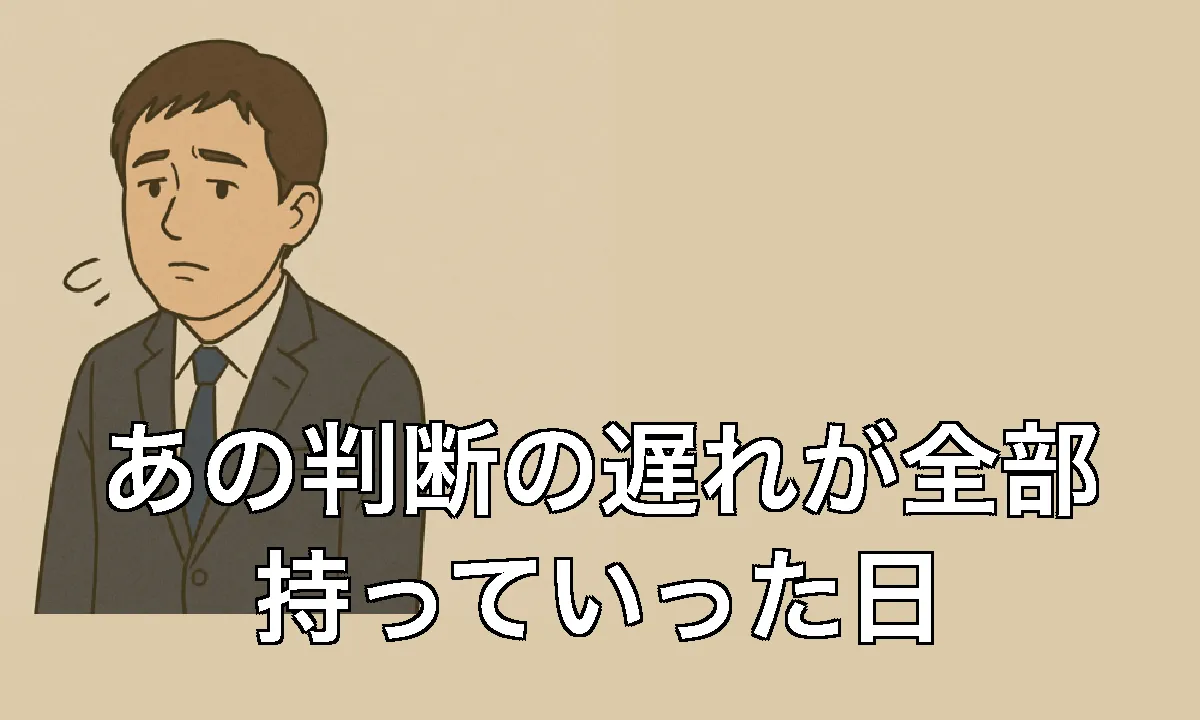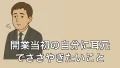迷っていたあの日のことを今でも思い出す
あの時、もう少し早く動けていたら──。そんな“たられば”が、頭の中でずっと反芻される日があります。日常業務のなかで発生したたった一つの判断の遅れが、まるでドミノ倒しのように次から次へと影響を及ぼしていく。最初は小さなほころびだったのに、気づいたときには全体にヒビが入っていた。そんな経験、司法書士として何度もありました。特に地方の小さな事務所では、誰かがカバーしてくれる余地もなく、判断が遅れた代償はすべて自分に返ってくる。今回は、そんな自戒を込めた話です。
判断を先送りした小さな理由
人はよく「忙しくて考える暇がなかった」と言います。私もよく言ってました。でも本当は、“考えないでいい言い訳”をしていただけだったかもしれません。例えば、ある依頼者からの登記の相談。判断を即決せず、「ちょっと調べてから折り返しますね」と言ったまま、3日放置。電話も出られず、気づけば相手は他の事務所に依頼していました。忙しいふりをして先延ばしにした自分が悪い。これは痛いほどに響いた出来事でした。
忙しさを言い訳にしていた自分
言い訳は簡単です。電話が立て込んでいた、外出が重なっていた、来客対応で手が回らなかった。でも、ふと冷静になって考えると、すべて「その気になればなんとかできたこと」ばかりでした。本当に「今すぐじゃなきゃいけないのか?」という問いにすら答えようとしなかった。元野球部で、瞬時の判断が大事だと叩き込まれてきたはずなのに、実生活になるとこんなに鈍るのかと自分に呆れました。
後回しのクセが身に染みついていた
後回しってクセになるんですよね。気づけば「あとでやる」が口癖になっている。業務が積み上がっていくと、どれもが“重要っぽく”見えてきて、本当に優先すべきことが見えなくなる。気持ちが疲れていると判断力も鈍る。そうして、ひとつの案件を決めきれずに保留にしていたせいで、他の案件のスケジュールもズレ込み、まさに“全部が崩れた”状態に。たったひとつの判断の遅れで、ここまでガタガタになるのかと愕然としました。
その判断が引き起こした大きな波紋
後悔は後からしかやって来ません。判断を先送りにしたその時点では、「まあ大丈夫だろう」と軽く考えていたのです。でも、結果はまったく大丈夫じゃなかった。ある法務局提出の期日ギリギリの登記申請で、依頼者が持参予定だった書類に不備があることに気づきながらも、「明日確認すればいいか」と流してしまった。結果、その“明日”には間に合わず、依頼者から怒鳴られ、信頼も失いました。自業自得とはいえ、かなり堪えました。
取引先の信頼を失った一通のFAX
ある日、土地の売買に関する委任状についてFAXが届いたのですが、確認を後回しにしていたせいで、内容に不備があることに気づいたのは提出期限の直前でした。本来であれば、数日前に余裕をもって修正をお願いできたはず。でも私は「どうせ大丈夫」と高を括っていた。FAXの送信ミスを見落とした責任は私にある。その一件以来、取引先の不動産業者からの紹介はピタッと止まりました。関係修復の難しさを痛感しました。
結局自分で全部かぶるしかない現実
小さな事務所です。事務員さんも精一杯頑張ってくれてますが、ミスの責任まで背負わせるわけにはいかない。結局、誰のせいにもできないんです。書類不備の処理、謝罪の電話、再提出の段取り、全部自分。孤独です。胃も痛みます。でも、誰に相談できるわけでもない。責任ある立場って、なんでもかんでも“自分のせい”になる。そう割り切らないと、この仕事は続けられない。でも、その割り切りが苦しいときもあります。
地方の事務所だからこそ逃げ道がない
地方で事務所を構えていると、都会のように“人もサービスも多様”という環境ではありません。人の流れも情報も少ない。だからこそ、一度信頼を失うと取り戻すのにものすごく時間がかかる。選択肢が少ない分、リカバリーの手段も少ない。言い訳も効きづらい。ミスや判断の遅れがそのまま「能力不足」と直結されてしまいがちなのがつらいところです。
少人数体制ゆえのプレッシャー
事務員さん一人と私。二人三脚でやっているからこそ、役割分担もギリギリ。忙しい時期になると、「もう限界です」と言いたくなる瞬間もある。でも、自分が倒れたらすべて止まるという現実が、気持ちにブレーキをかける。「ミスできない」「早く判断しないと迷惑をかける」そんなプレッシャーが積み重なって、余計に判断が鈍くなる悪循環。そんな時こそ落ち着いて──と頭ではわかっていても、なかなかできないんですよね。
事務員さんも限界 ギリギリのやりくり
たまに事務員さんから「これ、先生しか判断できないですよね」と声をかけられると、内心はドキッとします。「今その判断力が枯渇してるんだけどな…」という時でも、顔には出せない。彼女なりに必死で回してくれてるからこそ、投げ出せない。でも結局、どちらも疲弊する。心の中で「もう少し人を雇えたら」と思っても、人件費が…と現実が押し寄せる。地方の小規模経営の難しさを痛感する瞬間です。
「先生しかできないんですよ」と言われ続ける
この言葉、実は地味に効きます。「任せてもらえない」というより「逃げ道がない」と感じてしまう。すべての決定を自分が下す。たしかに責任感はある。でも、常に正解を出し続けるのは無理です。判断に迷いがあっても、それを見せるわけにはいかない。そうして、自分だけがどんどん疲れていく。年齢的にも集中力が落ちているのは自覚してます。でも、誰も「もう無理ですね」とは言ってくれない。しんどいです。
それでも判断し続けなきゃいけない日々
仕事である以上、迷っても止まることはできません。判断は遅れても、最終的には“決める”ことが求められる。だから、どれだけ疲れていても、心が重くても、立ち止まるわけにはいかない。まるでバッターボックスに立ち続けるような感覚。どんなに調子が悪くても、球は飛んでくる。見送ればストライク、打てばファウル、でも打たなきゃ終わり。そんな感覚で毎日を過ごしています。
疲れていても選ばなきゃいけない瞬間
夜の8時、事務所で一人、書類を前に唸っていることがよくあります。頭がぼんやりしてきて、「今この判断でいいのか?」と何度も問い直す。そういうときは、かつての自分なら「とりあえず保留」にしていた。でも最近は、「今決めよう」と意識してます。なぜなら、保留したことで痛い目に遭った回数があまりにも多すぎたから。疲れていても、やるべきことは目の前にある。選ばないことで失うものがあると学びました。
選んだ後の後悔と選ばなかった後悔
選んだ結果ミスをしたとしても、それは次に活かせる。でも、選ばなかった結果のミスは何も残らない。ただの後悔だけが心に残る。それが一番つらい。あの時、「やらなかった」ことに対する後悔は、ずっと尾を引く。まるで走塁ミスで負けた試合のように、記憶の中で何度も再生される。だからこそ、いまは「判断すること」自体に意味があると思うようになりました。
たまには「間違えてもいい」と思いたい
人間なんだから、間違えてもいい。そう言われたいし、誰かに言いたい。でも、司法書士という仕事はどうしても「正確さ」が求められがちで、間違いを許される余地が少ない。だからこそ、自分くらいは自分を許してあげたい。間違えたら謝る、訂正する、それでいいじゃないかと。完璧じゃなくてもいい。野球だって三割打てれば一流。失敗を恐れて動けなくなるより、動いて失敗した方がまだマシだと思いたいです。