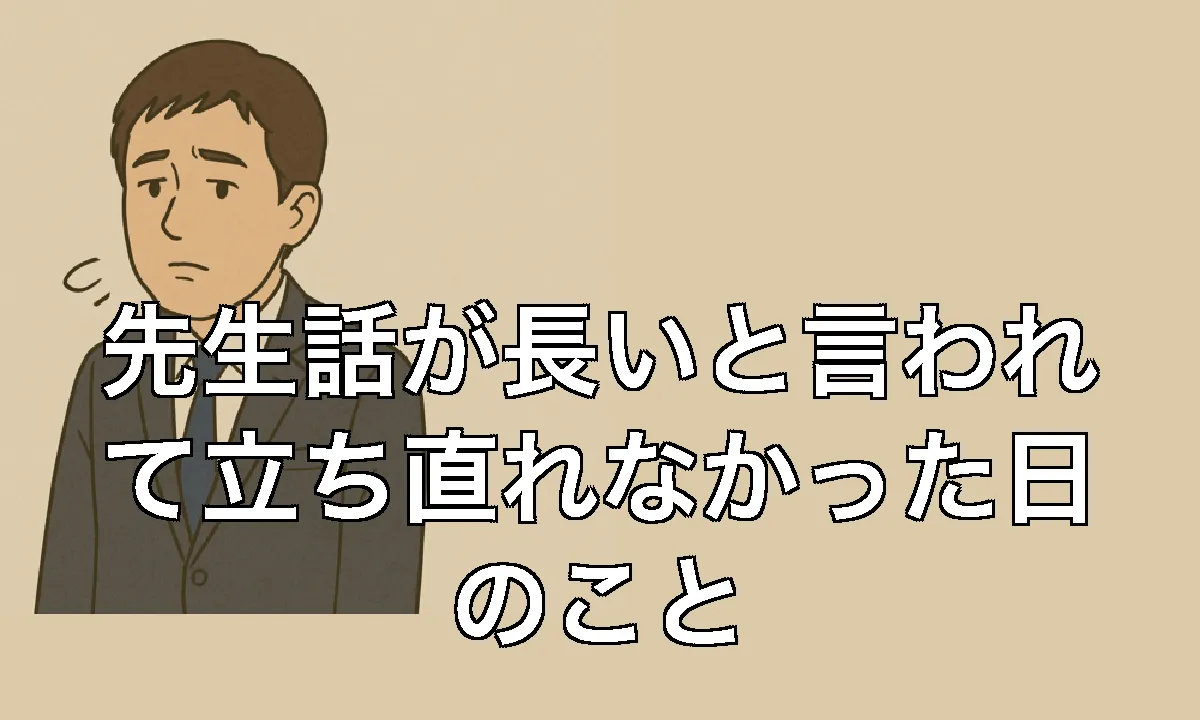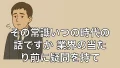なぜあの日の一言がここまで刺さったのか
「先生、話が長いんですよね」──この一言を言われた日、正直、立ち直れませんでした。事務所の空気が一瞬止まり、顔が熱くなったのを覚えています。冗談交じりではあったものの、相手は明らかに本気だった。それは、依頼者との面談のあと、事務員がぽつりと漏らした言葉でした。私は「丁寧に説明してるつもりだった」と思っていましたが、それは独りよがりだったのかもしれません。その瞬間、自分の話し方にずっと見落としていた「ズレ」があったのだと気づかされました。
司法書士という仕事と「話すこと」の関係
司法書士という仕事は、どうしても言葉が多くなりがちです。法律用語はわかりにくいし、登記や相続の手続きは細かくて複雑。だからこそ、丁寧に、わかりやすく伝えたいと思って、つい説明が長くなる。でも、それが依頼者にとって負担になることもある。僕はそれをまったく自覚していませんでした。元野球部のノリで「熱く語ることが誠意だ」と思い込んでいたのです。けれど、その熱意が逆効果になっていることもあるのだと、ようやく気づきました。
説明責任と自己満足の境界線
「説明責任を果たす」と「自分が納得するまでしゃべる」は、似て非なるものです。以前、相続の相談で1時間以上話し続けてしまったことがあります。後日、依頼者が他の事務所に乗り換えたと聞かされました。何がいけなかったのかと振り返ったとき、「伝えるべきこと」よりも「全部話さないと気が済まない自分」が前面に出ていたと気づいたのです。大事なのは、相手が理解して安心すること。僕の満足じゃない。その線引きをようやく考えるようになりました。
話しすぎて信頼を失う瞬間
信頼というのは、意外にも「言いすぎ」で失われることがあります。過去に、緊張している依頼者に対して「リラックスしてくださいよ」と言いながら、延々と法律の説明を続けてしまったことがありました。帰り際のその人の顔には、疲れと困惑がにじんでいました。信頼を得たいなら、まずは相手の状態を見て、必要なことだけを絞って伝える勇気も必要なのだと、今になって思います。「黙ること」は不親切ではなく、信頼の第一歩なのかもしれません。
元野球部的気質が裏目に出るとき
高校時代、野球部で「声を出せ」「全力でぶつかれ」と言われて育った僕は、何事も勢いで乗り切るクセがあります。気合があれば伝わる、そう思ってきました。でも、司法書士の仕事は繊細で、相手はクライアント。僕の全力トークは、時に相手を疲弊させるだけなのです。根性論で話しすぎると、かえって距離ができる。そんな当たり前のことに、45歳になってやっと気づくとは…。昔の自分をぶん殴りたい気分です。
熱さが空回りする恐怖
熱心に話しているつもりでも、空回りしていたら意味がありません。むしろ「この人、自分の話しかしてないな」と思われてしまいます。あるとき、成年後見制度の説明に力を入れすぎて、依頼者が「すみません、もう時間が…」と帰ろうとした場面がありました。熱量を注いだはずが、相手の心は遠のいていた。これは本当にショックでした。熱さは大切ですが、相手の温度に合わせることこそ、本当のプロだと痛感しました。
「伝える」と「押し付ける」は違う
「自分が知っていることを伝える」と「自分の価値観を押し付ける」は、まったく違います。僕はいつの間にか、「この話も役に立つから聞いてほしい」とどんどん話を詰め込みがちになっていました。相手のニーズを無視して、「俺の話を聞いてくれ」になっていたのです。どれだけ情報が正確でも、押し付けになった時点で、聞いてもらえない。相手の立場に立つことを忘れたら、どんなに話しても、ただのノイズでしかないと学びました。
反省と自覚がもたらした小さな変化
あの日の一言をきっかけに、自分の話し方を見直すようになりました。とはいえ劇的に変われたわけではなく、地味な努力の繰り返しです。それでも、以前よりは「相手の顔色」を気にするようになったし、「一呼吸置いてから話す」ことも意識しています。変わったと言っても、他人から見たら些細な違いかもしれません。でも、僕にとっては大きな一歩です。司法書士として、人として、少しずつでも成長できればと思っています。
沈黙の効用を知る
今までは「話していないと不安」でした。でも最近、沈黙も会話の一部だと感じるようになりました。ある日、相談者が沈黙したときに、あえて僕も黙ってみました。すると、相手が自分の言葉で話し始めたんです。沈黙の中にこそ、本音が出てくることがある。沈黙は「間」ではなく、「余白」なのだと気づかされました。司法書士という立場だからこそ、余白の大切さを忘れてはいけない。沈黙を怖れず、向き合うことが信頼への第一歩だと思います。
黙って聞くというスキル
人の話を「黙って聞く」というのは、意外と難しいスキルです。つい口を挟みたくなるし、アドバイスしたくなる。けれど、ただ聞くだけで相手の表情が緩むことがあります。ある相談者が「先生、ちゃんと聞いてくれてありがとう」と言ってくれたことがありました。僕はほとんど話していなかったのに。話すことより、聞くことのほうが信頼につながる場面もある。話すことにばかり意識がいっていた過去の自分に、教えてやりたい真実です。
話し方を変えるだけで空気が変わった
ほんの少し話し方を変えるだけで、事務所の空気も変わってきました。事務員とのやり取りでも、「一言で伝える」「要点をまとめる」ようにすると、向こうの表情が明るくなることが増えた気がします。依頼者とのやり取りもスムーズになり、以前より「安心しました」と言ってもらえることが多くなりました。言葉は空気を作る道具。無意識のうちに、自分が張り詰めた空気を作っていたことに気づいた今、言葉の力を改めて感じています。
短く話すと相手が話し出す
不思議なもので、自分が話す時間を短くすると、相手が自然と話し出すことが増えました。以前は僕が説明しすぎて、相手が話す隙を与えていなかったんでしょう。今は「ここまでで何か質問ありますか?」と一度区切るようにしています。そうすることで、依頼者の不安や疑問がぽろっと出てきたり、こちらの見落としに気づけたりするんです。司法書士の仕事は「一方通行」ではダメ。対話でしか見えないものが、たくさんあると感じています。
時間管理の面でも大きな効果
話を短くするよう意識すると、面談や業務の時間管理も楽になります。以前は予定時間を大幅にオーバーすることが多く、次の予定に焦ることもしばしば。今は、時間を区切って伝えるべき要点だけを整理してから話すようにしています。その結果、事務員の業務負担も減り、事務所全体のリズムが整ってきました。小さな改善かもしれませんが、「時間は有限」という当たり前をやっと実感できた気がします。年齢的にも無駄なエネルギーは使いたくないですからね。