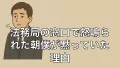昼休みの問いかけが予想以上に響いた
その日は、いつもと変わらぬ業務の合間に訪れた昼休みだった。出先での用事を済ませ、ふらっと立ち寄ったカフェのレジで言われた一言――「お一人ですか?」。たったそれだけのこと。にもかかわらず、その問いかけがなぜか胸にずしんと来た。声をかけた店員には、悪気などあるはずもない。ただの確認、ただのルーティン。でも、心のどこかで張りつめていた糸のようなものが、その言葉ひとつで音もなく切れたように感じた。疲れていたのか、あるいは、無意識に自分の「一人」である現実から目を背けていたのかもしれない。
ただの定型文のはずなのに
「お一人ですか?」は飲食店でよく聞かれるフレーズだ。だけどこの日は違った。少し遅めの時間帯で、店内はカップルや親子連れ、仕事仲間らしきグループでにぎわっていた。そんななか、ポツンと立っていた私に向けられたその一言は、まるで「あなたは孤独ですね」と宣告されたかのように感じてしまった。そんな意図はない。だが、聞き流せないほどに、自分のなかの何かが反応していた。ああ、そうか。俺って、本当に一人なんだなと、改めて突きつけられたような気がした。
忙しさのなかで無意識に避けていた言葉
仕事が立て込むと、寂しさなんて感じてる暇もない。登記の書類、不動産の相談、相続のトラブル…依頼は切れ目なくやってくる。事務員と必要なやりとりをして、あとは淡々と処理する毎日。日々をこなすことで、感じたくない気持ちは押し込めてきたのかもしれない。「お一人ですか?」という言葉は、そのフタを開けてしまう鍵だった。自分でも気づいていなかった孤独を、たった一言で突きつけられるなんて。そんな繊細な心の部分、仕事の顔しか見せていない自分は、誰にも話せない。
一人でいることと孤独は違うはずなのに
一人でいるのは嫌いじゃない。むしろ、仕事に集中できるし、誰かに気を遣わなくて済む。だけど、孤独は違う。孤独は静かに、じわじわと、心の隙間を広げてくる。友人と連絡を取る機会も減り、気づけば誰とも深くつながっていない感覚に包まれる。元野球部で、あんなに仲間と声を張っていたあの頃とは、まるで別人だ。「お一人ですか?」という言葉が、そんな過去と今を並べて見せてくる。今の俺には、応援するチームも、ベンチで隣に座る仲間もいない。
司法書士としての役割と孤独
司法書士という職業は、人の人生の節目に立ち会う仕事でもある。登記、相続、遺言、会社設立、時には離婚や裁判関係の相談もある。そのたびに、依頼者の話を聞き、正確に、丁寧に処理をしていく。だけど、心の奥底までは踏み込まない。プロとしての線引きがあるからこそ、自分のことを語る機会はほとんどない。だからなのか、自分の感情をしまい込む癖がついた。誰かに話す前に、自分で整理して、忘れていく。そんなふうに仕事をしているうちに、ふと気づくと、自分自身が誰ともつながっていないことに気づく。
相談者には寄り添えるのに
依頼者の不安には敏感だ。相続のこと、家族のこと、みんな胸にいろいろな想いを抱えてやってくる。それを否定せずに、少しでも安心してもらえるように言葉を選ぶ。でも、自分のことになると急に不器用になる。悩みを誰かに話すことにも慣れていないし、相談する相手もいない。人には寄り添えるのに、自分の寂しさに気づくと、どうしようもなくなる。「お一人ですか?」は、その矛盾を炙り出す一言だった。
自分自身の声は誰にも届かない
毎日誰かと話しているようで、実は独り言のような会話しかしていない。事務員とも、必要最低限の業務会話が中心。雑談らしい雑談なんて、最後にしたのはいつだろう。帰っても話す相手はいない。誰かの声を聞かずに一日が終わる。そんな日が当たり前になっていることに、ふと気づくと怖くなる。誰かの声は届いても、自分の声は誰にも届かない。そう思ってしまう夜は、長くて重い。
事務員と交わす言葉も業務連絡ばかり
「これ、明日までに出します」「午前中の面談、10時からです」そんな言葉しか交わしていない。事務員さんはとても助かっている存在だけど、業務以外の会話になると、気まずさが勝ってしまう。こっちが一人者であることを、あまり知られたくない気持ちもあって、どこか壁を作っているのかもしれない。冗談の一つでも言えばいいのに、それができない。何をどう話せばいいかわからないまま、今日も「お疲れさまでした」で一日が終わる。
いつのまにか日常にしみついた一人
気づけば、「一人」であることが前提の日常になっていた。誰かと食事に行くことも、出かけることも、すっかり減った。誘うのも億劫だし、誘われることもない。日々のルーティンを守ることで、寂しさを感じないように生きてきた。だけど、ほんの少しのきっかけで、崩れる。今日は、その一言だった。「お一人ですか?」。本当にただ、それだけの一言。けれど、その日の心の隙間に、すうっと染み込んできた。
モテない自覚と向き合う夜
正直なところ、女性にはモテた記憶がない。元野球部で声はでかかったし、人懐っこかったはずなのに、どうもそういう方面には縁がなかった。今となってはもう、自分のことを異性として見る人なんていないんだろうなと、諦めにも似た感情で受け止めている。だけど、そう思いながらも、どこかで人恋しさが消えない夜もある。SNSで誰かの結婚報告や、家族との写真を見るたびに、自分の空白が浮き彫りになる。
期待しないように生きることの楽さと虚しさ
期待しなければ、傷つかなくて済む。そう思って、一人に慣れたつもりだった。たとえば誕生日に誰からも連絡がなくても、「別に気にしてない」と言い聞かせる。休日も一人で過ごすことが多くなったが、「このほうが気楽だ」と思っていた。けれど、ふとしたときに、それが強がりだったと気づかされる瞬間がある。心のどこかで、誰かとのつながりをまだ求めている自分がいる。それを認めるのが、少しだけ怖い。
お一人様に慣れたはずなのに
「お一人様」。その言葉に抵抗を感じることも、もうないと思っていた。牛丼屋もラーメン屋も、カウンター席が一番落ち着く。誰にも気を遣わず、誰の会話にも巻き込まれない。それが快適で、自由で、自分に合っていると信じていた。でも、今日だけは違った。「お一人ですか?」と聞かれた瞬間、自分が“孤立している人間”のように思えてしまった。慣れたつもりだったのに、慣れてなかった。そう痛感した、ある昼下がりのことだった。