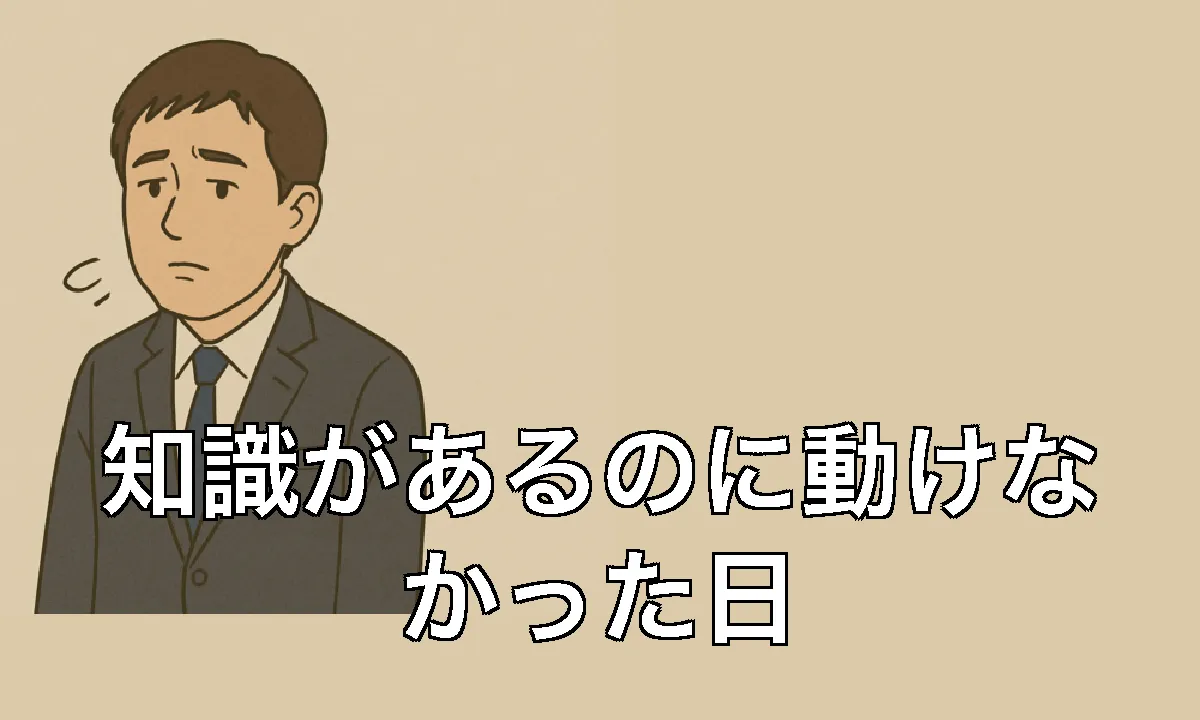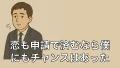現場では正解が通用しないときがある
司法書士の仕事は、知識と経験がものを言う世界だとずっと思っていた。それは間違いではない。でも、ある日の現場で「知識はあるのに動けなかった」経験をして、自分の中で何かが崩れた。頭ではわかっていた。でも、それをその場で出すことができなかった。そんな場面が、本当にあるんだと実感した。現場には、人の感情も、場の空気もある。それに圧倒されると、たとえ正しい判断が頭に浮かんでいても、身体が動かなくなるのだ。
頭では分かっていたけど体が止まった
先日、ある高齢の依頼者が遺言書の件で訪ねてきた。事務所で学んだ通りの対応なら、形式的に確認して進めれば済む内容だった。だが、その方は明らかに不安そうで、何度も同じことを繰り返し聞いてきた。その瞬間、「これは単なる書類作成ではないな」と直感した。でも、どう対応すればいいか分からなかった。正しい説明はできる。けれど、その説明で相手の不安は消えない。自分が発した言葉が、どこにも届かない感じ。気づけば、ただうなずくことしかできていなかった。
事務所で学んだ知識が現場では通じなかった
事務所での研修や書籍で学んだ知識は、確かに役立つ。しかし、現場では「教科書通り」に行かないことばかりだ。相手が涙ぐんだ瞬間、こちらもどうしていいかわからなくなる。形式的に説明を続けても逆効果だと感じたが、他に何をすればいいか見当もつかなかった。「ここで必要なのは、知識じゃない」と思いながらも、自分の引き出しにはそれ以外の対応がなかった。
書類一枚の重みに心が折れそうになる
普段、何気なく扱っている一通の書類。でも、その人にとっては人生の最終章に関わる重たい紙切れなんだよな。自分が目の前に差し出すその紙が、家族との別れ、財産の行方、生きてきた証に関わる。そう思った瞬間、手が震えた。間違ってはいけないというプレッシャーと、人としての対応に悩む自分が、頭の中でせめぎ合っていた。
「知識があるのに」と責められる理不尽
時には、依頼者やその家族から「先生なのに、どうして分からないんですか」と言われることもある。こちらが間違っているわけじゃない。説明すれば分かってもらえることも多い。でも、感情的になっている相手に、冷静に論理で返しても火に油を注ぐだけのこともある。そんなとき、「知識があるのに動けない」というのは、まさに現実に起こる。
相談者の期待と現実のギャップに悩む
「司法書士に頼めば全部うまくいく」と思っている依頼者が多い。でも実際には、こちらも法的な範囲でしか対応できない。限界はあるし、魔法のような解決策なんて存在しない。そのギャップに悩む。一度、家族内のトラブルを相談されたとき、明らかに法律ではどうにもならない感情のもつれがあった。解決策が頭にあっても、実行できる場がなかった。
「先生なんだから当然でしょ」のプレッシャー
「先生」と呼ばれるたびに、胸が痛くなる。そんなに立派な人間じゃない。ただ、少し勉強して、少し経験を積んだだけの、ひとりの男だ。でも社会は「専門家」に完璧を求めてくる。間違えることすら許されない雰囲気。そのプレッシャーに押しつぶされそうになる日もある。笑顔で対応しているけれど、心の中ではいつもビクビクしている。
経験不足ではないけれど対応できなかった
20年もこの仕事をしていれば、多少のトラブルにも慣れてくる。それでも「初めての場面」は必ず訪れるし、想定外の感情の揺れに巻き込まれることもある。だから、「経験が足りないだけ」とは言えない。「慣れ」と「慣れすぎ」は紙一重で、気を抜くと見落としや判断ミスにもつながる。それを恐れるがあまり、逆に動けなくなる。
実務歴20年でも初見のケースはある
先日、全く見たことのない種類の土地売買契約書を目にした。古い慣習が残っていて、判例もほとんどない。資料を一通り揃え、法務局にも確認を取り、それでも「このままで大丈夫」と自信を持てなかった。周囲からは「先生なら平気でしょ」と言われたが、内心では「誰か代わってくれ」と叫んでいた。知識があっても、「自信」が伴わないと手が止まる。
マニュアルでは片付かない人間関係の壁
書類の手続き以上に難しいのが「人」だ。例えば、相続の場面で家族が揉めている場合、誰の味方にもなれない。公平を保ちながら進めるのは至難の業だ。感情のこじれた現場では、正しい説明が逆に怒りを生むこともある。冷静さを保とうとすればするほど、相手の感情とのギャップが広がっていく。どれだけ知識があっても、「人間としての立ち回り」はまた別物だ。
相手の感情に触れてしまう場面の怖さ
「これ以上、掘り下げないでください」と涙を流されたことがある。その一言で、それまで準備していた質問や確認がすべて吹き飛んだ。正しい手続きを取るためには必要な確認事項だった。でも、相手の心に深く踏み込みすぎたと感じた。そのとき、自分が持っていたのは知識だけで、相手の感情を受け止める器ではなかった。怖くなって、言葉が出なくなった。
落ち込んでもやり直せる環境を作るには
こんな経験を重ねるうちに、自分の中で一つだけ確かなことがある。それは「落ち込んでも、やり直せる」という感覚。自分の中にスペースがあるかどうかが大事だ。知識だけに頼らず、人としてどうあるかを問い続けることで、少しずつ「動ける自分」を取り戻せる気がする。
自分を責めすぎずに「休む勇気」を持つ
失敗した日や、対応できなかった日。そんなときは無理に取り返そうとしないことにしている。昔は反省ノートをびっしり書いていたが、今は温泉にでも行って気分を切り替えるようにしている。休むこともプロの仕事だ。走り続けるだけでは息切れする。休んで、また戻ってくる。それでいい。
反省と自省の違いを意識する
「反省」は人の目を意識した言葉で、「自省」は自分の内側と向き合う行為だと最近思うようになった。依頼者に対して申し訳なかったと感じるとき、ただ謝るだけでなく、「なぜできなかったのか」「次にどうすべきか」を静かに考える。答えは出なくても、そうやって自分と向き合う時間を持つことが、次への一歩につながる。
気持ちを吐き出す相手がひとりでもいればいい
事務員にはあまり見せないが、実は週に一度、昔の同級生と電話している。特に何か相談するわけではない。ただ、「今日も疲れたな」「また対応できなかった」と呟けるだけで、少し気が楽になる。司法書士は孤独な仕事だ。だからこそ、誰かに「正しくなくていい自分」を見せられる場が必要なんだと思う。
「知識だけでいい」と思っていた昔の自分へ
若い頃の自分に言いたい。「知っていること」と「できること」は別物だよ、と。知識を詰め込むだけでは、仕事はうまく回らない。むしろ、人とどう向き合うか、どう言葉を選ぶか、そういう部分にこそ司法書士としての価値がある。失敗も、恥も、全部が財産だ。そうやってしか、動ける人間にはなれない。
若い頃は理屈でなんでも解決できると思ってた
受験勉強の延長で、司法書士の実務も攻略できると思っていた。でも現実は、理屈の外にある「感情」や「空気」との戦いばかりだった。それに気づくまで、何年もかかった。今も完璧ではないけど、理屈をひとまず脇に置くことも覚えた。大事なのは、目の前の人と「向き合う」こと。その姿勢だけは、絶対に忘れたくない。
実は野球部時代にも同じようなことがあった
高校時代、試合で自分のエラーがきっかけで逆転されたことがあった。ルールも、動き方も分かっていたのに、とっさの判断ができなかった。あのときの悔しさが、今も胸に残っている。知識と実践には、決して越えられない壁がある。司法書士の現場でも、それはまったく同じだ。
技術より「空気を読む力」が問われる世界
技術だけでは、信頼は得られない。むしろ、「あ、この人は話を聞いてくれそう」と思ってもらえることの方が大事な場面が多い。特に田舎ではなおさらだ。言葉にしなくても伝わる何か。空気を読む力、人間くささ。そういうものを、若い頃には軽視していた。でも今は、それこそが自分の武器になると信じている。