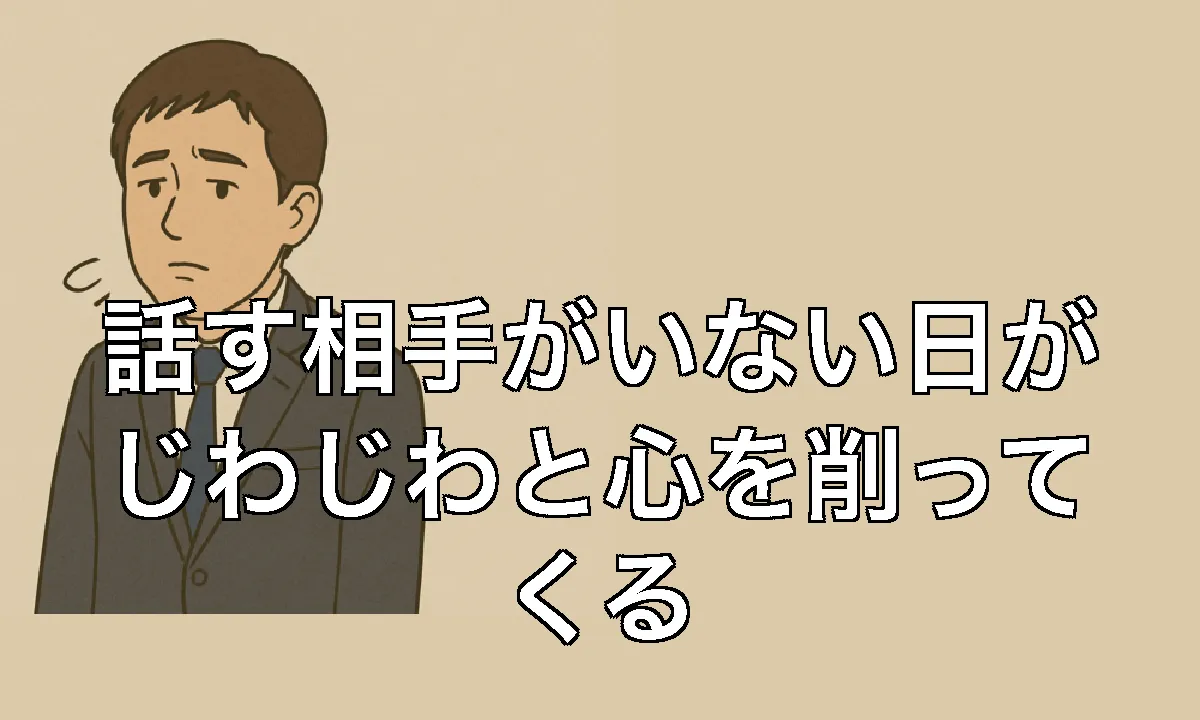静かすぎる朝に気づく孤独
毎朝、目覚ましの音に起こされて、布団から出て、顔を洗い、コーヒーを淹れる。誰にも話しかけられず、話しかける相手もいない。その一連の流れが、まるで無音の映画のように淡々と進む。テレビの音だけが部屋に流れていても、どこか“本当の声”が足りないと感じてしまう。若い頃はこんなこと気にしなかったのに、気づけば「このまま誰とも話さずに一日が終わるかもしれない」という不安が、じわじわと染みこんでくる。
誰かと話す予定がない一日のはじまり
昔は「今日は誰と話すかな」なんて思ったこともなかった。仕事をしていれば、自然と誰かと話す時間があった。でも今は違う。朝の時点で「今日は話す予定がないな」とわかってしまう日もある。依頼が減ったわけではない。むしろ書類の山は増えている。だが、メールやチャットで完結してしまう仕事が増え、電話すら来ない。人と話すことなく一日が過ぎる。それは効率的かもしれないが、人としての“何か”が削られている気がしてならない。
声を出すのが億劫になる瞬間
そんな日が続くと、たまに電話が鳴っただけで妙に緊張する。「久しぶりに声を出すな」と、口の筋肉がぎこちなく動くのがわかる。昔はクライアントに堂々と話していたはずの声が、今は少し上ずっていたりする。特に声を張るのがしんどい。使っていない筋肉は衰えるというが、それが声でも起きるとは思ってもみなかった。元野球部だった自分が、声を出すことに躊躇するなんて、笑える話だ。
コンビニ店員との会話が唯一の交流になる現実
夕方、少し外に出てコンビニで弁当を買う。「温めますか?」と店員さんに聞かれて、「はい」と答える。その一言が、今日初めて発した“会話”だと気づく時の切なさといったらない。話したというより、返しただけだ。でも、それすらない日はもっときつい。「ありがとうございました」だけで店を出た日は、自分の存在がこの世界に薄れていくような、妙な不安に襲われる。
相談できる相手がいないという職業病
司法書士という仕事は、個人で黙々とやる側面が強い。誰かに相談したいと思っても、守秘義務もあるし、専門性も高い。昔はちょっとしたことで先輩に聞けたが、今は聞かれる側になってしまった。そうなると、ますます自分の中に抱え込むことが増えていく。
同業者はライバル 友人には専門性が通じない
同業者と話す機会があっても、どうしても警戒してしまう。業務の内容、顧客の動き、報酬額──話せるわけがない。昔の友人と飲みに行っても「へえ、そんな仕事なんだ」くらいの反応で終わる。共有できることがないから、会話が広がらない。仕事の愚痴を話す場所がなくて、自分の中だけでループしてしまう。これが意外と堪える。
ひとり事務所の責任と緊張感
誰にも相談せずに判断しなければならない案件が続くと、神経がすり減る。事務員さんは頼りになるが、最終判断はすべて自分。間違えれば信用問題になるし、損害も出るかもしれない。だからこそ慎重になるし、だからこそ孤独が増す。責任が重くなればなるほど、話せないことが増えていく。結果、無口になる。
元野球部の声を出す文化はどこへ行ったのか
昔は「声出していこう!」が口癖だった。グラウンドでも、試合でも、朝の挨拶も全力だった。今は? 事務所で小さく「おはよう」と言うのが精一杯だ。声を出すことが、こんなにも苦手になるとは思ってもいなかった。外に向かって声を出す機会が減った今、あの頃の自分が別人のようだ。
事務員との距離感と気遣いの疲れ
事務員さんがいるとはいえ、仕事上のやりとりは形式的なものが多い。雑談をしたくても、年齢差や立場の違いから、言葉を選んでしまう。相手も気を遣っているのがわかるから、こちらもさらに気を遣う。気づけば、何も話さないほうが楽になっている。
近すぎても遠すぎてもやりづらい
関係性が近すぎると注意もしづらいし、遠すぎると業務の連携に支障が出る。絶妙なバランスが必要で、その維持がまた面倒だ。話しかけようとしてやめることもしばしばある。言葉が詰まって、気まずくなるのが怖いのだ。そういう日々が続くと、誰かと自然に話すという感覚を忘れていく。
感情を出さないことで保つ関係
無理に笑ったり、怒りを押し殺したりして過ごすことが多くなると、自分の感情がどこにあるのか分からなくなる。事務員さんにとっても居心地が悪くないように、なるべく一定のテンションを保つ。それが続くと、もはや人間関係ではなく業務関係だけになっていく。それが寂しい。
孤独の正体と向き合う時間
仕事が終わり、家に帰って、誰もいない部屋で一人。テレビをつけても、スマホをいじっても、心は満たされない。この空白の時間に向き合わなければならないのが一番つらい。
忙しさでごまかしてきたものの正体
「忙しいから仕方ない」と言い聞かせていたが、本当は寂しかっただけかもしれない。話し相手がいない現実を、業務で埋めていたのだ。だが、ふと時間ができるとその現実がむき出しになる。逃げていたものが、いきなり目の前に現れる感じだ。
会話が減ることで増える妄想癖
人と話さない時間が続くと、頭の中で勝手に誰かと会話していたりする。「もしあのとき〜だったら」と過去を繰り返したり、「次にあの人が来たら〜」とありもしない未来を想像したりする。こうなると現実と妄想の境目が曖昧になってくる。危ういな、と思いながらも、それを止める手段がないのが現実だ。
それでもこの仕事を続けている理由
誰にも頼られないことのほうが、実はつらい。たとえ一言も話さない日があっても、誰かが「お願いします」と言ってくれる限り、自分はこの場所にいていい。そう思えるだけで、また一日がんばれる。
誰にも頼られなくなるのが一番怖い
「もういいですよ」と言われる日が来たら、と思うとゾッとする。仕事の量がある限り、たとえ孤独でもこの日常を続けられる。話し相手はいなくても、依頼があるだけで救われているのかもしれない。
自分の存在を確認できる瞬間があるから
登記が完了して、依頼者から「ありがとうございました」と言われたとき。それだけで「ああ、自分は必要とされていた」と思える。それがある限り、この仕事を続けていこうと思える。孤独と戦いながらでも。