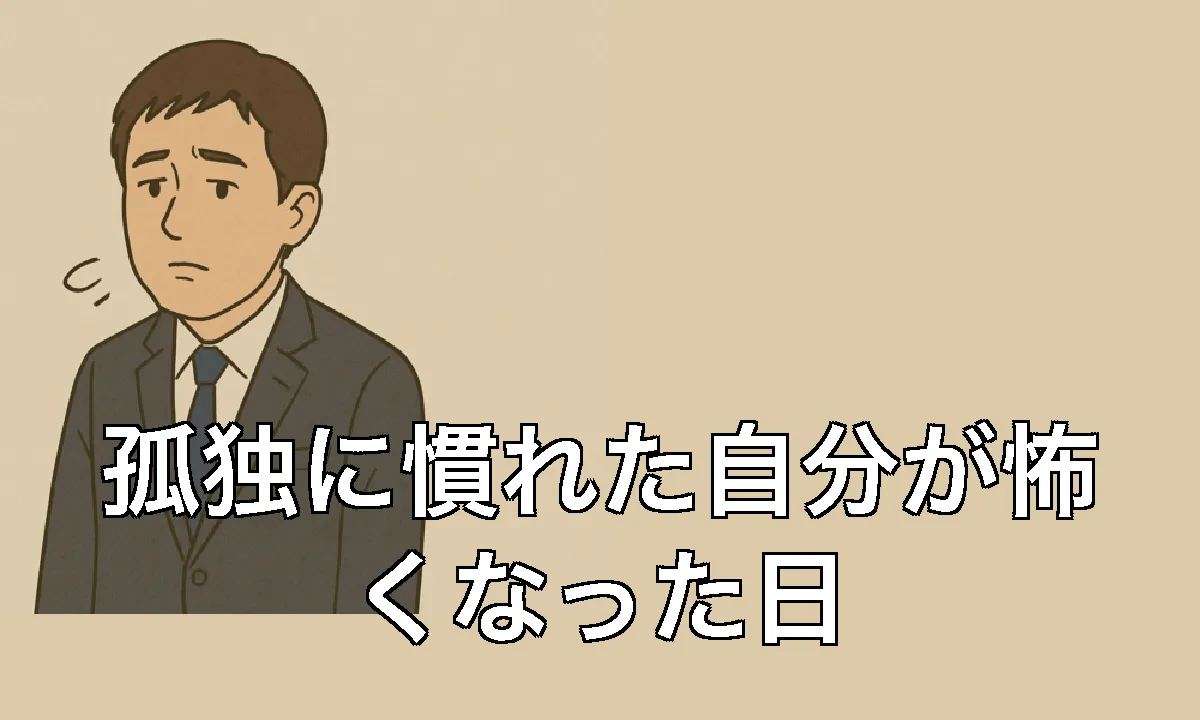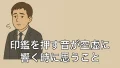孤独に慣れてしまったことへの違和感
誰かと会わない日が続いても、まったく苦じゃなくなった。それどころか、一人で過ごすことのほうが心地よくなっていた。最初は「この職業だから仕方ない」と思っていた。でも、ある夜ふと、テレビの音だけが響く事務所のソファに沈みながら、「あれ? こんなに一人が平気になってていいのか?」と自分に問いかけてしまった。慣れることは楽になることでもあるけれど、同時に何か大事なものが失われている気がしたのだ。
忙しさの中で気づかぬうちに独りになっていた
登記や相続の案件で毎日が目まぐるしく、気がつけば週末も平日と同じように書類をめくっていた。電話の鳴らない日が嬉しくなり、昼休みに誰とも話さずにおにぎりを頬張るのが日常になった。あの頃の私は「仕事が充実してるから」と自分に言い聞かせていたけれど、実のところ誰かと向き合う余裕がなくなっていただけだった。
誰かと話す時間より書類と向き合う時間が増えた
午前中から相続登記の相談、午後は法務局への問い合わせ、夕方は報告書の作成。こうして一日が終わっていく。電話やメールでのやりとりはあっても、直接会って話すのは月に数回程度。書類の山が積み重なるたびに、私は人と向き合う時間を置き去りにしてきたのだ。パソコンの前では流暢でも、対面では言葉が詰まることが増えた。
「慣れ」と「諦め」は紙一重
「もうそういうもんだ」と思うようにしていた。でもそれは「慣れ」ではなく「諦め」だったのかもしれない。若い頃は、依頼者とのやり取りにも熱が入ったし、同業の仲間とも飲みに行ってよく語り合った。それが今では、「どうせ誰も誘ってこないし」「一人のほうが楽」と、どこかで自分をごまかしていたのだ。
人付き合いが減ると感情も平坦になる
感情の波が小さくなっていることにも、ある日ふと気づいた。喜びも、怒りも、寂しさも、すべてが鈍くなっていた。感情を動かす相手がいない日々は、まるで低刺激の生活。穏やかと言えば聞こえはいいが、それは単に自分の心が静かに冷めていっている証拠のようにも思えた。
人と会わなくても平気になった自分への戸惑い
昔は休みの日に誰かと会わないと気が滅入った。でも今では、何の予定もない週末がむしろ嬉しい。朝ゆっくりコーヒーを飲んで、昼に一人でスーパーに行って、夜は好きなドラマを見て寝る。それが何の苦もないどころか、安心すらする生活になっていた。それなのに、ふとした瞬間に「このままでいいのか」と不安に襲われるのだ。
感情の起伏が少なくなると人生が淡々としていく
感動することが減った。泣くことも、腹を立てることも、声を上げて笑うことも減った。事務所のデスクで黙々と作業をこなすうちに、「感じない自分」になっていた。仕事はミスも少なくなったし、効率も良くなった。でも、それが本当に良いことなのか、わからなくなる。人生の彩りがどんどん薄くなっているような気がしてならない。
司法書士という職業が持つ孤独
人の人生に深く関わる仕事であるにもかかわらず、自分の人生には誰も立ち入ってこない。司法書士は「先生」と呼ばれることが多い。でも、その呼び方にはある種の壁がある。依頼者との距離感、同業者との張り合い、そして自分の内面との距離。どれも近づけそうで近づけない、その微妙な孤独が日常になっていた。
「先生」と呼ばれることの重みと距離感
「先生、ありがとうございます」と言われるたび、少し居心地が悪い。「先生」と言われると、どこかで自分を演じなければいけないような気がする。失敗できない、感情を出せない、弱音を吐けない。依頼者は感謝してくれるけれど、そこに親しさはない。どれだけ丁寧に対応しても、超えられない壁のようなものを感じるのだ。
頼られるけれど、相談されない
相続や不動産の手続きで「頼りにしてます」と言われることはある。でも、相手が私に悩みを打ち明けることはまずない。一方的に相談を受けるだけで、私のほうが何かを話す機会はほとんどない。専門家としての信頼はあっても、人としてのつながりは希薄だ。相談されるけど、相談できないという不均衡さが心に重くのしかかる。
信頼はあるのに親密さはないという矛盾
何年も付き合いのある依頼者でも、私生活の話をしたことはほとんどない。年賀状や贈り物は届くけれど、誕生日を祝ってくれるわけでもない。そういう関係性が積み重なる中で、私は「仕事上の信頼」と「人としてのつながり」は別物だと割り切るようになった。でも、たまにふと、「それって寂しくないか?」と立ち止まる瞬間がある。
仕事の性質上、誰にも弱音を吐けない
司法書士という肩書が、時に自分の感情の自由を奪う。法的なことを扱う以上、常に冷静であることが求められる。ミスが許されない世界で、感情的になることはリスクだ。だからこそ、どれだけ心が疲れていても「大丈夫です」と言わざるを得ない。そしてその「大丈夫」が、ますます孤独を深めていく。
愚痴をこぼす相手もいない日常
かつては同業者との飲み会で愚痴をこぼすこともあった。でも今は、そういう場に誘われることも減り、自分からも出向かなくなった。仕事の話をできる相手はいるが、気持ちの話をできる相手がいない。家に帰って話す相手もいない。だからこそ、こうして文章にして吐き出しているのかもしれない。
言葉を飲み込む習慣が孤独を深める
「こんなこと言っても仕方ない」と思って、つい言葉を飲み込む。言いたいことがあっても、どうせ誰もわかってくれないと決めつけてしまう。そうして何も言わないまま日々が過ぎていく。気づけば、心の声すら聞こえなくなっている。孤独とは、誰かがいないことより、自分の声すら届かなくなることなのかもしれない。
それでも続けている理由と支え
こんな孤独に囲まれた仕事でも、やっぱりやめられない理由がある。それは、誰かの役に立っているという実感だったり、ささやかながら心を許せる人の存在だったりする。完璧じゃなくていい、ただ少しでも前に進めればいい。そんな気持ちが、今日も私を机に向かわせている。
一人の事務員の存在に救われている
事務所には事務員が一人いる。年齢は少し若いが、仕事に対する姿勢は真面目で、雑談も適度にできるありがたい存在だ。彼女の笑顔や一言に、何度も救われてきた。たった一人でも、気を許せる人がいるというのは、本当に大きい。それだけで、今日もまたやっていける気がしてくる。
淡々とした毎日を支えてくれる相棒のような存在
毎朝の「おはようございます」、お昼前の「そろそろお弁当にしますか?」という何気ない言葉。こういうやり取りがあるだけで、私の中の「誰とも話してない一日」は回避される。彼女の存在が、事務所に人のぬくもりを残してくれている。私の「仕事だけの時間」を「人との時間」に変えてくれる、ささやかながら大きな支えだ。
孤独を共有することの大きな意味
人は完全に孤独でいることはできない。少しでも、誰かと感情を分かち合えれば、それだけで救われる。私は司法書士という仕事を通じて、誰かの不安を取り除く手助けをしている。でも、本当は自分もまた、誰かに救われているのだ。小さな交流、小さな共感、その一つひとつが、孤独に慣れすぎた心を少しずつ溶かしてくれる。
同じように悩む人へのエール
もしこれを読んでいるあなたが、孤独に慣れてしまったことに違和感を覚えているなら、あなたはまだ大丈夫だと思う。その感覚を見失わずにいてほしい。誰かと笑うこと、話すこと、気持ちを共有すること。それらを諦めずにいれば、きっとまた、心が動く瞬間に出会える。私も、まだあきらめていない。
孤独は悪いことじゃないけれど、慣れすぎなくていい
一人でいることが好きな人もいる。孤独を楽しめる人もいる。でも、私のように「仕方なく一人に慣れた」場合、それは本当の意味での自由ではない気がする。慣れた自分に甘えすぎず、たまには人の中に飛び込んでみる。そんな小さな行動が、心を元に戻す第一歩になることもあるのだ。
誰かと少しでも心を通わせることが今日を変える
今日は誰かに「ありがとう」と言えただろうか。誰かに「元気?」と聞けただろうか。たった一言のやり取りが、自分の中の孤独を和らげてくれることもある。仕事に追われているとつい忘れてしまうけれど、人と心を通わせることは、思っている以上に大きな意味を持っている。今日が少しでも優しい日になるように、私はまた、誰かに声をかけてみようと思う。