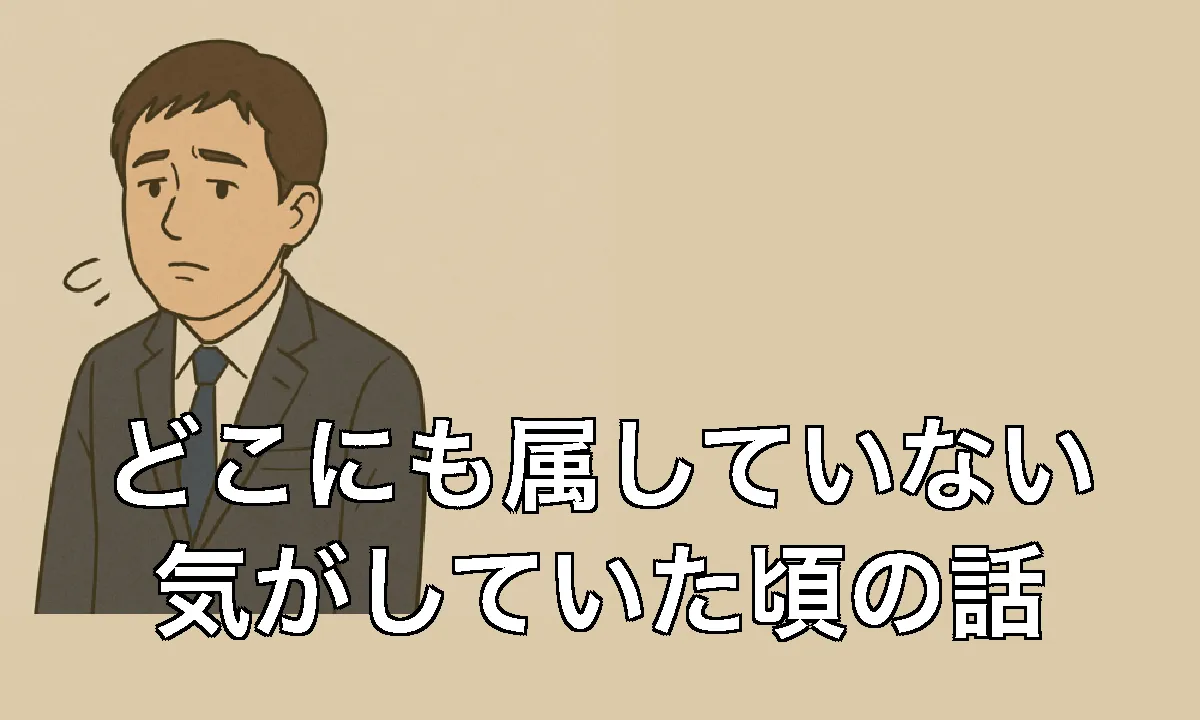朝起きた瞬間からどこにも行きたくない日がある
目覚ましが鳴って、目を開けた瞬間から、どこか胸が重たい。やらなきゃいけないことは山ほどあるのに、身体が布団に沈み込むように動かない。そんな朝が、定期的にやってくる。理由ははっきりしない。ただ、「今日は誰にも会いたくない」と思う。事務所は開けなきゃいけないし、依頼者の予定もある。でも、気持ちだけが置き去りにされている感じ。自分が自分にすら属せていないような、そんな朝に限って、なぜか予定は詰まっているものだ。
書類の山に囲まれていても空っぽな感覚
机の上には案件の資料や登記申請の下書き、提出期限のメモが所狭しと並んでいる。それなのに、心の中はからっぽで、書類の文字がまるで読めない暗号のように見える日がある。手は動いていても、気持ちは別の場所にいる。焦っても集中できず、「今日は進んだ気がしないな」とため息をつく。仕事があるというのはありがたいことだと頭ではわかっている。でも、心がついてこない日もある。あの頃の自分は、まさにそんな日々を繰り返していた。
仕事があるだけマシという言葉に傷ついたこと
「仕事があるだけ幸せよ」と、何気なく言われたその一言が妙に心に刺さった日がある。もちろん感謝している。依頼してくれる人がいるから、事務所を続けられている。でも、その「ありがたさ」と「自分の孤独感」は別物だ。誰かと一緒に働いて、喜びや苦労を分かち合うという感覚が薄いからこそ、余計にそう感じたのかもしれない。ひとりで抱える司法書士業務の中で、誰にも相談できない気持ちはじわじわと心をむしばんでいた。
事務員の明るさだけが救いだったあの日
そんなとき、うちの事務員が「先生、今日なんだか顔色悪いですよ」と笑って言った。その一言が、ずいぶん救いになった。大げさだけど、その時は本当に「この人がいてくれて良かった」と思った。誰かに気づかれることで、「あ、自分はここにいていいんだな」と感じられる瞬間がある。忙しさと孤独が交差する日々の中で、ささやかな声かけがどれだけ心を軽くしてくれるか、身に染みた日だった。
司法書士という肩書に救われたはずだった
司法書士の資格を取ったとき、「これで自分の場所ができる」と思っていた。でも、いざ実務が始まってみると、肩書ひとつで居場所が得られるわけじゃなかった。名刺にはしっかり「司法書士」と印字されていても、それが自分を守ってくれる盾にはならなかった。むしろ、周囲からの期待や誤解が重くのしかかることもある。名刺だけが独り歩きして、自分自身はどこにも根を張れていない感覚。それが、一番しんどかったかもしれない。
名刺の重みと心の軽さのギャップ
名刺交換のとき、相手が「おお、司法書士さんなんですね」と反応するのを見て、少しだけ誇らしくなる。でも、そう思った直後にふっと「中身はからっぽなのに」と心がつぶやく。資格がある、仕事がある、それは事実。でも、それが自分の価値と一致しているかと言えば、正直自信はない。外から見た自分と、内側の自分があまりにも違う。だからこそ、名刺の一枚が時には自分を苦しめる。そんな自分を演じる日々に、疲れを感じていた。
どこにいても所属できないと感じる瞬間
集まりに出ても、なんとなく浮いてしまうことがある。誰と話せばいいかわからない、話しかける勇気も出ない。周りは同業者でも、妙な距離感がある。世間話で笑いあっている輪の中に、どうしても入っていけない。所属しているはずの「司法書士会」ですら、どこか居心地が悪い。だからこそ、「自分はどこにも属していないんだな」と感じることがあった。肩書や立場があっても、心が置ける場所とは限らないのだ。
声をかけられない会合と沈黙の名刺交換
研修会や懇親会で、名刺だけは何枚も配る。でも、話は弾まない。名刺交換しても「どちらで開業を?」と聞かれるだけで、それ以上の会話が続かない。こちらも聞き返す気力がないから、沈黙だけが残る。声をかけてくれる人がいても、どこか表面的な会話になってしまい、心がついてこない。ひとりで会場をぐるっと回って、最後にはトイレに逃げ込んだこともある。「ここにも自分の居場所はなかったな」と、また一つ、疎外感を抱えるのだ。
野球部にはちゃんと居場所があった
学生時代、野球部にいた頃のことをふと思い出す。ポジションがあって、背番号があって、「そこに自分がいる意味」が確かにあった。あの頃は、下手でもレギュラーじゃなくても、「チームの一員」だと感じられていた。怒鳴られても、走らされても、仲間と目を合わせて「キツいな」と笑い合えた。そういう関係性が、今の自分にはあまりに少ない。だから、余計にあの時間が懐かしく、まぶしく感じるのだと思う。
ポジションが与えてくれる安心感
ポジションがあるって、すごく安心する。自分に割り当てられた役割があって、そこに立っていればよかった。ミスをしても、次は頑張れと誰かが言ってくれた。司法書士の世界では、そういう「役割の中の安心感」はなかなか得られない。すべてが自己責任、誰かにカバーしてもらうことも少ない。だからこそ、ふと「自分のポジションはどこなんだろう」と立ち止まってしまう。社会の中での居場所がぼやけて見えるとき、野球部のあの時間が恋しくなる。
チームに属するという意味を今になって知る
当時はただ部活をこなしていただけ。でも今になって、その価値がわかる。チームに属するって、「誰かに頼られること」でもあり「自分が誰かを支えること」でもある。役割が明確で、つながりがあって、そこには「属している感覚」が確かにあった。それが社会に出てから、すっぽりと抜け落ちた。自営業という立場ではなおさらだ。誰かの下にいるわけでもなく、上に誰かいるわけでもない。だから、自分の居場所は、自分で作っていくしかないのだ。
今の自分にポジションはあるのかと問う夜
夜遅く、机に向かっているときふと考える。「自分のポジションって、どこなんだろう」と。依頼人がいて、仕事がある。だけど、それだけでは満たされないものがある。心の中に「ここにいていい」という確信がないと、日々の努力もどこか空回りしてしまう。そんな思いに押しつぶされそうになったとき、自分自身に問いかける。「今日も無事に仕事を終えた。それだけで、ここに立つ意味はあるんじゃないか」と。ポジションは与えられるものではなく、積み重ねの中で育てていくものかもしれない。
所属しなくても生きていけると気づいた日
どこにも属していないような感覚。それは時に孤独で、苦しい。でも、その分、自由でもある。誰かに合わせなくてもいい、自分のルールで働ける。その中で、少しずつ信頼を得て、自分の居場所を作っていく。司法書士という仕事は、そういう孤独を引き受けながらも、「自分なりの属し方」を見つけられる職業なのかもしれない。そう思えたとき、ほんの少しだけ、心が軽くなった。
誰にも属さないからこそ見えたもの
ひとりで仕事をしていると、見える景色がある。誰かの顔色をうかがわず、依頼人のことだけを考えて仕事ができる。そういう時間の中で、ふとした瞬間に「ああ、この人の役に立てたな」と思えることがある。その時、何かに属していない寂しさは少しやわらぎ、「この仕事をしていてよかった」と思える。どこかに属することで得られる安心感もある。でも、属さないからこそ築ける信頼関係や、人とのつながりもあるのだと思う。
司法書士としての覚悟が少しだけ芽生えたとき
ある日、依頼人から「先生にお願いしてよかった」と言われた。それが、どれほど心に響いたか。肩書や所属ではなく、自分自身を見て評価してくれたその言葉が、これまでの孤独を少しずつ癒してくれた。どこにも属していないように思えた日々も、実は自分を育ててくれた時間だったのかもしれない。司法書士として、誰かの人生に寄り添う覚悟が、やっと芽を出した。たとえひとりでも、誰かのために立ち続ける。それが今の、自分なりの“所属”の形だ。