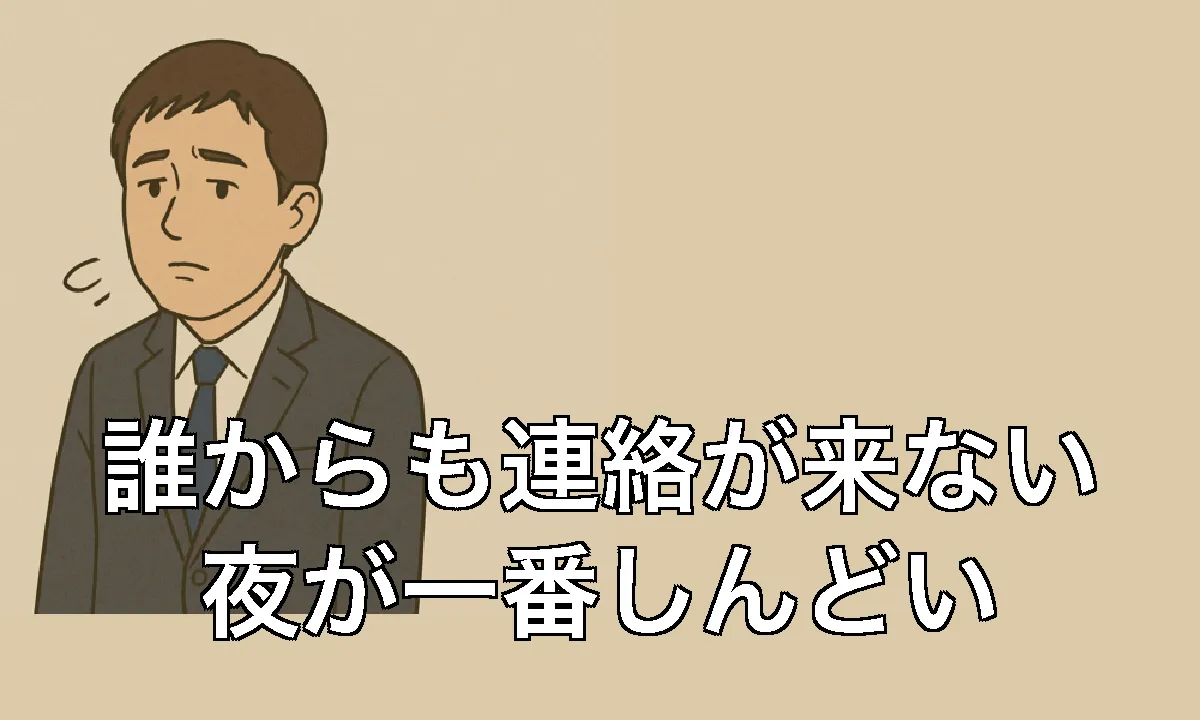鳴らないスマホと静まり返った事務所
一日の業務を終えて事務所に一人残る時間、ふとスマホを見る。通知はゼロ。電話もメールもLINEも来ない。静まり返った空間に、自分の存在が薄れていくような気がする。昼間は依頼人と電話で話したり、役所に書類を出しに行ったりして、それなりに「人と関わっている」実感がある。でも夜になると、一気にその温度が下がる。独身で、家に帰っても誰かが待っているわけでもなく、連絡をくれる人もいない。たったそれだけのことなのに、「なんか寂しいな」と思ってしまう。
通知ゼロの夜が増えてきた
昔はもっと頻繁に連絡があった気がする。大学時代の野球部の仲間や、同期の司法書士とのやり取り、そしてかつての彼女からのLINE。今はそれがほぼゼロになった。誰かが自分のことを思い出してくれるだけで、どれほど気持ちが軽くなるかを、通知がない夜に痛感する。歳を重ねるごとに、自然と連絡が減っていくのは仕方ない。でも、あまりにも減りすぎると、自分が透明になっていくような感覚に襲われる。
忙しさの中でふと訪れる静寂の恐怖
日中はバタバタと業務に追われていて、孤独なんて感じている暇もない。でも、ふと仕事が一段落した瞬間、静寂が訪れる。その静けさが怖い。誰からも必要とされていないんじゃないか。仕事以外の自分って、いったい何なんだろう。そういうことを考え出すと、思考が止まらなくなる。だからこそ、休みの日でもつい何かしらの仕事をしてしまう。考える時間を与えてしまうと、気持ちが沈んでしまうから。
賑やかさが懐かしくなる瞬間
ふと、昔の居酒屋の賑やかな声や、夜に電話で他愛もない話をしていた日々が思い出される。あの頃は、連絡があることが当たり前だった。今はそれが特別になってしまった。通知音ひとつで嬉しくなる。そんな自分が少し情けないけれど、それが今の現実だ。事務所で一人、パソコンの電源を落とすとき、もう少し誰かと話していたかったな、と胸のどこかがぽっかり空く。
誰にも求められていない気がする夜
「今日も誰からも連絡なかったな」と思いながら家に帰る夜、まるで自分がこの世から忘れられた存在なんじゃないかとさえ思えてくる。仕事の上では必要とされている。でも、それは「肩書き」が求められているのであって、「自分」という存在そのものが求められているわけじゃない。そう考えると、どこか空しくなる。名前ではなく、「先生」としか呼ばれない世界に、僕は少しずつ飲み込まれている。
「あの人も忘れてるだろうな」と思ってしまう
かつて親しかった人の顔がふと浮かぶ。あの人、今どうしてるだろう。でも連絡はしない。向こうも忘れているだろうと思うし、こちらもあえて思い出に触れたくない。それでも、頭の片隅で「連絡来ないかな」なんて期待してしまう自分がいる。待ってばかりの夜は、ひたすら時間が遅い。そして朝が来ても何も変わらない。誰とも繋がっていないという感覚は、思っている以上に心をすり減らす。
仕事はあるのに心が満たされない
司法書士の仕事は、決してヒマではない。むしろ、毎日バタバタしている。でも、どれだけ案件をこなしても、どこか満たされない感覚が残る。感謝されることもあるし、必要とされている実感もある。それでも、心の奥底にある「誰かとちゃんと繋がっていたい」という欲求は、仕事だけでは埋められない。結局、自分の名前で誰かに連絡してもらえることが、こんなにも嬉しいとは思っていなかった。
このまま老いていくのかという不安
もう45歳。このまま誰にも求められず、ひとり事務所で働き、静かな夜を過ごし続けて、気づいたら定年を迎えているのかと思うと、ぞっとする。昔は「独身貴族」と冗談めかして言えたけど、今はただの「孤独中年」だ。友人たちは家庭を持ち、子どもと旅行に行ったりしている。自分はというと、誰にも気づかれないうちに人生の夕方を迎えているような気がしてならない。
司法書士という仕事の「孤独」
司法書士の仕事は、ある意味で人と深く関わる仕事でもあるけれど、それはあくまで「業務」としての関わりでしかない。依頼が終われば、その人と連絡を取ることもない。何十人とやり取りしているのに、心に残っているのはほんの数人。逆に、こちらのことを覚えてくれている人がどれだけいるだろう。仕事のための人間関係が、気づけば自分の世界の全てになってしまっている気がする。
お客様とのやりとりは一時的
登記手続きや相続相談が終われば、お客様との関係もそこで一区切りになる。「また何かあればお願いします」と言ってくれる人もいるけれど、次に連絡があるのは数年後か、あるいはもう一生来ないかもしれない。そういう関係性が続く仕事だからこそ、気を抜くと自分が孤立していることに気づく。毎日人と話しているのに、誰にも本音を話していない。そんな不思議な感覚に襲われる夜がある。
誰かに頼られても心は埋まらない
業務上「頼られている」ことは多い。書類のことなら何でも聞かれるし、時には人生相談のような話までされる。でも、そこには距離がある。その人が僕の存在そのものを求めているわけじゃない。書類の専門家として、信頼されているだけ。それは嬉しいけれど、虚しさもある。人と人として、誰かに必要とされたい。そう思ってしまうのは、我儘なんだろうか。
信頼と孤独はセットなのかもしれない
信頼される仕事をしているはずなのに、孤独感は増していく。真面目に、誠実に仕事をしているつもりでも、そのぶん自分のことを話す機会は減っていく。相手にとって「安心できる存在」にはなれても、「近づきたくなる存在」にはなれていないのかもしれない。だからこそ、どこか遠くにいるような存在になってしまう。そしてまた、誰からも連絡が来ない夜が、静かに訪れる。
気づけばスマホを何度も見てしまう
机に置いたスマホを、何度も何度も確認してしまう自分がいる。通知が来ていないことは分かっているのに、つい見てしまう。そして、画面の明かりだけがやけに眩しく感じる。誰かの存在を感じたくて、SNSを開いても、ますます孤独になるだけだ。それならもう、見なければいいのに。けれど、やっぱり見てしまう。誰かからの小さなサインを、必死に探しているのかもしれない。
通知が来ないことに慣れたくない自分
通知がないのが当たり前になってしまうと、もう何も感じなくなる気がして、それが怖い。寂しさに慣れてしまうと、もう誰かを求めることすらやめてしまうのではないか。だから、まだ期待している。通知音ひとつで心が軽くなる自分がいる限り、まだ誰かとの繋がりを信じたい。誰にも連絡しないくせに、連絡を待っている自分が情けない。でも、それが人間なのかもしれない。
「お疲れさま」の一言が欲しい夜
ただ「今日もお疲れさま」と言ってくれるだけで、救われる夜がある。別に長い話がしたいわけじゃない。ただ、自分の存在を認識してくれる誰かがいることを感じたい。それだけで明日も頑張ろうと思えるのに、その一言をもらえる日は少ない。だからこそ、誰かに「お疲れさま」と言うようにはしている。誰かの夜を少しでも軽くできたら、自分の夜も少しは軽くなる気がする。
だからこそ人に優しくなれるという言い訳
連絡が来ない夜はつらい。でも、そういう経験があるからこそ、人の気持ちに敏感になれる気がする。誰かの寂しさに気づけるのは、自分がその痛みを知っているから。そう思えば、連絡が来ない夜にも意味があるのかもしれない。…なんて、自分を納得させる言い訳を並べながら、今夜もまたスマホをチラ見して、ため息をひとつ吐く。いつか誰かからの通知が鳴ることを願いながら。