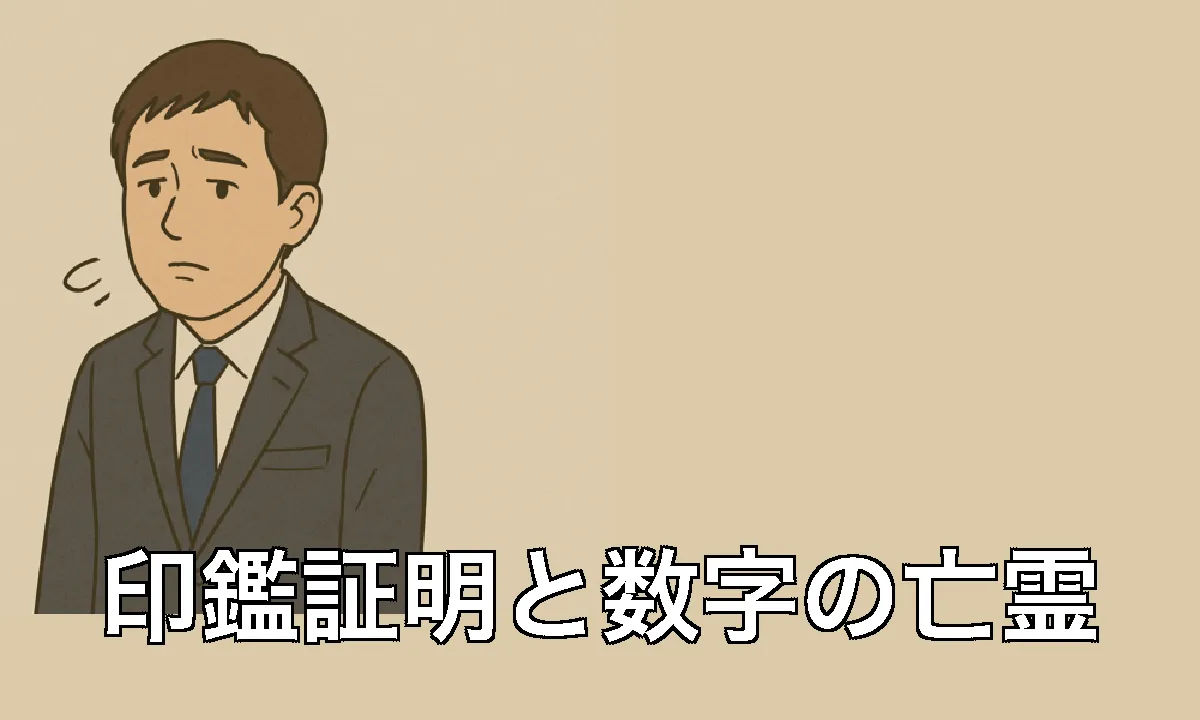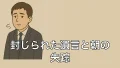見知らぬ依頼者と一通の封筒
朝の事務所に届いた封書
月曜の朝。サトウさんが淹れてくれたコーヒーを片手に、ぼんやりと机に広げた郵便物を眺めていた。封筒のひとつに見慣れない筆跡と、差出人不明の表記。宛名は確かに「司法書士シンドウ様」だったが、差出人名はどこにも書かれていない。 封を開けると、入っていたのは一枚の印鑑証明書のコピーと簡素なメモ。「この番号を追ってください。」たったそれだけの文言が、妙に気味悪く胸に残った。
名前だけで来所した男の正体
その日の午後、男が訪ねてきた。身なりはきちんとしていたが、身分証も出さず「この証明書について調べてほしい」とだけ言った。不審に思ったサトウさんがすぐに「具体的に、どういうご依頼でしょうか」と詰め寄る。 男は少し怯えたように「これは、亡くなった父のものです」と言った。しかし名前は印鑑証明のものと一致せず、そこからこの物語は、少しずつ動き出した。
書類に記された一つの番号
印鑑証明のコピーと違和感
最初に目についたのは、証明書の右上にある番号の桁数だった。通常より一つ多い。まるで改竄されたか、異なる制度下のものであるかのように思える。だがそんなはずはない。 「これ、いつ発行されたかご存知ですか?」と問いかけると、男は黙った。サトウさんが静かに資料を開き、過去の印鑑証明番号の体系について調査を始めた。
サトウさんの鋭い視線
「この番号、おかしいですね。平成15年のものとしては新しすぎる」とサトウさんが呟いた。彼女の視線はすでに印影の不自然さにも注目していた。 コピーの裏には薄く別の印影が写っている。二重写し? いや、スキャナーの癖ではなさそうだ。何か、誰かが隠している。
登記済証の行方
急がされる売買契約
男は「急いでいる」と何度も繰り返した。不動産の売買契約が迫っているというのだ。しかし、登記済証の提示もなければ、所有権移転の正当な理由も乏しい。 何より、印鑑証明に記された住所は現在の住民票とも一致していない。シンドウの脳裏に、「これはただのうっかりでは済まされないな」という警鐘が鳴った。
謄本に残る不自然な履歴
オンラインで謄本を確認すると、直近の所有者は確かに依頼者の父の名義。しかし、その前後の登記原因がやけに簡素で、付属書類の保存が確認できない。 「登記官のクセですね。これ、当時よく見た手抜きです」とシンドウはボヤいたが、それは単なる過去のことでは済まされなかった。
印鑑証明番号の持つ意味
登録年月と番号の法則
印鑑証明番号には、実は規則性がある。サトウさんが示した資料では、番号の一部が発行年度と市区町村コードに対応しているとされていた。 「これ、発行元が一致していません。番号はA市のもの、でも証明書にはB市の印」と彼女は静かに断定した。その瞬間、男の顔色が明らかに変わった。
誰が本当の所有者か
父親の名義が偽造された可能性が浮上する。いや、あるいは父親自体が書類の上だけの人物かもしれない。古い登記簿からは、途中で名義が空白になっていた期間さえ見つかった。 「つまり、これは“数字の亡霊”に踊らされてるってわけか……」と、シンドウは自嘲気味に呟いた。
サザエさん症候群と僕の週明け
シンドウのうっかりが導いた気づき
サザエさんを見た後に襲ってくる日曜夜の憂鬱。月曜の朝にふと「あの番号、見覚えがある」と思い出したのは、古い顧客リストだった。 そこには過去に依頼を断った人物の名前と、ほぼ一致する番号が記録されていた。つまり、これはリサイクルされた番号だったのだ。
サトウさんの静かな叱責
「……最初からちゃんと見ていれば、もっと早く気づけましたよね」とサトウさん。塩対応にもほどがあるが、的確すぎてぐうの音も出ない。 やれやれ、、、まるで波平さんに説教されるカツオのような気分だ。
裏書きに隠された過去
旧住所と過去の名義人
旧住所の登記簿を取り寄せたところ、なんと依頼者の名字が、かつての所有者とも一致した。遠縁の相続か、意図的な名義貸しか。 「この家系図、少し調べさせてもらいます」とサトウさんが申し出た。彼女の言葉には確信があり、僕はそれに従うしかなかった。
昔の登記のクセが手がかりに
最終的な鍵は、20年前の登記簿にあった。筆跡の癖、押印の位置、そして用紙の経年劣化の具合が一致しなかった。つまり、証明書は“今風”の偽造だったのだ。 古い司法書士のクセを逆手に取った犯行。だが、シンドウはかつてその時代に紙を扱ってきた男だった。
指印と証明書のズレ
なぜか合わない筆跡
父親の遺言として提示された書面の筆跡も、鑑定の結果一致しなかった。しかも押印の力加減が違いすぎる。 プロはそんなところも見る。いや、見るべきだったのだ。
印影の複製技術の落とし穴
よくある印影複製アプリが用いられていた形跡もあった。だがスキャナーでの変形を見逃さなかったサトウさんの観察眼が突破口を開いた。 印鑑は確かに力を持つが、悪意と組めば法を欺く刃にもなる。
やれやれで辿り着いた真実
本人になりすました意外な人物
結局、依頼者の男は他人の不動産を自分の父親になりすまして売却しようとしていた。だが、その父親は実在せず、虚構の存在だった。 番号に隠された真実が、亡霊のように浮かび上がったのだ。
小さな番号が語った大きな嘘
印鑑証明番号ひとつで人は信用する。だが、番号は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつだって人間の方だ。 やれやれ、、、またしても数字に踊らされたか。だが、それが司法書士の宿命というものだろう。
司法書士としての決断
通報か、説得か、沈黙か
依頼者の男には不動産業者との接触を断ち、警察に自首するよう促した。詐欺未遂で済むうちに、と。 シンドウが通報するか迷ったのは、どこかにわずかでも“善意の過ち”があったのではと感じたからだ。
シンドウの選んだ道
結局、通報はしなかった。だが、記録は残した。次に同じ番号が現れたときには、ためらわず通報する。そう決めた。 僕は善人ではないが、かといって完全に冷たくもなれない。
静かな午後と二人の会話
コーヒーと報告書
事件が一段落した午後。いつものようにサトウさんがコーヒーを淹れてくれた。香りだけは、相変わらず高級喫茶店レベルだ。 「報告書、まとめておきます」と彼女は言った。さすがだ。
サトウさんの少しだけ柔らかい声
「……でも、最後はちゃんと活躍しましたね、先生」 その一言に、心なしか肩の荷が下りた気がした。やれやれ、、、まだもう少し、やっていけそうだ。