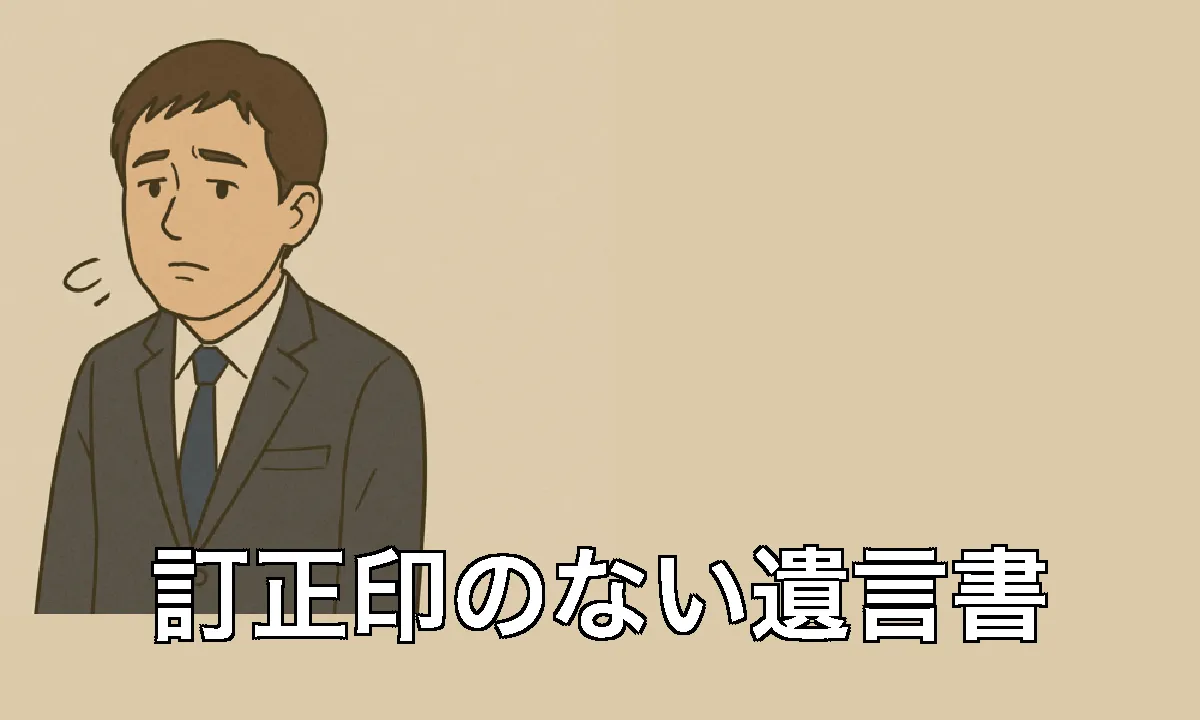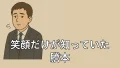午前九時の依頼人
古びた封筒と震える手
「この遺言書、正式なものだと思うんですけど……」
細く震える指が差し出したのは、黄ばんだ封筒。表には達筆な字で「遺言」とだけ書かれていた。
目の前の男は、喪服姿のまま、私の机の前で所在なげに目を伏せていた。
遺言書に足りないもの
遺言自体は公正証書でもなく、自筆の形式だった。本文はぎこちないが、内容には問題ない。
ただ、一ヶ所だけ訂正されていた。その訂正箇所に、訂正印が、ない。
その一点を指摘すると、男は顔を真っ青にし、「兄が書いたんです」と口を滑らせた。
訂正印を拒む理由
「これは父の字じゃない」
「この字、父のじゃありません。見ればわかります」
依頼人の妹だという女性がやってきて、封筒を見るなり言い放った。
言葉には迷いがなかったが、根拠は感情に近かった。
筆跡鑑定か心の問題か
私は筆跡鑑定の専門家ではないが、疑義があれば家庭裁判所も動くことがある。
訂正印がなければ、有効性は危うい。だが、それ以上に家族の間にある見えない亀裂が気になった。
まるで「サザエさん」の波平の遺産をめぐってカツオとマスオが争ってるような、妙な緊張感が事務所に漂っていた。
サトウさんの冷たい視線
塩対応の背後にある鋭さ
「それ、印鑑登録の印影と違いますね」
背後から聞こえた声に私はハッとする。サトウさんだ。
いつもながら、鋭すぎる。冷たい視線をよそに、私は資料を確認し直した。
チェックリストに現れた違和感
私の作った「遺言書確認リスト」には、筆跡不一致、訂正印の不在、封筒の違和感と三つのチェックがついた。
決して偶然とは言い切れない。
そのとき、封筒の裏から、もう一枚の紙が滑り落ちた。
家庭裁判所の記録を追え
戸籍謄本と過去の養子縁組
封筒に入っていたのは、昭和52年の戸籍謄本の写しだった。
そこには「養子縁組」の記載。依頼人の兄が、実は父の実子ではなかったことが示されていた。
「やれやれ、、、また家族の話か」と、私は頭をかいた。
封印された兄弟の存在
サトウさんが「養子縁組が無効になってますね」と指摘した。
過去に一度破棄され、後に再縁組された履歴もある。何があったのか。
血の繋がりと法的な繋がり、その狭間に今回の遺言が引っかかっているのだった。
元野球部の勘が働く
クセ球とクセ字の共通点
「クセって、フォームに出るんですよね」
私はかつてのキャッチャーの勘を思い出していた。筆跡も、どこか似たクセがある。
一つの文字を見つめ、私は確信に変わった。「この“之”の書き方、間違いないな」。
「やれやれ、、、またか」
「またこのパターンか……やれやれ、、、」
遺言書の訂正箇所は、兄ではなく、依頼人本人が書いたと見て間違いない。
故人の字と称するには、不自然な滑らかさがそこにあった。
最後の一筆が語る真実
遺言書の空白欄と偽りの訂正
訂正印が押せないのではなく、押せなかったのだ。
なぜなら、その訂正は偽造だった。父はすでに亡くなっており、訂正などできるはずもなかった。
空白のままにされた訂正は、まさに罪の証だった。
訂正印を押せなかった関係
押せないのは印だけじゃない。家族との絆もまた、修正できなかったのだ。
法的な争い以前に、人として信頼を壊してしまった結果がここにある。
サトウさんがそっとファイルを閉じた。「これは裁判所行きですね」。
告白と解放
依頼人の涙と兄の手紙
「兄さんが書いた手紙、読んでませんでした……」
依頼人の目には涙が浮かんでいた。そこには、謝罪と感謝が綴られていた。
印ではなく、言葉で遺した真実が、そこにあった。
誰が許しを必要としていたのか
許してほしかったのは、依頼人のほうだったのかもしれない。
偽造に手を染めたこと、それ以上に兄へのわだかまりを持ち続けた自分を。
その心の訂正には、印ではなく、涙が必要だった。
事務所に戻る日常
サトウさんの無言の褒め言葉
事務所に戻った私は、いつも通り椅子に深く座り込んだ。
サトウさんは黙ってお茶を淹れ、私の前に置いた。
その表情は変わらなかったが、どこか優しかった。
「次は印鑑を忘れないでくださいね」
私が認印を忘れて出かけようとすると、サトウさんが言った。
「次は印鑑を忘れないでくださいね。司法書士なんですから」
やれやれ、、、それはこっちのセリフだっての。
訂正印が教えてくれたこと
証明と信頼のあいだ
法は証明を求めるが、人は信頼を求める。
訂正印ひとつで崩れるものがある一方で、そこにある真実が救うこともある。
今回の件で、それを強く実感した。
人が押せない印の重み
人は皆、人生のどこかで訂正したい過去を持っている。
だが、それに印を押す勇気が持てるかどうかは別問題だ。
そして、その印の重みを知るのが、司法書士という仕事なのかもしれない。