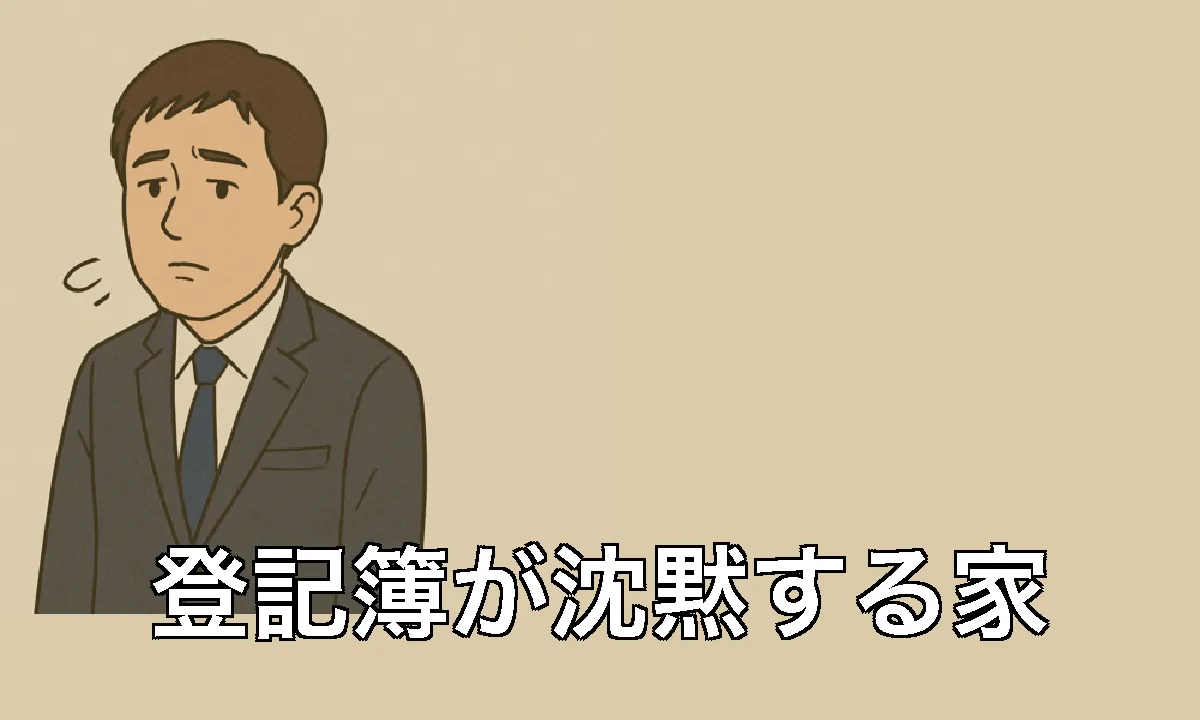依頼の朝
朝一番、事務所のドアが開いたとき、コーヒーに口をつけたばかりだった。入ってきたのは、黒いスーツを着た中年男性。どこか憔悴した顔つきで、手には一通の封筒を握りしめていた。
「空き家の登記について相談したい」と男は言った。場所は市内のはずれ、竹林の奥に佇む築60年の木造家屋だという。相続登記をしたいが、どうにも腑に落ちない点があるというのだ。
面倒な予感しかしないが、食えない仕事ではない。カレンダーに空きを見つけて、日を決めた。サトウさんの鋭い視線が刺さっていた。
不機嫌なサトウさん
「またですか」とサトウさんが言った。表情は相変わらずの塩対応。だが手元のPCでは既にその住所の登記情報を検索していた。
「この名義、相続されてないままですよ。平成三年に亡くなったって記録ありますけど、以降手付かずです」
淡々としながらも、要点をきっちり押さえてくるのが彼女らしい。気分屋の自分とは対照的だった。
謎の依頼人と空き家の話
依頼人の名前は多田誠一。彼の話によると、家は叔父のもので、自分が唯一の相続人だという。だが、なぜか地域では「誰にも相続されていない幽霊屋敷」として有名になっているという。
「気味が悪いんです。誰かが夜な夜な入っていくという噂もある。なのに警察も取り合ってくれなくて…」
そんなオカルトっぽい話には関わりたくなかったが、ここまで聞いてしまうと職業柄無視できない。やれやれ、、、嫌な予感しかしない。
登記簿の違和感
確認した登記簿には、確かに多田誠一の叔父である「多田重蔵」の名前が記されていた。だが不思議なことに、抵当権や仮登記の痕跡も一切ない。
まるで誰にも関心を持たれなかった土地。逆に不自然なほどに清廉な記録だった。
「こんなに空白な履歴、逆に怪しいですね」とサトウさんが漏らす。確かにその通りだ。
名義変更が語る過去
唯一の動きは、昭和53年に名義を「重蔵」に変更した際の所有権移転だけだった。売買によるものだったが、売主の名前が微妙に読みづらい。
「この文字、旧字体じゃないですか?電子化の際に誤記されてる可能性あります」
つまり、現物の紙の登記簿を閲覧しないと正確な情報が掴めない。また法務局行きか、、、
消えた共有者の影
サトウさんが、紙の登記簿から気になる名前を発見した。「昭和48年時点では共有名義でしたよ。この“笹山”って人、いつの間にか消えてます」
その後の名義変更にその記載はなかった。つまり誰かが故意に削除した可能性もある。
共有名義が片方だけに移るには、売買や贈与、相続などの原因が必要だ。記録がなければ違法。これは怪しい。
近隣住民の証言
現地に赴いたのは、曇天の金曜日。周囲には人家も少なく、草が伸び放題だった。
隣の家の老婆が声をかけてきた。「あそこはねえ、昔から“夜に人が入る家”って有名でねえ」
どうやら、この地域ではちょっとした都市伝説のような扱いを受けているらしい。
鍵が開いていた夜のこと
老婆は続けた。「去年の秋ごろかねぇ。深夜2時に若い人が懐中電灯持って入っていくの見たよ」
「警察に連絡したけど、空き家だからって取り合ってくれなくてねぇ」
誰かが不法に立ち入っていた形跡がある。もしそれが遺産や登記に関係する何かを探していたとしたら、、、
老女の言い残した一言
「昔の持ち主ね、親戚に揉め事があったらしいよ。あの笹山って人、急にいなくなったんだって」
まるで伏線のように老婆は言った。笹山、共有名義人だった人物。何が起きたのか。
私の中で、怪盗キッドのように一枚の絵が浮かび始める。不自然な登記。消えた人物。そして誰かが家を狙っている。
現地調査と発見
家の中は埃まみれだったが、何者かが最近入った形跡があった。床板の一部が不自然に緩んでいる。
工具でこじ開けると、小さな木箱が出てきた。中には古い登記簿の写しと、1枚の手紙。
「この家の真の所有者は笹山健吾である」と書かれていた。署名と拇印付き。日付は昭和55年。
ひとつだけ外された表札
玄関の外にある表札跡。重蔵の表札だけが残っていた。だが、もう一つの跡がうっすら見える。
サトウさんがスマホで照らすと、「笹山」の文字がかすかに読めた。
表札を外し、記録を消した。それで“消えた共有者”が完成したわけだ。
サトウさんの推理
事務所に戻ると、サトウさんはすぐに調査に入った。法務局の閉鎖登記簿、戸籍、旧名義人の親族関係図。
「この“多田重蔵”、実は笹山健吾の従兄弟だったみたいです」
つまり、身内による不正な所有権の取得。昭和の闇が令和に浮上した。
消えた名義人の真意
「もしかしたら、笹山さんは騙されて名義を移したんじゃないですかね」とサトウさん。
確かに手紙の文面には、不安や不信の言葉が多く、重蔵への疑念がにじんでいた。
もしかしたら彼はそれを訴えようとしたが、力及ばず埋もれてしまったのかもしれない。
登記と現実の矛盾点
登記は正しいように見えて、実はその裏に多数の闇があることもある。今回がまさにそれだ。
合法であっても道義的に問題のあるケース。私たち司法書士が見過ごしてはいけない部分だった。
サザエさんのように平和な日常の裏に、波平さんが隠していた魚の骨のような真実があった。
真相への道筋
我々は旧笹山家の親族に連絡を取った。彼の息子が今も市内に住んでいるという。
彼は涙ながらに父の手紙を受け取り、正式に相続の申し立てを行う意志を示した。
司法の場で、重蔵の行為が明るみに出る日は遠くないだろう。
二重売買の裏にいた男
調査の結果、重蔵は一度、誰かに売却しようとして失敗していた。その相手がまた怪しい人物で、今もその家に夜な夜な侵入していた可能性が高い。
つまり、家の秘密を知っていた者がもう一人いたということだ。偶然とは思えない。
昭和の未解決事件が、登記簿によって再び動き出した。
意外な犯人の動機
その人物は、不動産ブローカーだった。曰く、「一度逃した金のなる木は忘れられなかった」と。
人の家を“金のなる木”などと表現するその神経には、さすがの私も怒りがこみ上げた。
ただ、司法書士としては感情に流されず、冷静に手続きを進めるしかない。
司法書士としての決断
今回のように“記録”が嘘をつくとき、我々の役目は重い。事実を掘り起こし、正しく届け出る義務がある。
相続放棄の誤解、共有者の抹消、手紙という証拠。すべてを総合して申立書を整える。
「やれやれ、、、」と独り言を漏らしつつ、私は書類をプリンターに流した。
正義と手続の狭間で
何が正しいのか。法律と倫理のズレを感じたとき、我々はどこに立つべきか。
答えは出ない。だが少なくとも、誰かが見ている。その記録は、登記簿として残る。
その“沈黙”が、やがて真実を語り出すと信じて。
書類一枚の重み
たった一枚の書類が、誰かの人生を左右する。責任は、いつも重い。
今日もまた、静かにその重みと向き合う。それが私の仕事だ。
例え誰にも気づかれなくても、塩対応されようとも。
解決とその代償
家は無事、笹山家へと戻った。息子は取り壊して新しい家を建てると言った。
「父の名前が正しく記録された。それだけで十分です」と彼は微笑んだ。
登記簿は沈黙していたが、その沈黙こそが真実だったのかもしれない。
登記簿が語る沈黙の意味
それは、長年の誤解と罪の沈黙。だが、それを解いたのは紙の記録と手紙、そして人の意志だった。
書かれたものが語らぬとき、我々が代わりに語る。司法書士の矜持だ。
今日もまた、登記簿と向き合う日々が続く。
やれやれと思いながら
戻ってくると、サトウさんがひと言。「これで今週の予定、全部詰まりましたよ」
「ああ、やれやれ、、、」私は天井を見上げるしかなかった。
だが、少しだけ心が晴れていたのは、気のせいだろうか。