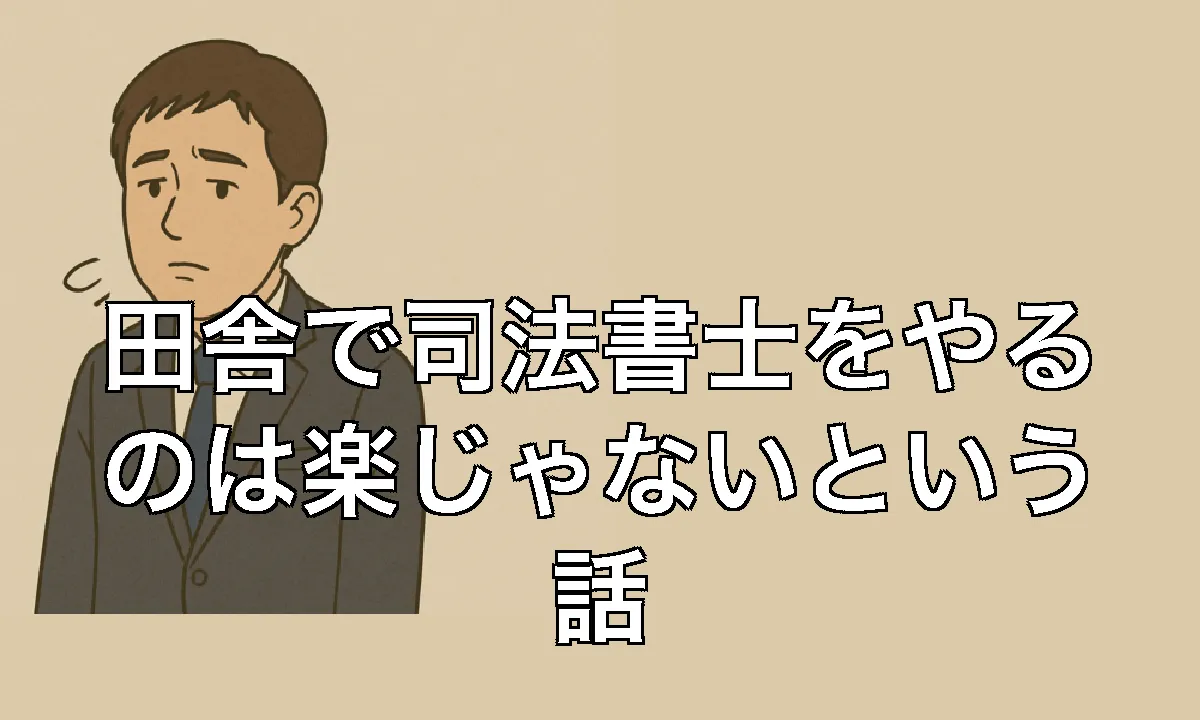田舎で司法書士をやるのは楽じゃないという話
田舎で司法書士をするという選択
「田舎なら人も少ないし、仕事もゆるくて楽そうだよね」なんて言葉を聞くたびに、胃がキリキリする。実際にやってみればわかるが、田舎で司法書士をやるのは決して楽な仕事ではない。むしろ、孤独で、過剰に期待され、誤解され、そして地味に追い込まれる。そのうえ、仕事が途切れる不安と、急に案件が集中するストレスとの間を、綱渡りのように歩かされる毎日だ。
のどかな風景に潜む緊張感
田舎に住んでいるというと、「自然に囲まれて、のんびり仕事ができるなんて羨ましいですね」と言われる。確かに、窓を開ければ田んぼ、通勤時に信号は一つもない。けれど、それは景色の話であって、仕事がのんびりしているわけではない。逆に、地域の数少ない法律専門職として、村の揉め事から個人の悩みまで全部相談される。軽トラが止まって、「○○さんが亡くなってなぁ…」と突然の相続話が始まることもある。
草刈りより厄介な人間関係の刈り込み
地域の人間関係は、草と同じで、放っておくとすぐに絡まる。ちょっとした言い回し一つで「感じが悪い」と陰で言われたり、誰かの味方をすれば敵を作る。依頼人同士が親戚だったり、過去に土地でもめた相手だったりするのは日常茶飯事で、対応を間違えると仕事どころではない。草刈りは機械がやってくれるが、人間関係の調整は誰も代わってくれない。
仕事が来ないと思ったら突然の集中砲火
ひと月まるまる電話が鳴らないこともある。暇だなと思っていたら、ある日突然、相続案件が5件重なったりする。特に法務局の締切前や、農繁期が終わった後は注意だ。皆一斉に「今のうちにやっとこう」となる。こちらとしてはパソコンとプリンタと一人の事務員だけが頼りで、ひたすら徹夜で処理する羽目になる。ゆるいどころか、命を削るような忙しさだ。
「楽そう」だなんて言われるたびに思うこと
地元の同級生から「いいよなー、独立して自由で」なんて言われるたび、思わず笑ってしまう。確かに自由だ。自由に稼げなくなるし、自由にクレームもくる。休みも、ボーナスも、誰かが与えてくれるわけじゃない。独立というのは、ある意味「全部自分で責任取る地獄」でもある。楽をしているように見えるときは、たいてい頭の中で何かしらのシミュレーションをしている。
暇じゃないのに暇に見られるジレンマ
事務所に人の出入りが少ないと、「あそこ、仕事ないんじゃない?」と噂される。実際には一人で5件も案件を抱えていて、内1件は不動産がらみで複雑極まりない。だけど、外からは見えない。田舎の人の噂の拡がりは、天気より早い。だからこそ、無理してでも笑顔でいないといけないときがある。
自営業の自由と不自由の境界線
好きな時間に仕事ができる、というのは確かに事実。でも実際は、相手の都合で時間が決まり、トラブルがあれば夜でも休日でも対応する。電話が鳴ったら出ないわけにはいかないし、「緊急なんですけど…」という言葉にNOとは言いにくい。自由とは名ばかりで、実際は「責任の重さ」が支配している。
孤独と忙しさと事務員のありがたみ
毎日一緒に仕事をしてくれている事務員がいる。それだけでも、うちは恵まれているほうだ。とはいえ、その一人が休んだだけで業務は一気に麻痺するし、何より話し相手がいなくなるのが痛い。忙しいのはもちろんつらいけど、孤独のほうがじわじわ効いてくる。
一人で抱えることの限界
忙しくなると、すべてを一人でやろうとしてしまう。でも、限界はすぐやってくる。登記のミス、日付の勘違い、書類の印刷ミス…。ミスをしたくてしているわけじゃないのに、「司法書士だからしっかりして当然」と見られる。だからこそ、信頼できる事務員の存在は本当に大きい。ひと声かけてくれるだけで救われる瞬間もある。
事務所というより体力勝負の現場
朝から法務局に走り、昼は相談者の家へ出向き、夕方は相続の書類作成、夜は電話対応と調査…。もはや事務所というより、体を動かし続ける現場だ。たまに「書類仕事だけでしょ?」と言われるが、それは表面だけを見ている。机に向かっていても、心と体は常にフル稼働状態だ。
たまの雑談が唯一の救い
疲れ切った夕方、事務員が「今日のお昼、パン屋の新作でしたよ」と話しかけてくれる。それだけで、何となく気がゆるむ。人と話すって、本当に大事なんだなと痛感する。独身のおっさんにとっては、職場の雑談が唯一の人間らしい時間だったりするのだ。
事務員の存在が命綱だった日
一度、事務員がインフルエンザで一週間休んだことがある。その間、登記3件、裁判所への提出書類2件、相談3件…。もう何も覚えていないほど大混乱だった。事務員が戻ってきたときは、涙が出そうになった。あのとき、「この人がいなければうちは終わる」と本気で思った。
辞められる恐怖との向き合い方
田舎では、代わりの人材を探すのが本当に難しい。しかも、司法書士事務所で働きたいという人はほとんどいない。だから、今いる人に辞められたら詰む。そう思うと、言いたいことも我慢する。お互いに気を遣いすぎて疲弊することもある。でも、それでも続けていくしかない。
気づけば自分がマネジメント下手
元野球部で後輩を引っ張っていた自分が、いまや一人の事務員に気を遣ってペコペコしている。時々ふと、「俺って、マネジメント向いてないんじゃないか」と落ち込む。でも、正解なんてない。人との関係に「これでいい」は存在しない。だから、失敗しながら、なんとか続けている。
それでも田舎でやっていく理由
田舎で司法書士をやるのは確かに大変だ。でも、それでも自分がここでやっていく理由はある。誰かに必要とされている実感、地域に貢献している感覚、そして、たまにふと感じる「ここにいてよかった」の瞬間。大変だけど、全否定できない不思議な魅力が、この仕事にはある。
都会に出なかった後悔と納得の狭間で
同級生の中には、都会の大手事務所でバリバリ稼いでいる人もいる。SNSで見るたびに、「あのとき東京に出ていれば…」と思わないわけじゃない。でも、こっちにはこっちの役割がある。たとえ小さな町でも、自分を頼ってくれる人がいる限り、それはやりがいになる。
地域に根差すことの重さとやりがい
地域の人に名前を覚えられるのは、良くも悪くも責任が重い。でも、その分、仕事を通して人の人生の節目に関われる。登記、相続、成年後見、すべてがその人の大切なタイミングだ。そのときに「○○先生に頼んでよかった」と言われると、苦労が報われる。
この場所で続けるために必要な覚悟
田舎で司法書士を続けるには、多少の孤独や誤解を受け止める覚悟がいる。愚痴を言っても、結局やるのは自分。文句を言いながらも、依頼に真摯に向き合う。それがこの仕事の本質だと思っている。今日もまた、電話が鳴る。「先生、ちょっといいですか?」—さて、また一日が始まる。