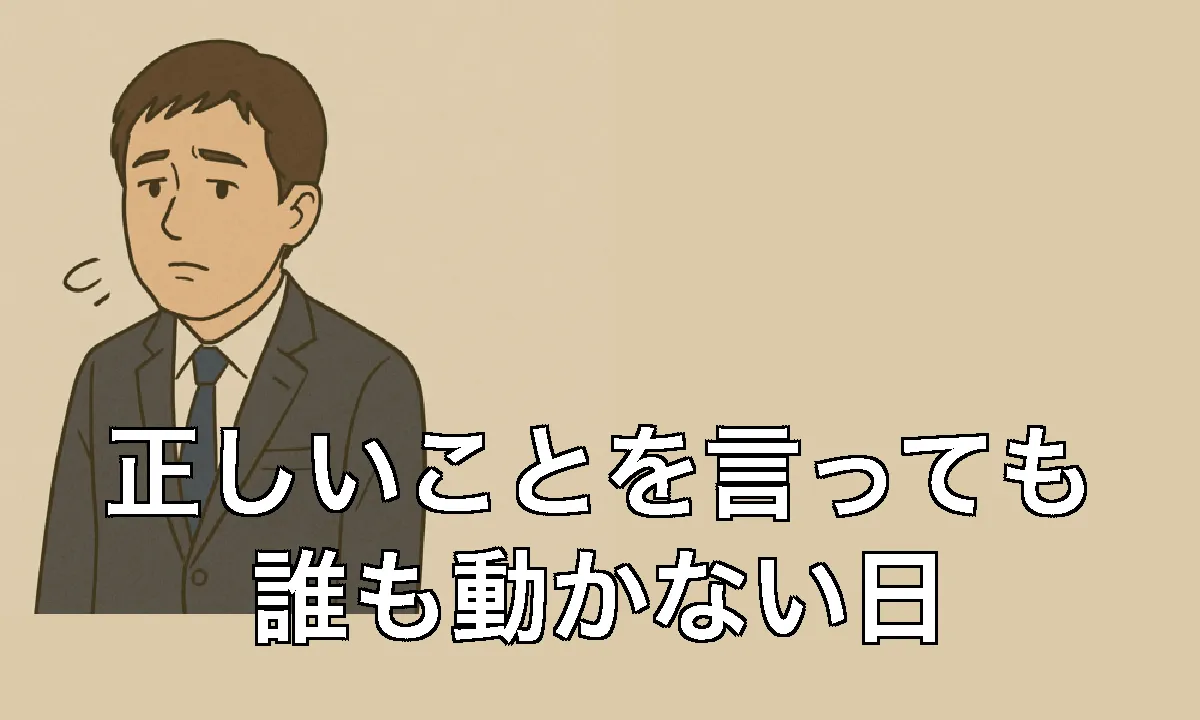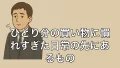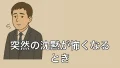誰も間違っていないのに前に進まない
ある日、相続の相談で親族が集まった場に立ち会った。誰もが自分の言い分を主張し、私は法律的に「正しい」提案をした。しかし、空気はどんより重たく、誰も返事をしない。全員が間違っていないけれど、誰も折れない。その場は無言のまま時間だけが過ぎていった。正しさは場を動かす力にならない。そんな瞬間があるのだ。
正論が通じない現場の空気
実務では、「法律上はこうです」と伝えた瞬間、ふっと空気が冷えることがある。相続や遺産分割の現場では特にそうだ。家族の関係性、長年の感情が交錯する中で、正論は時に「冷たい」と映る。昔、野球部でルールを守らない後輩に怒ったことがある。でも今は違う。正しさが人を遠ざける。そんな現実が司法書士の仕事にはある。
それが正しいのはわかるんですけどの壁
「それが正しいのはわかるんですけど……」という言葉に、どれほどの無力感を味わっただろう。こちらは全力で法律に基づいて考え、誠意を持って説明しているつもりだ。でも、相手はそれを受け取れない。心が動いていないからだ。正しさよりも納得できるか、感情に寄り添えているか。そこの溝が埋まらないと、話は一歩も進まない。
空気を読む司法書士の苦しさ
「言わない方が良いこともある」と、最近特に感じる。でもそれは逃げではないかという自問もある。空気を読みすぎて、本当に伝えるべきことを避けてしまう恐れがあるのだ。元野球部の感覚からすれば、「はっきり言わなきゃ伝わらない」が染みついている。でもこの仕事では、時に黙る勇気も必要で、そこがまた苦しい。
正しさよりも安心感が求められている
依頼者は正解を求めているように見えて、実は「安心」を求めていることが多い。法律に明るくない方にとって、正しさは逆に不安を呼ぶことがある。正しい説明だけでは心が動かない。求められているのは共感や温度感であり、それが信頼に繋がる。この矛盾に気づいてから、伝え方が変わった。
依頼者の納得とは何か
ある高齢の女性の依頼で、登記の内容を丁寧に説明したが、ずっと不安そうだった。私は書面を示しながら「これは法的に正しいです」と繰り返した。最後に彼女が言ったのは、「それで私はどうすればいいの?」だった。正しさより、行動の指針や安心感を求めていたのだ。以来、「正しいこと」と「納得」は違うのだと強く意識するようになった。
気持ちに寄り添うことと仕事の境界線
感情に寄り添いすぎて、法的な立場を曖昧にしてしまう危険もある。依頼者の気持ちを理解しようとするあまり、法律上できないことに同調してしまいそうになることがある。でも、そこは踏みとどまらなければならない。そのバランス感覚は、経験と失敗の中でしか磨けないのがまた厄介だ。
事務所でたったひとり正しさをかき集めて
独身で事務所にこもり、黙々と案件をこなす日々。事務員は一人いるが、法律判断は結局すべて自分の責任。誰に相談するでもなく、自分で「これが正しい」と決める。野球部時代のように、仲間と話し合って答えを出す環境はここにはない。正しさを一人で抱える日々は、正直しんどい。
孤独な判断誰も答えをくれない
「こういう場合、他の司法書士はどうしてるんだろう」そう思うことは多い。でも検索しても明確な答えは出てこないし、相談できる相手も少ない。結局、自分で調べて、自分で責任を取るしかない。その繰り返しに、精神的に疲弊することもある。でも、それがこの仕事の現実なのだ。
元野球部の俺にチームがいない
昔はキャッチボールの相手がいた。意見をぶつけ合い、ミスをカバーし合う仲間がいた。今は違う。書類を前に、ひとりで判断を下し、間違えればすべて自分の責任。正しさに自信を持つほど、間違った時のダメージが大きい。仲間のいない正しさは、時にただの重荷になる。
事務員さんとの温度差もまたリアル
うちの事務員さんはよく気が利くし助かっている。でも、やっぱり専門的な判断になると温度差を感じる。「これは急ぎじゃないですよね?」と言われた案件が、実は結構重たかったりする。こちらの緊張感はなかなか伝わらない。その差が積もると、孤独感が強くなる。
正しさを伝えるって意外と体力が要る
「これはこうなっていて…」と説明を始めると、事務員さんの目が徐々に遠くなるのがわかる。でも、それでも説明しなければならないのがこの仕事。相手の理解力に合わせて、例え話を交えて噛み砕いて説明する。正しさを“伝わる言葉”にする作業は、想像以上に体力を使う。
まあまあの落としどころを探す日々
「これが100点の正しさだけど、現実的には80点で着地しよう」そう考えることが増えた。完璧を目指すと、誰も納得しないことがある。妥協ではなく、落としどころを見つける力。それが司法書士に求められる“技術”なんだとようやくわかってきた。疲れるけど、そういう仕事だ。
それでも言わなきゃいけないことがある
正しさが伝わらなくても、伝えなければいけないことがある。それが専門職の責任だと思っている。嫌われても、空気が悪くなっても、言うべきことは言う。それが将来のトラブルを防ぐことにつながる。だから、今日も正しさを持って説明する。ただ、その言い方は常に工夫している。
伝え方を諦めないのが専門職
正しいことを正しく伝えるのは難しい。でも、諦めたらもうプロではない。言い方、順序、たとえ、間の取り方、全部工夫しながら、伝える。うまく伝わったときの「ああ、そういうことか」という表情を見るたびに、「ああ、やってよかったな」と少しだけ報われる。
誰かが正しさを拾ってくれると信じて
今日伝えた正しさが、明日誰かの心に残ってくれるかもしれない。そんな小さな希望を持っている。すぐには理解されなくても、時間が経てば「やっぱり先生の言った通りだった」と思ってもらえる日が来ると信じている。それが、孤独なこの仕事を続けていくための、ささやかな支えだ。
共感と実務のちょうどいいバランス
専門職としての立場と、人としての優しさ。そのバランスをどう保つかがいつも難しい。正しさ一辺倒では共感は得られない。でも、感情に流されすぎても危うい。だからこそ、日々揺れながら、迷いながらやっていくしかない。正しいことを言っても誰も動かない日。それでもやめられないのが、この仕事なんだと思う。
正しさの代わりに届ける温度
法的な正解ではなくても、「この人がそう言うなら大丈夫」と思ってもらえることがある。それは、声のトーンだったり、表情だったり、沈黙の使い方だったりする。正しさを超えた“温度”が、信頼を作っていく。そんな風に、言葉以外のものも届けられるようになりたいと、最近は思う。