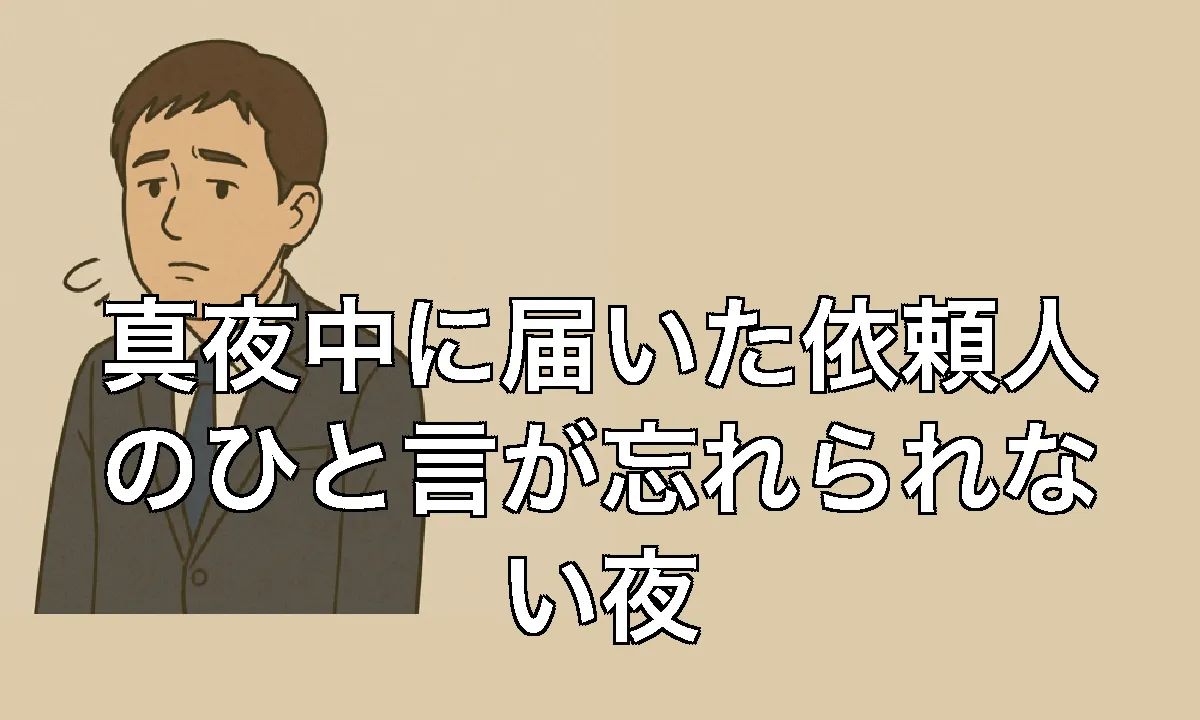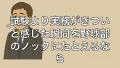眠れぬ夜に突然鳴ったスマホの通知音
司法書士をしていると、時間外の連絡も珍しくないが、それにしてもあの日の通知音は異質だった。夜中の0時ちょうど。LINEのポップアップには「今から話せませんか?」の文字。寝つけずに布団の中でぼんやりしていたところだったので、つい返信してしまった。こんな時間に業務対応なんて本来はすべきじゃない。けれど、あの文面ににじんだ切迫感に、無視できるほど冷たくもなれなかった。
常識の境界線は人によって違う
相手にとっては“今”が本当に限界のタイミングだったのかもしれない。私たちはどうしても、自分の常識を基準に物事を見てしまう。夜中の連絡なんて非常識だ、と思うのが普通だろう。でも、その人にとっては、昼間には相談する勇気が出なかったのかもしれない。だからこそ、夜中にようやく「助けてください」と言えるところまで気持ちが高まったのだろう。
真夜中の連絡に戸惑いながらも応じた理由
寝ていたわけではない。布団の中でモヤモヤと過ぎていく時間に嫌気がさして、スマホを手にしていたところだった。そこに依頼人からの一言。「先生、少しだけでいいので話を聞いてもらえませんか?」戸惑いながらも、Zoomのリンクを送り返した。仕事というより、もはや人間としての対応だったと思う。
本当に緊急なのか見極める難しさ
依頼人の「緊急」という感覚と、こちらの「緊急」の基準がズレていることはよくある。登記の期限が数日先でも、本人にとっては今日の不安が限界だったりする。だからといって、全てに応じていたら身がもたない。そうわかってはいても、声をかけられると、無視できずに応えてしまう自分がいる。これは優しさなのか、ただの断れない性格なのか。
Zoom相談を受けたその夜の記憶
Zoomの画面がつながった瞬間、相手の目元が少し赤いのがわかった。感情を押し殺していたのか、あるいは少し泣いていたのかもしれない。初めは「些細なことなんですが…」と遠慮がちに話していたが、次第に話は深くなっていった。内容は、相続登記の手続きが思うように進まず、兄弟間の関係も悪化しているというものだった。
画面越しに見えた依頼人の表情
夜の照明が顔を照らす中、依頼人の目は疲れ切っていた。何かを耐えているような、その場から逃げ出したいような、そんな表情。私は「これは大変ですね」と繰り返すことしかできなかった。法律的な解決は後日できる。でもそのとき彼女が求めていたのは、ただ話を聞いてくれる誰かだったのだと思う。
深夜だからこそ出る本音と涙
「昼間は気が張ってるから言えなかったんです」と依頼人は漏らした。夜という時間は、人を無防備にさせる。不安や孤独が膨れ上がるのも深夜だ。そんなときに“司法書士”という肩書きよりも、“ただの人”としての私が求められた気がした。なんだか昔の部活の後輩に泣きながら相談された時のことを思い出した。
話の本質は登記ではなかった
最初は「手続きのことを教えてほしい」という趣旨だったが、話の核心はまるで違っていた。家族との確執、兄弟間の嫉妬、父親の遺言をめぐる葛藤――話すうちに、登記の手続きは話題の一部でしかなくなっていった。結局、私は“話し相手”として、1時間以上、深夜の相談に付き合っていた。
結局、私は便利屋なのかもしれない
深夜相談が終わったあと、ベッドに戻っても眠れなかった。「なんで俺がここまでやるんだろう」そんな疑問が頭をよぎった。司法書士って、ここまで求められる職業だったっけ?お金のことより、精神的な疲れがどっと押し寄せてきた。
求められることが喜びである一方で
人から頼られるのは嬉しい。でも、それが当たり前になってくると、だんだん苦しくなってくる。断ることができない自分もまた、問題なのかもしれない。人の役に立ちたい気持ちと、自分を守りたい気持ちの間で、いつも揺れている。
断る勇気を持てないまま歳を重ねた
若い頃なら「今は時間外なので」と断れたかもしれない。でも今は、そう言う気力もなく、つい相手のペースに巻き込まれてしまう。結局、優しさというよりも、弱さかもしれない。野球部時代の“先輩命令には絶対従う”という体質が抜けていないのかも。
感謝されるけど空っぽになる感覚
相談が終わったあと、相手は「本当に助かりました」と言ってくれた。その言葉は確かに嬉しかった。でも、自分の中には何も残らなかった。ただ疲れて、空虚だった。これが“誰かのために動くこと”の代償なのかもしれない。
事務員にこの話をしたら呆れられた
翌日、出勤してきた事務員に軽く話したら、「先生、ほんとよくやりますね」と呆れたように笑われた。正直、その反応でちょっと救われた。誰かに「変ですよそれ」って言ってもらえるだけで、自分が少しまともな気がしてくる。
境界線を引くのが下手な自分
プライベートと仕事の線引きが苦手で、曖昧なままここまで来てしまった。特に地方だと、依頼人との距離が近い。スーパーで声をかけられたり、法事に呼ばれたり、もはや仕事の範囲がわからない。たぶん、これが限界なんだと思う。
ただの優しさでは仕事にならない現実
優しさだけでは、事務所は回らない。利益も出ないし、自分が壊れてしまう。本当はもっとシビアに対応すべきなんだろう。でも、それができないから、今日も夜中にスマホを枕元に置いてしまう。来るかもしれない誰かの「助けて」を、やっぱり無視できない。
真夜中に見えた司法書士のもう一つの顔
この仕事、ただの書類屋じゃない。人の人生や感情の、奥底に触れる瞬間がある。真夜中のZoom相談は、まさにそんな瞬間だった。疲れたけれど、逃げなかった自分を、少しだけ誇りに思う。
人間関係の疲労感は想像以上に深い
書類仕事より、人間関係に疲れる。気を使い、言葉を選び、相手の感情を推し量る。それを一日中繰り返すと、ぐったりするのも当然だ。どれだけ経験を積んでも、人間相手の仕事は慣れない。
お金では割り切れない相談の代償
今回の深夜相談、もちろん報酬は取っていない。そんなこと請求できる雰囲気じゃなかったし、仮に出しても向こうは払わないだろう。でも、だからといって「損した」とも思えない。ただ、こういう“代償”が積み重なっていくのは、正直しんどい。
誰にも頼れない人が最後に来る場所
司法書士って、意外と“最後の砦”になってる気がする。弁護士に行くほどじゃないけど、友達にも話せない。そんなグレーな悩みを抱えた人が、ふらっと来る。私は、そういう人たちの声を、画面越しに、窓口越しに、今日も聞いている。
それでもこの仕事を続けている理由
やめたいと思った夜もあった。でも、誰かの「助かりました」に救われて、ここまで続けてきた。元野球部の根性なのか、ただの意地なのか、もうわからない。ただ、「あなたがいてくれて良かった」と言われると、不思議とまた頑張れる。
思い出すのは一言の「助かりました」
いろんな言葉を聞くけど、心に残っているのは「助かりました」の一言だけ。それだけで、一週間は頑張れる。たった五文字の重みを、きっと他の職業の人にはなかなかわからないだろう。
野球部時代の泥臭さが今の支えになっている
練習中に泥まみれになっても、最後までやり切る。それが野球部時代に叩き込まれたことだった。今も、そんな泥臭い精神で仕事をしている気がする。スマートでも要領よくもないけど、不器用なりに、人と向き合っている。