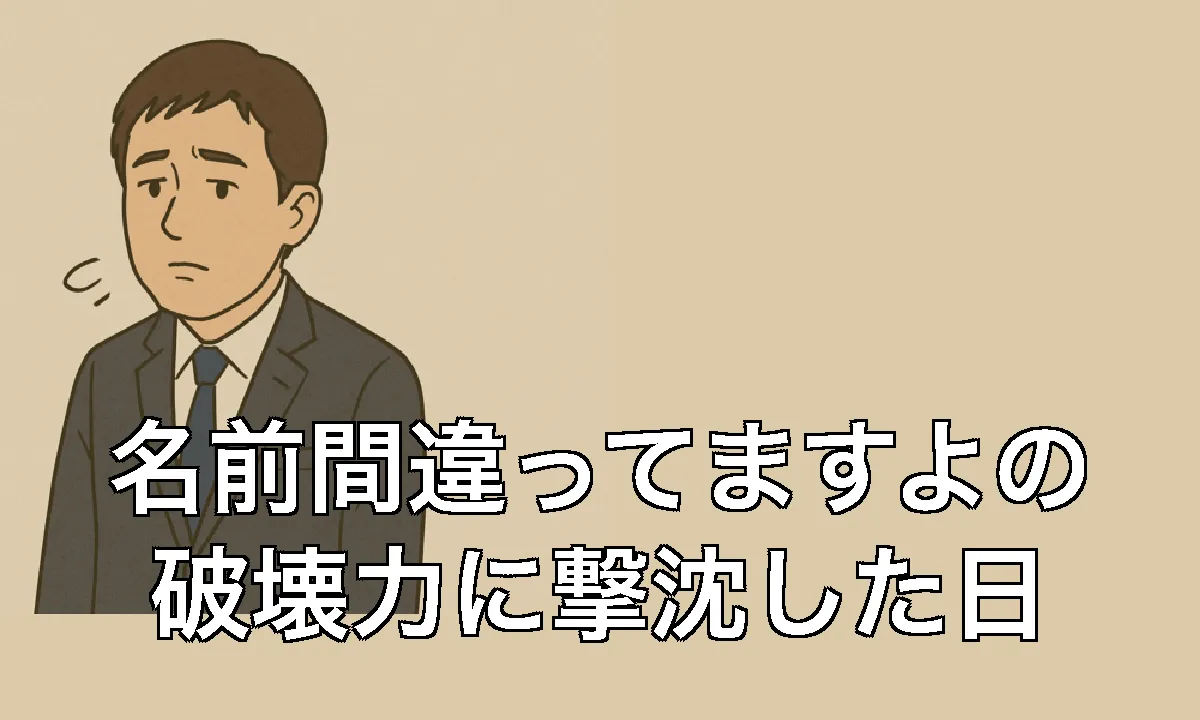朝一番の一言で心が折れる日もある
司法書士として毎日多くの人と接するなかで、意外とダメージが大きいのが「名前を間違えられる」ということだ。とくに朝イチ、頭がまだ回ってない状態で「◯◯さんですよね?」と、違う名前で声をかけられると、心のスイッチが一気にオフになる。そんなことで?と思う人もいるかもしれないが、自分の名前って、存在の根っこの部分だからこそ、それを間違われると、自分の存在が揺らぐような気がしてしまう。今日もまたその一言から始まった。朝9時の来所予約。相手は間違いなく初対面。なのに開口一番「稲垣さん、じゃなくて…えーと、伊藤さんですか?」。いや、違うんだけど。笑顔で訂正しつつ、心の中では「またか」とため息が漏れる。
その言葉が持つ地味な破壊力
「名前、間違ってますよ?」――この言葉自体をこちらから言う瞬間も、それを相手から浴びせられる瞬間も、地味に効く。どちらにしても場の空気が一瞬止まる。そのあと何事もなかったように話を続けることはできるけれど、心には小さなさざ波が残る。小さいこと、だけど無視できないこと。とくに自分の名前は、日々の名刺交換でも毎回確認されるものだから、繰り返されるたびに自己肯定感が少しずつ削れていく。元野球部のくせにメンタルが弱いんだよなあ、と自分でも思う。でも、そもそも「人と接する」という仕事をしていれば、ちょっとした一言がその日のテンションを左右するのは当たり前なのかもしれない。
名刺の字面だけで評価される怖さ
名刺を渡した瞬間、相手の目線が名前に止まる。そこで相手の顔が一瞬曇ったら、「あ、読み方が分からないな」とわかる。こちらから「いながきです」とすかさずフォローしても、相手はもう少しの間、漢字と発音のズレに意識を持っていかれている。そんなとき、仕事の話よりもまず自分の名前の説明から入ることになる。名刺という小さな紙片に詰まった、名前の難しさ。読み間違えられるたびに、ひとりの人間としてではなく“漢字の構造物”として見られている気がしてくる。
気づいてたけど言えなかったときの苦しみ
ときには、相手が間違ったまま会話を進めてくることもある。こちらも途中で訂正のタイミングを失ってしまい、30分、1時間と違う名前で呼ばれ続ける。あの時間の気まずさといったらない。「いま言うと気まずいかな」「最初に言えばよかった」と悶々とする。でも、終わってから訂正するのも変な空気になるし…と結局モヤモヤだけが残る。その日はどっと疲れてしまう。名前を正しく呼ばれるだけで、これほど気持ちよく仕事できるのに。
仕事以前に人として間違われる虚しさ
司法書士という職業は、信頼がすべてだ。にもかかわらず、名前を覚えられない、間違われるというのは、スタート地点にも立てていないような感覚になる。自分は一体この仕事でどれだけ信頼されてるんだろうか…そんな考えが頭をよぎる。相手に悪気がないのはわかってる。でも、悪気がないならなおさら根が深い。印象に残らない存在、記憶に残らない顔、そういう自分に気づかされてしまう。田舎の町で司法書士事務所を構えて十年以上。それでも名前を間違えられるというのは、どこかに自分の足跡が残っていないことを突きつけられるようで、ひどく虚しい。
名前すら覚えられない存在感の薄さ
イベントに呼ばれて挨拶しても、翌週にその人から「えっと…どこかでお会いしましたっけ?」と言われたときのショック。いや、先週あなたの隣で乾杯してましたけど?と心の中で突っ込む。そんなことはもう何度も経験してきた。司法書士は地味な仕事だ。誰かの人生の裏方であって、目立つことはない。それは覚悟していたけれど、それにしても“名前すら”覚えられないという現実は、思っていた以上にこたえる。自分はこの町に必要とされているのか?そんな問いがふと頭をよぎる。
それでも笑顔で訂正する自分が嫌になる
相手が名前を間違えても、こっちは笑顔で「いながきです」と訂正する。それが仕事だし、大人としての対応だ。でも心の中では、「またか」と小さなため息。どこかで「こんなことで落ち込んでる自分が情けない」とも思う。独身で、モテず、愚痴っぽくて、でもどこかで誰かに認められたい――そんな自分が、ただ「名前を正しく呼ばれたい」という小さな願いを抱えている。笑ってごまかす自分を客観的に見ると、ちょっと哀しい。でも、それでも笑顔を絶やさない自分を、少しだけ誇りに思いたくなる。
独立開業したのに自信が持てない現実
独立して10年以上経っても、自分に自信が持てない。司法書士という肩書きがあっても、結局は「名前も覚えてもらえない人」でしかないのでは?という思いが消えない。忙しい日々の中で結果も出してはいる。でも、それはただ仕事をこなしているだけ。認められているという実感が伴わない。ふとした瞬間に、自分が“地元に溶け込めていない感覚”に襲われる。名刺に書かれた文字ではなく、自分という人間が見てもらえているのか。不安になることばかりだ。
地方で名前が知られてないという壁
地方で開業していると「地元の人」というだけで信頼されることもあるが、自分のように外から来た人間には、最初からその恩恵はない。地元の名字でなければ、それだけでハードルがひとつ上がる。たとえば「佐藤さん」や「田中さん」なら覚えやすいが、「稲垣」という名前はこのあたりではあまり見ないらしい。だから、毎回毎回、初対面のたびに「初耳です」と言われるのが地味に効く。信頼以前に、まず名前を覚えてもらうのに時間がかかるのが辛い。
地域密着型なんて言葉が遠く感じる
「地域密着で信頼を築く」――そんな言葉を新人のころは信じていた。でも現実には、密着どころか、入り込む隙すらない感覚になることもある。地元出身であればそれだけで話が弾むのに、自分は自己紹介からハンデを背負っている気分になる。おまけに名前を間違えられると、その一歩すら踏み出せない。地域に根ざすって、どうやったらできるんだろう?自問するけれど、正直まだ答えは出ていない。
一人で背負う肩書きの重さに押し潰される
「司法書士事務所の代表」という肩書きは、他人から見れば立派に映るかもしれない。でも実際は、一人で事務所を回し、事務員を一人抱え、ミスも成功もすべて自分の責任。名前ひとつ間違えられても、それを笑って流す余裕すらない日もある。自分の存在の軽さと、肩書きの重さ。そのギャップに押しつぶされそうになる日が、実は一番しんどい。