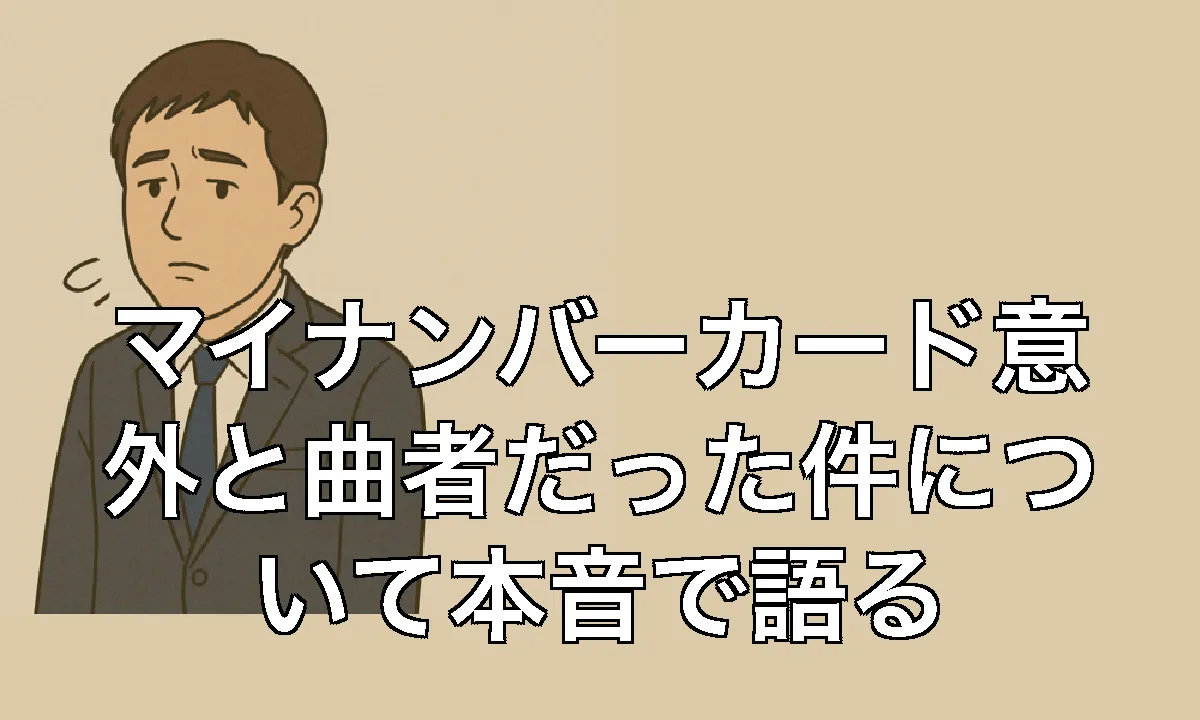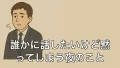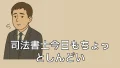最初は便利そうに見えたマイナンバーカード
マイナンバーカード、最初は正直ちょっと期待してましたよ。行政手続きがスムーズになるとか、本人確認がラクになるとか、うちのような小さな司法書士事務所でも恩恵があるんじゃないかと。でも、現実はそんなに甘くなかった。制度の理想と現場のギャップに、じわじわと疲弊していく日々。たまに思うんです、「これ、本当に便利になってるのか?」って。
導入当初は希望もあった
マイナンバーカードの導入が本格化したころ、うちでも「これで手続きが楽になるかも」と、事務員と少しだけ盛り上がったんです。手続きの一元化や、住民票の取得が簡単になるといった話を耳にして、正直ワクワクしていました。自分で言うのもなんですが、こう見えて効率化には興味があるんです。元野球部なもんで、無駄な動きは嫌いなんですよ。
行政の効率化に期待していたあの頃
あの頃は、「マイナンバーで全部つながるなら、いちいち役所に行かなくて済むじゃん!」って思ってました。登記に必要な住民票とか戸籍謄本なんかも、カードでパッと取れれば、依頼者さんの負担も減るし、こちらの手間も省ける。まさにWinWinじゃないかと。でも、そういう思い込みこそが、現実とのギャップを生む原因だったんです。
事務手続きも楽になると思っていた
事務員も「これからは紙の時代じゃないですよね!」なんて言ってたんです。たしかに、コンビニで住民票が取れるってのは一歩前進だったと思います。でも、実際にやってみると、「あれ?これ、むしろ手間増えてない?」って場面が多々。慣れてない人には説明が必要だし、カードの暗証番号を忘れてる人も多くて、進まないんですよ、話が。
実際に使ってみて見えてきた現実
制度の外側から見ているときにはわからなかったことが、実際の業務に落とし込んだときに浮き彫りになってきました。たとえば、マイナンバーの記載がある書類を扱う時の注意点や、本人確認での取り扱いルールなど、細かくて地味に厄介な点が多い。しかも、そのルールが役所ごとに違ってたりして、「結局どれが正しいの?」と混乱する始末です。
法務局との相性は思ったほどよくない
法務局での登記申請に使えるようになったとはいえ、実務的にはあまり活躍してません。結局、紙の証明書を要求されるケースが多くて、「じゃあマイナンバーカード何のためにあるの?」と疑問になる。特に地方の法務局はデジタル化に消極的で、カードを提示しても、受付の方に「紙でお願いします」と言われてガックリ。期待外れ感、すごいです。
トラブルの問い合わせが地味に増加
一番面倒なのが、依頼者さんからの「マイナンバーカードが使えると思ってたのに」というクレームに近い問い合わせ。例えば、銀行手続きや相続書類で「カードがあれば大丈夫ですよね?」と言われて、説明に30分かかるなんてザラ。誤解が広がってるのに、それを是正する仕組みが追いついてないのが一番の問題かもしれません。
現場ではむしろ余計な手間が増えている
便利になるどころか、余計な確認作業やトラブル対応で疲弊してる実感の方が強いんですよ。制度は整っていても、使う人も、受け取る側も、その制度をちゃんと理解してるとは限らない。その狭間で右往左往するのが、結局われわれ司法書士なんです。毎回、現場で調整して、時には謝って、ようやく仕事が進む。やれやれって感じですよ。
依頼人とのすれ違いの種になる
依頼人がマイナンバーカードの万能感を信じすぎているせいで、説明が面倒になることが多くなりました。こちらとしては「そのカードでは対応できません」としか言いようがないのですが、相手は「え?何のためのカードなの?」と不満げ。そうなると、ちょっとした不信感が生まれてしまうんですよね。こちらは制度の説明役じゃないんですけどね。
説明しても伝わらないこのモヤモヤ
正直なところ、カードの機能をひとつひとつ説明するのって、時間も気力も食うんです。しかも、相手が高齢の方だと、専門用語をかみ砕いて話さなきゃいけない。その間にも他の案件が山積みで、電話も鳴ってて、「何やってんだ俺」と思う瞬間もあります。言っても伝わらないって、精神的にけっこうダメージでかいんですよ。
カードがあるからこそ起きる混乱
昔は「戸籍謄本が必要です」と言えば済んでいたのに、今は「マイナンバーカードがあるんですが」と食い下がられる。便利ツールのはずが、むしろ混乱の火種になってるのってどうなんでしょう。制度の使い方をわかってないまま導入された結果がこれ。うちの事務員も「最近またマイナンバー関連の問い合わせが増えてますね…」とため息です。
事務員にも負担がじわじわ
うちの事務員は若いけど、最近は疲れた顔を見せることが増えてきました。「またマイナンバーですか…」とボソッと言われたとき、なんとも言えない気持ちになります。彼女の負担も少しずつ増えていて、精神的なストレスもあるようです。これじゃあ効率化どころか、現場の空気がどんよりしてくる一方。元も子もないですよね。
マイナンバー記載ミスの確認が地味に辛い
書類にマイナンバーを記載する場面も増えてきたんですが、1桁でも間違えると一大事。なので、事務員と一緒に何重にもチェックしてるんです。これが地味に時間を食う。しかも、番号が正しいかどうかを即座に照会できるわけじゃないので、「不備がありました」って言われた時の落胆ったらないですよ。こういう無駄、本当に減らしたいです。
システムエラーで二度手間三度手間
オンライン申請でマイナンバーカードを使うと、たまに謎のエラーが出ます。役所に問い合わせても「こちらでは原因不明です」と言われることもしばしば。結局、紙で出し直して、再度申請して、って完全に二度手間三度手間。「じゃあ最初から紙でよかったじゃん!」と叫びたくなることもしばしば。ほんと、誰か助けてって言いたくなります。
じゃあ結局どうすればいいのか
ここまで愚痴ばっかりでしたが、嘆いてばかりでも前に進めません。制度がある以上、それをどううまく使っていくかを考えるしかない。マイナンバーカードとの付き合い方を、こっちで工夫するしかないんです。文句はあるけど、放り出せないのが現場のリアル。だからこそ、せめてストレスを減らす方向に知恵を絞っていくのが今のテーマです。
制度に振り回されないために
完璧を求めると疲れるので、「これはこういうもんだ」とある程度割り切るようにしています。使える場面では使う、ダメなときは早めに紙に切り替える。この線引きを明確にしておくと、意外とストレスが減るんですよね。マイナンバーカードが悪いんじゃなくて、運用が中途半端なだけ。そう思うだけでも、少しは気が楽になります。
完璧を求めない付き合い方
理想を求めすぎると、現実に失望するだけ。だったら最初から「中途半端な制度」として受け入れておけば、多少の不具合も「まぁそんなもんか」と思えるんです。依頼者にも「使えると便利ですが、念のため従来の方法もご準備を」と一言添えるようにしています。先にハードルを下げておけば、後でトラブルになりにくいですから。
使うべき場面と避けたい場面
例えば住民票を急ぎで取りたいときには便利ですが、登記の本人確認では紙の証明書の方がスムーズなことが多い。そういう「向いてる場面」「向いてない場面」をこちらで把握しておくことが大事。マイナンバーカードを盲信せず、使い分けの感覚を持つ。これ、ほんと大事です。道具として割り切れば、無用な苛立ちも減ります。
愚痴って終わらせずに対策を考える
文句を言うのは簡単ですが、現場を預かる立場としては、それだけでは済まされません。少しでも業務をスムーズにするために、自分なりのルールや対処法を作っておくことが大切です。昔の野球部時代も、文句ばかり言ってるやつはレギュラーになれなかった。今思えば、あの経験が今の自分を支えてくれてる気がします。
自分なりのルールを作っておく
マイナンバーに関する問い合わせがあったら、最初に「カードが使えない場合も多いです」と伝える。手続きの案内文にも、補足説明をつける。そんな小さな工夫の積み重ねで、トラブルが減ってきました。完全に防げるわけじゃないけど、備えておくだけで、精神的な負担はだいぶ違います。やっぱり、準備って大事です。
相談者にも先回りして伝える工夫
最近では、初回相談の時点で「マイナンバーカードだけでは対応できないケースがあります」とあらかじめ伝えるようにしています。驚く方もいますが、大体の方は「そうなんですね」と納得してくれます。情報の先出しって、意外と効きます。忙しい中でも、先回りすることで、余計な説明やストレスを減らす。これ、だいぶラクになります。