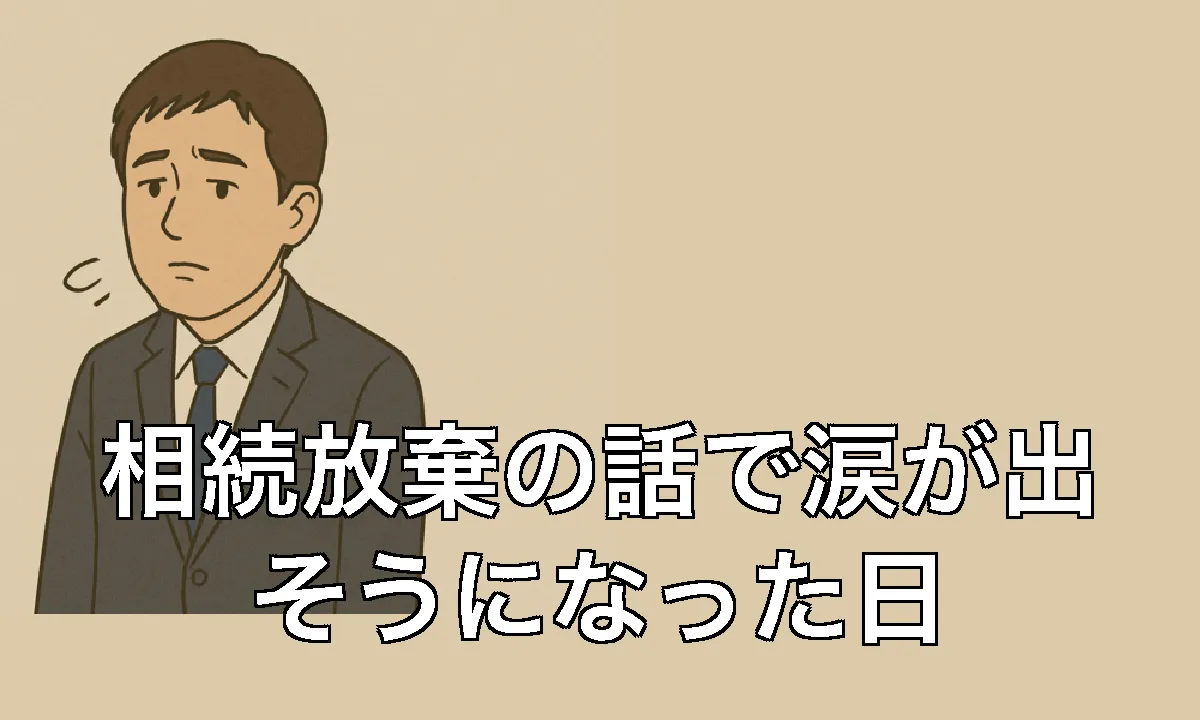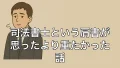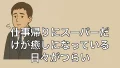相続放棄という言葉にざわつくとき
相続放棄という言葉を聞くたびに、私は少し胸の奥がざわつく。財産を放棄するという行為は、一見シンプルな手続きに思えるかもしれない。でも、その裏には家族の事情や感情が複雑に絡んでいる。誰かを嫌っての放棄もあれば、誰かを守るための放棄もある。ただ、それを説明する側にいる私の立場でも、時々その重みに言葉を失いそうになる。今日は、そんな「言葉にならない思い」があふれた一日だった。
依頼の電話で声が震えていた
午前中、事務所の固定電話が鳴った。最近はメールでの問い合わせが多くなったが、ときおりこうして直接電話が入ると、相手の緊張がそのまま伝わってくる。受話器の向こうから聞こえた女性の声は、明らかに震えていた。「相続放棄をしたいのですが……」と小さな声で切り出したその瞬間、ただの手続きでは終わらない案件だと直感した。内容を聞けば、亡くなった兄が抱えていた多額の借金。彼女はそれを背負うことに耐えられず、放棄を選ぶ決意をしたという。
たった一言で察することがある
司法書士として多くの相談を受けてきたが、「あ、これは感情の問題が大きいな」と気づく瞬間がある。電話の最初の一言、間の取り方、沈黙の長さ――そういう小さなサインから、依頼者がどんな気持ちでいるかを読み取るのもこの仕事の一部だ。声を張って話す人もいれば、途中で言葉に詰まる人もいる。今回の相談者は、まるで謝るように話していた。「こんなことをお願いしてすみません」と。いや、謝ることなんてない。それでも、そう言わずにはいられないくらい、彼女は心を痛めていたのだ。
この仕事は感情の受け皿だと思うことがある
「手続き代行業」なんて言われることもあるけれど、本当のところは感情の受け皿だと私は思っている。怒り、悲しみ、後悔、罪悪感。そういう感情が、相談者の言葉の中にはぎゅっと詰まっている。私たちはそれを受け止めて、法的な言葉に変換していく役割を担っている。けれど、感情を完全に無視することなんてできないし、してはいけないと思っている。だから時々、終わったあとにこっそりトイレで深呼吸をする。それでも、また次の人の声を聞く準備をする。それが、この仕事の日常だ。
「もう放棄するしかないですよね」と言われて
面談の日、彼女は資料をきれいにファイルにまとめて持ってきた。律儀な人なのだと思った。席に座るなり、「もう放棄するしかないですよね」と真っ先に口にした。その言葉の裏に、何度も悩み、眠れぬ夜を過ごしてきた様子が見えた。「できれば相続したくない。でも、父や母のことを思うと、それもまたつらくて……」と、ぽつりぽつり話し始めた。どうしたらよかったのか、と自問し続けた時間の重みが、彼女の目元に現れていた。
淡々と説明しながら心が揺れる
手続きの流れを説明する。家庭裁判所の管轄、提出期限、必要書類の確認。私はなるべく平静を保って話すよう心がける。でも心の奥では、彼女の苦悩がずしりと響いていた。自分が冷たい人間のように感じることもある。だけど、説明しなければ手続きは進まないし、正確に伝えなければあとで彼女が困る。だからこそ、この仕事には「感情」と「法務」の狭間でバランスを取る難しさがある。
事務員さんの沈黙にも重さがある
面談が終わったあと、隣で記録を取っていた事務員さんがぼそっと「……つらいですね」とつぶやいた。彼女は普段ほとんど私語をしない人だ。だからこそ、その一言が重く響いた。きっと、彼女もいろいろ思うところがあったのだろう。こういう案件のあと、私たちはそれぞれ心のどこかに何かを残して帰る。感情労働って、まさにこういうことなんだと痛感する。
財産のない相続はなぜこんなに重いのか
「相続=お金がもらえるラッキーな出来事」と思われがちだ。でも、現場にいるとそんな簡単な話じゃないとすぐにわかる。実際、私が扱う相続放棄の案件の多くは「財産なんてない」「むしろマイナスばかり」というパターン。財産がゼロでも、相手との関係性、亡くなった人との過去が、放棄の決断をより一層苦しくさせるのだ。
遺されたものは借金と喪失感だった
今回の依頼者も、「兄は家族の縁を切って出ていった人で、もう何年も会っていなかった」と話していた。それでも、訃報を聞いて何かが引っかかる。その引っかかりが、手続きを通してずっと心に残り続ける。借金の通知書や督促状を前にしても、「兄が生きていた証のようで処分できなかった」と言っていた。借金の存在は確かに重いけど、それ以上に心に残るのは、関係が切れたまま終わってしまったことへの後悔や悲しみなのかもしれない。
数字で割り切れない現実
司法書士としては、借金の額を見て「これは放棄しかない」と即断することもある。でも、依頼者にとっては金額の問題じゃないのだ。1万円でも100万円でも、「兄の借金を放棄する」という事実そのものが心をえぐる。私たちが思っている以上に、人の心は数字では動かないし、割り切れない。だからこそ、この仕事はいつまでたっても難しい。
家族の歴史に線を引くような感覚
相続放棄の書類にサインをする瞬間、多くの人が静かに深く息をつく。その姿を見るたびに、「家族の物語に一本の線を引いた」ような気がしてならない。放棄することで終わらせる。だけど、それは決してすべてを忘れるということではない。その人の中には、ずっと何かが残る。線の向こうに、もう届かない何かがある。その重みを、私はいつも感じている。
司法書士のくせに泣きそうになる理由
泣いたらいけない。感情移入しすぎるな。そんな声が自分の中にある。でも、そう割り切れない案件にときどき出くわす。そして今回のように、相続放棄というテーマのなかで依頼者の「本音」に触れたとき、思わず涙腺が刺激されることがある。司法書士である前に、ひとりの人間であるという現実を、こういう場面で改めて思い知らされる。
感情移入するなと自分に言い聞かせるけど
プロとしての立場を崩さないよう、一定の距離感を持つ努力はしている。でも、どうしても揺れるときがある。相続放棄を通じて見えてくるのは、法律書には書かれていない「人の気持ち」だ。それに触れてしまったとき、心がついていかないことがある。今回もそうだった。「兄を恨んでなんかいないんです」と言った彼女の声が、今も耳に残っている。
でも誰かの感情を無視する仕事なんてできない
この仕事がつらくなるのは、感情を無視してはいけないという葛藤があるからだ。淡々とした説明だけで終われば、自分も楽になるかもしれない。けれど、それでは依頼者にとっての救いにならない気がしてしまう。誰かの人生の一部に関わるということは、それだけ責任が重い。でも、やっぱり逃げたくはない。そう思う自分がいる。
独身でよかったと思う瞬間がある
ふと、「もし自分に家族がいたら、この仕事を続けていられるだろうか」と考えることがある。夜遅くまで残って考え込む日、疲れ果てて家に帰る途中で一人の静けさにホッとする瞬間。誰かがいたら、迷惑をかけていたかもしれない。そう思うと、独身でいることが、この仕事には合っているのかもしれないとすら思えてくる。
家庭を持っていたらこの案件は引き受けなかったかもしれない
家に帰って子どもや妻がいたら、きっともっと明るい気持ちでいられるんだろうと思う。でも同時に、依頼者の感情に引きずられてしまうようなこの仕事を、家庭に持ち帰るわけにはいかない。もし誰かがそばにいたら、「その案件、引き受けないほうがいいんじゃない」と言われていたかもしれない。だからこそ、今の自分にはこの孤独が必要なのかもしれないとも感じている。
この仕事に意味はあるのかという問い
時々、自分のしていることが意味あるのかと考えてしまうことがある。目に見える成果もなければ、感謝の言葉がないこともある。むしろ、恨み言を言われることのほうが多い。それでも、今日みたいに「話してよかったです」と帰っていく姿を見ると、少しだけ報われた気がする。そんな小さな積み重ねが、この仕事を続ける理由なのかもしれない。
野球部時代の厳しさより心が折れそうな瞬間
学生時代、炎天下で怒鳴られながらグラウンドを走ったあの日々より、今のほうがよっぽど精神的にきつい。体の疲労は寝れば取れるけれど、心の疲れはなかなか抜けない。でも、不思議なことに「また頑張ろう」と思える瞬間がある。きっと、それは誰かの人生の「転機」に少しだけ関われたという実感があるからなのだと思う。
でも逃げたくないと思わせてくれる人たちがいる
つらい、しんどい、やめたい。そんな言葉が頭をよぎる日もある。それでも、笑顔で「ありがとうございました」と言ってくれる人がいる限り、逃げたくないと思ってしまう。愚痴っぽい自分でも、やっぱり誰かの力になれるのなら、この場所にいようと思う。今日もまた、相続放棄の話で涙が出そうになりながら。